※LiveJournal 2006(Jul-Dec)バックアップ
2006-07-01 20:43:00,狭き門より入れ
[http://bmg.nikkei.co.jp/review/index.cfm?contents_id=4から引用] 体験と魂 のレベルに達した智恵を獲得するために ――『知的プロフェッショナルへの戦略』(田坂 広志著、講談社、2002年3月刊、本体1500円)を読んで、私自身がかなりテクニックやスキルに こだわっていると反省させられました。スキルやテクニックの向こうに、プロフェッショナルという世界があったのですね? 田坂 インターネット革命の到来によって、知識を得ることはたしかに容 易になりました。同様に、ビジネススキルやテクニックも学べるようになりました。しかし、これらはさらに深いもの、すなわち「心得」と結びついていなければなりません。本書では、高度なスキルやテクニックに 「心」を宿した人を「知的プロフェッショナル」と呼び、単なる知識だけで仕事をする「ナレッジワーカー」と区別しています。これからの知識社会において我々が目指すべきは、まさにこの「知的プロフェッショナ ル」なのです。 ――この違いがわかる具体的なケースをご紹介いただけますか? 田坂 例えば、弁護士。弁護士をめざす人々は専門知識を習得することで専門資格を取得するわけですが、そ れだけではナレッジワーカーにすぎません。法律に関する専門知識を切り売りしているだけのことです。しかし、知的プロフェッショナルたる弁護士は、顧客の心理を細やかに理解し、問題の状況判断を的確に下し、 訴訟の戦略、戦術を巧みに実行する、といった深い智恵を駆使して活躍します。こうした弁護士は、単なるナレッジワーカーとしての弁護士よりもずっと評価され、活躍もするでしょう。そして、そのような付加価値 の高い仕事は、当然、報酬にも反映します。 ――なるほど。 田坂 こうした「心得」の大切さは、職種に関わりありません。例えば、タクシーに乗っていても、ときどきプロフェッショナル に出会うことがあります。車内への迎え入れ方、目的地までの安全な走行、車内の雰囲気作り、料金の受け取り方、おつりや領収証の手渡し方に至るまで、細やかで心配りのある仕事ぶりに、プロフェッショナルとし ての覚悟と誇りを感じます。こうした運転手の方は、自分の仕事を「作品」へと昇華させているといえます。しかし、こうした運転のプロフェッショナルに出会ったのは、この10年でもわずか二度、三度というのが実 情ですが(笑)。 ――同じ仕事をしていても、それを「作品」にまで高められる人と、単なる仕事で終わる人がいるわけですね。 田坂 これからの知識社会においては、自分の仕事を「商品」ではなく、「作品」にできるかどうかが問われてきます。こういう時代において、経営の環境、企業の状況、そして職場の心理、などの変化に対する一瞬一瞬の意思決定とマネジメントは、まさにアートと呼べる領域になっています。そして、マネジメントというものをアートのレベルに到達させるには、深い智恵が不可欠です。書物などで得られた小手先の知識は、社員や部下との魂の格闘を通じて得られた体験的な智恵には到底かないません。そして、その深い智恵を掴むために最も大切なのは、プロフェッショナルとしての基本的な姿勢、すなわち「心得」に他ならないのです。"
2006-07-01 23:11:00,Vision
John F. Kennedy 人類を10年以内に月へ送ろうではありませんか! Walt Disney Family Entertainment 家族のおもてなし Ritz Carlton もうひとつの我が家 (一歩前へ出る性格の人) Federal Express なにがなんでも届ける Nordstrom お客様の希望にかならず応える アサヒビール 「食」と「健康」を通じた生活文化の創造"
2006-07-01 20:55:00,出会い系サイトにご注意
Movable Typeを使い始める前に、日本におけるブログ事情をしらべた。その調査結果のひとつであるBlog Rankingの一覧が新規開設ブログの最初の投稿記事である。 2004年9月5日時点のランキングの第一位がuwasa.tv?芸能界の噂話? であった。クリックして斜め読みしたら「出会い系の話」があった。かつてより日本の出会い系は「やくざ」が運営していて無垢な素人が参加するのは危険だと思っていた。このサイトの記者がその危険さや出会い系にくる男女は現実世界ではもてない人たちであることを裏付ける調査の結果を掲載していた。 >出会い系サイトの裏の裏...:uwasa.tv?芸能界の噂話? >出会い系利用者はブスばかり?:uwasa.tv?芸能界の噂話?"
2006-07-02 04:06:00,LAMP
http://musashino.town-info.com/cgi/units/index.cgi?siteid=musashino&areaid=36248&unitid=okada より転載
大口顧客管理プロセス LAMP (Large Account Management Process
多くのビジネスにおいて、20%の顧客が80%以上の売上をもたらしています。又5%の顧客が50%の利益をもとらすともいわれています。「大口顧客管理プロセス」はこれらの重要客先を管理し、その関係を発展させてゆく手法の確立をお手伝いします。
顧客指向に基づいた独自の「大口顧客管理プロセス」は、営業をする際に、営業担当者が自分より年齢や地位の上位の顧客内の人達と共に、如何にして顧客企業における事業あるいは組織上の課題に対して問題解決をしながら、顧客企業が求める成果を達成していくかということを学びます。
Miller Heiman, Inc.は1978年に、Mr. Robert Miller とMr. Stephen Heimanの二人により設立されたInternational Sales Consulting会社です。以来、Fortune 500 に名を連ねる多く企業を顧客に持っています。日本でも徐々に得意先を広めています。
顧客の代表者やマネジャーとチームを組んで活動していくことにより「大口顧客管理プロセス」の参加者は主要客先との関係を戦略的に発展させ、確実な数字、現実的な収益目標を達成し、更に各自の目標に到達するための行動計画を作成することが出来ます。"
2006-07-07 21:41:00,※ROCKETBOOM daily with Amanda Congdon
米国では昨年来vlogが急速に普及している。その代表格のひとつがROCKETBOOM daily with amanda congdon だろうか?毎日3分間のニュースをインターネットを通じて世界に放送されている。 従来のTV放送とは一味ちがう。PCをもちインターネットに接続している人なら誰でも無料で見れる。RSSを利用して配信され、いつでもどこでも見れるという利便性がある。ある意味、サービスのユビキタス化といえる。 番組は、Andrew Baron が制作・演出し、共同脚本とホスト役を Amanda Congdon が担当している。消費者用のビデオで撮影し、インターネットで放映するため制作コスト、放映コストともに僅少である。 Rocketboomで一躍有名になったAmanda Congdonは一昨日辞めた。ハリウッドでの新しい仕事のためだと発表されているが、当のAmandaは彼女のブログサイトで「解雇された」といっている。 <参考1>Rocketboom Archives ・4/15/2005 Mac or PC? ・12/2/2005 Internet Explorer or Firefox? ・5/9/2006 time 100 most influential people
<参考2>Rocketboom制作・放送で使用しているソフトウェア 








 <参考3>Online Aggregator bloglines, apple itunes, fireant, dtv, mefeedia, google reader, podcast yahoo, blue-ball aggregator"
<参考3>Online Aggregator bloglines, apple itunes, fireant, dtv, mefeedia, google reader, podcast yahoo, blue-ball aggregator"
2006-07-08 23:08:00,rss reader testing
![]() Subscribe to this blog What? Tell me more...
Subscribe to this blog What? Tell me more...
| using RSS | |
| via Bloglines |  |
| using Newsgator |  |
| with MyYahoo |  |
| with Google | |
| with My AOL |  |
登録 http://www.google.com/reader/view/feed/http%3A%2F%2Fhome.elmblog.com%2Fatom.xml?q=http%3A%2F%2Fhome.elmblog.com%2F http://www.google.com/ig/add?moduleurl=http%3A//home.elmblog.com/index.xml rssには、rss+xml (rss.xml) , rdf+xml (index.rdf), atom+xml (atom.xml)があり、<head>に <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS" href="http://mysite.com/rss.xml" />のように書いている。この記述のhrefで指定するURLをfeedburnerのサイト"ElmBlog"に変更する。 <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS" href="http://feeds.feedburner.com/ElmBlog" /> feedburnerにリンクすることによりBloglines, MyYahoo!, Googleなどすべてから購読できるようになる。"
2006-07-09 11:45:00,DropShots
DropShots.com Declared as Number One Site for Family Video Sharing on the Internet (Forbes 01.24.06, 12:41 PM ET) 家族のビデオ共有サービスでNO.1だと宣言。商用ビデオの違法コピーが横行しているYouTube, Vimeo, Sharkleなどのサービスとは異なる家族向けサービス。15万のビデオと2百万の写真がアップされ、毎月35%で成長している。 Renewed Video Sharing Trends Spurs Competition (By K.C. Jones, TechWeb News Jan. 25, 2006) Skype Users Connect Via Santa Cruz Networks' API (By W. David Gardner, TechWeb Technology News, June 15, 2005 ) 謹厳実直な企業人向け雑誌Forbesオンライン版のVideo Networkで、"Most Popular Video"の今週のトップは Top Topless Beaches(内容はTravelレポートなので期待?には応えられない)"
2006-07-09 23:17:00,※Ten Things That Will Change The Way We Live
Forbes Lifestyle Feature
Breckinridge Ely 02.17.06, 12:30 AM ET
Fuel Cells
In fuel cells, the energy of a reaction between a fuel, such as liquid hydrogen, and an oxidant, such as liquid oxygen, is converted into electrical energy. Fuel cells will change the global economy, and not just because they will be as big a development in motoring as the internal-combustion engine was. They will also be used as cell-phone batteries and power generators, among other things. And they will eliminate the problem of what to do with used batteries: Theoretically, fuel cells are renewable forever.
Link"
2006-07-10 18:43:00,Googleが日本のソフト業界にもたらすもの
ソフト技術者にとっての「居心地の良さ」は、日本のソフトウェア業界が肝に銘ずるべき重要な課題である。
サイボウズ・ラボの畑慎也社長が、「大げさかもしれないが,日本の優秀な技術者はみんなGoogleに獲られてしまうのではないか,という恐怖感がある」といった。「Google(の東京研究開発センター)に勤務するある技術者と会ったとき,ここは居心地が良すぎて逆に怖いくらい,と言っていた。とても印象に残っている」ともいっている。
大げさではないと思う。かつてアメリカでソフト技術者を採用した際にかならず聞いた質問のひとつ、「あなたは何故当社で働きたいと思うのですか?」に対して、「開発したいものを自由に開発させてくれるから・・・」という答えが多かった。金よりも創造する喜びを求めるのがエンジニア気質でもある。金と出世だけを求めるエンジニアは採用後に仲間と問題を起こすケースが多い。
Googleの「居心地の良さ」とは,何よりも優秀な技術者集団から得られる刺激や,社会で話題となるサービスを手がけているという「やりがい」、革新的な技術の開発に挑戦できる「喜び」からなるはずだ。
働く意欲を持った優秀な技術者の確保が最重要課題である。働きたいと思う企業・職場をつくり候補者に訴えかけることは、技術者が企業を選ぶ時代においては大変重要である。Googleのように「トップ技術者がそこで働きたいと思う会社」が,日本国内に増えることが求められる。
Googleを日本の脅威と見なして,経済産業省主導で検索エンジンを共同開発するプロジェクトが立ち上がったことは記憶に新しい。しかし,日本のIT人材をどうするかという切り口で見れば,「働きたい職場としてのGoogle」こそが,日本が脅威として認識すべき対象だと思う。Googleはモチベーションが高く優秀な人材を世界中から集めている。このままでは,"あちら側のGoogle"という言葉では表現し切れないほどに勝ち抜かれてしまうかもしれない。
というITproの高下記者の意見に賛同する。 Link
90年代後半の日本企業をあちら側からみていて驚いたのは、「研究所も自ら事業を考えろ!」という経営者(もどきの人)の声でした。もちろんその前に事業部内の研究者・開発者・技術者に対して「事業を考えろ、製品を売れ、売り上げをあげろ!」との声があった。人間の、特に技術開発に命を賭ける人たちの本質を知らないとしかいいようがない。
研究者たちの心を知っていた研究所の役員は嘆いていたし、「人生の喜びを謳歌しながら働くシリコンバレーの研究者集団に勝てるわけがない!」と言い切っていたのが印象的で、わたしもまったく同感であった。研究者たちがやっていることのすばらしさを見抜くことのできない経営者の下で働くことほどやる気を失わせ、惨めな思いにさせることはない。これが日本の多くの企業が陥った過ちであり、技術立国の妄想を裏付ける現実であろう。
アメリカにおける優秀な経営者はベンチャーキャピタリストである。革新技術企業や著名になった成長企業の陰には必ずといってよいほどベンチャーキャピタリストがいる。その能力のひとつが「目利き能力」であろう。これが優秀な技術者にやる気を起こさせその能力を最大に発揮させる元であろう。
http://www.opensources.jp/lilina/index.php?hours=168
2006-07-10 19:09:00,Success On Demand Tour 2006 Summer,
セールスフォースCEOベニオフ氏の基調講演「ソフトウェアの未来─SaaSがもたらす経営のスピードと柔軟性─」で掲げた次世代のソフトウェアに求められる10の要件――
1.マルチテナント方式の共有システム
2.高性能と高信頼性
3.ビジネス・アプリケーションの民主化
4.大量データによるカスタマイゼーション
5.マッシュアップ
6.Webサービス・ベースとの統合
7.開発環境をサービスとして提供
8.アプリケーションの選択
9.マルチ・アプリケーションの提供
10.マルチ・デバイスの提供
「すべてがWeb上に公開されているということは、もはや、ソフトウェアの未来の前提である」とすれば、今後のソフト・サービス業界の取るべき道は「マッシュアップ」に注力することであり、Google MapやAdobe Acrobat Online、Writely(Ajax採用)といったさまざまなアプリケーションを活用した、新たな革新と価値を生み出すことではないか?
セールスフォースドットコムはマルチテナント共有を可能にするAppExchangeを提供することによりSaaS潮流の主導権を握ろうとしているようである。
2006-07-10 20:01:00,Mashups今昔
「マッシュアップ」という言葉が最初に使われたのはポップミュージックの世界である。アーティストやDJが2つの曲を合わせて、ひとつの曲を作ることをマッシュアップという。テクノロジーの世界では、複数の情報源から提供されるコンテンツを組み合わせて、ひとつのサービスを提供すること、そのサービスを利用できるウェブサイトまたはアプリケーションを指す。さまざまな分野から登場しているが、GoogleやAmazonが多様なデータを比較的簡単にオンライン地図と統合できるツールを提供したために、とくにデジタル地図の分野で未曾有の盛り上がりを見せている。
言葉はどうあれ、マッシュアップでいわれていることは既存の複数のアプリケーションを組み合わせて新たな価値と可用性をもったアプリケーションを生み出すことであり、インターネットやウェブが登場する以前からあった。ERPの世界でもCAD/CAMの世界でも、それがパッケージとして生まれ高付加価値の商品として成長する過程で、既存の革新的な技術や製品を飲み込み、統合されていった。ソフト事業開発や商品開発に携わった人たちは「マッシュアップ」の意味とその重要性にすぐ気づくはずである。
パッケージの時代とWebサービス(新語ではSaaS)の時代の違いは、現実世界(こちら側)にあるパッケージ(開発者、販売者、ソースコド、設計ドキュメント、利用マニュアルなど)を咀嚼し改造して組み入れることと、すでにインターネットやWebで利用できる仮想世界(あちら側)にすでにあるサービスを(APIを利用して)活用することの違いである。さらに決定的に異なるのは後者の方ではアプリケーションの機能がリアルタイムに進化していくことであろう。後者の方が格段に早く簡単に、また多様なアプリケーションを生み出すことができるのは明らかである。ロートルの開発者にとっては夢の世界が現実となっている。Javaもひとつの夢の世界であったが、mashupはそれを超えた利用者の世界で実現しつある。
その昔、CADの開発でCPUとグラフィックディスプレイノ間のスピードを上げるためにハードウェア(77Kbpsの光ファイバー接続)を開発しなければならなかったことを思うと夢の世界が実現している。当時のアプリケーション開発者たちがハードやOS分野の開発まで担当しなければならなかったのが、いまやその多くが半導体に組み込まれている。
とすると、いまのアプリケーション開発者たちが注力すべきことは過去の開発者たちとはまったく異なる分野であることは自明の理である。いま求められる大切なことは、技術そのものより、「どんな技術が今後の革新を生むか」を見極め、「その技術を製品(サービス)開発に迅速に組み入れる」能力であろう。Serendipity(目利き能力)が事業の成否を決めるといっても良い。
これを養うためには世界の英知が集まる開発技術者集団やそうした頭脳が集まる集積地域に住み日常生活のなかで交友関係を深め刺激を受け合うことに勝るものはない。
Mapping a revolution with 'mashups'
By Elinor Mills
Staff Writer, CNET News.com
November 17, 2005 4:00 AM PT
翻訳記事link trackback: http://tb.japan.cnet.com/tb.php/20093879
Googleの地図サービスとCraigslist(昔も今もシンプルな形で地域情報を提供するサンフランシスコ拠点のサイト)が提供する人気の不動産情報を組み合わせたサービス:housingmaps がmashupブームの幕開けを告げるものとなった。
このサービスの利便性は、ベイエリア(シリコンバレーを含むサンフランシスコ湾周辺の都市圏)で不動産を探したことのある人なら誰でも納得できるものである。mllistingsで不動産屋の売り出し物件を探し、これぞと思った物件の地図上の位置をmsnやyahooが提供するMapで探し、複数の物件情報と地図情報の一覧をつくって印刷し、物件めぐりの計画を立てる・・・ということをする。こうした物件探しの準備がhousingmaps 利用でどれだけ軽減されるかは、そのありがたみは大変大きなものである。ここ日本、特に大都市圏での物件探しにもその威力を発揮するものと思う。そのことに早く気づき早くインプリメントした業者が先駆者利益を得るに値する。そういうスピードが事業の成否を決める時代でもある。
すでに何百個ものマッシュアップが存在し、オンライン地図上でさまざまな情報を提供している。それらのなかには、ガソリンスタンドの価格情報、ハリケーン情報、温泉の場所、犯罪の統計といった実用的なものもあれば、便器の写真、UFOの目撃情報、ニューヨークの映画ロケ現場、シアトルのタコス屋台、さらにはGoogle Mapsと人気の投稿サイト「HotorNot.com」を組み合わせた「Hot People by ZIP Code」のような、軽薄とはいわないまでも、娯楽に近いものもある。
- Google Maps Mania マッシュアップサイトをカタログ化(Mike Pegg)
- Gmaps Pedometer ランニングコースやウォーキングコースの距離を計算するマッシュアップ。ジョギングのルートを書き込むと、どこで休憩をとるべきかを教えてくれる。
- Dartmaps ダブリンの通勤列車の位置をリアルタイムで伝える。
- FBOweb.com 飛行機のフライト状況を追跡できる。
- TravelPost.com 旅行中の日記や写真を投稿し、ホテルのレビューを見ることができる。 旅行愛好家のなかには、部屋の壁に世界地図を貼り、行ったことのある国に画鋲を刺して、印を付けている人が少なくない。これをオンラインで再現したいというのが動機(CEOのSam Shank)
- HomePriceRecords.com 他人がいくらで家を買ったのかを調べる。Trulia.comとHomePages.comは、物件情報と公園や学校などの近隣情報を組み合わせた不動産マッシュアップ。
- Platial 地図のパーソナライズを可能にし、その場所に関する話や出来事を記入できる。
コミュニティや社会に焦点を当てたマッシュアップ
- CommunityWalk.com 集団で地図を作成/共有する。
- WeFixNYC.com ニューヨーク市の道路の穴を調べ、修復までの時間を追跡する。
- Zvents.com 種類、日付、場所ごとにイベントを検索できる。
写真と地図を組み合わせたマッシュアップ
- SmugMaps.com 国や地域別に写真を検索できる。
- Amazon.comのA9 住所をもとに通りの写真を表示する。
- GeocoderUS 住所を入力し、緯度と経度を無料で調べられる。企業には検索2万件あたり50ドルを課金している。
KMapsは、Google Mapsを使って、特定の地域に関する情報(近所のレストラン、そこに行くための経路情報など)を、さまざまな携帯機器から入手できるソフトウェアを開発した。現在では、近くのデート相手を探す機能など、ソーシャルネットワーキング的な機能も追加されている。
企業は成功した技術に群がるもので、地図も例外ではない。ほとんどのマッシュアップは、個人が他者と情報を共有するために、熱意を持って作成したものだ。一方、企業は精度の高いターゲット広告など、収益性の高いアプリケーションを構築することを目指している。
「実用的なインターフェースとデータベースを構築できれば、特定の地域に的を絞った、文脈型の広告を配信できる」と、The Kelsey GroupアナリストのGreg Sterlingはいう。
たとえば、特定の地域のレストランを検索している人は、そこで食事をしようと考えている確率が高い。地域密着型の企業が魅力を感じるのは、こうした具体的な行動予測だ。地域密着型の企業はこれまで、費用対効果が悪いという理由で、世界中のユーザーを対象とした広告には興味を示していなかった。
The Kelsey Groupの予測によれば、ローカル検索市場の規模は今年の4億1800万ドルから、2009年には34億ドルに拡大する見込みだという。
草の根の共同思考が持つ力に突き動かされて、この分野の技術は急速に進化している。マッシュアップで利益を出すことが可能になれば、いずれ淘汰が起きる。生き残るのは、ソリューションを持つ者だけだが、最後に笑うのはだれかを判断するのはまだ早い。
これからさらなる進化の段階に突入する。とくに有望なのは道路上場サービスだろう。リアルタイムの地図情報(ライブ衛星画像)が利用できれば、事故情報や気象情報を利用者に提供できるようになる。
関連記事(日本語)
- 活況が続くオンライン広告市場--どこまで成長するのか 2006/05/11 21:20
- Web 2.0技術を使ったアパート探しサイト、米国に登場2006/05/02 17:15
- グーグル、今度は3Dデザインツール「Google SketchUp」を無償公開2006/04/28 13:17
- マッシュアップは儲かるか--大ブームの現状と可能性2006/04/26 22:04
- グーグル、Google Localで実験--地図広告の機能強化を計画か2006/03/29 10:26
- マイクロソフト、ビジネス向けの「マッシュアップ」を提唱2006/03/28 11:20
- 「Windows Live」で怒涛のサービス攻勢を仕掛けるマイクロソフト2006/03/15 13:16
- グーグルの「Writely」買収で浮き彫りになったWeb 2.0ブームの実状2006/03/14 14:37
- ヤフー、新しいマッシュアップツールを提供へ2006/03/08 15:27
- 人気テレビ番組をマッシュアップ--米で急増するファンお手製の地図サービス2006/03/07 14:22
- ヤフーが開発者向けに「Yahoo!カテゴリ」のAPIを公開2006/03/01 17:52
- スカイアーチ、地図上に「足あと」をつけてクチコミ情報を共有できるSNS2006/02/27 22:17
- 米で「マッシュアップ」コンテスト開催--優勝グループには弱冠22歳のメンバーも2006/02/22 21:14
- マッシュアップ・カンファレンスは異例ずくめ--「MashupCamp」レポート2006/02/22 20:23
- 自社の所在地をGoogle Mapsで表示する無料サービス「こっちだ象」2006/02/09 20:29
- オンライン広告サイトのCraigslist、成功の秘密は「あくせくしないこと」2006/02/03 20:37
- 「livedoor 地図情報」に周辺情報や詳細情報のバルーン表示機能を追加2006/02/03 20:01
- Ask.jpが新たにローカル検索--ブログの口コミ情報も一緒に表示2006/01/31 10:00
- ブログサービス「ブログ人」、地図にトラックバックを打てる「ブログ人マップβ」開始2006/01/19 21:21
- Google Earth、Mac OS X Tigerに対応--Windows版も正式リリース2006/01/11 19:42
2006-07-10 22:44:00,Mashups for fun--and profit?
マッシュアップが大きな人気を集めているのは、制作がかなり簡単なためだが、投資家らが慎重な姿勢を見せる最大の理由も、まさにその点にある。つまり、成功を収めているサイトを真似て、似たものをつくることもそれほど難しくないからだ。さらに、これらのサイトがどの程度の利益につながるかも明らかになっていない。マッシュアップは、ウェブ上に現れた「Next Big Thing」なのか、それとも小さな企業やマニア向けのスタイリッシュなニッチ技術で終わるのだろうか。
実のところ、マッシュアップサイト側はコンテンツの販売代行をしているに過ぎない。だからといって、マッシュアップがビジネスにならないと言っているわけではない。地図技術を提供するGoogleやMicrosoftなどはいずれ、地図上に広告を掲載するようになるとみられている。これらの広告は、表示されている地域と関連性があるため、その分売上につながる可能性も高い。さらに、「Platial」(The People's Atlas 万人のための大地図を標榜、KPCBなどから資金調達)や「Trulia」(Accel Partnersや複数のエンジェル投資家から、800万ドル弱の資金を調達)などのマッシュアップサイトは、ほかには見られない特徴を十分に備えていることから、すでに投資家の関心を集めている。
Zillow.com マッシュアップに、他の提供している複数のサービスや不動産資産評価、各種情報源のデータを組み合わせている。Benchmark Capitalが3200万ドルを出資。
「マッシュアップの課題は、その運命が他社に左右される場合があることだ。彼らの運命は、Googles、Yahoos、Microsoftsが提供するオープンコンポーネントが握っている。現在までのところ、独立運営できる会社になれそうなマッシュアップはない」(Outlook VenturesのマネージングディレクターRandy Haykin氏)
Mashups for fun--and profit?
By Elinor Mills, Staff Writer, CNET News.com, Published: April 19, 2006, 4:16 AM PDT
翻訳記事: マッシュアップは儲かるか--大ブームの現状と可能性
Related news
- A celebrity stalker mashupBlog, March 22, 2006
- Social atlas for friends and burritosMarch 8, 2006
- MashupCamp--a new kind of get-togetherFebruary 21, 2006
- Mashups for social changeBlog, February 14, 2006
- How much is your house worth? Zillow knowsFebruary 7, 2006
- Tour New York with a Google-Wikipedia-GPS mashupBlog, January 18, 2006
- Mapping a revolution with 'mashups' Special report, November 17, 2005
- Get this story's "Big Picture" >"
2006-07-10 23:53:00,A Brief History of Porn
Wednesday, March 29, 2006
A Brief History of Porn Over at the Oprano messageboard for adult entertainment webmasters, there's an interesting thread today -- users are constructing a timeline of the adult industry. It's pretty comprehensive. Here's one of the more densely annotated timelines, submitted by user "Gonzo." After the jump, and into the late 20th century, we get into tech-centric milestones like Betamax and Section 2257 that made the present-day biz what it iz. I love how the timeline does one humongous warp-speed leap from the 1400s to Dr. Ruth. Guess there wasn't much shagging going on for 500 years! Snip:
1st century BC - Kama Sutra was created 1440 - Gutenberg Press Invented 1928 - Dr. Ruth was born. 1953 - Hugh Hefner starts Playboy 1965 - Bob Guccione starts Penthouse 1968 - Al Goldstein starts Screw 1969 - First mainstream movie to represent the swinger lifestyle - Bob & Carol & Ted & Alice, Directed by Paul Mazursky 1970 - Penthouse shows pubic hair for the first time.
1970 - Notable Porn Movies - Cycle Studs - Le Salon (Gay) 1971 - Notable Porn Movies - The Boys in the Sand - Wakefield Poole (Gay) 1971 - First condom to appear in a movie - Carnal Knowledge, Directed by Mike Nichols 1972 - Notable Porn Movies - Deep Throat - Gerard Damiano (Straight) 1972 - Notable Porn Movies - Behind the Green Door - The Mitchell Brothers (Straight) 1972 - Notable Porn Movies - Fritz the Cat - Ralph Bakshi (Anime) 1974 - Larry Flynt starts Hustler. 1975 - Betamax introduced 1975 - First condom commercial air on television 1976 - VHS introduced 1978 - Larry Flynt is shot in an assassination attempt that left him paralyzed from the waist down. 1983 - Name server developed at University of Wisconsin 1984 - Penthouse publishes pictures of Vanessa Williams naked. She resigns her Miss America crown. 1984 - Domain Name Systems (DNS) introduced 1985 - Symbolics.com is the first registered domain in history 1985 - Earliest domains to be registered - cmu.edu, purdue.edu, rice.edu, berkeley.edu, ucla.edu, rutgers.edu, bbn.com, mit.edu, think.com, css.gov, mitre.org 1986 - Traci Lords is discovered to be underage 1986 - US Attorney General Edwin Meese published 1,960 page report investigating porn at the order of President Ronald Reagan. 1988 -Title 18 United States Code Section 2257 was enacted 1990 - First commercial provider of Internet dial-up access - world.std.com 1992 - Term "Surfing the Internet" is first heard 1993 - Don't Ask Don't Tell introduced by President Bill Clinton. 1993 - World Wide Web goes live. 1994 - Sex.com was registered by Gary Kremen 1995 - First confirmed blowjob in the White House. 1995 - Sex.com was stolen by Stephen Cohen 1996 - Domain name tv.com sold for $15,000 1997 - DVD introduced 1997 - Domain name business.com sold for $150,000 1998 - Viagra introduced 1998 - Al Goldstein installs Fuck You Finger in his backyard in Florida. 1999 - Domain name business.com sold for $7,500,000 2000 - Sex.com was given back to Gary Kremen after a legal fight. 2000 - AEBN launched first VOD site 2000 - American Express stops accepting porn transactions 2001 - Yahoo removes porn banners from search engine 2003 - Paypal stops processing adult transactions 2003 - Penthouse files bankruptcy 2005 - Sex.com theif Stephen Cohen arrested 2005 - Video iPod introduced 2006 - Sex.com sold for a reported $12,000,000 2006 - Google resist court order for porn search results
Link (Thanks, Honey Juggs Ninja Pony!) http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=2257&btnG=Search+Boing+Boing&domains=boingboing.net&sitesearch=boingboing.net
"
2006-07-11 00:12:00,Boing Articles
Use of term "flash mob" dates back to 1800s Tasmania?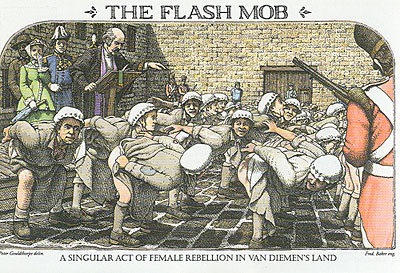
Technology for parents to spy on kids
The San Francisco Chronicle has a great article on the rise of technologies for parents who want to spy on their kids: web-bugs, car-trackers, and GPS-enabled cellphones that covertly or openly spy on kids and rat them out to their parents:
Another company, Alltrack USA, offers a service that e-mails or calls parents if the car they're monitoring exceeds a certain speed or leaves a defined geographic area. DriveCam, which now installs cameras in fleet vehicles, plans to offer a monthly service to parents and teens next year that will let them watch video clips of their driving and receive coaching from driving experts.CarChip-type devices differ from the "black boxes
Art installation: 180,000 lumpy clay people
An English sculptor, Antony Gormley, has produced an installation of 180k hand-made clay figures that stand in a giant hangar-like building as part of an art show in Sydney, Australia:
For the Biennale, Gormley has shipped out his Asian Field, an installation of 180,000 hand-sized clay figurines. Three hundred and fifty villagers in southern China individually crafted the figurines in just five days from more than 100 tonnes of red clay. Together, the figurines form a vast sea of bodies that dominates the huge upper space of Pier 2/3. Lumpy and almost featureless, they eerily stare out with blank holes for eyes. As Gormley says, "The art is not there to be looked at; it is looking at you."
Link to egenerica's Flickr photoset, Link to Sydney Morning Herald article (via Make Blog)
Ted Stevens "Internet of Tubes" mirrors Singaporean ISP site
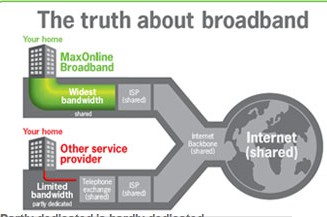 Senator Ted Stevens' mind-bogglingly dumb explanation of how the Internet works ("it's made of tubes, it's not a truck") shares some eerie similarities with this stilted Singaporean ISP site. StarHub/MaxOnline's "Fat Green Pipe" page has lots of graphics ready-made to be remixed into a visual accompaniment to Stevens's presentation. Link (Thanks, Geoff!)
Senator Ted Stevens' mind-bogglingly dumb explanation of how the Internet works ("it's made of tubes, it's not a truck") shares some eerie similarities with this stilted Singaporean ISP site. StarHub/MaxOnline's "Fat Green Pipe" page has lots of graphics ready-made to be remixed into a visual accompaniment to Stevens's presentation. Link (Thanks, Geoff!)
Porneologisms: "Limbaugh" to become slang for "Viagra"?
"Taking a Limbaugh" has should become slang for "taking Viagra" in the adult entertainment world, according to this AVN article. Link (Thanks, Thomas)
Friday, July 7, 2006
WWII US military comic: "How to Spot a Jap from 1942 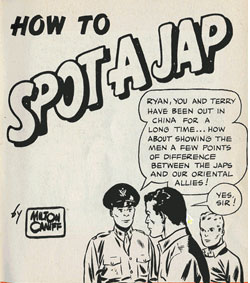 An eleven-page publication illustrated by Milton Caniff (creator of the "Steve Canyon" comic). The Army provided this test to US Soldiers stationed in China during WWII. Link. (thanks, Ethan)
An eleven-page publication illustrated by Milton Caniff (creator of the "Steve Canyon" comic). The Army provided this test to US Soldiers stationed in China during WWII. Link. (thanks, Ethan)
Vintage timepieces with sexually explicit displays
|
|
Vintage tech: Commodore 64 espresso maker plugin
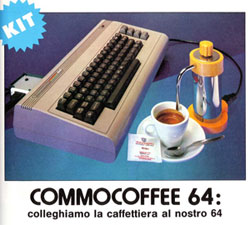 Scanned from a 1985 issue of the Italian computer magazine Microcomputer: a coffeemaker timing device for the Commodore 64. Link (thanks, Se?or Tonto) Scanned from a 1985 issue of the Italian computer magazine Microcomputer: a coffeemaker timing device for the Commodore 64. Link (thanks, Se?or Tonto)
The 40-page tract from 1892 is a fun read, mainly for the relish Faulkner takes in describing the carnal urges that get stirred up in people when they dance:
What is this ad for?
|
The Internet, a series of tubes -- for children.
Xeni Jardin: Danny Silvermansays,
Link Previously: T-shirt design: "The Internet, a Series of Tubes" |
US gov. memo to federal agencies mandates laptop security
Xeni Jardin: Federal civilian agencies have just over a month left to comply with new guidelines mandating encryption and two-factor authentication for notebook computers:
The memo follows a wave of high profile data thefts and major security breeches involving remote access or the theft of government laptop computers containing sensitive personal information. The official memo (PDF)from the executive office of the U.S. president stipulates that all mobile devices containing sensitive information must have their data encrypted. The recommendations also say that two-factor authentication must be used for remote access, that remote access must time out after 30 minutes of inactivity, and that all data extracts must be logged. The memo does not detail any specific technology recommendations beyond this broad outline, presumably leaving agencies to decide on their own specific implementations.Link to Security Focus article (Thanks, Mike Outmesguine!) |
Stephen Hawking turns to Yahoo Answers for help
Mark Frauenfelder:  Even Stephen Hawking gets stumped once in a while. He posted the following question to Yahoo Answers: Even Stephen Hawking gets stumped once in a while. He posted the following question to Yahoo Answers:
"How can the human race survive the next hundred years?" Link |
Slides for Ted Stevens's "it's made of tubes" speech
Cory Doctorow: 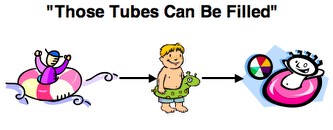 Here's a set of homemade powerpoint slides to accompany Senator Stevens's hilariously craptastic "the Internet is made of tubes" speech. Link (via Vertical Hold) Here's a set of homemade powerpoint slides to accompany Senator Stevens's hilariously craptastic "the Internet is made of tubes" speech. Link (via Vertical Hold)
Update: Patrick sez, 'The original slideshowof Senator Ted Stevens' "Internet is made of tubes" speech was Meryl Yourish's.' Company will archive 200k pages onto 2" nickel square
|
"
2006-07-11 00:54:00,Tribe.net self-censoring to conform with 2257 porn laws?
Friday, December 9, 2005
Tribe.net self-censoring to conform with 2257 porn laws?
Author and sexblogger/podcaster Violet Blue tells Boing Boing that popular social networking site Tribe.netis proactively, voluntarily applying 2257 laws to its members and service architecture.
This makes approximately zero-to-the-tenth-power sense. Tribe is not a producer of content, they're a forum for end-users to communicate and share content they create or collect. What's next? AOL, Microsoft, and Yahoo ban jpeg attachments because there's no way to enforce age documentation for amateur nudie shots swapped by users of those free email services?
Two weeks ago Tribe asked me for a phone meeting; I didn't know what it was about but I figured it had something to do with Tribe's mature content. They explained to me in a half-hour conference call that they were gearing up to change Tribe's architecture (entry pages, etc) to conform to updated 2257 laws, which are record keeping requirements.
The federal law now requires website owners to keep *physical* records documenting, among other things, that "a book, magazine, periodical, film, videotape, digitally- or computer-manipulated image, digital image, picture, or other matter that contains a visual depiction of an actual human being engaged in actual sexually explicit conduct" is over the age of 18. Visual depictions *after* 1990, mind you.
(...) I think they are making a huge mistake, based on a law that is unenforcable. The law violates privacy -- I was sent the 2257 information for the porn performers I featured in my last podcast. I now have enough information to steal the actual identity, and stalk, every performer in that film. They performers don't even know I have that information, or who else might have it as a legal requirement, and nothing makes me more uncomfortable than having that information in my posession.
The law is meant for primary and secondary producers of porn, not online communities. The law violates our federal right to freedom of speech. The law is obstensibly created "to protect children from being exploited as [porn] performers", not healthy adult enjoyment of human sexuality. In truth, 2257 laws are less about protecting children from porn exploitation, but instead about regulating porn businesses, free speech and healthy adult sexual expression into unfesability.
Link to Violet Blue's blog post. Linkto text of law.
Previously on Boing Boing: Bad news for free speech: "Children's Safety Act" passes in House Rotten.com: gapingmaw, othersites shut in anticipation of 2257
Image: Jacob Appelbaum.
Boing Boing: Tribe.net pre-emptively censors groups in fear of fed ...
| Previous posts on Boing Boing related to 2257 (Link) and Tribe.net's self-censorship (Link). Image: Jacob Appelbaum. posted by Xeni Jardin at 11:58:14 AM ... ★http://www.google.com/search?q=2257&hl=en&lr=&domains=boingboing.net&sitesearch=boingboing.net&start=0&sa=N |
"
2006-07-11 01:29:00,Taking Back the Web
http://news.com.com/Grassroots+taste+makers+define+opinions/2009-1025_3-5942440.html?tag=ne.tbw.nav
Day 1 ENTERTAINMENT
Grassroots 'taste makers' define opinions
By John Borland
Staff Writer, CNET News.com
November 14, 2005 4:00 AM PT
Late on a Sunday evening last month, a caravan of mildly intoxicated moviegoers wound their way down a dark gravel road to a shooting range at the outskirts of Austin, Texas.
Most of the cars were coming from an advance screening of the film "Domino which included an appearance by its screenwriter. The studio had supplied drinks at the theater and was sponsoring a shotgun-toting after-party at the insistence of Harry Knowles, whose "Ain't It Cool News" site of rumors, reviews and industry gossip has a wide following from "fanboy" circles to studio offices.
Hardly a typical release event--but well worth the price of a few liability lawyers to put Knowles in a good mood. For he and others like him are, in effect, defining America's tastes.
"I'm sure we made studio lawyers go into hissy fits said the flame-haired, larger-than-life Knowles, 33, who called the movie "one hell of a film" in a subsequent review posted on the Web site he founded a decade ago. "But still, we actually got them to loosen up and have fun with their own movie, which is something that rarely happens in this industry."
If Knowles' ways seem unconventional to the Hollywood establishment, they are entirely appropriate for the maverick sphere he represents: an expanding universe of opinionated blogs, fervent fan networks and other communities, where the power to confer popularity--or at least the fragile aura of "buzz"--can appear virtually overnight.
Like the Web itself, the impact of such grassroots opinions has grown geometrically to change the way hits are made in movies, music and television. Their significance goes far beyond the realm of entertainment, fundamentally recasting the way opinions are shaped in a society whose sensibilities have been saturated by mass-media campaigns for generations.

The undeniable influence of these organic taste makers has been made possible by the rise of blogs, tags, collaborative bookmarks and other so-called social technologies that are fulfilling some of the utopian objectives espoused in the early days of the Internet, when it was hoped that the Web would empower the individual and dismantle communication barriers across the globe. Many of those altruistic goals were vastly overshadowed by mass commercialization. But, in the years since the dot-com meltdown, they've been resurrected with a new generation of digerati who are developing and exploiting the social aspects of the medium.
"Media has traditionally been pushed down, from the companies at the top. But in the 21st century, it is increasingly pushed up from online communities said Eric Garland, chief executive officer of Big Champagne, a company that taps peer-to-peer networks for data on what's most popular on the networks. "The file-sharing community is a good reflection of the marketplace precisely because there is no push mechanism."
For media and entertainment companies seeking tomorrow's fans, this can be a bewildering frontier. In the last decade, average marketing costs for a Hollywood film have more than doubled to almost $35 million, according to the Motion Picture Association of America, but box-office attendance has continued to decline.
It's not that Rolling Stone, corporate radio stations and big-city movie critics no longer help sell tickets and records. But they're increasingly sharing their influence with a more democratic landscape of MP3 blogs and MySpace friends lists, in which a rave review or free download can reach tens or even hundreds of thousands of people.
Continued: Roots in 'Star Trek' conventions...
Day 2 WIKIS
How wikis are changing our view of the world
By Daniel Terdiman
Staff Writer, CNET News.com
November 15, 2005 4:00 AM PT
Moments after the eye of Hurricane Katrina made landfall along the Gulf Coast on Aug. 29, news agencies everywhere rushed to report the story. But among the quickest to begin offering comprehensive coverage wasn't a formal news organization at all.
Instead, it was a loose collection of self-appointed "citizen journalists" reporting, linking and photographing from Louisiana and around the world. And the organization for which they were working, called Wikinews, wasn't paying them a dime.
"With all of that bad news, it's nice to know that at least one cool thing has emerged from this: The Katrina Information Map, which brings together the power of wikis and Google Maps to create a useful public resource for tracking or reporting flood damage former Louisianan Matt Barton wrote on the blog Kairosnews. "I see that most people are using the service to inquire about loved ones or report flooding on various streets."
this way comes
A wiki is a group of Web pages that allows users to add content, as on an Internet forum, but also allows others (often completely unrestricted) to edit the content. Wiki is sometimes interpreted as the acronym for "what I know, is which describes the knowledge contribution, storage and exchange up to some point. "Wiki" with an uppercase W and WikiWikiWeb are both used to refer specifically to the first wiki ever created (March 25, 1995). The name is based on the Hawaiian term wiki, meaning "quick "fast" or "to hasten."
--Source: Wikipedia
News is one of the most effective uses of an oddly named technology created in 1995 by a Portland, Ore., programmer named Ward Cunningham, which was based on the idea that information should be shared openly and remain accountable to everyone. Known as "wiki the software allows the creation of Web pages that can be edited indefinitely by anyone with access, regardless of who wrote the original work.
Although initially conceived as a form of communal publishing, the wiki is quickly evolving into a multipurpose interactive phenomenon. As evidenced in the aftermath of Katrina and the London bombings a month earlier, wikis can be a life-saving resource that provides real-time collaboration, instant grassroots news and crucial meeting places where none exist in the physical world.
The popularity and proliferation of wikis are particularly significant in an age of increasing distrust of mainstream media. In many ways, wikis are emblematic of the democratizing principles of the Information Age that seek to give voice to ordinary citizens.
"With the distributed nature of the Internet, you now have the ability for people with common interests to rapidly aggregate themselves and apply their nearly unbounded knowledge of different subjects into cohesive organization in a matter of hours said Rob Kline a product manager for Marchex who helped create the KatrinaHelp.info wiki. "Because it's distributed, it's global, so when I have to go to sleep, someone else can pick it up and keep working on it."
Wikis began in various forms, but it was the online encyclopedia known as Wikipedia that propelled the concept into the popular consciousness. Wikipedia and Wikinews were created by the same nonprofit organization, Wikimedia Foundation, and are available free of charge.
Online collaboration tools are changing the way individuals and companies share information.
As an indication of Wikipedia's growth, the open-source encyclopedia tallied more than 814,000 articles as of this writing, in English alone. Although Wikipedia undoubtedly owes at least some of its popularity to the pursuit of trivia that is a hallmark of the Web, it has also fundamentally altered societal attitudes about access to information.
For all its benefits, some worry that those who participate in sites like Wikipedia or Wikinews are more interested in pursuing an agenda or personal opinions than the kind of accurate documentation expected of professionally edited resources like the Encyclopedia Britannica.
Continued: From weddings to Dungeons & Dragons...
Day 3 TAGGING
'Tagging' gives Web a human meaning
By Daniel Terdiman
Staff Writer, CNET News.com
November 16, 2005 4:00 AM PT
If you've been to a technology event recently, especially one with a high concentration of digerati, you may have seen someone stand up and tell everyone what the event's Flickr tag is.
It may sound like another language, and in a way it is: Flickr is a popular photo-sharing service that allows anyone to view most of the more than 50 million member-submitted images it hosts. Tags, meanwhile, are the searchable keywords the individuals can assign to either their own images or to those of nearly anyone else that say something about the information--the defining characteristic of Flickr and a growing number of other online services.
"In Flickr, tags worked because they were fundamentally social said Stewart Butterfield, Flickr's co-founder. "By agreeing on a tag in advance, users could collectively curate collections of photos in a dead simple way. Now we see people announcing at events, 'The tag for this is baychi05' and stuff like that."
The idea behind tagging may be irresistibly simple, but its ramifications are enormous and complex. For more than a decade, the primary way to categorize and find information on the Internet was through the automated algorithms of search engines, a process at once laborious and highly imprecise. Tagging has quickly gained popularity because it allows human beings to bring intuitive organization to what otherwise would be largely anonymous entries in an endless sea of data.
Also known as "folksonomies tagging systems are usually created by users themselves, rather than site owners, and make many online services far more accessible and useful than they had ever been before. The practice brings a social context to such resources as blogs, shared bookmarking, photography and even books.
Moreover, beyond its practicality, others find a philosophical significance in tagging because it is consistent with the social thinking often associated with the beginnings of the Internet. What many fans of tagging like best is that it is a system that empowers individuals. And after years of users trying to find their way around Web sites using categories defined by a small number of people running those sites, tagging is a huge relief.
"Tagging" is a term used to describe human indexing of material on the Web, which in theory makes content more intuitively found and shared. Tagging systems are also known sometimes as "folksonomies"--a combination of "folk" and "taxonomy"--as well as "shared bookmarking."
"We've had this decades-long program of top-down metadata. People (were asked) to go out and become familiar with one ontology and to make sure data is categorized like this. But people are not very good at this said Cory Doctorow, an editor of the technology culture blog BoingBoing and the European outreach coordinator of the Electronic Frontier Foundation. "I think what's completely right about folksonomies is asking people to do something for their own benefit, to have them organize their own information and then find the accidental or fortuitous positive externalities."
Because tagging is used as an indexing tool and as a way to search for information, both in discrete databases or across the Internet, some say it is conceivable that the technology could one day give search engines like Google a run for their money.
Brad Hill, an author who has written about search engines, sees tagging at this stage as a tool for collaborative social use, not for universal searching. But he added that tagging could become so deeply embedded in the social fabric that "tag clouds"--large groupings that collectively cover many areas of information--could one day become the first search choice for many people.
Continued: 'A gigantic tag cloud'...
Day 4 MAPS
Mapping a revolution with 'mashups'
By Elinor Mills
Staff Writer, CNET News.com
November 17, 2005 4:00 AM PT
Even before Google gave its blessing, Paul Rademacher was hacking away at the code behind its mapping application so he could mix it with outside real estate data and see exactly where homes listed for sale were located in the San Francisco area.
Little did the computer graphics expert know that his HousingMaps.com, which combines a Google map with house listings from the popular Craigslist community, would be the start of an Internet phenomenon. Although Rademacher created his site about two months before Google publicly released its application programming interface--the secret sauce that allows developers to create their own recipes with its maps--the company wasn't angry.
In fact, Google hired him shortly thereafter.
"Now we see that all along there has been a huge amount of interesting information tied around location Rademacher said. "Before, they had no way of expressing that and doing anything useful with it."
With such "mashups"--hybrid software that combines content from more than one source--digital maps are quickly becoming a centralized tool for countless uses ranging from local shopping and traffic reports to online dating and community organizing, all in real time and right down to specific addresses.
Online mapping is evolving into a historic nexus of disparate technologies and communities that is changing the fundamental use of the Internet, as well as redefining the concept of maps in our culture. Along the way, map mashups are providing perhaps the clearest idea yet of commercial applications for the generation of so-called social technologies they represent.
They are, in a very real sense, bridging the gap between the virtual and physical worlds.
"This information has been on the Web for years said Mike Pegg, a Canadian programmer who runs a site called Google Maps Mania. "The map is all of a sudden bringing this information to life for us. I think it has inspired a lot of people."
So prolific has the mapping movement become that Pegg has dedicated his site to documenting the staggering growth of mashups. He estimates that at least 10 mashups are created every day, each providing data that pop up in info balloons from the digital pushpins dotting various online maps.
Not surprisingly, this unprecedented interest is forcing change at old-world cartography institutions. Just last week, Rand McNally announced a new online mapping service of its own called MapEngine, which will allow businesses to integrate maps, directions and location search functionality into their Web sites. But such established companies will increasingly compete with free applications that have sprung up organically on the Web.
The term "mashup" was first used in pop music when artists and DJs began playing two songs simultaneously. In technology, it refers to a Web site or application that combines content from multiple sources but appears seamless upon use. Although used for various software, mashups became an unparalleled phenomenon in digital cartography because of the relatively easy ability to overlay all types of data on an online map with tools from such companies as Google and Amazon.
Already, hundreds of mashups overlay maps with everything from such practical information as gas station prices, hurricane movements, hot springs sites and crime statistics to the more entertaining if not frivolous, including photos of urinals, UFO sightings, New York movie locations, taco trucks in Seattle and Hot People by ZIP Code, a mashup of Google Maps and the HotorNot.com Web site.
This wildfire popularity has touched off feverish competition among the major portals that provide mapping services, especially since Yahoo, Microsoft's MSN and Google all released their map programming software to the public. But another reason cited for the boom in map mashups is one of hardware, specifically the processor speed and storage capacity needed for satellite photos and other resource-hogging images.
"They are taking off because the hardware has gotten to the point where it is possible and the software has achieved a bit of maturity, especially with Google Maps said Rich Gibson, co-author of the book "Mapping Hacks." "Until very recently you couldn't effectively do mapping work on a personal computer."
Hardware and software aside, however, it is the ability for anyone to add information to a map that is increasing the usefulness exponentially and has inspired the mashup wave.
A case in point is Gmaps Pedometer, a widely distributed mashup that records distances traveled during a running or walking workout.
Continued: Trains, potholes and real estate...
Day 5 YOUTH
The 'millennials' usher in a new era
By Stefanie Olsen
Staff Writer, CNET News.com
November 18, 2005 4:00 AM PT
The future can be found in the virtual stacks of the International Children's Digital Library.
The "simple search" feature at the Web site, which was designed in part by schoolchildren, provides as many as 50 choices to find the right title while displaying large buttons that link to fairy tales, adventure stories or books designed in favorite kid colors. It also offers personalized bookshelves and three types of software to read them, including a child-inspired viewer that shows pages in a spiral rack so that kids can jump to any page.
It's hardly a sophisticated algorithmic index, but it makes perfect sense to children who may not know how to search like an adult or spell a keyword. That is precisely why the University of Maryland, which built the site, continues to invite children to test its software and suggest new designs.
"If there's only one way to find or read a book, to a child it doesn't make any sense said Allison Druin, associate professor of the university's College of Information Studies and director of its book project, which was started in November 2002. "Our traditional educational tools limit how children access information to learn or fit us into one way of learning things."
The library offers an important view into the minds of what some sociologists are calling "the millennials"--a generation of children and teenagers who came of age at the dawn of the millennium.
Members of this generation are thought to be adept with computers, creative with technology and, above all, are highly skilled at multitasking in a world where always-on connections are assumed. Their everyday lives are often characterized by immediate communication, via instant messenger, cellular conversations or text messaging. No member of this generation, it can be assumed, would ever wait on a street corner for a late friend.
The changing ways that members of this generation can learn, communicate and entertain themselves are a primary reason behind the viral popularity of socially oriented technologies such as blogs, wikis, tagging and instant messaging. Children who were born when Netscape Communications went public are now 10 years old and have been raised on a steady diet of digital technologies that have fundamentally shaped their notions of literacy, intelligence, friendship and even the anxious adolescent process of learning who they are.
For their grandparents, the bicycle was a symbol of childhood independence. Today, for many kids and young adults, it is the Internet.
"It consumes my life said Andrea Thomas, a senior at Miami University. "If I'm not texting my friends over the cell phone, I have my laptop with me and I'm IM'ing them. Or I'm doing research on Google. Honestly, the only reason any one of my college friends use the library is for group meetings."
"Millennials" is one term sociologists use to designate those youths raised in the sensory-inundated environment of digital technology and mass media at the millennium. Unlike Gen X, which referred generally to people born in the 1960s and 1970s, this generation has yet to carry a name popularized by mainstream culture. Also known as "Echo Boomers as the children of Baby Boomers, millennials were born from the 1980s on.
Jonathan Steuer, technology consumer strategist for Iconoculture, a research firm, said those like Thomas are simply using today's technologies to express a sense of belonging that young people have always desired. "What sets millennials apart is that they use technology to push the boundaries of the values that have been associated with their generation in ways not possible before."
By only their seventh birthday, most children in the United States will have talked on a cell phone, played a computer game and mastered a TV-on-demand device like TiVo, much to the amazement of technically challenged parents. By 13, researchers say, the same children will have gone through several software editions of instant messaging, frequented online chat rooms and downloaded their first illegal song from BitTorrent.
College-age millennials will likely own a laptop and take for granted ubiquitous broadband Internet access. They may also be intimately familiar with the feeling of "highway hypnosis"--the ability to drive or multitask with little memory of the process of getting there.
Their inevitably short attention spans are the reason Seymour Papert of MIT's Media Lab coined the term "grasshopper mind" five years ago, for the inclination to leap quickly from one topic to another. A mathematician and founder of artificial intelligence, Papert addressed the effects of this behavior as far back as 1995 in congressional testimony about technology and learning.
"The question at stake is no longer whether technology can change education or even whether this is desirable Papert wrote in his testimony. "The presence of technology in society is a major factor in changing the entire learning environment."
Continued: Cyberspace replaces the mall...
GROUND ZERO
The law of 'spontaneous order'
By Declan McCullagh
Staff Writer, CNET News.com
November 14, 2005 4:00 AM PT
Do technologies like collaborative Web sites, methods of "tagging" photos and documents, and mapping-related projects really represent the next Internet revolution?
That's the buzz. Web bookmarks manager Delicious has received a round of funding from Amazon.com and others; the Web 2.0 conference last month in San Francisco was sold out; video-sharing companies YouTube and Revver also have landed financing. Skype's $2.6 billion price tag deserves a mention too.
In an eerie echo of the 1990s boom, Wired magazine is touting the world-shaking consequences of the Internet today. Compared with the average Google user, writer Kevin Kelly concludes, "I doubt angels have a better view of humanity."
It's true that these developments are useful, even fascinating. But I've been using the Internet since 1988, making me probably just enough of an old-timer to say we should view them through the wide-angle lens of history.
So to put this ostensibly new-world order in the proper perspective, it helps to recall the historic computing breakthroughs that made the modern Internet possible. Even if today's technologies do usher in a new digital society, they may simply represent the culmination of many advances that have long been in existence but are finally coming together by serendipity if not design--an example of what late Austrian economist F.A. Hayek called "spontaneous order."
It wasn't too long ago, for instance, that researchers at the University of Minnesota invented a novel way to catalog and retrieve information on the Internet.
Instead of adopting the free-form approach of the Web, Paul Lindner and Mark McCahill wanted a well-structured hierarchy for pages. Their resulting text-based approach proved to be simple for users and programmers to understand, perfect for devices with tiny screens, and a boon for the visually impaired.
The year, of course, was 1991 and that invention was called Gopher. It soon became as widespread as its eponymous namesake, thanks to volunteers who built search engines around it (one was named Veronica), contributed technical tweaks, and offered server space at no cost. Some Gopher aficionados believe that the protocol would have triumphed over the World Wide Web had the University of Minnesota not started to demand licensing fees.
The venerable Usenet was an even more revolutionary development at the time. Conceived by Duke University graduate students Tom Truscott and Jim Ellis in 1979, it began as a project to let people at different Internet sites chat with one another by exchanging public messages.
Continued: The birth of the FAQ...
PREDICT THE FUTURE - Reader Wiki
"
2006-07-11 02:00:00,CCC Business Model,
1990年代半ばのContent brings Community brings Cashのビジネスモデルは現在も生きている。
インターネット利用者の80%は毎日のように検索をしており、これが巨大な仮想空間でのコミュニティを作っている。このコミュニティが高校をクリックすることにより、Googleほかの検索エンジン企業だけでなくそのアフィリエイト企業にも莫大なキャッシュを生み続けている。
<試算> 5?x24x90x12millions=$1.3Billion
マーケティングの視点から見ると、こうしたコミュニティは伝統的なメディア(新聞、雑誌、TVなど)とは比較にならないほどきめ細かなデモグラフィックを提供している。今後は、モバイル(podcastsやvideo-phones)により生み出されるコンテントが主流になってくるのではないか。<日本ではすでにモバイル(携帯電話)によるコンテントが主流になっていると思われ、ブログスフェアでは日本語権のブログが英語圏のそれを追い抜いたことが裏づけている。>
2006-07-11 02:14:00,CNET News Downloads
 |
The tax man cometh after iTunes Internet shoppers accustomed to tax-free digital downloads may be in for an unpleasant surprise from their state. (5 pages, 347 KB file) |
 |
Microbe-managing Mother Nature This three-part series features scientific advancements that use nature to make natural gas, pesticides and electronics. (10 pages, 684 KB file) |
 |
Silicon money The tech industry reverses its strategy and spends millions to buy influence in Washington. (16 pages, 1 MB file) |
 |
Taking back the Web A new generation weaned online is using wikis, blogs, tagging and other new technologies to return the Internet to its social roots. (21 pages, 237 KB file) |
 |
India's tech renaissance Beyond offshoring, a new powerhouse is in the making. Led by a young work force, the country of 1 billion people is expanding into all things technology. (9 pages, 1600 KB file) |
This special series offers realistic solutions on key issues involving technology, its business and relevant policies.
 |
Homeland security: The price of safety The U.S. government's multibillion-dollar drive for homeland security has produced a boom in antiterror technologies. At the same time, it has created problems ranging from industry confusion to lack of basic accountability, and privacy concerns are higher than ever. (20 pages, 4057 KB file) |
 |
Broadband: Breaking the digital gridlock High-speed Internet access is rapidly evolving from a Web-surfing luxury into an everyday necessity. But the development of broadband technology remains stunted by market uncertainty and mind-numbing bureaucracy. (24 pages, 2032 KB file) |
 |
Offshoring: Reality behind the politics In a special series, CNET News.com offers tangible steps to maintain America's leadership in technology. (38 pages, 4209 KB file) |
Previous report PDFs
- Me TV: Finally, you are in control
April 11, 2005 (1449 KB file) - Japan's sun rises again
December 8, 2004 (4576 KB file) - South Korea's digital dynasty
June 23, 2004 (1768 KB file) - Bigger blue
June 14, 2004 (1780 KB file) - Playing for keeps
December 9, 2003 (148 KB file) - Corporate Classrooms
Novemeber 11, 2003 (320 KB file) - Vision Series 4: Industrial evolution
Part 1: Computers replace petri dishes
June 2, 2003 (136 KB file)
Part 2: Wall Street turns dollars to digits
June 10, 2003 (155 KB file)
Part 3: Intensive care for medical data
June 16, 2003 (154 KB file)
Part 4: The high cost of national security
June 23, 2003 (149 KB file)
Part 5: Hollywood's digital blockbuster
June 30, 2003 (176 KB file)
- Digital remix
May 28, 2003 (11 pages, 305 KB file)
- Mother of invention
April 11, 2003 (11 pages, 216 KB file)
- It's a buyer's market
February 11, 2003 (12 pages, 227 KB file)
- Nothing but air
February 3, 2003 (18 pages, 399 KB file)
- Vision Series 3
December 2, 2002 (88 pages, 1.24 MB file) - Day 1: Security (17 pages, 288 KB file)
- Day 2: Web services (18 pages, 284 KB file)
- Day 3: Open source (20 pages, 310 KB file)
- Day 4: Personal technology (17 pages, 282 KB file)
- Day 5: Wireless (16 pages, 289 KB file)
- A mortal Microsoft
October 11, 2002 (18 pages, 436 KB file)
- E-Terrorism
August 26, 2002 (13 pages, 343 KB file)
- China's new dynasty
July 9, 2002 (16 pages, 430 KB file)
- Vision Series: Tech chiefs dictate the future
June 10, 2002 (68 pages, 5.7 MB file)
- Vision Series: Survey results
June 10, 2002 (11 pages, 85 KB file)
- Cracking the nest egg
April 26, 2002 (20 pages, 398 KB file)
- Sun's Java jigsaw
March 28, 2002 (22 pages, 429 KB file)
- The Gatekeeper: Windows XP
October 17, 2001 (26 pages, 422 KB file)
- A bitter pill
September 26, 2001 (9 pages, 142 KB file)
- Privacy vs. safety
September 17, 2001 (3 pages, 142 KB file)
"
2006-07-11 07:16:00,vloggercon
 ビデオブログ「ブイログ」、目指すは映像の大衆化6月にサンフランシスコで開催されたビデオブログ(ブイログ)カンファレンス「Vloggercon」。そこでは、ブイログのスタイルについて活発に意見が交換されていた。2006/06/20 18:04
ビデオブログ「ブイログ」、目指すは映像の大衆化6月にサンフランシスコで開催されたビデオブログ(ブイログ)カンファレンス「Vloggercon」。そこでは、ブイログのスタイルについて活発に意見が交換されていた。2006/06/20 18:04
- Vloggercon: Where everyone's the media
- 米「ビデオブログの女王」争奪戦が勃発か?CNET Japan Staff BLOG | Tracked: 2006/07/06 15:23 RocketBoomといえば、ビデオポッドキャストの草分けのひとつで、日本版も...
- 視聴者の学級崩壊で仏壇と化していくテレビSeekPC.com | Tracked: 2006/06/25 23:58ビデオブログ「ブイログ」、目指すは映像の大衆化 海外旅行雑誌の草分け的存在だったエイビーロードが休刊するそうだ。時代の流れという意見が多い。すでに内容がインタ..."
2006-07-11 06:47:00,YouOS
Take a look at YouOS
MIT, Stanford, Caltechの学生4人が昨年末からオープンソース形式で開発を始めた。言語はPython, php, Javascript, Pascalなどを使い分けているようだが、開発の仲間とのコミュニケーションにWordPressを使ったブログ、開発ドキュメント作成はTrac社のwikiを活用し、フォーラムにはphpbbsを使って、YouOSだけでなくこの上で動くアプリケーションまで同時進行で開発を進めている。4人のリーダーは現在サンフランシスコとシリコンバレーに住んでいるがどこに住んでいようが問題外であろう。開発資源は、人間が住む現実のこちらではない、あちらの世界にある。それは瞬く間に地球規模になってしまう。開発開始半年で試用版(彼らの定義ではイプシロン0.11版)がリリースされている。アプリケーションも150がテストされているとの話(これもあちらの世界で聞いたこと)
YouOSサイトを覗くだけでも、若者たち(geeks)がいかに楽しく、面白く開発に取り組んでいるか、その雰囲気と熱気が伝わってくる。えっ、感じられない?・・・とすると、それはあなたに感性が不足で、情緒力が不十分ということかも知れない。優れた記憶力、論理力、問題回答能力だけでは、開発者の情熱ましてやその心を理解することはできない。その心に共鳴したあちらの世界の人たちが一緒に開発に取り組んでいる。
最近のslate.com記事、Where's My Google PC? (July 3, 2006, at 1:13 PM ET )で Paul Boutin がYouOSに触れている。WebベースのOSなどないという頭でっかちにわからせる効果はあるという。90年代に流行ったNetwork PCとかThin Clientというのが、いまやGoogleがひそかに世界のどこかで開発しているのではとの噂の真偽を推し量る格好の材料でもある。
このPaul Boutinの記事を引用して、CNET News.comでRafe Needlemanが、YouOS: A very cool science experiment(July 7, 2006 4:56 PM PDT)という記事を書いている。ここからは日本語の紹介記事が7月10日に書かれているのでそちらを参照されたい。
これからYouOSがどんな展開をみせるのか楽しみである。"
2006-07-11 14:46:00,rss
 購読
購読







RSSとは - おすすめRSSリーダー"
2006-07-11 16:56:00,FeedBurner BuzzBoost
"
2006-07-12 11:11:00,Re-birth of a salesman,
近年Webが営業プロセスをどう変えたか、購買機能の効率化を狙った伝統的なCRMの欠点は何かを検討する。またIT活用と新しい営業マンを育てる道具となる Operational Business Intelligence についても紹介する。
2006-07-13 11:46:00,★Junk Trackback
88.198.241.110 88.198.252.148 61.129.102.208 205.177.79.121 213.200.246.7 219.240.113.2 24.234.200.113 68.3.26.145 88.198.252.149 202.71.102.94 72.20.3.58 88.198.241.109"
2006-07-15 14:03:00,※海外旅行客
夏の季節に限らないが、旅行客が多いときは交通費、滞在費がかさむ。感覚的に、オフ時の費用の2倍を覚悟したほうがいいのだろう。
一ヶ月先にアメリカに出発する便を予約しようと思ってインターネットで調べた。八月一杯まで、空席がほとんどない状況である。仕方なく旅行業者に「キャンセル待ち」の予約を依頼した。はじめてのことである。
過去20数年、仕事で海外を飛び回ることが多く航空券の手配はセクレタリに頼むだけでなく自分でもオンライン予約をすることが多かった。時代とともに予約の仕方がかわりその利便性は進化してきた。
いまや学生や主婦も手軽にインターネットで旅の予約ができる時代である。いろんな旅行商品が、バーチャル世界で紹介されており、日毎に替わっている。旅行業者は時間との戦いであり、利用者への利便性提供に勝つことが生き残りの条件になっている。
利用者側に選択権があり、その範囲は広がっている。自分はこれまで各地を点々とする、日程も頻繁に変更になる、という条件を満たすために試行錯誤の結果、UnitedとAmericanを利用することが圧倒的に多くなった。個人旅行もこの二社を利用するのが多い。
今回の目的地はアメリカ南部の都市である。成田からサンフランシスコあるいはシカゴ、アトランタ、ダラスといったハブ空港までの国際線チケットを買ってあとは現地で格安国内チケットを買うという手もある。しかし、今回の一番の問題はエコノミークラスを前提としたときだが「空席がない」ということがわかった。マイレージ特典でビジネスクラスも探したが八月一杯は満席であった。考えることは万人ほぼおなじなので妙案が功を奏すことも少ない。
結局、自分であれこれ調べて思案する時間がもったいないので業者に「キャンセル待ち」を頼んだわけである。空港使用料、燃料代、税金などをいれて25万円!これがオフのときだと10万円くらいというから驚きである。1~2万円が2?3万円になる「2倍」とは、負担金の大きさが違う。
ところで、海外旅行者数はどうなっているのかと気になって調べた。LINK"
2006-07-15 21:32:00,※広大な露天風呂でオーロラ鑑賞!
asahi.comトラベルに「テーマで行く旅」というコーナーがある。至福のザルツブルグ音楽祭プレミアムツア、地中海・エーゲ海15日間、アルプス三大秀峰とスイス氷河特急10日間など興味引かれる企画がたくさんある。どれもこれも美しい写真が掲載されており、こんな美しい自然に触れ、自分の眼で写真を撮りたいと思ってしまう。
このサイトに限らないが旅行サイトを眺めているだけで世界旅行をした気分にもなってしまう。数年前に比べるとWebページのコンテンツと表現手法は非常に洗練されてきた証拠であろう。
さきの企画ツアーのなかに「50歳からの海外旅行」というのがある。今月のおすすめは、ベテラン添乗員・岩本由起子レポート「私のおすすめ マッターホルン(スイス)」であるが、ここは一度行ったことがある。仕事の合間を縫って、日本の出張者たちを案内した。案内というのは私自身がツアーコンダクタ(フライト・ホテルの予約、通訳、運転手・・・という男芸者)であったためで、その実マッターホルン地域ははじめてであった。
インターラーケン、グリンデルワルド、ユングフラウなどなつかしい名称地も紹介されている。氷河特急、登山列車を乗り継ぎ、標高3500メートル地点まで普段着で、女性でもハイヒールを履いた普段の格好でもいけるところである。われわれは、ジュネーブ(だったかチューリッヒ)でレンタカー(メルセデスベンツ!)を借り、4人の出張者を乗せて旅をした。仕事の合間であったため、長距離を日帰りで行った。
いまも鮮明に記憶に残るのは、大自然の美しさである。カメラを持っていなかったのが残念であるが、だからこそ脳裏には強烈な印象が残っているのだろうか?
車だからこその自由な行程で、気が向くままに途中停車して、遠くの風景に見とれ、湖畔で一服し、あるいは小さな骨董店に立ち寄り記念の品を買ったりした。骨董店というが、じつは田舎の村のリサイクルショップみたいなもので、たまに訪れる観光客のために家族がやっている静かなたたずまいの店である。アメリカでもそうだが、まわりの風景に溶け込み、そうした店自体が絵になる。思わず立ち止まりその雰囲気を味わいたいと思うのは私だけだろうか。運転手の特権で、結局は私が気に入ったところで「休憩しましょう!」「ちょっとトイレ!」「お土産でも見ますか?」などともっともな理由を付けて途中停車(駐車)したものである。そうした旅のつれづれに家族に買ったおみやげもたくさんある。いつか整理して飾ろうと思いながらそのまま押入れに眠っている。
この記事を書き始めたときの意図とはまったくちがう内容になってきたが、話を戻そう。「私のおすすめ・・・」は件の記事を見ていただければよい。『匠人が設計する旅』のひとつ―「火山と氷河の国アイスランド7日間」がわたしの目に留まったのが、もともと記事を書くきっかけだった。これからの旅の候補先としてメモしておこうと思った。以前にNHK「世界遺産」の中でも紹介されていたのが記憶のはしにあった。
 |
|
| (写真)済んだ空気と美しい町並みのレイキャビック |
アイスランドとい国についてはほとんど何も知らない。土地の名前で知っているのはレーガン、ゴルバチョフによる首脳会談で有名になった「レイキャビック」くらいなものである。それも名前だけしか知らなかった。
このツアの案内を読むと、冬の風物詩オーロラ、豪快な間欠泉、氷河が溶け出した滝、地球の割れ目、そして広大な露天風呂といったキャッチフレーズが眼に飛び込んでくる。旅をしたい、すばらしい自然の美しさに触れたいという人間本来の願望(と私は思っている)に訴えかけてくる。
オーロラは昔々、北極圏上空を飛んだ飛行機の中から目撃したきりである。娘は友達の故郷というアラスカのフェアバンクスに遊びにいってオーロラを見たという。「父を差し置いてさきにオーロラをみたのか!」と悔しく思った。オーロラ観光を目的でいっても「見れなかった!」と良く聞くし、TV番組の企画でも、ながながと期待感を抱かせながら結局見れなかった(オーロラが出現しなかった)!」というドジというじゃ、しc乗車をコバカにしたような結果がよくある。だからこそ希少価値があって、「一度は見たい!」という期待感が高まっていき、憧れに似たものになっていくのだろう。「昔、飛行機の中から見た」と書いたが、じつはもう一回ある。それは、フィンランド、ヘルシンキからさらに飛行機で1-2時間北へ飛んだラップランドであった。しかし、それは眠れる夜、ホテルの窓から寝ぼけ眼でちょっと見た程度で証拠写真も取れなかった。私の中では、数分間はしっかりと見て写真にもキチット収めてはじめて「見た!」といえるのである。その意味では「まだオーロラをみていない」ということである。
 |
|
 |
|
| (写真上)人口の露天風呂「ブルーラグーン」/(写真下)「ブルーラグーン」で撮影したオーロラ |
そうしたオーロラ願望に訴えかけてきたのが、「オーロラ鑑賞は、9月から4月の八ヶ月間。一夜で2回ほど出現し、一時間程度。大きいオーロラは15分ほど。」とあったことである。しかも、オーロラがス告げんする確率は月に30%、7~10日」と書いてあり、これなら10日間滞在すればかならず見られる!と思った。さらに、レイキャビックから車で40分、硫黄の匂いと水蒸気が立ち込める地熱地帯にある露天風呂に入りながらオーロラを鑑賞できる!とあるではないか!これで一挙に、旅先の候補NO.1にランされてしまった。まあ、単純といえば単純な論理なんだが――。
・アイスランドのオーロラ
参考にツアー費用は、一人37万円。ロンドン乗継で20時間かかるのはしんどいかな。おなじ7日間だが現地での自由時間が多いアイスランド航空チャーター便でいくツアーは28万円で、飛行時間は12時間である。
費用はツアー内容を見ないとなんともいえない。現地で個人的な自由裁量で行動したいのなら自分で企画するほうが格安可も知れない。たとえば企画ツアーとおなじ出発日9月13日のブリティッシュエアウェイズでは往復126000円でロンドン途中下車で滞在することもできる。ただし、ロンドン・アイスランドともにホテル代が高い。中級でも一泊数万円と考えたほうがいいかもしれない。残念ながら特典が使えるSheratonはアイスランドにはない。"
2006-07-17 23:01:00,デジカメ
春に5代目のデジカメを買った。手ぶれ補正x高感度のCyberShot モデルDSC-T9である。6 Mega PixelのCCDを備えている。つまり、有効画素数600万画素で、2816x2112ピクセルの写真を撮影できる。これはA4サイズでプリント写真とおなじ品質で印刷できることを意味する。家庭で鑑賞する限りにおいては十分な精度である。A4印刷することは滅多にない。また、20インチ程度までのパソコンや家庭のテレビで見る場合は必要以上の精度である。第一、パソコン画面の精度は1024x768が多いため、これ以上の精度があっても表現しきれない。メモリ容量を消費するだけである。
6M(2816x2112)で撮った画像一枚の容量は、ファイン(カメラが撮影できる最高の品質)で3MBくらいである。1GBのメモリースティックであれば300枚以上撮影できる。38枚撮りフィルム8本分である。一枚3MBの写真であれば、30インチ以上のハイビジョンTV画面でもきれいに見れるのではないか?我が家の骨董品に近いテレビ(十数年前にある会社の桜祭り抽選会での特等賞で当った)しかないので、それを確認できない。
高精度のデジタル写真で良いのは、写真の一部を切り取ってパソコン画面いっぱいに表示しても十分な精度できれいに見れることである。縦横それぞれ1/3(面積で1/9)の大きさの部分を切り出しても画面表示の品質はほとんど変らない。これは、写真全体のサイズ、容量で1/10(300KB)にしても画面表示の品質はほとんど変らないということでもある。
それじゃ、最初から低品質(小容量)で撮ればいいではないか。1M(1280x960)スタンダードで撮れば、容量は3Mファインで撮ったときの1/10近くになり、3000枚も撮れる・・・という議論がある。そうした判断に結構迷うものである。品質とメモリ容量、現在の要求と将来の要求の折り合いをどう付けるかということである。
10年前はじめてスキャナーを買って古い写真をパソコンに取り込んだときもおなじ悩みがあった。デジカメのない時代、一枚一枚の写真は貴重であった。それらを子供たちのためにもデジタル化して大切に保存したいと思った。高品質で取り込むとパソコン/CD-ROMの容量を大量に食ってしまう。しかし品質面であとで後悔しないように当時の最高品質で取り込もうか・・・というジレンマである。いまではDVD一枚が4GB以上もあり、十年前に取り込んだ当時の最高品質(800x600で100KB弱)の写真を、4万枚以上も保存できる!!! しかも費用は50円(10年前の1/100)!!! 今思えばバカなことで迷っていたものだ!といえるが当時は費用対効果を真剣に考えていたものである。
そして今も悩みがある。テクノロジーが進歩し費用が激減したと同時に使える機能も激増したからである。アメリカ的なプラグマティズムの立場に立てば、「過剰機能・過剰品質」のほかのなにものでもない。ハイテクに弱い、知識のない消費者が商業主義に踊らされているというのは言いすぎだろうか?そんな風に思えて仕方がない。
「足るを知る」ことのない人間の「欲の深さ」に付け込まれている。ある意味、贅沢品にはそういった側面があっても仕方がないだろう。「生活必需品」ではないのにだれもが持つような社会になると「生活必需品」のような錯覚にも陥る。携帯電話も同じようなものではないか?なくても生活に支障はない。しかしいったん使い出すと離すことができなくなり、「仕事で必要だ」とか「友達と連絡を撮るのに必要だ」、「持っていないと仲間はずれになる」とかの理由を挙げ正当化するようになる。そしてそれは現代社会の「生活必需品」となるのである。いやそういう錯覚をもつようになってしまう。その意味ではインターネットもおなじく「生活必需品」になってきたのであろう。
話が「生活必需品論」に逸れてしまったが、件の写真品質と容量の問題はいまも時々迷うことである。この記事を書くきっかけになったのは、昔のスキャナとプリンタ品質ではなく、画像編集ソフトの選択という視点での「品質と容量」を決める「圧縮率」の判断に困ったからである。圧縮率そのものは昔から判断に困ることであるが、それに加えて選択できる画像編集ソフト(無料)の幅が増えたのが新たな迷いになった。
Nikon製(といってもOEMだが)のソフトにPicture Projectというのがある。このソフトを使って写真を補正すると容量が一挙に倍近くに増える。補正後の圧縮率が小さくなっているからであろう。自動補正すると「目鼻立ちくっきり」のきれいな写真になるのは確かである。しかし、もともと過剰品質の大容量が気になっているからさらに増えるのは癪に障る・・・ということもあるが、問題はWebにアップするときである。媒体が安くなって保存費用は問題ないのだが、Webで写真共有するときは表示スピードの問題が出てくる。容量が大きくなれば遅くなるのは当然である。だから品質をあまり下げないようにして容量も少なくすることを考えるわけである。ブロードバンドの時代だといっても接続スピードには限度がある。
無料の写真共有サービスも増えてきたが容量制限がある。たとえば、重宝しているFlickrでは一ヶ月にアップロードできるのは20MBまでである。いまのCybershotで標準的に撮った写真は1?3MBだから、そのままだと一ヶ月に7?20枚しかアップできない。これでは用をなさないので、当然「JPG圧縮」をしたうえでアップする。品質をあまり落とさないで・・・という条件がつく。ここ数年は「縮小専用」という切れ者ソフトを使っている。圧縮率は1?100%のあいだで自由に設定できる。経験から、圧縮率は60%としている。これだと画面サイズで異なるが一枚50?150KBになり、月200枚までアップできる。
「縮小専用」で不満なのは撮影情報が消えてしまうことである。Picture Project(PP)
を使って画面サイズ変更・圧縮しても撮影情報は残るのでこれからの活用を考えた。そこで困ったのが圧縮率である。%での指定はなく、標準圧縮・高圧縮・最高圧縮という指定である。これまでの経験上の値を使えないのは結果の品質の程度が見えないので困る。それで簡単なベンチマークをした。PPで「標準圧縮」は縮小専用での80%、高圧縮が60%、そして最高圧縮が40%に対応する。ただし、圧縮後の容量での対応である。品質が同程度かどうかは確認できない。目視では同じようにしか見えない。ソニーでもカシオでも、どのデジカメでもおなじであるが、過剰品質気味に圧縮率を設定しているように思う。一枚あたりの容量が大きい方が、デジカメ用メモリをたくさん使うことになるので商売の視点からは有利に働くからであろう。ソニーなどはデジカメ、パソコンなどの本体とは別にメモリースティック事業もあるわけだから、大量のメモリを消費する需要が増えたほうがいいに決まっている。
いずれにしても品質と容量・スピードのバランスを判断するのは意外と難しいものである。テクノロジが進歩し、機能が増え、普及とともに価格も低下していく将来も考慮してどうバランスをとるか?貧乏性の昭和人は、どうしても最適化を考えてしまう。暇人故なのかもしれないが。
一昨年あたりからは画像よりも動画の品質・容量のほうが気になっているが、これを書き出すとまた話が長くなり、切りがなくなるのでやめる。
"
2006-07-21 15:32:00,One red paperclip
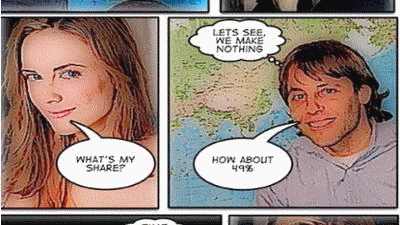 二週間前にRocketboomのキャスターAmanda Congdonが辞めた話を書いた。その後アメリカのメデアでは「何があったのか?」「アマンダはハリウッドに行くのか?」「アマンダの後任は誰か?」「Video blogのパイオニアの今後は?」「サイバースペースのソープオペラ(昼メロ)」などとかしましく記事が踊る。
二週間前にRocketboomのキャスターAmanda Congdonが辞めた話を書いた。その後アメリカのメデアでは「何があったのか?」「アマンダはハリウッドに行くのか?」「アマンダの後任は誰か?」「Video blogのパイオニアの今後は?」「サイバースペースのソープオペラ(昼メロ)」などとかしましく記事が踊る。 そして、7月12日・・・予定から二日遅れでRocketboomの再放送がはじまった。新しいキャスタはJoanne Colanである。オンラインの3分間ニュースで取り上げたのは「One red paperclip」であった。これは、カナダのKyle MacDonald が一年前の7月12日に「赤いクリップをちょっと大きな、なにか良いもの、たとえばペンとかスプーンとかと交換したい」という記事をブログに投稿したときからはじまる。そして一年後、かれはKipling Saskatchewan(カナダ中部にある町)の家と交換することになった...という話である。
そして、7月12日・・・予定から二日遅れでRocketboomの再放送がはじまった。新しいキャスタはJoanne Colanである。オンラインの3分間ニュースで取り上げたのは「One red paperclip」であった。これは、カナダのKyle MacDonald が一年前の7月12日に「赤いクリップをちょっと大きな、なにか良いもの、たとえばペンとかスプーンとかと交換したい」という記事をブログに投稿したときからはじまる。そして一年後、かれはKipling Saskatchewan(カナダ中部にある町)の家と交換することになった...という話である。
これを題材にして、Joanneが町に出て実際に交換を繰り返していくストーリである。その日のホットなニュースや視聴者からの投稿ビデオをもとにニュースが制作されているが、この日の「One red paperclip」は、Kyleと連絡を取って、意図的・計画的に制作されたようである。Kyleが「家と交換することになった」という記事をポストした日とRocketboom放送日がおなじである。![]()


それから一週間...one red paperclipが一躍有名になった。Kyleのブログサイトのそのいきさつが書いてある。当のKyle自身がおどろくほど彼のストリーは世界に広がった。モロッコで知り合ったオランダの友人が彼に教えてくれたのだが、オランダの放送会社RTLが彼の話からヒントを得た番組De Editie NL-ruilactie を放送した。paperclipの替わりにリンゴとタマゴからはじめて車との交換に至った話を紹介している。
これらの話はいずれもインターネットが生み出した新しい可能性を証明する例でもある。"
2006-07-21 17:19:00,Podcasting Hacks
―構成、録音、発信の必須テクニック (単行本) ジャック・D. ヘリントン 
次世代のラジオと称され、注目を集めるPodcast。この新しいメディアを使って情報発信を行うための実践的な情報を提供するのが、本書『Podcasting Hacks』です。ニュース、音楽、映画レビュー、技術解説、身辺雑記など、テーマ別のPodcastの適切な構成、クリーンな音声ファイルを作成するためのツール(ハードウェア、ソフトウェア)とテクニックを具体的かつ詳細に解説し、あなたのPodcastが多くのリスナーを獲得することを助けます。また、著作権やプライバシーに関する注意、インタビューの際のマナーなど、音声コンテンツの作成に必要な心得も紹介し、さまざまなトラブルを避けることも可能にします。「IT Conversations」、「Coverville」など、米国の人気Podcastの制作者が、自らのノウハウを公開していることも見逃せません。
"
2006-07-21 20:09:00,便利なツール
・HandM@il 迷惑メール対策のためにメールアドレスを画像に変換して利用
・Xoops 2.0.14
・BotTorrent
・ Download Plugins User Guide
Download Plugins User Guide
・FireAunt
Vlog Ranking - ブイログ ランキング"
2006-07-21 20:41:00,Podcasting

(RSS リーダーには フレッシュリーダー をお薦めします)
"
2006-07-22 16:37:00,フィッシングとセーフ ブラウジング機能のセキュリティ方法について
Googleツールバーをインストールするときの注意事項
フィッシングは大変多く見られる詐欺行為で、公式なページに似せたウェブ ページで、ユーザー名やパスワード、または社会保障番号や銀行口座番号、PIN 番号、クレジット カード番号や母方の旧姓、誕生日などの個人情報の入力を要求するものです。
多くの場合、フィッシング ページへのリンクは、公式らしく見える偽装のアドレスから届くメールに記されています。 また、ウェブ上にあるリンクやインスタント メッセージをたどっていくことで、偽装ページに誘導される場合もあります。
Google セーフ ブラウジングは Firefox 用Google ツールバーの機能で、お客様がアクセスするページが不正にお客様の個人情報を要求していると思われる場合に警告を発します。
Google の技術と複数のソースから得た詐欺のページに関する報告を活用し、セーフ ブラウジングは疑わしいページにアクセスした場合に自動的に警告を発する機能を備えています。
"
2006-07-24 00:00:00,Download Javascript
<SCRIPT type=text/javascript>
function download()
{
window.location.href = 'http://www.kbcafe.com/juice/juice.setup.msi';
}
</SCRIPT>
<DIV style="FLOAT: right; WIDTH: 10em; TEXT-ALIGN: center">
<DIV>Download the latest version of the Juice News Reader.</DIV>
<DIV><INPUT title=juice.msi onclick=download() type=button value=Download></DIV>
</DIV>
"
2006-07-25 17:53:00,米国のオンライン広告市場,2011年には全市場の9%へ
JupiterResearch Finds Online Advertising Will Represent Almost Nine Percent of the Total US Advertising Market by 2011
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--July 24,
2006--JupiterResearch, a leading authority on the impact of the Internet and emerging consumer technologies on business, finds that advertisers will continue to increase the share of total budget spent online between 2006 and 2011, with the market reaching $25.9 billion or almost nine percent of total US advertising spending in 2011.
米JupiterResearchは,米国オンライン広告市場に関する調査結果を発表。米国のオンライン広告支出は今後も伸び続け,2011年には259億ドルに達し,広告支出全体の約9%を占める見通し。 予想を超える勢いで伸びており、2005年には前年比40%増加した。2006年は同21%増の見込みである。
市場を牽引しているのは検索広告で、2005年にはその売り上げがディスプレイ広告のそれを上回った。今後5年間はこの傾向が続き,検索エンジン広告がオンライン広告で最も大きなシェアを占めると予測されている。
Link(読むためには会員登録が必要)
2006-07-28 11:16:00,※SLATES
昨年からWeb2.0というコトバがメディアを賑わすようになった。SLATESツール―blog, wiki, tags, RSS, そしてopen APIsがインターネット社会に影響を与えているのは明らかである。こうしたテクノロジーが企業のイントラネットにどのような影響を与えるのか?HBSのMcAfee助教授はその研究を大きなテーマにしている。 ※LINK McAfee, Andrew. "Will Web Services Really Transform Collaboration?" MIT Sloan Management Review 46, no. 2 (winter 2005): 78-84. McAfee, Andrew. "Enterprise 2.0: The Dawn of Emergent Collaboration" MIT Sloan Management Review Spring 2006 Vol. 47, No. 3, pp. 21-28"
2006-07-28 12:35:00,※革新するための12の視点
The 12 Different Ways for Companies to Innovate
革新―Innovationとはなにか?今日多くの企業が生き残るために革新しなければならないという。CEOたちが掲げる経営課題のトップが「革新」である。しかし、一体何を革新するのか?新製品の開発やR&Dの革新と同義語であるとすれば視野が狭すぎるというものだろう。それは革新というより、競争優位に立つための手段にしか過ぎない。 ※LINK Mohanbir Sawhney is the McCormick Tribune Professor of Technology and the director of the Center for Research in Technology & Innovation at Northwestern University's Kellogg School of Management in Evanston, Illinois. Robert C. Wolcott is a fellow and adjunct professor and Inigo Arroniz is a postdoctoral fellow at the Center for Research in Technology & Innovation. Link
"
2006-07-28 23:54:00,命名を思案
目的別のサイトに整理したいが、命名が難しい。新しい名前を探している。思いついたのがダルマから発想したDalma, Dalman, Dalmanianである。
英和辞典にあるのは、{dalmaの前方一致}
・Dalmatia― クロアチア南部のアドリア海に面する地域 Dalmacija
・Dalmatian ダルマチア犬、ダルマシャン
・Dalmatica ラテン語で、古代ローマ末期から中世にかけて着用されたT字形の緩やかな衣装のこと。現在はキリスト教聖職者の儀式服として残る。
Googleでdalmaを検索すると、142万件あった。カナダ・ケベック州のDalma移民のグループ、サウジアラビアのDalma Group(dalma.com.sa)など。domain名では、「だるま商店」のdalma.jp、Web designコンサルのdalma.comがある。
dalmanになると、40万件に減るが、dalman.com(貿易会社のサイト)はすでにあった。
そして、dalmanianになると、なんと41件しかなかった。意外と使われていない。嫌がるような意味があるのか、それとも単純にだれも思いつかないのだろうか?
goo三省堂の英和辞典にはなかった。dullmannというのが推薦として出てきた。
FactMonsterにもなかった。Dalmatianの間違いでは?とのメッセージが出た。
ユニークせいの追求という意味ではよい名前である。ドメイン名もいまなら確保できるが、すでに二つ持っているので三つも取るのはためらってしまう。さぁ どうするか?
dalmasanを検索すると524件あり、なぜか韓国語のサイトが多い。標高489メートルの山の名前でもある。
dalmannはWikiにあった。何語かは不明。
Dalmann er ?slenskt karlmannsnafn. アイスランドかノルウェイかな?男の名前のようでもある。「属格」に関係するようでもある。
ふーむ どうもアイスランド語のようである。"
2006-07-30 00:36:00,格差論争
格差拡大は現実か幻想か
格差拡大に対する関心、懸念が引き続き高い。メディアは、パート・派遣社員の賃金の低さや労働環境の劣悪さ、生計を維持できないほどの低収入を余儀なくされる労働者の実態を生々しく報じる。OECDも報告書の中で、「日本は先進国の中で、貧困層の割合がもっとも高い国のひとつになった」と書いた。
http://www.asahi.com/business/column/TKY200607260101.html
"
2006-07-30 02:43:00,Carnivore

Carnivore, a controversial program developed by the U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI) to give the agency access to the online/e-mail activities of suspected criminals. For many, it is eerily reminiscent of George Orwell's book "1984." Although Carnivore was abandoned by the FBI in favor of commercially available eavesdropping software by January 2005, the program that once promised to renew the FBI's specific influence in the world of computer-communications monitoring is nonetheless intriguing in its structure and application."
2006-07-31 18:59:00,北欧女性30人がトップレスの日光浴、町が「騒然」
2006.07.29
Web posted at: 14:25 JST
- CNN/REUTERS
アルバニア・ティラナ――南欧、アルバニア南部の地中海に面する海岸町で、北欧の女性約30人が胸部を露出して、一斉に日光浴を行い、地元の母親が子供たちを現場から慌てて追い出すなどの騒ぎがあった。
サランダ町での騒動で、地元紙は、苦情を受けた警官が駆け付けたものの、英語を話せず、ただ、ぼう然と見つめていた、と伝えている。女性にも近付かなかったという。
北欧の女性たちのガイドが、地元の海では禁止されている行為と知らされ、約2時間後に着衣して、立ち去ったという。
アルバニアは1990年まで、労働党の一党独裁政権が続き、91年に自由選挙を実施している。
"
2006-07-31 20:10:00,スイカの栄養は室温保存で増加
 スイカの栄養(カロチンなど)は室温で保存すると、収穫後も次第に増加するとの研究結果が、米農務省から発表された。
スイカの栄養(カロチンなど)は室温で保存すると、収穫後も次第に増加するとの研究結果が、米農務省から発表された。
CNNの記事ではじめて知ったが、スイカには体内でビタミンAに変化する「ベータカロチン」と、抗酸化作用の強い「リコピン」が含まれる。これらの含有量が、室温に近い21°で保存したスイカは、収穫したばかりのスイカと比べると、ベータカロチンが50?139%、リコピンが最大40%増えたことがわかったそうである。
(写真は千葉県大広町のスイカから借用しました。地中温度測定結果<資料提供:岩手県>は地熱利用促進協会ホームページより)
スイカの栄養価にはあまり興味がなかったが、おいしさにはこだわる!冷蔵庫に入れて冷やしたスイカは冷たすぎてだめである。数時間近く、部屋において置くと生ぬるくなってしまう。ある程度歯ごたえがあって、ある程度の冷たさが歯と唇に感じながら、シャキシャキとかじるスイカの味が最高である。
どれくらいの温度に冷やすと一番おいしく感じられるのかは知らない。テレビのグルメ番組で放送されたかもしれないが、グルメの世の中、そんな研究があってもおかしくない。
個人的には、子供のころに食べた、井戸に入れて冷やしたスイカの味が忘れられない。あの井戸水の温度がいちばんなのだろう。
ところで、いったい井戸水の温度は何度なのだろうと調べたら、年中平均16℃くらいだそうである。地熱利用促進協会に、「地中の温度とエネルギー」の説明がある。それによると、深さ5mよりも深い地中の温度は一年中10?15℃でほぼ一定だそうだ。3?5メートルの井戸では16℃、真夏でも18℃以下のようである。
ちなみに大広町のネット販売のスイカは7月23日に完売したとのこと。この頃に獲ったスイカを仏壇の前において保存し、三週間後のお盆に井戸水に冷やして食べるのがいちばんおいしかった記憶がよみがえる。米農務省の研究は室温保存で二週間後には栄養価が増加しているということだが、「おいしさ」も増加しているのではないか。
"
2006/08
2006-08-02 22:32:00,企業内ブログの是非
ブログの制作をはじめてから2年が過ぎた。もともと情報発信と知識共有のツールとして日々の経営に使うべきと考えて、最新の技術やソフト、利用動向を調べはじめたのが契機である。そのことはこのブログの初期の記事に書いた。ある企業での導入を薦めたが、保守的な経営幹部たちのマインドが異なり遅々として進まない。若手の社員たちは新しい変化に機敏に反応するが、全社的に活用するには経営幹部のリーダーシップが必要である。
アメリカ的に「やって見せねば」と思い、自ら実践することにした。最初は、むかしからのホームページを整理し、これらを新興ブログサイトに展開することを考えた。Geocities, Engelfire, Locust, Xoomなど数多くのISPサイトで試しに作ったHPのほとんどは、M&Aの嵐のあとに消えていった。残ったHPのバックアップと新しいWebの構想を練った...というのは大げさで、電車やトイレの中で考え、暇を見つけていろんなサイトでブログを開設して試行した。
むかしと違って実に簡単に開設、運用できるようになった。ものの10分もあれば新しいブログを開設でき、すぐに運用が開始できる。 そうした利便性と迅速さが多くのユーザを即席ブロガーにしている。ただ、アメリカのジャーナリズムや政治、起業家、経営者が注目したブログの社会性にはまだ気づいていない人が多いようで、即席ブロッガーたちは「日記もどきのブログ」の域にとどまっているようである。伝統的・保守的な企業の経営者たちの認識も似たようなものであろう。
自らが「考えて、書いて、情報を社内外に発信する」ということに慣れていないのがひとつの阻害要因となっているのだろう。社内の会議だけでなく、お客さまに提案したり解決策を説明したりするときも、使うツールはパワーポイントが主流である。要約しスライドにまとめるのは得意でも「文章を書く」ことに慣れていない。知的作業のプロであるコンサルタントといえども、事情はおなじである。パワーポイントが思考結果の表現ツールであるだけでなく、逆にそれが思考の枠を決めることになっているのではないか。
思考のプロセスには、じつに数多くの言葉の選択があり、論理と情緒の積み重ねと試行錯誤がある。それは言葉を文章にする、書いて見なければ、考えられず表現できないことがたくさんあることを意味している。この訓練が、日本の教育・訓練体系の中に組み入れられていないのは残念である ...などと嘆いても仕方がない。
実践という意味では、すでに企業のホームページはXoopsを活用したCMSを採用して運営をはじめた。グループ内や個人レベルでの情報の整理と発信、共有にはMovable Typeを採用して試行を始めた。しかし、なぜ日本の経営というのは感度が鈍くスピードがでないのか?二ヶ月でできるのが二年以上かかるというのでは変化に対応できない。人が変わらなければ何も変わらないものなのだろうか?環境の変化を敏感に感じ取り、自らの考えを新たにして新たなやり方を実践していくことが求められる。"
2006-08-03 17:43:00
Free AOL: Too little, too late?"
米国時間2日、AOLがAOLソフトやEMAILをブロードバンドユーザに無料提供すると、親会社のタイムワーナーが発表した。これほど長く秘密をあきらかにせず躊躇していたのは最悪であるとの論調がメディアやアナリストの間にある。
AOLの利用者であれば、AOLメンバーから逃げ出し、豊富な無料のサービスが提供されているYahooやGoogleに移行したくなる。そうした利用者の目からみれば、専門家のコメントなど聞かなくともAOLのビジネスがおかしくなっているのはわかる。しかも、それは2001年にタイムワーナーと合併して1?2年でおかしくなった。
その頃からインターネット接続にAOLは使わず、EarthLinkやNetZero(当初は無料だった)をダイアルアップで使うようになり、BB接続に切り替えていくユーザが増えた。それは日本の急激なBB普及をみても明らかな時代の潮流であった。
そんな利用者の変化にも気づかずに、気づいていたとしても何の手も打てなかったのだろうか?1990年代後半、時代の寵児でもあったAOL(わたしには苦い事業経験だった)がその成功体験であるサブスクリプションモデルに執着しすぎたのが原因であろうか。
インターネット利用者が明らかに変わっているのに、そうしたお客の要求の変化に答えることができず経営者も変わらなかったことが業績不振を招いたのであろう。今年はじめでさえも伝統的なダイアルアップ接続の無料お試しキャンペーンをやっているAOLを知って驚いたものである。
利用者のAOL離れに歯止めがかからず、この一年で300万人のメンバーが脱退したという。ピーク時の2002年に3500万人だったメンバーが、いまや約半分の1770万人になった。たった3年半で半減する変化が現実に起こったのである。時代の潮流、それをつくる利用者の変化を読み取り、これに迅速に対応することの大切さを教えてくれる。
今回のAOLの対応は、遅すぎたと言わざるを得ない。少なくとも3年は遅い。しかも、EMAILをBBユーザに無料提供するくらいの手しか打っていない。アナリストや投資家たちはあきれている。なにもしないよりはいいのでNYSE株価は50セント上がったが、一過性のものだと思う。
タイムワーナー/AOL経営者は、「2008年から再び成長路線にもどる」といっているが、そのことを信じる人は少ないのではないか。すでにAOLの凋落は始まっていると言っても過言ではない。救いは、この一年で300万人ものメンバーを失ったにもかかわらず、オンライン広告収入が40%伸びたことである。あらたなビジネスモデルに事業を転換し競争に勝てるかが問われている。
LINK
"
2006-08-05 00:30:00,※攻撃対象になるSNS社会
SNSは、仮想世界における伝統的なコミュニティよりも安全である、と過信するのは危険である。友達の招待がないとSNSに参加できない。知り合いの知り合いが参加するので安全だ、とはいえない。 人口100人の村社会が互いに信頼し、自分の村は自分たちで守る。そのためには、明文化されていようが暗黙の了解であろうが、なんらかの「掟」が自然発生する。日本のかつての村社会で、その掟を破って村民100人の安全を脅かすようなことをすれば「村八分」になり、もうその村では生きられなくなる。そんな掟や法律、規範といったものがあって始めて村の安全と安心が保たれる。 ※つづき"
2006-08-05 02:43:00,Blinkx
昨年、Rupert Murdochsがオンライン市場への参入を加速するためにMySpaceを買収したが、おなじ頃に買収しようとしていたBlinkxは、その事業を順調に伸ばしているようである。
すでに約400万時間相当(6/14時点で、Yahoo!やGoogleを追い抜いた)のTVやviral videoがアップロードされており、見たい、知りたいものが簡単に検索できるというのを謳い文句にしている。たとえば, vlogパイオニアのひとりであるRocketboomのAmanda Congdonに関して放送されたTVニュースのアーカイブや最新のRocketboomビデオが簡単に検索でき、その場で見ることができる。メディアの新しい潮流のひとつである。 同社の検索エンジン、"blinkx Pico"は無料で提供(今年3月から)されている。世界最小(1MB)の検索エンジンとのこと。テクストを扱うアプリケーション、ワープロやメールソフト、ブラウザーに住み着いて、そこで使っているコトバに関連した情報を自動的に検索して表示してくれる優れものである。検索対象は、news, blogs, video, Web, Wikipedia, images, and "people"で、MySpaceを代表とするオンラインコミュニティからの情報が含まれる。 Bruce Clay, INC's Search Engine Relationship Chart ? ihelpyou, INC's Search Engine Partnership Chart"
2006-08-05 07:03:00,Warming Bra unveiled in Japan
Warming Bra unveiled in Japan Warming Bra unveiled in JapanLingeriemaker Triumph unveiled it's answer to Japan's Warmbiz campaign - a Warmbiz bra."
2006-08-05 21:22:00,Al Camarani Dance
2006-08-09 22:01:00,新しいソフトウェア
平成13年度未踏ソフトウェア創造事業 初心者による3次元アニメーションの構築と利用のためのインタフェースhttp://www.ipa.go.jp/NBP/13nendo/13mito/mdata/6-51.htm 開発者:五十嵐 健夫(東大ポストドクター)http://www-ui.is.s.u-tokyo.ac.jp/~takeo/index-j.html 2002年東大・講師、現在:大学院情報理工学系研究科・助教授 パロアルトでteddy、プロビデンスでsweater作った。 月曜の朝から日曜の夜まで熱中(集中が大切) SIGGRAPHを舞台に世界に通用する新しい技術を研究 ブラウン大学(昔からCG研究で名高い)在職中の仕事 思いついたアイデアうぃJavaを使って短期間にプロトタイピング この技術の芽をビジネス化するプロが必要とされている 別の視点では、日本はこの目利きに劣る SIGGRAPH2006でSignificant New Researcher Awardを受賞(7/31) Keynote Address: From Myth to Mountain: Insights Into Virtual Placemaking Joe Rohde Joe Rohde is an Executive Designer and Vice President with Walt Disney Imagineering. He is currently in charge of design and development for Disney's Animal Kingdom at the Walt Disney World Resort in Lake Buena Vista, Florida. Joe has led conceptualization, design, and production for Disney's Animal Kingdom since its inception in 1990. 成長期には巨大な権威が業界に影響を与え、研究だけでなく産業新興に大きな役割を果たした。最近は巨大になりすぎて、官僚化もすすみ、論文選考にしても一部の人間に権力が集中するようになり不公平さが目立つようになったようである。某グラフィックス教授が反旗を翻している。http://www.cs.utah.edu/~michael/leaving.html"
2006-08-09 22:55:00,※Naur名誉教授がACMチューリング賞を受賞
ACMの賞にはいろいろある。一番有名なのは、チューリング賞で2005年度は、コペンハーゲン大学のPeter Naur名誉教授が受賞した。あの有名なAlgol60開発者であり、BNF(backus-Naur Form)をつくった一人である。今日までのプログラミング言語設計とその発展の基礎を築いた。「正しいプログラムを書くための方法論」の先駆者で、構造化プログラミング(goto-less programminngともいわれた)の提唱者としても名高い。彼のコンセプトを継承し発展させたことで名をはせたのが、 Floyd, Dijkstra, Hoareたちである。 LINK"
2006-08-10 00:14:00,男女の節目は87の倍数
三千年前の中国の医学書には、 "男性は8の倍数で節目をむかえ、 女性は7の倍数で節目をむかえる" と書かれています。 --------------------------------------- 男性の場合
8歳・・ 毛髪が完全に成長し、歯が生えかわる 16歳・・精液ができ、子供をつくれるようになる 24歳・・肉体が成熟し、親しらずが生える 32歳・・腎精の頂点(これを境に精力が落ちていく↓) 筋肉と骨が完成し、もっとも充実した身体になる 40歳・・髪や歯が抜けはじめる(腎のパワーがおとろえはじめる) 48歳・・顔の張り、つやがなくなり、白髪が目立ちはじめる 56歳・・精液が少なくなり、老衰をはじめる --------------------------------------- 女性の場合
14歳・・初潮がはじまる 28歳・・女性としてのピークをむかえる 49歳・・閉経をむかえる ---------------------------------------
注意すべきなのは、20代なのに白髪が生えていたり 幼い頃から病弱で体力がない人。このような人は 早くから精力がなくなりはじめるので注意が必要です。
もちろん個人差がありますが、精力のおとろえの原因は 先天的なもの、加齢慢性病などが主なものです。しかし、 若い頃からの過労、不摂生も深く関係しています。
過労にはストレスなどの精神的なもの、セックス、 自慰の過剰によるものがありますので注意しましょう。
仕事をバリバリやり続けていくためには、 精力が必要不可欠です。 精力は夜早く寝るとたくわえられます。ですから、 なるべく早く寝るよう心がけることとが大事です。
"
2006-08-10 02:40:00,Google Sketchup
昨年7月のMacworldで Best of Show Awards を受賞した。Macで最初に開発されたが現在はWindowでもリリースされている。建築設計用でUS$495で販売されている。@Last Softwareが開発した。 今年3月にGoogleが買収し、Google Sketchupの無償配布を開始した。また6月にはGoogle Earthおよび3D Warehouseとの連携(plugin)もリリースされている。"
2006-08-10 03:18:00,Windows Live
| 製品名(開発コード名) | 概要 | 競合相手 | ステータス |
| Windows Live Mail (Kahuna) | Hotmailの後継サービス。Outlookのような普通の電子メールプログラムに近い。 | Yahoo Mail、Gmail | 3月に"M5"ベータテスト(約90万ユーザー)を実施 |
| Windows Live Search | Microsoft社内開発の検索エンジン | Google、Yahoo、Accoona | 先週パブリックベータが公開に |
| Windows Live Local | 地図、道順案内サービス(俯瞰、路上イメージ) | Google、Yahoo | 12月にパブリックベータが公開に |
| Windows Live Search Mobile | 独自検索エンジンのモバイル版 | Google、Yahoo | ベータ |
| Windows Live Expo (Fremont) | 無料のオンラインマーケットプレース。ソーシャルネットワークのメンバー限定での取引可能。 | Craigslist、eBay | 米で限定的なパブリックベータテストを実施。 |
| Windows Live Family Safety Settings(Vegas) | ペアレンタルコントロール用ツール | Net Nanny | 限定ベータテストを実施(1万ユーザー以下を対象)。初夏にパブリックベータテストを予定。 |
| Windows Live OneCare (A1) | ウイルス対策サービス(サブスクリプション形式) | Symantec、McAfee | ベータテストを実施(31万5000人を対象) 6月に有料サービス開始予定。 |
| Windows Live Video Warhol | ユーザーが作成したビデオ | YouTube、Google Video | 未公開 |
| Windows Live Messenger | MSN Messengerの後継サービス。ソーシャルネットワークや連絡先共有機能が追加に。 | Yahoo Messenger、AIM、ICQ、Gmail chat、Plaxo | ベータテストを実施(150万人を対象) |
| Live.com | 各種ガジェットやRSSフィードなどを提供 | MyYahoo、Google | ベータテストを実施(300万人を対象) |
| Microsoft Gadgets | JavascriptやHTMLで書かれた簡単なアプリケーション(Live.comやWindows Vistaで利用) | Yahoo Widgets、 AppleのDashboard | 160種類以上が入手可能 |
| adCenter (Moonshot) | 有料検索広告を配信。検索内容と検索者のプロフィールを組み合わせることが可能 | Yahoo、Google | シンガポールとフランスで提供開始。米ではベータ。MSNの有料検索広告の40%をまかなう |
| Windows Live Safety Center | ベーシックな無料ウイルス対策サービス | McAfee、Symantec | ベータ(2月末時点で130万台のPCをチェック。15万台のPCからウイルス除去) |
| Windows Live Favorites | オンラインのブックマーク管理サービス | - | 11月以来パブリックベータを提供 |
| Windows Live Custom Domains | Windows Live Mailを既存のドメイン名で利用可能にするサービス | 限定ベータ(米国のみ) | |
| Windows Live Toolbar | ウェブツールバーから各種のサービスにアクセス可能にする | Yahoo、Google | 先週ベータ公開 |
| Windows Live Answers | 事実に基づいたウェブクエリに対し直接答えるサービス | Yahoo Answers、Google Answers | スケジュールは不明 |
| Windows Live Clipboard | Ray Ozzieが提案。PCのテキスト用クリップボードに相当する手段をマッシュアップで実現 | - | - |
| Windows Live ID | 各種のLiveサービス用の認証ツール | Liberty Alliance | 2006年末までに公開予定 |
| Windows Live Mail Desktop | Windows Live Mail閲覧用のデスクトップアプリ | Google、Yahoo | 今月初期のベータテストへ。2006年末までに対象を拡大したテストを実施予定。 |
"
2006-08-10 04:28:00,GoogleとMySpaceが広告提携
Google pledges $900 million for MySpace honors Microsoft, Google, Yahoo Vie for MySpace Search Win Google Goes Sole Searching with MySpace, Fox <日本語関連記事> ・GoogleのMySpace向けの検索・広告サービスの提供 ・MySpaceをめぐり、グーグル、ヤフー、マイクロソフトが三つどもえの戦いへ ・マードック氏率いる米News社が「MySpace.com」を買収 ・米SNS最大手のMySpace、Yahoo!やGoogleを抜いて米国一のサイトに ・Facebook: $750mil買収オファー蹴り、$25mil資金調達"
2006-08-10 04:45:00,SNSから始まる恋愛「ありえる」が6割以上
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20191867,00.htm --アイシェア調査ニューズフロント 2006/08/04 16:14 トラックバック(19) コメント(0) コメントする アイシェアは8月4日、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)の利用実態に関してユーザーにアンケート調査した結果を発表した。それによると、SNSに1日10回以上アクセスしているユーザーは全体の12.2%。このうち56.4%は1日3時間以上をSNSへのアクセスに費やしているという。また42.5%は「SNSに依存している自覚がある」と回答した。 携帯電話からSNSにアクセスしたことのあるユーザーは30.0%。1日10回以上アクセスするユーザーでは、71.8%が携帯からSNSにアクセスしたことがあると回答した。 またSNSユーザーのうち、ユーザー同士で実際に顔を合わせるオフラインミーティング(オフ会)へ参加した経験があるのは34.4%。1日10回以上アクセスするユーザーでは、この割合は65%だった。 このほかユーザー全体の33.4%がSNS上で昔の知人に再会した経験があり、1日10回以上アクセスするユーザーでは62.5%に達した。「頻繁なアクセスは、再会の喜びや、趣味から始まった出会い、恋愛への期待からくるもの」(アイシェア) 「SNSから始まる恋愛がありえると思うか」という質問に対しては、ユーザー全体の66.1%が「ありえる」と回答した。1日10回以上アクセスするユーザーでは、この割合は82.5%だった。 調査は7月26日?28日の期間、インターネット上で実施した。有効回答数は860。性別内訳は53.8%、女性46.2%。"
2006-08-11 00:55:00,Innovation Leaders
www.innovationleaders.org主要20分野について、1000社の革新パフォーマンスを評価した結果を公表している。
These companies are today's Innovation Leaders Innovaro conducts an annual assessment of the innovation performance of 1000 companies across 20 key sectors. This is based on detailed research into 8 key areas that is summarised in an innovation scorecard Each section of this website provides: ? Individual profiles of each leading company ? Innovation scorecard and key data ? Sector overview ? Innovation drivers and ones to watch
|
The eight key areas that we research and input into the assessments are: 1. Organisational culture and supporting structure 2. Strategic focus on innovation and its role in driving corporate growth 3. Number of major new product launches and relative success ratios 4. Growth in revenues, profits and market capitalisation 5. Average margin per product or customer 6. Investment in innovation-related activities such as R&D and marketing 7. Brand value and human capital growth 8. Peer review from within the sector At a high level, across these firms, several common traits are evident: ? Strategic Focus ? There is a strong strategic focus on the role of innovation within their markets and the contribution that innovation makes to the business. ? Insight ? They have an excellent understanding of the marketplace, customers and an ability to configure products and services around emerging needs. ? Collaboration ? They clearly understand the core capabilities of themselves and their partners and work together to deliver innovative products and services. ? Process ? They have simple yet effective approaches to conceiving, qualifying, developing, and then quickly launching, new products and services. ? Organisation ? Roles, responsibilities and culture all support innovation while appropriate metrics are used to measure and reward successful innovation"
2006-08-11 03:20:00,A. Michael Spence
Prize Lecture
Signaling in Retrospect and the Informational Structure of Markets
 |
A. Michael Spence held his Prize Lecture December 8, 2001, at Aula Magna, Stockholm University. He was presented by Lars E.O. Svensson, Chairman of the Prize Committee. |
Presentation 1 min. ![]() ? Prize Lecture 40 min.
? Prize Lecture 40 min. ![]() ?
?
 The Nobel Laureates
The Nobel Laureates
Three Stanford Business School faculty members have been awarded the Nobel Prize in Economics in recent years.
 |
Michael Spence Philip H. Knight Professor, Emeritus and Dean Emeritus
In 2001, Spence shared the prize with George A. Akerlof of University of California, Berkeley, and Joseph Stiglitz of Columbia University. The three were honored for their work on signaling theory and credited by the Swedish Academy with creating the field of information economics.
In the 1970s, the three laid the groundwork for a theory about markets with so-called "asymmetric information." Their work explained how agents with differing amounts of information affect various markets. Their work has led to applications in areas ranging from agriculture to modern financial markets.
Related Links
Feature Story Prof. Spence's Nobel Speech Presentation Speech at 2001 Nobel Awards Ceremony Spence Prize Details Nobel Biography Faculty Profile
The Nobel Award Ceremony Stockholm, Sweden, December 10, 2001 ![]() Video File, 6:42 minutes A toast led by Dean Robert L. Joss, October 12, 2001
Video File, 6:42 minutes A toast led by Dean Robert L. Joss, October 12, 2001 ![]() Video File, 1:56 minutes (QuickTime? format) National Public Radio, October 11, 2001
Video File, 1:56 minutes (QuickTime? format) National Public Radio, October 11, 2001 ![]() Audio File, 9:09 minutes "Signaling Retrospect and the Informational Structure of Markets" Stanford Institute for Economic Policy Research, April 2002
Audio File, 9:09 minutes "Signaling Retrospect and the Informational Structure of Markets" Stanford Institute for Economic Policy Research, April 2002 ![]() Audio File, 11:00 minutes (Windows Media Player format)
Audio File, 11:00 minutes (Windows Media Player format) ![]() Video File, 3:30 minutes (Windows Media Player format) "The Changing Structure of the Global Economy"
Video File, 3:30 minutes (Windows Media Player format) "The Changing Structure of the Global Economy" ![]() Video File, 29:30 minutes GSB Last Lecture, 2004
Video File, 29:30 minutes GSB Last Lecture, 2004 ![]() Video File, 41:38
Video File, 41:38
"
2006-08-11 03:39:00,Net Impact 2005 Conference
http://www.gsb.stanford.edu/news/conferences_social.html
Bridging the Gap: Leading Social Innovation Across Sectors November 2005
Net Impact 2005: Doing Good Is Now Big Business More than 50 panel discussions ranging from green buildings to California's stem cell research initiative engaged 1,600 attendees at the 2005 Net Impact Conference, held at Stanford Graduate School of Business. [Details]
Businesses and Social Responsibility KQED's Forum, November 10, 2005 Michael Krasny interviews Kriss Deiglmeier, executive director at the Center for Social Innovation, about the issues covered at the Net Impact Conference. ![]() Audio File
Audio File
Keynote and Thought Leader Speakers
Gore
Al Gore Kicks Off Net Impact Conference Former Vice President Al Gore kicked off the conference at the Stanford Graduate School of Business, the largest annual gathering in the world for MBA students and young professionals focused on corporate social responsibility, social entrepreneurship, international development, and environmental management. [Details]
Video File, 1:20 hour
"
2006-08-11 03:45:00,Leadership
 Leadership
Leadership
At the Stanford Graduate School of Business, leadership means taking full responsibility for changing an organization for the better. The Business School takes the study and practice of leadership seriously and offers a variety of resources to support this important topic.
Leadership Resources
The Center for Leadership Development and Research List of books and other academic resources on leadership Course offerings in organizational leadership Public Management Program Stanford Center on Ethics Barbara and Bowen McCoy Center in Ethics in Society Executive Program in Leadership Executive Program for Nonprofit Leaders
Jack Welch, Retired Chairman and CEO, General Electric Encourage candor. If you reward candor, you'll get it. [Details] ![]() Video File, 1:03 hour
Video File, 1:03 hour
Anne Mulcahy, CEO, Xerox Effective communication is the single most important component of the company's successful turnaround strategy. If you spend as much time listening as talking, that's time well spent. [Details] ![]() Video File, 29:14 minutes
Video File, 29:14 minutes
"
2006-08-11 04:37:00
Coming soon, television over the web"
And sooner than you may think, says a study Aug 1, 2006 Accentureがエグゼクティブ302人にインタビューした結果、現時点でIPTVが収入をもたらすことに自信を示しているのは4%にすぎない。しかし、今後3年間を考えたときは37%の、長期的には57%のエグゼクティブは大きな事業チャンスがあると思っている。主な収入源がVODで広告収入は6番目に上げられた。
Two years ago the big thing was VoIP, telephone over the internet. The new big thing is TV over the internet, and it's a tempting big new thing indeed, promising to represent a real challenge to cable. At the least, it stands to force down the high price consumers pay to watch television. And as a competing distribution stream, IPTV could also usher in a flood of new, innovative programming choices.
The question is when? Technologies on the horizon have a way of staying on the horizon, defying their promoters' promises of sweeping through the marketplace any minute now. Link
|
Top 25 parent companies Through July 23 |
||||
|
# |
Parent |
Unique Audience (000) |
Reach % |
Time Spent per Person (hh:mm:ss) |
|
1 |
Microsoft |
76,290 |
58.6 |
0:41:29 |
|
2 |
Yahoo! |
70,081 |
53.8 |
1:05:09 |
|
3 |
Time Warner |
65,932 |
50.6 |
1:38:20 |
|
4 |
|
62,993 |
48.4 |
0:22:28 |
|
5 |
News Corp. Online |
33,119 |
25.4 |
0:44:01 |
|
6 |
eBay |
31,813 |
24.4 |
0:48:47 |
|
7 |
InterActiveCorp |
25,068 |
19.3 |
0:14:03 |
|
8 |
Amazon |
18,942 |
14.6 |
0:13:12 |
|
9 |
Landmark Communications |
17,602 |
13.5 |
0:26:46 |
|
10 |
Apple Computer |
16,702 |
12.8 |
0:33:23 |
|
11 |
Walt Disney Internet Group |
16,557 |
12.7 |
0:24:33 |
|
12 |
RealNetworks, Inc. |
16,178 |
12.4 |
0:27:37 |
|
13 |
YouTube |
15,821 |
12.2 |
0:14:05 |
|
14 |
New York Times Company |
14,254 |
11.0 |
0:08:18 |
|
15 |
Verizon Communications |
12,554 |
9.6 |
0:14:56 |
|
16 |
United Online |
12,048 |
9.3 |
0:33:57 |
|
17 |
Bank of America |
10,839 |
8.3 |
0:28:03 |
|
18 |
CNET Networks |
10,646 |
8.2 |
0:09:32 |
|
19 |
AT&T Inc. |
10,427 |
8.0 |
0:18:17 |
|
20 |
Wikipedia |
10,179 |
7.8 |
0:08:38 |
|
21 |
E.W. Scripps Company |
9,921 |
7.6 |
0:06:06 |
|
22 |
Gannett |
9,397 |
7.2 |
0:10:49 |
|
23 |
Comcast Corp. |
9,230 |
7.1 |
0:26:26 |
|
24 |
Viacom |
9,138 |
7.0 |
0:28:13 |
|
25 |
Expedia |
8,571 |
6.6 |
0:12:53 |
|
Source: Nielsen//NetRatings |
||||
最新月間視聴率ランキング "
2006-08-11 04:40:00,Top 25 brands
2006-08-11 04:59:00,Top 25 advertisers
Top 25 advertisers (excludes house ads)
Through July 23
|
# |
Company | Impressions (000) |
| 1 | GUS Plc | 7,271,586 |
| 2 | Verizon Communications, Inc. | 1,719,905 |
| 3 | NexTag, Inc. | 1,697,866 |
| 4 | United Online, Inc. | 1,632,021 |
| 5 | Netflix, Inc. | 1,333,910 |
| 6 | Low Rate Source | 1,135,391 |
| 7 | Vonage Holdings Corp | 941,604 |
| 8 | Echostar Communications Corporation | 830,989 |
| 9 | HSBC Holdings plc | 818,669 |
| 10 | Apollo Group, Inc. | 798,903 |
| 11 | Providian Financial Corporation | 654,418 |
| 12 | Time Warner Inc. | 548,576 |
| 13 | Cablevision Systems Corporation | 525,870 |
| 14 | YourGiftCards.com | 517,132 |
| 15 | Bank of America Corporation | 509,316 |
| 16 | American InterContinental University | 503,342 |
| 17 | Reunion.com L.L.C. | 482,941 |
| 18 | QuinStreet | 436,465 |
| 19 | Monster Worldwide, Inc. | 431,441 |
| 20 | E*TRADE FINANCIAL Corp. | 379,895 |
| 21 | Dell Computer Corporation | 376,322 |
| 22 | ConsumerSavingCenter.com | 354,702 |
| 23 | Scottrade, Inc. | 347,374 |
| 24 | ConsumerPromotionCenter.com | 341,915 |
| 25 | Skype Technologies S.A. | 314,808 |
|
Source: Nielsen//NetRatings AdRelevance |
||
Top 25 advertising sites (excludes house ads) Through July 23
|
Company |
Impressions (000) |
|
| 1 | Yahoo! | 17,715,126 |
| 2 | MySpace | 8,060,993 |
| 3 | MSN | 3,935,012 |
| 4 | AOL.com | 707,742 |
| 5 | eBay | 524,203 |
| 6 | The Weather Channel | 473,286 |
| 7 | Juno | 439,635 |
| 8 | CNN | 393,050 |
| 9 | iWon | 335,618 |
| 10 | NetZero | 332,410 |
| 11 | New York Times | 330,816 |
| 12 | MSNBC | 272,073 |
| 13 | YouTube | 266,759 |
| 14 | FOXNEWS.COM | 235,542 |
| 15 | Pogo | 225,609 |
| 16 | IMDb | 218,445 |
| 17 | Realtor.com | 214,196 |
| 18 | The Weather Underground | 212,974 |
| 19 | Excite | 193,202 |
| 20 | EarthLink | 172,652 |
| 21 | About.com | 167,535 |
| 22 | Drudge Report | 161,806 |
| 23 | Forbes | 151,540 |
| 24 | ESPN.com | 148,427 |
| 25 | Comcast.net | 137,315 |
|
Source: Nielsen//NetRatings AdRelevance |
||
Average use Through July 23
|
Current Week |
Last Week |
% Change |
||
| Sessions/Visits per Person | 16 | 16 | 0 | |
| Domains Visited per Person | 37 | 38 | -2.63 | |
| PC Time per Person | 15:59:36 | 16:31:42 | -3.24 | |
| Active Digital Media Universe | 130,189,910 | 128,663,401 | 1.19 | |
| Current Digital Media Universe Estimate | 209,091,770 | 209,029,180 | 0.03 |
Source: Nielsen//Net Ratings AdRelevance
"
2006-08-11 05:42:00,MySpace
Myspace.com Becomes Most Trafficked Website In US Surpassing Google And Yahoo
NEW YORK (Reuters) - Online teen hangout MySpace.com ranked as the No. 1 U.S. Web site last week, displacing Yahoo Inc.'s top-rated e-mail gateway and Google Inc.'s search site, Internet tracking firm Hitwise said on Tuesday. News Corp.'s MySpace accounted for 4.46 percent of all U.S. Internet visits for the week ending July 8, pushing it past Yahoo Mail for the first time and outpacing the home pages for Yahoo, Google and Microsoft's MSN Hotmail. Link MySpaceはSNSの代名詞になり、SNSを超えた社会現象になっている。ポータルサイトとしてもYahooやGoogleを追い抜いたという報告もある。SNSでは80%を占有しており、第二位FaceBook(7.6%)以下の追随を許さなくなっている。FaceBookは数の論理ではなく、大学生というコミュニティに根をおろすのが狙いのようである。登録には大学が発行する.eduのEメールアドレスを必要としている。昨年9月時点での登録者数は340万人、月間のページビュー数は30億であった。その時点で、SNSの草分け的存在のFriendsterの4倍の訪問者(220万人)がいた。そして、そこに音楽サービスを充実させティーンズをターゲットにしたMySpaceが急速に会員を増やしていたのである。変化のスピードは速い。半年後にはMySpaceは独走体制に入ったというわけである。
"
2006-08-11 06:10:00,Mashup Camp 2,
マウンテンビューにあるコンピュータ歴史博物館で先月7月12日と13日に「Mashup Camp 2」が開催された。マッシュアップの仕掛人がアイディアを持ち寄り、オープンな議論を通じてアイディアに磨きをかける。企業側からの注目度も高く、Adobe、AOL、Google、Intel、Microsoft、Sunなどがスポンサーに名を連ねている。1回目からの変更点としては「Mashup University」というトレーニングセッションの追加だ。講師はスポンサー企業(APIの提供者という立場から......)や著名な開発者である。Mashup全体で見れば、開発者のアイディア交換会の場であるCampに、Universityが追加されたことで、ビジネス側からのアプローチとのバランスが図られた形になる。言い換えれば、アイディアだけではなく、いかにビジネスとして成立させるかがMashupの議論のポイントになっている。
2006-08-11 06:17:00,Cambrian House
Cambrian House Mission Statement Cambrian House's mission is to discover and commercialize software ideas through the wisdom and participation of crowds. Contributors earn royalties, sharing in the success of the products.
How it Works

 |
You think itMost aspiring entrepreneurs and armchair innovators have more ideas than resources. Why let the fruits of your genius languish on the vine? They're yours to grow. Put them in play. |
 |
Crowds test itBut don't buy that Mercedes just yet. Before we greenlight production, your freshly baked ideas run the consumer gauntlet. Flourish or flounder? The market decides. |
 |
Crowds build itSo the people have spoken, and they love your idea. With the help of the worldwide development community, we turn it into reality. Contributors can take their pick of exciting projects, and in return, they get a piece of the royalty pie. |
 |
We sell itShow time! YourIdea 1.0 hits the virtual shelves with all the marketing power of Cambrian House behind it and with a little help from Chameleon. Every contributor ? including you ? has a vested interest in helping the product shine, because every contributor benefits from its success. |
 |
You profitWhen we say "every contributor benefits |
we don't mean warm and fuzzy feelings. We mean real money. When you collaborate with Cambrian House, you get Royalty Points. That means as long as the product generates profit, so will you.
Whoa - that seems like a lot of steps but really it's not as hard as it looks. We guide you through the entire process and keep you in the loop. We take care of you! Try submitting an idea today.
http://www.cambrianhouse.com/google/ http://www.innocentive.com/ http://www.istockphoto.com/index.php"
2006-08-11 07:59:00,Netflix
NetFlixのCEOであるReed Hastingsは、「Starbucksがビジネスのヒントを得た。顧客の満足度、それが成功のポイントだ。」という。ビデオレンタルの二台巨頭を脅かすNetflixのビジネスモデルはオンラインとメールオーダーの組み合わせで、2001年末の年末商戦後、DVDがヒット商品となり、それが同社ビジネスの発展につながった。今後は、CinemaNow(日本法人は2005年1月設立、今年1月BIGLOBEと配信提携)などのVODやデジタル・ケーブルTVとの競争が激しくなる。2004年末からはSNS機能を採用しコミュニティ化を進めている。また、同時期からBlockbusterやWalmart、AmazonもNetflixと同様のインターネット+郵送のDVDレンタルを始めている。Netflixが提供する6万タイトルがお客をひきつけている。メジャーではないタイトルも揃えると、それを目当てで集まる客で繁盛するということ。いわゆるLong Tailである。"
2006-08-11 20:39:00,Computerworld記事リンク
- 「Web 2.0系情報共有ツール」企業での活用法を考える
- IBMがファイルネットを16億ドルで買収──大再編が進むECM市場
- 2005年の国内ERM市場、前年比3.5%増の8,089億円
- 2005年の国内ERM市場、前年比3.5%増の8,089億円
- Web 2.0でビジネスを変革する!【前編】
- 最新のWeb技術が企業ITにもたらすメリットとは
- Web 2.0でビジネスを変革する!【後編】
- Ajaxを採用し、顧客起点の中古車紹介サイトの構築に挑んだヤマトリース
Social Bookmark
多くの人がブックマークしたページのほうが有用と判断する
CMS
- XOOPS
- TikiWiki
- DotNetNuke (asp.net利用)
Web 2.0を構成するトレンドを質的変化と量的変化の観点から示した概念図(出典:フィードパス 小川浩氏)
2006-08-12 00:35:00,SaaS Providers
- @Road
- 24SevenOffice
- 37signals
- Acquity Group
- Apptix
- Ariba
- CollabNet
- CSC
- ebdex
- eMeta Corporation
- Exact Software
- Intuit
- Journyx
- Microsoft
- NetSuite
- RightNow Technologies
- Salesforce.com
- Serials Solutions
- SPS Commerce
- Twinfield
- WebEx
"
2006-08-12 00:59:00,Salesforce.com記事
![]() これからはヤフオクもセールスフォースで管理? (@ITNews)
これからはヤフオクもセールスフォースで管理? (@ITNews) ![]() セールスフォースが次に目指すのは"ビジネスウェブ" (@ITNews)
セールスフォースが次に目指すのは"ビジネスウェブ" (@ITNews) ![]() "オンデマンドWindows"になりたい、セールスフォース (@ITNews)
"オンデマンドWindows"になりたい、セールスフォース (@ITNews) ![]() Salesforce.comの新サービスは"iTunes+eBay" (@ITNews)
Salesforce.comの新サービスは"iTunes+eBay" (@ITNews) ![]() Salesforceがカスタマイズで「Google Maps」と連動 (@ITNews)
Salesforceがカスタマイズで「Google Maps」と連動 (@ITNews) ![]() セールスフォース、新プラットフォーム搭載で機能強化 (@ITNews)
セールスフォース、新プラットフォーム搭載で機能強化 (@ITNews) ![]() ケータイでWebサービスと直接通信、セールスフォースの挑戦 (@ITNews)
ケータイでWebサービスと直接通信、セールスフォースの挑戦 (@ITNews) ![]() 「他社は勝負にならない」、業績好調のSalesforce.com (@ITNews)
「他社は勝負にならない」、業績好調のSalesforce.com (@ITNews) ![]() Salesforce.com、新製品「Customforce 2.0」を発表 (@ITNews)"
Salesforce.com、新製品「Customforce 2.0」を発表 (@ITNews)"
2006-08-12 02:08:00,Google Code
この試みの戦略的意味を考えたい。 http://code.google.com/hosting/"
2006-08-12 18:00:00,Zimbra
Feedpath社が日本語化中で、SaaSとして法人向けの提供を計画している。年内に開発を終えて来年に正式版を提供の予定。Feedpathの法人向け情報共有ポータルとして"Wolf"が11月にリリース予定。Zimbraとの連携は未定のようである。 Web2.0代表企業とメディアはとらえているが、経営陣の出身母体であるサイボーズ・ビジネスはどうなるのでしょう。今年の最新版を導入したが、数年前のものと代わり映えがしない。それどころかレスポンスが遅くなっていらいらさせられる。サイボーズのせいではなくインストール環境の変化によるものかもしれないが、それは利用者には分からない。ベンダーはインストール環境まで踏み込んでエンドユーザの満足度を把握し、これに迅速に対応しないと減点される運命に陥る。"
2006-08-12 23:06:00,AppExchange
「The Future of Software」
"
2006-08-13 04:27:00,Web2.0 by Beniof
Web 2.0 サービスの代表例として Writely、Num Sum、Google Spreadsheets などを取り上げ、そしてこれらの「コンシューマ・アプリケーション」と同じ使い勝手がビジネスの場でも導入されるべきと説いた。 ソフトウェアの「民主化」を進める! エコノミー、マーケティング、そして IT セールスフォースのCEOが来日、ソフトウェアの未来像を語る - ZDNet Japan 「SaaSが企業向けアプリケーションの"標準"になる」、米Salesforce.com会長:ITpro 当日のセミナー関連記事(抜粋) 1) IT Pro(2006/7/7) 「「SaaSが企業向けアプリケーションの"標準"になる」、米Salesforce.com会長 」 http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20060707/242819/ 2) Enterprise Watch(2006/7/7) 「「アプリケーションはパッケージからサービスに」?米salesforce.comベニオフCEO」 http://enterprise.watch.impress.co.jp/cda/topic/2006/07/07/8215.html ▼その他の掲載記事はこちらをご覧下さい▼ http://www.salesforce.com/jp/newsevents/news.jsp
-
9 2006/05/25 空白の1年...「ローマの休日」は誰のもの?
動いた。昨年11月、ゲイツは「サービスとしてのソフトウエア(SaaS)」分野への参入を発表。「ソフトというものへの概念に革命が...
-
10 2006/05/11 SaaSのセミナー
今日は、あるセミナーに行ってきました。お題は、SaaS(SoftwareasaService)です。日本語Wik...で働いたあと、NetSuite、Siebelと今話題の有名なSaaS企業を渡り歩き、最終的に今は自分でSaaSの会社を作ってるそうです。今までのエンタープライズ向けソフトウェアと、SaaSだと何が違うのか、ということをいろんな視点で語ってくれまし...
"
2006-08-13 04:31:00,ITベンチャーが守るべき7ヶ条
ボストンで行われている TiECON East 2006 というカンファレンスで、"Future of Software"というパネルディスカッションが行われ、そこで「ITベンチャーが守るべき7ヶ条」なるものが提言されたそうです:
■ Kleiner Perkins 7 rules for software start-ups (Don Dodge on the Next Big Thing)
ベンチャーキャピタルの Kleiner Perkins のパートナー、Ajit Nazre 氏の意見とのこと。7ヶ条を翻訳してみるとこんな感じ:
- ユーザーがすぐに価値を手にできるようにせよ -- 初めて使った瞬間から、何か問題が解決できたり、価値が実現されるようにしなければならない。
- クチコミを利用しろ -- プッシュ型ではなく、プル型で利用者を増やせ。営業部隊は必要ない。
- 追加で必要なIT技術(ソフト/ハード)はできるだけ少なく(ゼロが望ましい)。SaaSがベストだ。
- シンプルで直感的なユーザーインターフェースを。トレーニングなしでも操作できるように。
- カスタマイズ可能にして、各ユーザーがパーソナライズされた経験ができるようにせよ。
- テンプレート等を活用し、コンフィグレーションが簡単に行えるようにせよ。
- コンテクストを意識せよ -- 使われる場所、グループ、端末など、状況に応じて最適なサービスを提供するように。
Kleiner Perkins の経験では、少なくとも上記のうち5つのルールをクリアしていないと、ビジネスモデルを再考した方が良いとのこと。
どれも大切なルールで、これまでも様々な方々が主張されていることだと思いますが、7つ目のルールはユニークなのではないでしょうか。確かにブロードバンド網・ワイヤレス接続が一般化し、様々な端末が普及した現在では、これまで以上に「ユーザーがどのような場面でどのようにサービスを使うか」を想像するのは難しくなっています。しかしそのようなコンテクストを無視するのではなく、積極的に対応して初めて、ユーザーを満足させることができるというアドバイスではないかと感じました。
また個人的にですが、この7つ目のルールは『発想する会社!』の中にある「動詞で考える」という発想に近いのではないかと感じました。例えば写真共有サービスをデザインするとしたら、「写真共有」という名詞で考えるのではなく、それを様々な形で動詞化して考えてみる -- 「写真共有にアップロードする」「?からダウンロードする」「?で遊ぶ」「?で儲ける」「?で誰かを楽しませる」などなど -- ことで、「サービスが使われる場面=コンテクスト」を幅広く把握することが可能になるのではないかと思います。
"
2006-08-13 09:22:00,Is Slashdot the future of media?
The most popular site for the tech cognoscenti is created entirely by its users and readers. By David Kirkpatrick, FORTUNE senior editor February 10, 2006: 10:02 AM EST
NEW YORK (CNNMoney.com) - If you want to see the future of media, go to Slashdot.org.
Two things distinguish it -- it's the most popular news and information site with the tech cognoscenti, particularly programmers and engineers. And all of its content is created by its users. They submit about 700 stories per day, which staff editors vet and reduce down to the 30-35 that get published. Of the site's 5.5 million unique visitors per month, about 25 percent post comments about those stories.
"
2006-08-15 03:32:00,Web2.0
少量制作大量コピー時代から、大量制作超大量コピー時代へCSSを使いこなす [R30] YouTube?Google型企業になるための4つの法則 My Life Between Silicon Valley and Japan"
2006-08-15 19:11:00,Blogger Charlie's FAME
It came to my attention that Charlie posted "FAME" message when I was trying out how 360 works.
Here's his message on the top profile(?) page;
Want to be my friend? Suddenly a lot of people do. Check out the highlighted blog post FAME before you invite me.--> Click here Reply
Should you find the "FAME" message if you click it.
How am I going to deal with this? I have had 40 invites to add me to your friends list in the past ten hours! I am so flattered I can hardly keep from blushing! But I am on a 28.8 KBPS dial-up. It takes about 15 seconds just to go from the list to an individual message, and another 15 seconds to go back to the list.........
I do understand what a mess he faced because I did have a similar experience long time ago, let's see, circa 1990. At that time "emerging communication technologies" were commercializing and availavle for "Nerds" The new dial-up modem claimed to achieve 14.4 Kbps you could afford to buy at just a few hundred dollars !!!
I click my "HOME" on the newly created 360 page and noticed Charlie's thumbnail with other two ladies. I wondered what that is! Why they appeared on my "HOME"!
Anyway I clicked Charlie's, not the pretty woman's one. I felt comfotable with his lifestyle and his pictures so that I wanted to subscribe his 360 blog. While I tried to find a button to "add favorite" or "Friend", I did notice his message on the top of the page and went through his post titled "FAME".
What an idiot I am, at first I thought he would have talked about celebrity as his friend. In any case I realized his trouble with a lot of request to be a friend, frustration and difficuly of reviewing them on 28.8 Kbps dial-up.
You click "Add Friend" button, and notice the check box "Invite Friend". If you send with no check, you can add it to your "Favorite" blog. Somehow it makes me confuse.
When you click the "Add Friend" button at second time, you'll see a different page with "default message" Yahoo 360 staff prepared. People just click, click.... to add friend without any personal message explaining why they want to be a friend.
This caused his trouble.I am impressed with his courtesy and politeness in the way of notifyng people who clicked "Add Friend" button. Most people just neglect the requests in cyberspace.
"
2006-08-15 22:45:00,プロシューマ
Flickr, Slide, iFilm, blip.tv, rocketboom(25%)などで一般ユーザが作品をアップロードしメンバーと共有することが普通になってきた。カメラ付携帯電話、デジタルカメラ、DVカメラ、ブロードバンドの普及があたらしいコミュニティを生む素地となっている。広告モデルとその収入の安定化が、無料のコミュニティサイト提供に拍車をかけていることも間違いない。その時流に乗り遅れたAOLは大きな戦略転換を余儀なくされているのもその現れである。 一般の人たちが自分で作成した写真やビデオを公開し友達と共有して楽しむ・・・そんな世界が一般化していることをどう表現すればよいかを考えていて、「プロシューマ」という古いコトバを思い出した。 記憶が曖昧なのでWikipediaで調べた。 1972年、Marshall McLuhan と Barrington Nevitt が著書「Take Today」の中で、「電子技術の進展により消費者(Consumer)が生産者(Producer)になる日がくるだろう」と述べた。そして1980年に未来学者 Alvin Toffler が『第三の波The Third Wave』で、生産者と消費者の役割があいまいになり両方の顔を併せ持つ人が出現することを予言し、そうした人のことをProsumerと呼んだ。それが mass customization の行き着くところであるという。 ところで日本の用語辞典では、多少異なった解釈がされているようだ。 1分で用語はやわかり![]() では「先見的な消費者(pro-active con-sumer)あるいはプロフェッショナルな消費者(pro-fessional con-sumer)のこと。商品に対する知識が豊富にあり、使いこなす高度な能力を持つ消費者であるとすると、たとえば、ハイエンド・マシンにプロフェッショナル・バージョンのソフトウェアをインストールし、プロ並みの成果物を産み出すパワー・ユーザーがこれにあたる。」と解説している。 @nifty:デジタル用語辞典:プロシューマーは、「Consumer(消費者)とProfessional(専門家)を合わせた造語。Apple社は映像や音楽表現においてプロなみの技術をもったアマチュアをプロシューマーと呼んでおり、自社製品の重要なターゲット層としている。」と説明している。 また、『プロシューマ開発型』という用語があり、「商品メーカー(プロデューサ)と消費者(コンシューマ)が、共同で商品・サービスを開発していくことを意味する」(日本総研)と定義している。 アルビン・トフラーの予言は現実となっていることは間違いない。彼の"
では「先見的な消費者(pro-active con-sumer)あるいはプロフェッショナルな消費者(pro-fessional con-sumer)のこと。商品に対する知識が豊富にあり、使いこなす高度な能力を持つ消費者であるとすると、たとえば、ハイエンド・マシンにプロフェッショナル・バージョンのソフトウェアをインストールし、プロ並みの成果物を産み出すパワー・ユーザーがこれにあたる。」と解説している。 @nifty:デジタル用語辞典:プロシューマーは、「Consumer(消費者)とProfessional(専門家)を合わせた造語。Apple社は映像や音楽表現においてプロなみの技術をもったアマチュアをプロシューマーと呼んでおり、自社製品の重要なターゲット層としている。」と説明している。 また、『プロシューマ開発型』という用語があり、「商品メーカー(プロデューサ)と消費者(コンシューマ)が、共同で商品・サービスを開発していくことを意味する」(日本総研)と定義している。 アルビン・トフラーの予言は現実となっていることは間違いない。彼の"
2006-08-15 22:47:00,Spin
Jo Moore http://en.wikipedia.org/wiki/Cherry_picking"
2006-08-16 00:00:00,News Clip
■「Web 2.0系情報共有ツール」企業での活用法を考える ?Wiki、ソーシャル・ブックマーク、CMS......個性的なツールが多数登場? http://www.computerworld.jp/track.html?6783.000000016434 http://www.computerworld.jp/ist/index.html/ ■[米国]「本格的な」サイバー組織犯罪グループの台頭にFBIが警鐘 http://www.computerworld.jp/track.html?6787.000000016434 ■[米国]グーグル、危険サイトへのアクセスを警告する新機能を追加 http://www.computerworld.jp/track.html?6789.000000016434 ■[米国]IBMがファイルネットを16億ドルで買収──大再編が進むECM市場 http://www.computerworld.jp/track.html?6790.000000016434 ■[米国]「Google Checkout」のサービス遅延に不満の声が噴出 http://www.computerworld.jp/track.html?6791.000000016434 ■[米国]オープンロジック、オープンソース・ソフトの実装支援プログラムを開始 http://www.computerworld.jp/track.html?6792.000000016434 ■[米国]グーグル、広告付きビデオ・クリップを配信へ──今月からテスト開始 http://www.computerworld.jp/track.html?6796.000000016434"
2006-08-16 05:31:00,上野千鶴子
 バタフライが意味しているものは、機能性ではなくて、シンボル性です。ストリップ・ティーズは、男のもっている女性の身体に対するファンタジーに合わせて、女が演技します。そのファンタジーの求心点は当然女性器ですから、その周縁からまわりこんで行って、最後に求心点にストンと入る。その焦らしのテクニックの中で、最後に取り去る小さな布切れがバタフライです。つまり最後の部分を隠す、取るために隠す装置です。 パンティの起源はそれしかないのではないか、と思えてくる。そうでも考えないと、ブルマー型のパンティからいまのようなタイプのパンティへの変化は、断絶が大きすぎます。 『スカートの下の劇場』より"
バタフライが意味しているものは、機能性ではなくて、シンボル性です。ストリップ・ティーズは、男のもっている女性の身体に対するファンタジーに合わせて、女が演技します。そのファンタジーの求心点は当然女性器ですから、その周縁からまわりこんで行って、最後に求心点にストンと入る。その焦らしのテクニックの中で、最後に取り去る小さな布切れがバタフライです。つまり最後の部分を隠す、取るために隠す装置です。 パンティの起源はそれしかないのではないか、と思えてくる。そうでも考えないと、ブルマー型のパンティからいまのようなタイプのパンティへの変化は、断絶が大きすぎます。 『スカートの下の劇場』より"
2006-08-17 17:48:00,Birth of the PC
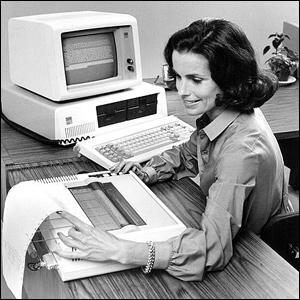 The IBM PC was announced to the world on 12 August 1981, helping drive a revolution in home and office computing. The PC came in three versions; the cheapest of which was a $1,565 home computer which had a 4.7Mhz processor and 16K of memory. The machine was developed by a 12-strong team headed by Don Estridge.
The IBM PC was announced to the world on 12 August 1981, helping drive a revolution in home and office computing. The PC came in three versions; the cheapest of which was a $1,565 home computer which had a 4.7Mhz processor and 16K of memory. The machine was developed by a 12-strong team headed by Don Estridge.
BBC News ![]()
"
2006-08-17 21:00:00,迷路にはまった
LiveJournalの設定を試していたらlook and feelがガラリと変わってしまった。最初に設定したスタイルがシンプルで気に入っていたのだが、もとに戻すことができない。選択肢が増えてどれだったのかわからない。 機能も増えて、bloggishというMovableType風スタイルも追加されていた。試しに設定したが、イメージが表示されなくなってしまった。何が原因かまったく不明で、リカバリに時間をとられそうである。 機能はシンプルなのが良い。複雑になって使いにくくなるのは困る。"
2006-08-17 21:21:00,画像の読み込みオプション
イメージの表示について原因が分かった。Firefoxの設定が影響していた。ツール→オプションで「画像を読み込む」かどうかを選択でき、読み込む場合でも「同じサイトにある画像のみ読み込む」かどうかを設定できる。 これがチェックされていたため、自分のサイトに置いた画像や他のサイトの画像にリンクしていると表示されない。 気がつくとなんでもないことだが、意外と気がつかずフラストレートすることが多いものだ。このことをメモしておかないとまた忘れてしまいそうである。ところでIE6ではおなじような現象を経験していない。「画像を読むこむ」の選択が用意されていないのかもしれない。"
2006-08-17 21:31:00,IT管理者のためのPCエンサイクロペディア
![]() ――基礎から学ぶPCアーキテクチャ入門―― 元麻布春男
――基礎から学ぶPCアーキテクチャ入門―― 元麻布春男
第14回 PCのエンジン「プロセッサ」の歴史(8)?Intelに挑戦し続けるAMD--2003/03/15
第13回 PCのエンジン「プロセッサ」の歴史(7)?デスクトップPC向けと袂を分けたサーバ向けプロセッサ--2003/02/19
第12回 PCのエンジン「プロセッサ」の歴史(6)?プロセッサの新時代を開く「Pentium 4」--2003/01/30
第11回 PCのエンジン「プロセッサ」の歴史(5)?P6時代の最後を締めくくった「Pentium III」--2002/12/26
第10回 PCのエンジン「プロセッサ」の歴史(4)?Pentium IIで始まった本格的P6時代--2002/12/11
第9回 PCのエンジン「プロセッサ」の歴史(3)?商業的には失敗だった「Pentium Pro」の功績 --2002/10/26
第8回 PCのエンジン「プロセッサ」の歴史(2)?性能向上に勤しんだ486/Pentium世代 --2002/08/31
第7回 PCのエンジン「プロセッサ」の歴史(1)?i8088からIntel386までの道のり--2002/08/17
第6回 本家IBM PCの歴史(4)?プラグ・アンド・プレイの普及とIntelの台頭--2002/07/16
第5回 本家IBM PCの歴史(3)?ローカルバスの興亡--2002/07/06
第4回 本家IBM PCの歴史(2)?IBM PCからPC互換機へ--2002/06/29
第3回 本家IBM PCの歴史(1)?IBM PC誕生--2002/06/14
第2回 日本のPC史を振り返る(後編)?PC-9801からPC互換機へ--2002/05/31
第1回 日本のPC史を振り返る(前編)?PC-9801の時代--2002/05/24"
2006-08-18 01:43:00,Web2.0 by example
| Web 1.0 | Web 2.0 | |
|---|---|---|
| DoubleClick | --> | Google AdSense |
| Ofoto | --> | Flickr |
| Akamai | --> | BitTorrent |
| mp3.com | --> | Napster |
| Britannica Online | --> | Wikipedia |
| personal websites | --> | blogging |
| evite | --> | upcoming.org and EVDB |
| domain name speculation | --> | search engine optimization |
| page views | --> | cost per click |
| screen scraping | --> | web services |
| publishing | --> | participation |
| content management systems | --> | wikis |
| directories (taxonomy) | --> | tagging ("folksonomy") |
| stickiness | --> | syndication |
"
2006-08-18 02:34:00,The Wisdom of Crowds
In this fascinating book, New Yorker business columnist James Surowiecki explores a deceptively simple idea: Large groups of people are smarterthan an elite few, no matter how brilliant?better at solving problems, fostering innovation, coming to wise decisions, even predicting the future."
2006-08-18 03:04:00,Greasemonkey
- Greasemonkey is a Firefox extension that allows you to writescripts that alter the web pages you visit. You can use it to make awebsite more readable or more usable. You can fix bugs that the siteowner can't be bothered to fix themselves. You can alter pages so theywork better with assistive technologies that speak to a web page aloudor convert it to Braille. You can even automatically retrieve data fromother sites to make two sites more interconnected. greasemonkey.mozdev.org
2006-08-18 03:25:00
Hardware, Software, and Infoware
Open Sources: Voices from the Open Source Revolution
もはやデスクトップアプリケーションや業務ソフトウェアはキラーアプリケーションになりえない。いまや、たとえばamazon.comがそれにあたる。Amazon.comで本を買いたいためにパソコンを買うのである。インターネットを使うためでもなくWebを利用するためでもない。 http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/tim.html(つづく)"
2006-08-20 22:49:00,※WordPress
二年前にダウンロードして試したことがある。投稿用ツールにバグがあり使いにくかったので中断した。Wikiも試したが、これは個人用パブリッシングではなく共同でドキュメントをレビューしながら作り上げていくときのプラットフォームとして便利なものである。 ※Link"
2006-08-20 22:59:00,※LiveJournal
LJは若者を中心とした友達たちの交換日記のような形でスタートした。一般のブログでは、投稿記事はすべて公開が原則となっているが、LJでは友達グループをつくりグループ内で情報交換できるという特徴がある。いわゆるSNS機能が備わっている。 ※Link"
2006-08-21 00:25:00,※WordPress Hosting
WordPressが使える(設置条件を満たす)海外のWeb Hosting企業5社が、WordPressウェブサイトで紹介されている。動作に必要なPHP4とMySQLのサポートがある。GB当りのレンタルコストは日本の一番安いところ(500MB、年間4410円)と比べて30倍の差がある。経験と実績、市場の大きさが影響しているのだろう。大量の写真や動画を保存する場合は海外レンタルの方が断然お得である。 ※Link
WordPress設置条件を満たすかの確認はしていないが、Bravenetも手ごろに利用できる。古くからWeb用ツール、JavaScriptの勉強に重宝しているサイトである。Geocitiesと同じように、広告が表示される煩わしさがあるが無料で50MBまで利用できる。Webページの作成ツールやFTPも利用できる。 有料ではつぎの二種がある。 Basic 月4.95ドル、3GB、Email30、Subdomain30、ドメイン初年度無料(年8.95ドル) Premium 月6.95ドル、30GB,Email2000、Subdomain200、MySQLとPHPサポート Bravenet 設立1997年、登録会員800万人、月間ユニーク訪問者2000万人、the top 50 visited websites worldwide!"
2006-08-21 02:38:00,WordPressインストール
2006年8月21日 1時15分 wp2.0.4ダウンロード完了 (非圧縮1.7MB) Installationの説明を読む minimum requirements to run WordPress
lolipopのデータベース設定、phpAdminのユーザ名とパスワードを探すのに手間取ったが、インストール自体はたった5分で完了した。すばらしい!
"
2006-08-22 10:55:00,Mozilla L10N フォーラム
http://forums.firehacks.org/l10n/index.php Dalmanian ellm_blog@ybb aamy 0822
http://www.reference.com/browse/wiki/Mozilla_Firefox"
2006-08-22 11:09:00,Writely
http://www.writely.com/
Googleが買収した時点で新規のユーザ亜登録が凍結されたが、8月15日から新規登録を受け付けるようになった。ただし以前に登録予約をしていたユーザが優先される。
オンラインで共同作成・編集ができるソフト。ドキュメント・テキストは最大500KB,イメージは最大2MB間での制限がある。
http://osdn.jp/"
2006-08-23 14:19:00,IT分野一覧
| サーバ | ストレージ |
| ネットワーク | クライアントPC |
| モバイル&ワイヤレス | 情報漏洩対策 |
| ウイルス/ワーム/スパイウェア対策 | OSプラットフォーム |
| CPUプラットフォーム | 業務アプリケーション(サーバ) |
| オフィス・アプリケーション(クライアント) | システム/アプリケーション開発 |
| システム運用管理 | オープンソース |
| レガシー・マイグレーション | 仮想化 |
| ユーティリティ・コンピューティング | SaaS/ASP |
| アウトソーシング | SOA |
| 検索エンジン | グループウェア |
| eラーニング | 内部統制・日本版SOX法/コンプライアンス |
| ビジネス・コンティニュイティ/ディザスタ・リカバリ | 市場動向 |
| 電子政府/電子自治体 |
| ITPro | CNET Japan |
| ZDNet Japan | ITmedia |
| @IT | TechTargetジャパン |
| PC Watch | Enterprise Watch |
| MYCOM PC WEB | ASCII24 |
| WebBCN | キーマンズネット |
| CIO Online | NETWORKWORLD Online |
| Windows Servers World Online | JavaWorld Online |
| LinuxWorld Online | その他 |
"
2006-08-28 12:31:00,サイバーポルノ論争
http://clinamen.ff.tku.ac.jp/CENSORSHIP/Porn/
Cyberporn_1.html
サイバーポルノといっても、コンピューターで作ったり楽しんだりするポルノの話ではありません。ネットワークにおけるポルノ情報の量に関する、かなり重要な論争です。この論争で問題になっているデータは、日本での議論にもかなり関係すると思われるので、少し詳しく紹介します。 論争のはじまりを作ったのは、米国の週刊誌『タイム』が1995年7月3日号に載せたカヴァー・ストーリー「あなたの間近なスクリーンのうえでーーサイバーポルノ」(On a Screen Near You: Cyberporn)でした。筆者は同誌の記者であるフィリップ・エルマー=デウィットです。 彼はカーネギー・メロン大学(ペンシルヴァニア州ピッツバーグ)の研究グループが行なった調査を全面的に使って、コンピューター・ネットワークに流れているポルノ情報の「驚くべき」実態を明らかにしました。カーネギー・メロンの研究は当時まだ公表されておらず、まずこの記事によって、基本的な内容がかなりセンセーショナルに伝えられたことになります。調査の主な内容は、つぎのようにまとめられています。
驚くほど大量のポルノがオンラインにある。18カ月におよぶ研究において、調査チームは91万7410もの性的に明示的な写真、描写、ショート・ストーリー、フィルム・クリップを検分した。ディジタル化されたイメージが集積されているUSENETのニューズグループにあっては、写真の83・5%がポルノ的であった。 それはとても大衆的である。同報告によると、性的に明示的なイメージの交換はいまや「コンピューター・ネットワークの利用者たちの娯楽の最大とはいえないまでも、最大のもののひとつに入る」。ある米国大学では、40のもっともアクセスの多いニューズグループのうち、13が alt.sex.stories、rec.art.erotica、alt.sex.bondageといった名称を持っていた。 それは巨大な金儲け手段である。検分したニューズグループにある性的イメージの大部分(71%)は、成人向けの電子掲示板(BBS)から来ている。これらBBSのオペレーターたちは、成人指定の素材についての自分たちの私的なコレクションに、顧客を引きつけようと試みている。これら何千にもおよぶBBS サービスは有料で(一般につき10ドルから30ドル)、クレジット・カードを受けつけている。大手の五つの年間収入は、100万ドルを超える。 それはいたるところにある。BBSオペレーターたちの許可をえて入手したデータを使って、カーネギー・メロンの調査チームは米国の50州、それに世界中の40の国や地域の2000以上の都市にいる、個々の[ポルノ]消費者を同定した。そのなかには、ポルノの所持が死刑となりうる中国のような国々も含まれる。 それは男のものである。BBSオペレーターたちによると、オンライン・ポルノの消費者の98・9%は男である。残り1・1%の多くが、パトロンたちの心を安らげるために、「チャット」ルームや掲示板をうろついている女性だという証拠も一定程度ある。 裸の女性だけではない。おそらくハードコアのセックス写真がいたるところで入手できるので、成人向けBBS市場のかなりは、通常の本屋の雑誌の棚ではみつけられないようなイメージに対する需要に駆り立てられているように思われる。つまり、ペドフィリア(子供のヌード写真)、ヘベフィリア(少女愛)、それに研究者がパラフィリアイと呼んでいる、「倒錯した」素材の寄せ集めである。後者には、ボンディージ、サドマゾ、排尿、排便、それに動物で一杯な納屋での性行為[獣姦]が含まれる。
この記事の著者は、インターネットが巨大な可能性を持っているシステムだと強調したあと、カーネギー・メロンの調査でも、USENETニューズグループのメッセージのたった3%がポルノ・イメージであること、さらに、USENET自体がインターネットのトラフィックの11・5%を占めるにすぎないことを明らかにしています。さらに、ネットワークを流れているポルノ情報が、成人向けの雑誌や本からスキャンしたものであって、そこからえられるもの以上ではないことも指摘されています。 問題は、記者によれば、つぎの点にあります。
しかし、コンピューター・ネットワークにおけるポルノは別物である。あやしげな本屋や映画館に出向く必要なしに、それを自分の家で私的に入手できるのである。雑誌やビデオをまるごと買うのではなく、自分が興奮する部分だけをダウンロードできる。感染しうる病気や公的な嘲笑に身をさらすことなしに、自分のセクシュアリティのさまざまな側面を探索することができる。(もちろん、本年はじめに顔を真っ赤にした何十人ものハーヴァードの学生に起こったように、だれかがあなたのオンライン活動を追跡して、コンピューター・ファイルを押さえてしまわないかぎり、だが)。 当然ながら、両親や教師の大いなる恐怖は、大学生がこうしたしろものを見つける可能性にはない。それらがもっと若い人々の手におちるうることが問題である。そのなかにはおそらく、自分が見ているものをりかいできるほど情緒的に準備ができていない人々が含まれている。
ついでエルマー=デウィットはネットワーク上でのポルノ規制をめぐる論争(エクソン法案を含む)や、ポルノそのものについての対立する諸見解をざっと紹介し、以下のような結語で記事を締めくくっています。
ポルノは強烈な素材である。そして、それへの需要が存在するかぎり、つねに供給があることになろう。より優れたソフトウェアが、最悪の濫用をチェックする助けになるかもしれない。だが、それを完全にカットできるようなスイッチは決してあるまいーーインターネットの(そして民主主義の)最大の力の源泉である拘束されない表現を破壊することなしには。EFF[Electrinoc Frontier Foundation]の共同設立者であり三人の若い娘の父でもあるジョン・ペリー・バーロウが語るところによれば、厳しい真理は、重荷が最終的に、これまでつねにそれを引き受けてきたところに、つまり両親に落ちてくるということにある。「自分の子供たちが汚泥に固着するのを望まないなら、自分自身がしているように、子供たちがそれを不快だと見いだすよう彼らを育てあげるという、きつい仕事に立ち上がるしかない。」
『タイム』が使ったカーネギー・メロンの調査結果は、同大学の大学院生であるマーティ・リムによって「情報スーパーハイウェイでのポルノ販売」というタイトルの論文として、『ジョージタウン法律雑誌』に発表されました。その内容はネットで読めます(Marty Rimm, "Marketing Pornography on the Information Superhighway
Georgetown Law Journal, Vol.83, No.5, 1995.)。副題には「40の国、地域における200以上の都市で、消費者によって850万回もダウンロードされた、91万7410のイメージ、描写、ショートストーリー、アニメーションの調査」とあります。本文もかなり長いものです。 この調査の結果はエクソン法案をめぐる米国議会での討論でも、ただちに利用されています。それだけでなく、通信品位法に対する現在進行中の訴訟において、合衆国政府はACLU/EFFが起こした提訴への反論に、このリム論文を付属資料として貼りつけています。政策作決定に大きな影響を与えたといってよいでしょう。しかし、『タイム』の記事、そしてそのもとになったカーネギー・メロンの調査には手厳しい批判も寄せられています。それだけでなく、リムの経歴に怪しい点が多々あること、彼の調査なるものが信憑性に欠けるものであることなども、明らかにされつつあります。それらについては、次回に要約を出します。
マーティ・リムたちのグループの調査が、カーネギー・メロンにおいて行なわれたことは、象徴的でした。というのは、同大学はコンピューター・ネットにおける性的表現の規制の動きに、もっとも「先進的」に反応した大学のひとつだったからです。このことは日本ではほとんど報道されていませんが、大学における「自主」検閲の典型的なケースです。詳しい内容は、CMU Censorshipのページにありますが、要するにエロティックな画像がやりとりされるいくつかのBBSを、大学当局がキャンパス内で閲覧禁止にしたのです。 この調査も大学の資金的なバックをえてなされたのですが、『タイム』に内容が掲載されたときから、激しい批判にさらされました。とりわけ、そこで出された数字が一人歩きして、議会で確実なものとして引用されるようになったため、表現の自由を要求する側は、その信憑性をチェックする作業にとりかかりました。こうした点はいかにも米国らしいというべきなのでしょうか、リムの過去の経歴がネットのうえで暴かれ、彼が『ポルノ百科』なるあやしげな本の著者であること、『ペントハウス』誌の編集長におべっかつかいの手紙を書いていることなどまで、徹底して調べられています(My Friend Marty Rimm)。 批判の内容は後述するとして、リム論文がどう政治論争とかかわったかを、少し見ておきます。 1995年6月26日、上院においてグラスレイ議員はつぎのように発言しています。
議長閣下、今朝私が述べたいのは、最近当地で多大な注目を集めている話題についてであります。私の話題は、サイバーポルノ、すなわち、コンピューター化されたポルノであります。・・・ジョージタウン大学ロー・スクールは、カーネギー・メロン大学の研究者たちが行なったすばらしい研究を出版いたしました。この研究は、サーバーポルノの入手可能性と特質について、いくつかの重要な問題を提出しております。私はこの論文を、記事録にとどめておくよう要請いたします。 ・・・私が言及いたしたいのは、カーネギー・メロンの研究であります。私はカーネギー・メロン大学でなされたことを強調したい。これは、コンピューター・ネットワークにあるポルノを分析したどこかの宗教団体がやった研究ではありません。 当該の大学は90万のコンピューター・イメージを調査しました。この90万のイメージのうち、インターネットで入手しうるあらゆるコンピューター化された写真の83・5%が、ポルノ的であります。議長閣下、繰り返させていただきたい。カーネギー・メロンの研究によれば、対象となった90万のイメージーーすべてインターネットにあるーーの83・5%が、ポルノ的なのです。 もちろんだからといって、これらイメージの全部が憲法のもとで非合法だというわけではありません。しかし、コンピューター・ネットワークで入手可能なかくも多数の画像イメージを考えると、議会は日々攻撃にさらされている両親たちを助けるために行動すべきであり、その行動は憲法に合った仕方でなされるべきです。不潔なポルノが満ちあふれています。この満ち潮をくい止めるために、私たちは行動を起こすべきです。というのは、ロバート・ボーク判事のことばによれば、それは倒錯した精神を駆り立てるからであります。・・・
この議員の発言は、『タイム』の記事の数字を勝手にねじまげています。これではインターネットに流れている画像の83・5%が「ポルノ的」になってしまいますが、もともとの数字は、成人向けBBSでの数字であって、それはインターネットと同じではありません。それどころか、いまではリムが挙げた数字の信憑性が問われているのです。にもかかわらず、83・5%という数字は一人歩きします。 最初に、この調査がおかしいと声を挙げたのは、ドナ・ホフマンとトマス・ノヴァックでした。彼らはヴァンダービルト大学の経営学大学院の準教授です。ふたりは「『タイム』記事の詳細な批判」をオンラインで発表します。 リムの調査対象は、米国での選別された成人向けBBSでのポルノ的イメージという限定されたものでしかないこと、また、「驚くほど大量のポルノがオンラインにある」と『タイム』は述べているが、リムの調査からしても、USENETやWWWにあるポルノはきわめてわずかである。実際、リムはUSENETに関しては、2830のイメージという数字しかえられなかったとしていること、その他、「チャット・ルーム」に入る女性についてのコメントに事実の裏づけがないことなど、記事がインターネットへの無理解と、かなり意図的な歪曲にもとづいていると、彼らは結論しています。 ふたりはさらに、リムが『ジョージタウン法雑誌』に掲載した論文に対しても、徹底した批判を行なっています。こうした批判にリムも答えており、両者のやりとりはすべてオンラインで読むことができます(サイトはYahooの関係ページが網羅しています)。(未完)
"
2006-08-28 22:48:00,
USA Court Decision
Streamcast and Grokster have won a major court decision in Los Angeles, shifting the tides of the on-line P2P legal war. Federal court Judge Stephen Wilson has dismissed much of the studios' claims in their lawsuits against them, stating that Morpheus and Grokster were not liable for copyright infringements that took place using their software.
See News.com Article: Federal Judge Rules: File-swapping tools are legal The ruling stated loud and clear that innovating decentralized peer-to-peer Gnutella-like software is perfectly legal, and shouldn't be deemed illegal in the courts. The courts compared the technology with the innovation of the original Sony videocasette recorder (VCR).
Fred von Lohmann of the Electronic Frontier Foundation (EFF) stated the case is far from over, but that the case sends a "strong message to the technology community that the court understands the risk to innovation" the case could represent
The Recording Industry Association of America (RIAA) and Motion Picture Association of America (MPAA) offered no comment, but are of course issuing an appeal to the ruling already. Published By Mike Darrah - April 25, 2003
"
2006-08-30 22:20:00,WP機能
| 資格 | Dashboard | Write | Manage | Links | Presentation | Plugins | Users | Options | Import |
| Admin | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Editor | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | ? | Profile | ? | ? |
| Author | ○ | △ | △ | ? | ? | ? | Profile | ? | ? |
| Subscriber | ○ |
Write
| Write Post | Write Page | |
| Editor | ○ | ○ |
| Author | ○ | ? |
Manage
| Posts | Pages | Categories | Comments | Awaiting Moderation | Files Akismet Spam | Backup | ||
| Editor | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | |
| Author | ○ | ? | ? | ○ | ? | ? | ? | |
Links
| Manage Links | Add Link | Link Categories | Import Links | |
| Editor | ○ | ○ | ○ | ○ |
Presentation
| Themes | Theme Editor | Header Image and Color | |
"
2006-08-31 01:05:00,YouTube
<b>Booty Shakin #7</b> <object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://youtube.com/v/o9ycyHr85k4"></param><embed src="http://youtube.com/v/o9ycyHr85k4" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object><br>http://www.youtube.com/watch?v=o9ycyHr85k4 <b>Big White Booty</b> <object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://youtube.com/v/NgDpb7MRoRs"></param><embed src="http://youtube.com/v/NgDpb7MRoRs" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object><br>http://www.youtube.com/watch?v=NgDpb7MRoRs <b>Sexy Lesbians</b> <object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://youtube.com/v/A3qS_gk9aSk"></param><embed src="http://youtube.com/v/A3qS_gk9aSk" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object><br>http://www.youtube.com/watch?v=A3qS_gk9aSk <b>Is There Anything Hotter Than Girls Kissing?</b> <object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://youtube.com/v/vcLh6clqh1U"></param><embed src="http://youtube.com/v/vcLh6clqh1U" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object><br>http://www.youtube.com/watch?v=vcLh6clqh1U <b>Lesbians</b> <object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://youtube.com/v/eT9fUOOm6nI"></param><embed src="http://youtube.com/v/eT9fUOOm6nI" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object><br>http://www.youtube.com/watch?v=eT9fUOOm6nI <b>Sexy Lesbians</b> <object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://youtube.com/v/A3qS_gk9aSk"></param><embed src="http://youtube.com/v/A3qS_gk9aSk" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object><br><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/A3qS_gk9aSk"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/A3qS_gk9aSk" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object> http://www.youtube.com/watch?v=A3qS_gk9aSk"
2006-08-31 05:23:00,矮小惑星Dwarf Planet
太陽系惑星:冥王星を除外 賛成多数で最終案採択 IAU?今日の話題 ...
| プラハ会川晴之】チェコのプラハで総会を開いている国際天文学連合(IAU)は最終日 の24日、全体会議で惑星の定義案を議決、1930年の発見以来76年間、第9惑星の 座にあった冥王星を惑星から降格する最終案を賛成多数で可決した。 |
"
2006-08-31 08:14:00,The Wisdom of Crowds
"The Wisdom of Crowds" and the colors of collective intelligence http://www.community-intelligence.com/blogs/public/archives/000267.html On My Mind Mass Intelligence http://www.forbes.com/global/2004/0524/019.html
As Google understands, crowds do a better job of decision making than individuals.
When Google finally gets its gargantuan market capitalization later this year, it will turn its founders into billionaires and make individual investors everywhere swoon. But it will also validate an idea: The most valuable resource on the Internet is the collective intelligence of everyone who uses it. Google has succeeded for a simple reason: It regularly finds the Web pages that are most valuable and puts them at the top of the list. The heart of the technology that lets it do this is the PageRank algorithm (after cofounder Larry E. Page), which essentially asks Web page producers to vote on which other pages are most worthwhile. Each link to a page counts as a vote. Google is a republic, rather than a pure democracy; sites that have more links into them are effectively given more voting power. But the principle is fundamentally democratic--let the masses decide. Given the Wild West nature of the Web, you'd think that this would lead to chaos or irrationality. Instead, it leads to a remarkable order. How does this work? What Google is relying on is something I call the wisdom of crowds: Under the right circumstances, groups are smarter, make better decisions and are better at solving problems than even the smartest people within them. On any one problem a few people may outperform the group. But over time collective wisdom is near-impossible to beat. No one, you might say, knows more than everyone. http://www.kottke.org/04/07/wisdom-of-crowds
The wisdom of crowds you say? As Surowiecki explains, yes, but only under the right conditions. In order for a crowd to be smart, he says it needs to satisfy four conditions:
1. Diversity. A group with many different points of view will make better decisions than one where everyone knows the same information. Think multi-disciplinary teams building Web sites...programmers, designers, biz dev, QA folks, end users, and copywriters all contributing to the process, each has a unique view of what the final product should be. Contrast that with, say, the President of the US and his Cabinet.
2. Independence. "People's opinions are not determined by those around them." AKA, avoiding the circular mill problem.
3. Decentralization. "Power does not fully reside in one central location, and many of the important decisions are made by individuals based on their own local and specific knowledge rather than by an omniscient or farseeing planner." The open source software development process is an example of effect decentralization in action.
4. Aggregation. You need some way of determining the group's answer from the individual responses of its members. The evils of design by committee are due in part to the lack of correct aggregation of information. A better way to harness a group for the purpose of designing something would be for the group's opinion to be aggregated by an individual who is skilled at incorporating differing viewpoints into a single shared vision and for everyone in the group to be aware of that process (good managers do this). Aggregation seems to be the most tricky of the four conditions to satisfy because there are so many different ways to aggregate opinion, not all of which are right for a given situation.
There's more info on the book at the Wisdom of Crowds Web site and in various tangential articles Surowiecki's written:
- Smarter than the CEO - Interview with Bill James - Blame Iacocca - How the former Chrysler CEO caused the corporate scandals - Search and Destroy (on Google bombs) - The Pipeline Problem (drug companies) - Hail to the Geek (government and information flow) - Going Dutch (IPOs) - The Coup De Grasso (fairness in business) - Open Wide (movies and "non-informative information cascades")
スロウィッキー氏が語る、大衆の知恵: Wisdom and Madness of Crowd http://longtailworld.blogspot.com/2006/05/webwisdom-and-madness-of-crowd.html
"
2006-08-31 09:36:00,大衆はやっぱり賢い!の事例
James Surowiecki 28 Meg MP3 File (Wikipedia) スロウィッキー氏講演 James Surowiecki 28 Meg MP3 File Audio presentation at SXSW Conference 2006 [翻訳] satomi (Long Tail World) 1.1906年西イングランド、フランシス・ギャルトン(85歳)が出くわした雄牛の体重当てコンテスト:正解1,198ポンドに対し、全員の推定平均値は1,197ポンドで、一番手の予想より正確だった。 2.瓶詰めゼリーの個数当てコンテスト:5人が5回やって推定値の平均をとると、第1位の個人より平均値の方が実数に近かった。 3.クイズ番組「ミリオネア」:回答者が予め指名したエキスパート5人の正答率は3分の2。会場視聴者のアドバイスは正答率91%で、その道の専門家より暇つぶしに会場に来る雑多な集まりの方が頼りになる。 4.競馬:あまりにも予想順位そのまんまな結果になるので競馬離れが進行中 5.株式:完全とは程遠いことは周知の通りだが、どんなに一流の金融マネージャも10年、15年のスパンで見ると90?95%の人は市場平均に適わない。 6.予測市場:アイオワ電子市場は誰でも参加できる予測取引市場として1988年にアイオワ大が開設した。過去4回の大統領選では3回まで当落を当て、ギャロップの世論調査より命中率が高いことが実証されている。 7.TradeSports.com:スポーツの結果と、州選挙・上下院選の予想など。2004年は州選挙50選中50、上院選34選中33の当落を当てた。 8.HollywoodStockExchange.com:映画新作の興業収入を劇場公開前に賭ける取引市場。各スタジオの社内予想より当たることで知られる。オスカー賞のレース結果予想は8部門中8部門、8部門中7部門、8部門中7部門。今年は「クラッシュ」が外れたが、これはしょうがないだろう。 9.HP:社内に商品・サービスの予測市場を置き、昼休みに社員が自由に売り買いしている。これまで3年間、会社の予想より正確な結果が出ている。 10.Google、Siemensなど:社内に予測市場を置き新薬認可などの予想に活用 11.潜水艦スコルピオンの失踪(1968.05.22./大西洋上):軍外部から任意抽出の人々を集め別々の部屋で失踪のシナリオを組み立てさせると、ちょうどクロスした地点に遭難船発見(乗組員99名は既に死亡)。それはプロであるはずの軍の捜索範囲から220ヤード離れた海底だった。"
2006-08-31 10:02:00,集団を賢くする3条件
"
2006-08-31 10:43:00,次世代ブラウザFlock
次世代ブラウザとして評判のFlockを使っているが、今のところ快適である。 インストールも簡単であった。写真の共有は、flickrまたはPhotobucketと連携できる。試しに自分のflickrを設定した。瞬時に終わり、ブラウザ上部に表示されるようになった。flickrおよびPhotobucketで公開されている写真はメニューを切り替えると上部にサムネールが表示される。サムネールをクリックするとオリジナルの写真が下部に表示される。写真のブラウザーとして使いやすい。技術的にはそのインプリメンテーションはさほど難しくないと思う。Webページのマッシュアップの簡単な例として分かりやすい。 もうひとつは、「お気に入り」あるいは「ブックマーク」のセットアップで、del.icio.usとShadowsのいずれかが選択できる。"
2006/09
2006-09-01 18:03:00,性生活調査報告
驚きました!こんな性の報告が薬品会社から発表されている。「現代社会における二人の寝室と性生活に関する調査」という報告で、バイエル薬品が調査を実施し、8月3日に行われた「ふたりの寝室フォト&エッセイコンテスト」授賞式で発表された。ED治療薬レビトラ錠のマーケティング戦略の一環なのだろう。 増加するシニア世代の結婚数ここ数年、初婚・再婚を問わずシニア世代の婚姻数が増えているという報告です。1990年に比べると2004年には、たとえば50代女性の婚姻数が二倍になった。しかし、この数字だけで増えたとはいえないのではないか。 10年前の50台の女性の数は、2004年では、段階世代が中心だから、二倍近いとすれば、相対的な婚姻率はおなじだといえる。しかし、60台の男性・女性の婚姻数が増えているのは、やはり積極的に求めていることの現われかもしれない。とくに女性の場合は3倍以上に増えているのは驚きである。もっとも、これらの数字は再婚の件数だけを見ているから、うがった見方をすれば熟年離婚の件数が増えたからともいえる。また、50代で結婚した男性の二割以上が初婚というのも世相の表れなのかもしれない。"
2006-09-02 06:03:00,,Writelyを使ってWeb2.0関連の話を書いていこうと思う。ここで作成したドキュメントをブログに投稿できる機能があると聞く。それを先ず試してみるつもりである。現在フロントのブログ作成ツールとしてLiveJournalのプラグインソフトであるSemagicを多用している。またWordPressもV2からかなり使いやすくなり機能も充実したのでこれからもっと使いこなせるようにしていきたい。これらのツールと比べて、Writelyがどこまで使いやすいかを評価したい。感触的には「こういうツールがなぜもっと早く世に出てこなかったのか」と思うほどである。Googleが目に付けて買収したのがよくわかる。私が現役であったなら第一に目をつけ提携折衝をしたことだと思うソフトである。今後の成長が楽しみである。Googleの多様化戦略の中でどう位置づけられていくのか興味がある。
2006-09-08 18:13:00,日本版WikiEngines
AsWiki (Ruby) by TANIGUCHI Takaki(谷口貴紀) BitChannel (Ruby) by 青木峰郎 FreeStyle Wiki (Perl) by Naoki Takezoe HashedWiki (PHP) by SHIMADA Keiki Hiki (Ruby) by 竹内仁 KbWiki (Perl) by 川合孝典 MobWiki (Java) by Project Mobster PalmWiki (C) by 増井俊之 PnutsWiki (Pnuts) by 戸松豊和 PukiWiki (PHP) by sng / PukiWiki開発チーム RWiki (Ruby) by 咳、なひ Tiki (Ruby) by ksr UniWiki (Perl) by 千田大介 WalWiki (Perl) by 塚本牧生 WiLiKi (Scheme) Shiro Kawai YukiWiki (Perl) by 結城浩 YukiWikiMini 結城浩 参考サイト Ruby related project"
2006-09-09 00:34:00,日本のソフト業界
伝統的なIT業界、とくにSIやOutsourcingそしてソフト開発を事業の柱とする企業が大きな変革を迫られている。それがいまの問題意識である。このことを裏付けるために、いま業界で何が起きているのかを整理し、あたらしい技術と市場を認識して、それらにどう対応していけばいいのか、どんな対応策があるのかを考えたい。 日本のソフト業界が変わらない限り、米国製ソフト・サービスの日本への侵入はとめられない。「止める必要はない、それらを利用して事業家すればいい」という意見もある。事実そういう戦術を実行に移して成功してきた企業もある。かつての商社がその典型であろう。 一方、「いや米国製ソフトだけに依存することは将来を考えたとき、首根っこを押さえられる危険がある。どうしても日本製ソフト、世界に冠たるものを生み出す必要がある」という意見がある。どちらが正しいかという議論ではなく、これから日本のソフト業界はどういう進路を取ればいいのかというぎろんであり、いままた大いに意見を戦わし、将来を見据えた最適な進路を選択すべきときである。その選択肢はなにか?というのが目前の課題であろう。 ところで、話は急に各論になるが、『ソフトウェア変革の波』を考え、その講演の事前準備の過程で気づいたり、過去に知っていたことが大きく変容したりしていることを一つ一つ確認していこうと思う。"
2006-09-09 02:01:00,Wiki事業は成功するか
2001年に開設されてからねずみ算式に増殖を続け、いまや21世紀を代表する叡知のひとつに数える人もいる、Wikipediadオンライン百科事典プロジェクト・・・。 これを可能にしたのがWard Cunninghamである。1998年のことである。WikiWikiWebとよぶソフトをperlで開発し、プログラミングの解説(Portland Pattern Repository-PPR)を書くためのツールに使ったのが始まりである。PPRはとくにextreme programmingについて書いており、Wardはその道の権威でもある。 Wikiの原点を知りたい人は、c2.com/cgi/wikiから勉強するとよい。PPRはhttp://c2.com/ppr/にある。現在、このWikiから派生していろんなWikiがあり、WikiWikiWeb, WikiWiki, Wiki Engine, Wiki Software, Wiki Cloneなどいろんな言葉が使われており、大元のWikipediaをみても混乱する。おまけに日本語版になるとまた違う言葉を使っており、混乱を助長しているようである。これから学習する人はそのことを承知して自分なりに理解していくほかない。 最初に書こうと思ったこととは違うことを書いてしまった。 明日にでも書き直そう。"
2006-09-11 21:47:00,Social Media Optimization (SMO)
米国で、SMO(Social Media Optimization)という言葉が話題になっている。Ogilvy Public Relations副社長のRohit Bhargavaが、5 Rules of Social Media Optimization (SMO)という記事(8月10日)の中で使った。Googleで検索すると834万件ヒットした。日本でいち早く紹介されたのは多分「メディアパブ」のブログ(9月4日)ではないだろうか?この記事では、27万4千件ヒットしたと書いてあるから、恐ろしいほどのスピードで情報が伝播している。 ≪Rohitの五つのSMO対策≫ 1. Increase your linkability 魅力あるコンテンツを発信して、外部からできる限り多くのリンクを張ってもらうこと。ブログやホワイトペーパも有効。 2. Make tagging and bookmarking easy "add to del.icio.us"のようなボタンを設けて、ソーシャル・ブックマーク・サイトでwebサイトのコンテンツを簡単に取り込こんでもらえるようにする。 3. Reward inbound links ブロガーがリンクを張りたくなるような環境を整える。Webサイト内のコンテンツはパーマリンクにする。最近のリンク元をWebサイト上で掲載するのも、リンクを張るためのインセンティブになる。 4. Help your content travel Webサイト内で、PDFやビデオ・オーディオファイルのようなポータビリティの高いコンテンツを備えれば、外部からのトラフィックを誘導できる。 YouTubeのビデオファイルが良い例。 5. Encourage the mashup RSSのフィード配信をすると、Webサイトのコンテンツが外部のマッシュアップの対象となりやすい。トラフィックを誘導できるし,Webサイトのコンテンツが外部で議論されるようにもなる。
このブログにつづいてOnline Marketing BlogではNew Rules for Social Media Optimizationと題してさらに11のルールを提案している。
6.Be a User Resource, even if it doesn't help you
7.Reward helpful and valuable users
8.Participate
9.Know how to target your audience
10.Create content
11.Be real
- Don't forget your roots, be humble
- Don't be afraid to try new things, stay fresh
- Develop a SMO strategy
- Choose your SMO tactics wisely
- Make SMO part of your process and best practices
"
2006-09-15 10:22:00,ソフト開発基本契約と受託条件明細
お客様の求めるソフトウェアは、従来業務をシステム化するといった単純なものではなくなった。ステークホルダーを特定し、その要望を聞きだし、相反する要望は選別や調整をし、業務要件の詳細を確定しながらシステム化要件を決めていく。経営効果(業績向上)の視点から優先順位付けて選別し、相互理解・認識を高めて合意に達する。 1.個別契約 お客様が実現したいことと、当社が実現できることは異なる。この共通認識をもつことが重要。プロジェクト初期段階は、全体とたどる道が見えない状況で、正確な見積もりは非常に難しく、変化する可能性の高い不確実なものである。経営層を含めて、見積りの不確実性と再見積りの必要性を共通理解する。 プロジェクトは仕様が明らかになるにつれ変化する。その変化と対応を、誰が承認するかということと、そのときの見積り精度はどの程度かということの共通認識をもつ。 2.受託条件明細 それぞれの個別契約に、作業の詳細を定めた「受託条件明細」が付帯する。契約書には、金額と納期は明記されているが、なにをやるかは「受託条件明細」に記載する形態。つまり、受託条件明細がなければ契約書としては不備で、金額と納期だけを約束するという非常にリスクの高い状態になる。役割分担や開発作業の範囲などが合意されていない状況で作業に入ってはいけない。 3.契約の履行 合意された条件のもとでの対象ソフトウェアの完成は、共同作業を通じて始めて達成されるものである。 契約書および受託条件明細に定めた役割分担にしたがい、それぞれの分担作業を誠実に実施する。 4.開発推進体制 対象ソフト開発の履行のための連絡、確認を行う主任担当者およびその他の開発推進体制を、それぞれ相手方に書面で通知する。主任担当者を両者で確定し、受託条件明細に記載する。仕様変更も主任担当者を通してのみ実施する。 5.定期協議会 進捗状況の報告、問題点の協議・解決のために定期協議会を開催する。 要件定義・設計サービスお客様の提示する業務要件を前提として、対象ソフトウェアを構築するための仕様書(システム仕様書)を作成する。 6.要件定義・設計サービス 委託型―お客様が主体として行うシステム仕様書作成作業に対して、必要な支援作業を実施する形態。法的には委任契約(民法第643条)だが、事実行為であるため「準委任」(民法第656条)となる。 請負型―お客様の支援を得て、弊社が主体としてシステム仕様書作成作業を実施する形態。法的には「請負契約」(民法第632条)。請負人は、仕事を完成させる義務を負い、成果に対する責任がある。お客様は、仕事の目的物(システム仕様書)に瑕疵がある場合、?瑕疵修繕請求、?損害賠償請求、?契約解除の責任追求ができる。"
2006-09-21 19:05:00,MySQL Powering Web2.0
August 15th 2006 - MySQL Powering Web 2.0 Leading Web 2.0 sites such as YouTube, Flickr, Habbo Hotel, Linden Labs, CyWorld, Technorati, Facebook, FeedBurner, Feedster, Wikipedia, Digg, LiveJournal, Mixi.jp, SimpleStar, PhotoBucket, 37signals, del.icio.us, Trulia, Neopets, and Zimbra have all selected MySQL to power their explosive growth - due to the database's speed and ability to easily "scale-out" on low-cost hardware."
2006-09-21 22:25:00,Web2.0議論に参加し使ってみて分かるビジネス
Web2.0論議が過熱気味である。その発祥地であるアメリカにおいてもいまだに「Web2.0とは何か?」という議論がメディアを中心に活発である。その一方で、そんな議論はメディアに任せておけばいい、と冷ややかな目で見ている人たちもいる。開発を先行させ、みんなが気づいて参入する前にビジネスを立ち上げようとしているベンチャーキャピタリストや起業家たちもいる。情報感度が人並み以上に高く、事業機会を誰よりも早く見つけて参入する企業が利益を得る世界がある。 前者の「Web2.0定義論」はビジネスから見れば無意味である。人によって見解が大きく違う。2004年にはじめてWeb2.0という用語を使い世の中に広がるきっかけを与えたオライリーでさえ、「Web2.0とは何か?」を説明するために17ページに及ぶ記事を書かなければならなかった。「Web2.0の解釈はさまざまである。それは意味のない流行言葉だという人がいれば、確かな知恵を与えるものだという人もいる。」とオライリーは述懐している。またWebの生みの親であるバーナーズ・リーは、Web2.0議論の過熱にたいして、不毛の議論だと警告している。 しかし、Web2.0の議論に参加することで、企業の視点から新しいビジネスやマーケティングのアイデアが見つかる可能性がある。利用者の視点に立てば、ライフスタイルに影響を与えるような新しい利用方法が見つかる。 利用者の視点で新しい動きを見るとき、「それが何の役に立つのか?どんなビジネスの可能性があるのか?」という疑問を抱いたままの人は、すでに生き残りの戦いの仲間はずれになっている。それは経営者や事業家にはあるまじきことであろう。すべては疑問を抱いたところからはじまるのであるから、好奇心をもって自ら理解に努め行動を起こさなければいけない。 まず新しいもの、技術やサービスを使ってみることである。自ら体験してはじめて理解できることがある。聞くだけではなく、見て触って感じなければ分からないことが多い。実感することが大切である。 では、何を使えばいいか?それはWeb2.0の議論に参加して見えてくるもので、人それぞれの判断で異なるだろうが、ここではWeb2.0の特徴をビジネスモデル、情報モデル(開発と利用の形態)、テクノロジー(ツール)の視点から紹介し、そこから見えてくる具体的なソフトとサービスを使ってみることを提案する。そして、それらの体験から競争他社の動きを分析し、自社資源を有効に活用できるビジネス機会を多面的にかつ深く考えることである。 1.ビジネスモデル 1-1 ロングテール 新しい変化をとらえたキーワードの筆頭が「ロングテール」である。従来のパレートの法則(20?80の法則)に従えばよかったビジネスのあり方が根底から覆った。多様な商品や情報を武器にビジネスを展開することが定石になっている。amazon.comやGoogleがその典型的な例である。この世界でのソフト開発やソフトビジネスのあり方も必然的に変わっている。ロングテールについては「・・・」で解説されており、また提唱者である米国Wired誌のChris Andersonのブログ(英文)を参考にされたい。 1-2 インフォウェア アプリケーションのパッケージ型からオンラインサービス型への移行が進んでいる。つまり、従来からのパッケージソフトがWebサービス(情報インフラ)として提供される傾向が顕著になっている。GmailやGoogleMap、Writely、iRowなどである。特定のハードの上で動き、そのハードを利用するソフトウェアではなく、Webという情報インフラの上でサービスを提供(情報を処理)する意味で「インフォウェア」と呼ばれることがある。これらのインフォウェアが互いに連携しあい、情報と情報が結びつき組織化されていくことが重要なポイントである。ソフト開発のあり方が根本的に変わってきている。 2.情報モデル(インフラと利用形態) 3.テクノロジー(開発技術・ツール) Web 2.0: Marketing hype or the second coming of the internet? Web 2.0: The power of 2 マッシュアップの事例集mashupfeed"
2006-09-22 21:30:00,100歳まで生きられるならセックスやめる
=4割が回答?英調査 (AFP=時事)
【ロンドン21日】英国の健康保険会社が実施した調査で、英国人の10人に4人は、もし100歳まで生きられるとしたら、セックスするのをあきらめるとの結果が出た。
この性欲放棄による長生き願望は女性の方が強いようで、女性回答者の48%が100歳まで生きられるならセックスを犠牲にすると答えたのに対して、男性のそれは31%にとどまった。
一方で、長生きよりも貴重なものもあるようだ。94%の人が、100歳まで生きるとの約束と交換に友人や家族を捨てることはないと答え、74%が100歳まで生きるのと引き換えにお金を捨てるのはいやだと回答した。
また、3分の2近くの人が、"太く短く"生きるよりも、分別を持って長生きすることの方がより重要だと考えていることが分かった。さらに、約90%が、長寿社会に応じて英国の医療制度を変えなければならないと考えているとの結果も出た。
調査は、健康保険会社のBupaが1003人を対象に実施した。[ 2006年9月22日12時39分 ] http://news.www.infoseek.co.jp/topics/world/england/story/20060922afpAFP008785/
"
2006-09-24 20:01:00,投稿記事のアクセス回数を表示
WordPress2.0用プラグインCountPosts V 1.1 Beta for WP 2.0を設置した。
投稿記事が読まれた回数をカウントしてくれる。よく読まれている記事の上位n件を表示することもできるので、読者がどの記事に関心があるかを知ることができる。Web出版社にとって必須のツールであろう。
1.設置方法 (原文:http://djuki.padrino.co.yu/blog/?p=75)
- CountPostswoをダウンロードして解凍したphpファイルを、サーバのPluginフォルダーに保存する。
- WpにログインしてPluginsページを開くとCountPost pluginが表示されているので、このActivateボタンをクリックして有効にする。
- HitThisPost関数を呼び出すphpコード < ?php HitThisPost('Hits for this post:', ''); ?> をindex.php(またはsingle.php)の任意の位置(たとえばCommentsの前)に追加する。必要なら属性を変更する。
- アクセス回数を表示するコードをsidebar.phpに追加する。 < ?php mainCounter('Visits: : ', ' .'); ?> 属性はアクセス回数の前後に表示される文字列である。
- よく読まれた記事を表示するコードを追加する。 < ?php TopHitsList(); ?>
2.TopHitsList(); function ------------------------------- < ?php function TopHitsList($beforeRead = ' (', $afterRead = ' ).', $top = 5, $beforeAll = '', $beforeLink ='',$afterLink = '', $afterAll = '') ?> ------------------------------- $beforeAll - 先頭のHTMLコード $afterAll - 最後に挿入するコード $beforeLink - 記事へのリンクを挿入するコード $beforeRead - リンク表示名の前に挿入する文字列 $afterRead - アクセス回数の後に挿入する文字列 $afterLink - 記事表示の最後に挿入するコード $top - 表示する記事件数(デフォールトは5件)
呼び出し例
< ?php TopHitsList(' 参照 ',' 回', $top = 5, '', ' ', '', ''); ?>
実行結果例 記事名1 参照 12 回 記事名2 参照 34 回
Download Latest version: Download CountPost for WordPress 2.0
2006-09-28 11:16:00,情けないSNS元年
Mixiが上場した今年は、SNS元年というべきか? 日本ではSNS自体がはやり言葉になっているが、実態は、批判的に言えば「じゃれごと」の書き込みサイトで、業者や出会い系の格好の餌食になっているところが多い。
それぞれのサイト内に閉じて見知った友人たちだけで意見交換やイベント案内、楽しい会話が弾んでいるところは少ないのではないか。 livedoorはブログに浮かれ始めてから業者の巣窟になり、最悪の状態になった。Yahoo!やMSNもSNSに本腰を入れてきたようだが、その実態は昔のコミュニティと変わらない。閉鎖的になっただけではないのか?
SNSといいながら、メンバは自分のコミュニティをつくり見知らぬ人を呼び込んでメンバーを増やそうとしているところもある。そのコミュニティ自体には、内容のある書き込みはほとんどなく、ほかのサイトへ誘導するのが目的であったりする。 ひどいのになると、誘導先のブログを読むことを入会の資格にしている。訪問者を誘い込んでアフィリエートの成績をあげようとしている。
MixiからYahoo!Daysに流れ込んだ人たちの発言やその意識を垣間見ると、本来のSNSが目指すものとはまったく違うことが多い。 10余年前にはじまった、アメリカのEternal September問題が日本でも起こっているということに愕然とする思いである。
なぜこうも節操がなくなったのか?やはり「金儲け至上主義」がはびこったためであろうか?参加者だけでなく、運営者側のモラルの問題も大きいのではないかと思う。
ネットを活用して、まじめに友達付き合いをしたいと思う、良識ある人たちは、商用サイトではなく個人サイトにSNSエンジンを設置して使うことが多くなってくるのではないかと思う。それほどインフラが充実し、使いやすいソフトが普及してきたということである。
日本製ではMIT在学の日本人を中心に数年前から開発されてきたAffelioがあり、同じオープンソースのOpenPNEなどがある。後者はSNSを開発しているといっているが元はPukiWikiだろう。コアとなるソフトをうまく使って改良しているということである。
敢えてSNS専用エンジンでなくとも、Webで手に入るオープンソースを組み合わせてSNSを構築(マッシュアップ)することも個人レベルで可能になってきた。それが大きなWebの変化である。
"
2006/10
2006-10-06 05:29:00,Google Gadgetが一般公開,ブログやWebページでまん延しそう
widgetとかgadgetと称されるミニWebアプリケーションが一気に普及しそうだ。Googleが1200種を超えるGoogle Gadgetを公開し,ブログやWebページに自由に組み込めるようになった。 時計や検索窓,辞書,ゲームなどなどの,便利なネットGadget(ガジェット)をGoogleは揃えていたが,これまではGoogle運用のパーソナライズドページやホームページでしか利用できなかった。今回は,どこのサイトでもGoogle Gadgetを貼り付けて利用できるのだ。YouTubeが投稿ビデオをブログなどに自由に組み込めるようしたことが,爆発的な普及を後押ししたと言える。同じように,Google GadgetがあちこちのブログやWebページに出現することになるかも。 Google Gadgetに一覧表は,こちら(Google Gadgets For Your Webpage)"
2006-10-06 05:31:00,Gadget
"
2006-10-13 14:52:00,JQA-ES,1.
あなたは、FRIでは組織の価値観にもとづき、社員が自主的に行動できる環境がつくられていると思いますか?
(ここでいう「自主的な行動」とは、社員一人一人が組織価値観にもとづいて考え、組織全体で価値観を実現するためにおこなう自律的な行動を指します)
★組織価値観が何かを幹部社員を含めてもっと理解する必要がある。価値観がわからずに行動しても本来あるべき姿を目指すことにならない。迷える子羊集団になる。
★組織プロフィールに書いてある内容の背景と意味を、具体的な例をもとに説明し、できるだけ多くの人が賛同し共通の認識を持つようにするのが先決である。研修で対話を通じて認識を高めていくしかない。同時に各人が情報と意見を発信できる訓練をすることである。
2.あなたは、FRIでは組織価値観に合致した適材を見い出し、採用していると思いますか?
★われわれの価値観が何であるかの共通認識がないのに、適材はどんな人のことかが分かる道理がない。ミッションとビジョンの違いやその具体例を経営幹部が自分の言葉で説明し、社員に納得してもらえる機会を増やすべきである。
★たとえば、南波委員長のリーダーシップでその時点で合意された求められる人材、?情報感度が高い、?経営マインドを持つ、?技法・ツーをを磨く、というならその具体策を押す具実行に移すことであろう。そうした成果を忘れてまたつぎの議論にうつるのは戒めるべきである。
3.あなたは、FRIでは組織的能力を最大限発揮できるよう、適材適所の人員配置がおこなわれていると思いますか?
★いまだに、公共・産業といった10年以上も同じ組織体制のままで、お客様のお客様の要求・期待が把握できるとは思えない。またそうした要求期待とお客様の不満足がどこにあるかを把握する活動がなければ、全体最適な組織体制と能力を発揮できない。つまり、適材適所が何かが分かっていない状態である。
★お客様のお客様の視点でお客様の経営目標とそれを達成するための課題は何かを、具体的なお客さまごとに把握し文書化して共有する。提供したサービスについては、第三者がヒアリングをして不満足な点を明確にし改善に結び付けていく。それが最初にやるべきことでしょう。その上でどんな組織が最適化を考え、その組織に要求される人材と職務要件、それを果たしていくプロセスを考え、実施していく。
4.あなたは、FRIでは全体の最適を実現できるよう、組織横断的に協力して仕事が進められていると思いますか?
★前記1?3の認識がない状態では、全体最適はない。口でいくら組織横断といっても(役員が4年以上言い続けている)何もかわらない。自らの組織を分解し、お客様の声にこたえるという視点から組織を考えなければならない。
★当社が提供すら価値(サービス)を重点にラインの制約を受けないプロジェクトとして2?3年間活動。そのプロジェクトに参加する人材の選定と選任はリーダーに任せる。社員全員にそのプロジェクトに参加できる機会を持つ・・・そんなやり方もひとつ。外資系コンサルでは「事業部」など意味がない。顧客あっての組織である。
全体最適の意味を理解する研修、たとえばビールゲームを経営幹部全員が受けるべき。いまや新人が一日かけて研修する時代である。
5.あなたは、FRIでは組織の能力向上につなげていくため、業績評価と動機づけが適切におこなわれていると思いますか?
★業績すなわち売り上げを要求するなら、それは経営ではない。
したがって動機付けにつながるような業績評価ができるとは、社員は考えていない。全体最適の組織とは、朝夕の清掃をしてくれる人たちも公平(フェア)に評価できること、そんなメンタリティが前提となる。
★前記1?3が実現されて、業績の意味が明確になってくる。経営幹部が、MCも含めて、組織すなわち体制だけでなく、各組織がなすべきこと(顧客満足に向けて)を明確に提示し、それを実現するためのプロセスと各職位の職務を明快に記述する、そしてそれを効果的に遂行できる人材をアサインし、不十分な知識、スキルの開発・研修の機会を与える・・・。
8.あなたは、FRIでは、指導者の育成が適切におこなわれていると思いますか?
★社員以上に、指導者の自己啓蒙と研修が大切。いったい何人の幹部がビールゲームを体感したか?ミッションとビジョンの違い、戦略と戦術の違い、それらの具体例を三つ、自分の言葉で説明できるか? そのための研修プログラムがない。
★指導者とはなにかを勉強する。たとえばリーダーとマネジャとアドミニストレータ(管理職)の違いがわかっていること。お客様との信頼関係を構築する要諦はなにかを、一日かけて部下に研修させられるべきであろう。指導者とはなにかを勉強する。たとえばリーダーとマネジャとアドミニストレータ(管理職)の違いがわかっていること。お客様との信頼関係を構築する要諦はなにかを、アカウントプランはなにか、中期事業計画とはなにか、それらをどんなプロセスでどう作るのかなどの研修をすべきである。事業部ごとの事業計画の寄せ集めは、中期事業計画ではない。全体最適の意味さえ分かっていないことを社員に発信しているようなもの。これを改善することが重要。研修しかないだろう。それも合宿で強制(義務)でその成果が業績としてみなされるような人事考課、報酬の制度に結びついていくのが望ましい。
10.あなたは、FRIでは、社員の意見や苦情等を、制度設計や戦略策定、各種マネジメントなどの改善に活用されていると思いますか?
★見ざる聞かざる言わざる、まるで江戸時代に生きているようである。
もの言わぬ子羊であってはいけない。
★自由闊達に意見を言い合える職場、経営風土が目指す姿でもある。道のりは遠いが、1?3から着実に進めていくしかない。一部の幹部の意識は変わってきたと思うし、社長も思いをもって取り組むようになってきている。一方で、自分の意見と違う他の意見は封じこめる言動に走る幹部もいる。これでは社員は意見も苦情も言うわけがない。とすれば改善も望めない。
「知る努力、知らせる努力」を忘れないように!それが事業企画のひとつの評価基準。
そして新しい企画をして、実行を支援すること。組織プロフィールは三年前のままである。顧客価値前提での見直しが要求される。経営とはなにかの勉強を継続すること、そして意見を交換し合うことである。「対話の仕方」も学ぶと良い。
2006-10-15 12:36:00,Peeping Tom のぞき魔
のぞき魔、出歯亀のことを英語ではPeeping Tomという。同名のイギリス映画が1960年に制作されている。1999年度英国映画協会のベスト100作品で78位にランクされている。 Peepは「のぞく」ことだが、なぜTomという名前が用いられているのか。その由来は11世紀にさかのぼる。イングランド中部コヴェントリーの領民は重税に苦しんでいた。それをみかねた、領主の奥方ゴダイバ夫人(Lady Godiva)は、夫に税を軽減するように頼んだ。領主は冗談のつもりで、「おまえが裸で馬に乗り、町を一回りするなら考えてもいい」と妻に言った。夫人はその言葉を真剣に受け取り、裸で町に出ることを決心する。それを聞いた町の人々は夫人に感謝し、夫人が恥ずかしい思いをしないように、戸や窓を閉じ、婦人を見ないことで応えようとした。彼女は人っ子ひとりいない町内を馬に乗って裸で一周した。ところが、ただひとり好色な仕立て屋のトムが、裸のゴダイバ夫人をのぞき見していたのだ。 それがもとで、のぞき屋トム(Peeping Tom)は罰が当たり失明してしまったという。 高級チョコレート「ゴディバ」の名の由来も、このコヴェントリーの伝説にある。だから、ゴディバの商品には、髪を長く垂らした裸の女性が馬に乗っているマークがつけられているのである。"
2006-10-15 12:41:00,イギリスの新聞の読者層
イギリスでは、その人がどんな新聞を読んでいるかで、階級や思想が明確に区別できる。
- The Observer
- 政治的にはやや左(労働党)寄りで、インテリ層に好まれる毎週日曜発行のクオリティ・ペーパー(高級紙)。現在は"The Guardian"紙の傘下に入っている。
- The Times Daily Telegraph
- "The Times"はイギリスを代表するクオリティ・ペーパー(高級紙)で、"Daily Telegraph"も大部数を誇る高級紙。
- The Mirror
- 思想的には労働党寄りのタブロイド紙。 犯罪や芸能人・王室ゴシップ生地が好まれ、派手な見出しがセンセーショナルに雰囲気を盛り上げる。
"
2006-10-16 04:09:00,Linux興隆を支える陣営のしなやかな運営と共同体的推進力
5年前Linuxは,Linus Torvalds氏個人の運営から,参加するプログラマーが自主的かつ共同体的に活動する効率的なものへと変化した。Torvalds氏はリーダーシップを保っているが,補佐チーム(IBM,HP等から派遣)に支えられ,権限委譲も進んだ。SCO Group(米)等による法的攻撃はむしろ陣営の結束を強めている。Open Source Development Labs社が活動拠点だが,本社もなく,CEOもいない。まずプログラマーがコード修正を提案すると,maintainerが改善し,Torvalds氏とMorton氏(チーフ補佐)が監修,4?6週間毎にテスト版が出され,何千人ものプログラマーが検証を行う。(bw050131)2005年の世界の統合企業ソフト産業は好調と予想 2005年のソフトウエア産業は好調を予想され,統合企業ソフトで世界トップのSAP社(独)は,2005年の売上高を10?12%増,米国ではPeoplesoft社を買収したOracle社が24%の利益増を予想している。世界の企業ソフト市場全体は4%増と予想されるが,大型プロジェクトは少なく,システムの変更及び刷新が需要の中心となろう。SAP社は,新たに3000人の新規雇用を行うと予想されるが,その中心は外国,主として低賃金国になると思われる"
2006-10-16 04:20:00,株価低迷で組織再編へ向うHewlett-Packard社
業績の乱高下を不満とするHewlett-Packard社の取締役たちは,1月の年次計画会議で組織再編を考えている。Compaq社を買収したCarly Fiorina会長兼CEOは,任期中に売上げと利益を大幅に引上げたものの,就任後の株価は競合大手に比較して大幅な55%の下落となり,パソコン部門はDell社にシェアを奪われ続け,法人向け製品でもIBM社やEMC社の競合に曝されている。2004年8月には第3四半期の業績予測を大きく下方修正する事態も生じた。(wsj050124) 剛腕Fiorinaによるコンパック社との合併はHP社に何をもたらしたか(Fortune050207) Hewlett-Packard社(HP)とコンパック社の大型合併は,HP社の株主に価値をもたらすことに失敗した。また競争に勝ち残れるだけの新企業になれたかどうかも疑わしい。CEOのCarly Fiorinaと取締役会が犯した大きなミスは,負け組のコンピュータ部門2つを合併することで財務的に価値のあるコンピュータ事業を生み出せると考えたことである。またHP社がコンパック社の株主に新たに11億株を発行したために,HP社の資産の37%をコンパック社側に売り渡し,株主に240億ドルの負担をさせたこととなった。 HP社取締役会が著名CEOのFiorina氏をついに解任へ((wsj050210) Hewlett-Packard社取締役会は,業績に対する不満が高まる中,主要事業部門の首脳達に日常的権限を委譲する取締役会の提案を拒絶したCEOのCarly Fiorinaを更迭した。同CEOが設定した経営目標が達成できず,同氏への権限の過度の集中が意思決定を困難にしている点を取締役会では問題としていたが,この更迭により既存の経営戦略には変更はないと表明している。しかしインク・カートリッジ販売を主力に同社利益の75%を上げているプリンタ事業への集中が再度浮上する可能性はある。 解任されたHP社の前CEOが陥ったハイテクと低コストの罠(Fin.Times 050211) Hewlett-Packard社(HP)を解任されたCEOのCarly Fiorinaは,成功へのカギとしてハイテクと低コストを挙げていた。だがこの両者の間には,ハイテク企業にとって脅威となるほどの隔絶があることを同氏は身をもって示した。HP社の場合,R&Dに年間35億ドルを投じるなど,ハイテクはハイコストを意味してきた。一方で過剰生産や技術の標準化が価格を引下げ,事業の大半を薄利に変えてしまう。またLinuxを使用した低コスト・パソコンの台頭など,ITの標準化が大手技術企業に共通する問題となっている。 Carly Fiorina氏のCEO辞任で迷走深まるHP社(Economist 050212) Hewlett-Packard社(HP)のCEOを辞任したCarly Fiorina氏について,辞任は戦略の変更ではなく,戦略を促進するための変更だと,新会長に就任したPatricia Dunn氏は述べた。しかし同社の戦略とは何なのか,今ひとつ明確ではない。どんな戦略かを決定することこそ,同社にとっての真の挑戦であると指摘する人もいる。実際にプリンタ部門以外は問題があった。Fiorina氏がCOOを置くことに反対した結果,企業の方向性が一貫しなかったともいわれている。 HP社,個性の強いCEOのFiorina氏を解任,後任者に望まれる新戦略(fin.Times050210) Hewlett-Packard社は,会長兼CEOのCarly Fiorinaを解任し,後任にはより実践的なリーダーシップを持ち,増益を達成できる人材を登用すると発表した。同氏はコンパック社との合併に踏切ったものの,パソコン部門の経営悪化を招いた。また尊大にも見えるリーダーシップ・スタイルが批判を受けていた。同社の弱点として,重要な部門に強さがないことで,例えばシステムを扱っているがソフト部門が弱く,サービス部門の規模もIBM社などと比べて見劣りがする。これらの点から,次期CEOにとって戦略の選択が困難な課題となろう。"
2006-10-16 04:44:00,情報漏えい問題で揺れる米HP、Dunn会長の引責辞任に発展
米Hewlett-Packard(HP)は9月22日(現地時間)に記者会見を開き、同社会長のPatricia Dunn氏が同日付けで会長職を退き、後任として社長兼CEOのMark Hurd氏が就任することを発表した。今回の発表は、ここ1ヶ月ほど同社を揺るがしているメディアへの情報漏えいと、その情報源特定のために「プリテキスティング(Pretexing)」と呼ばれる不正手法による捜査を行った問題で、これらを指揮していたDunn氏が引責辞任したものだ。28日には Hurd氏が米下院での公聴会に出席する予定で、不正捜査に関する報告を行うことになる。 HPダン会長、情報漏えいをめぐるスキャンダルで引責辞任
Hewlett-Packard会長のPatricia Dunn氏が、同社の取締役会議後に会長職を辞任することに合意した。Dunn氏は、メディアへの情報漏えいを調査していたが、その手法が問題となっていた。
HPが米国時間9月12日に明らかにしたところによると、取締役会は、Dunn氏の後任に最高経営責任者(CEO)兼社長のMark Hurd氏を指名したが、Dunn氏は、2007年1月18日の定例取締役会まで会長職を続けるという。また、同氏は、その後も取締役にはとどまる予定だ。
The Most Powerful Women - Forbes.com http://www.forbes.com/lists/2005/11/6MVD.html#17 Patricia Dunn Nonexecutive chairman, Hewlett-Packard; Global chief executive, Barclays Global Investors U.S."
2006-10-18 09:43:00,※アメリカの人口が3億人を超える
10月17日 7:46am EDT (AP通信) アメリカの人口が3億人になった。米国国勢調査局の公式発表である。3億人目の赤ちゃんは発表されていない。移民の国アメリカでは、それは必ずしも赤ちゃんとはいえない。その日に移民した人が3億人目かもしれない。すでに何ヶ月も前に3億人を超えているともいう。そういったこともあり、記念すべき日を祝い、花火を打ち上げるといった催しなどはないとのことで、アメリカ国民は冷静に受け止めている。 ※LINK"
2006-10-23 14:10:00,JETRO 米国における実務ガイド
◇「米国における駐在員のビザ取得ガイドブック」
米国で会社を設立して間もない日本の中堅・中小企業およびベンチャー企業等を対象として、そのような日本の会社から駐在員を派遣する場合に、必要なビザの種類、取得手続きについて解説しています。
◇「カリフォルニア州における会社開設、維持、閉鎖ガイドブック」
カリフォルニア州で会社を設立しようとする日本の中堅・中小企業およびベンチャー企業等を対象として、会社を設立する手順、設立後の年次手続き、会社を閉鎖するまでの概要を解説しています。
◇「米国における資金、資金調達方法ガイドブック」
米国で一から事業を始める際に、当面どの程度の資金を準備すべきなのか、現地で資金調達を行うことは可能なのかといった疑問に対し、シリコンバレーエリアで活躍中の外国人経営のベンチャー企業、米国のベンチャーキャピタリスト、銀行員へのヒアリングを通して得た最新情報を、本書にまとめました。"
2006-10-28 23:44:00,※Enterprise 2.0活用ルール
The Dawn of Emergent Collaboration
ビジネス・コミュニケーションのツールとして、これまでの知識ベースのコラボレーションのあり方を大きく変える可能性をもったSLATESツール―それらの導入と実践により知的生産性の向上と高度なコラボレーションをもたらすと期待されている。一般のインターネットでは、すでに誰でも利用できるようになっている。しかし、企業内での活用は今後の課題である。とくに日本ではそれらのツールへとその効用の理解が遅れていると考える。世の中の進取の気性に富んだ人たちはどんどん取り入れていくだろう。しかし、日本の保守的な経営者たちはそうした新しい潮流に気づいているのだろうか?気づかない限り企業での採用と実践は遅れることになる。 ※LINK
2006-10-30 12:37:00,パソコン若葉マーク
Linuxサーバ環境でのcron設定を調べているときに、「パソコン若葉マークシリーズ」というページに出会った。建築関係の情報化システム部門の経験があるhosoyaという方が書かれている。耳順を過ぎてからリナックスを勉強し、RedHat Linux 9でサーバを立ち上げた、という話しである。WindowsCE, VC++も勉強しておられるそうで、そのエネルギーに感心させられた。新しいことにちょっかいをだすので、いつでも初心者の若葉マーク、といっておられる。 これを読んで自分も、いつも若葉マーク状態だなぁと苦笑してしまった。Apache,MySQL,PHPなどに手をだしてWindows XPで動かしたりしたが、いまだに若葉マークのままである。とてもLinuxまで手が回らないが、耳順になって時間ができたらLinuxサーバを勉強してみるかなと勇気付けられた。 「Windows XPは厚化粧なので嫌いです。」といわれているが、同感である。こういう「厚化粧」だと思う感覚は、昔アセンブラーでコーディングし、「コアダンプ」なるものでデバグをせざるを得なかった世代に共通の感覚ではないかと思う。いまも組み込みソフトの開発に携わる人たちなどは同じような感覚を持っているのではないか。"
2006-10-30 13:10:00,金銭感覚と時間感覚
金銭感覚と時間感覚は表裏の関係にある。昔から「貧乏暇なし」というように時間に追われている人は大金持ちにはなれない。労働時間が長くて、忙しい忙しいといっている人は、スケジュールが詰まって忙しいことでなぜか偉くなったような錯覚に囚われることがある。しかし、働くj間が長くなっても豊かにはなれない。心は貧しくなる。それは時間の余裕、冷静に物事を判断し考える余裕、心の余裕がなくなっていることでもあり、将来の方向性を見失う危険がある。 ユダヤ系の人はアメリカの金融界を牛耳り、政治にも大きな影響力を持っているといわれる。ユダヤ商法というが、富裕なユダヤ人は何をしているか?端的にいえば仕事をせずにパーティにでている!多くのひとに接し、情報を交換し、アイデアを持った人からビジネス、金儲けのヒントを得ている。つねに新しい情報とアイデアを求めているのである。そのアイデアを事業として実現したり、その事業を経営する人をつねに探している。そして投資をするのである。これが彼我の差となって現れる。 金銭感覚のあるひとは時間感覚がある。この「時間感覚」の意味が日本人とユダヤ人の間では違う。日本人は、仕事やスケジュールを時間通りにキチンキチンとこなすことが時間感覚のあることだと思っていないだろうか?忙しいからという理由でパーティにでる余裕がなく、またその必要性も感じていないのではないか?人と知り合えない、アイデアを考える時間もないという状況に陥っている。まさに「貧乏暇なし」で、金銭感覚の欠如を物語っている。 ユダヤ人は、仕事する時間をできるだけ減らし、密度を濃くして少ない時間で仕事をこなし、スケジュールを空けて、空き時間を「人に会う」ことに割いている。「会う」というのは、現実世界と仮想世界の両方で会うことである。会うのが目的ではなく手段であり、さまざまな人と会って話すことにより、有意の情報を誰よりも早く掌握し、そこで知ったアイデアを持った、それを実現できる人に投資をして儲ける・・・。それが目的である。 金持ちになるチャンスは(日本的感覚では)働いてない時間に生まれる。働くということの意味が日本人とユダヤ人では違う、時間感覚と金銭感覚が違う、ということである。仕事ができる人というのは労働時間をドンドン短くして、働かない時間つまり将来につながる時間を生み出せる人である。このことは、過去半世紀にわたって数々のアイデアとテクノロジー、そしてビジネスを生み出してきたシリコンバレーの風土に通じる。"
2006-10-30 16:20:00,鏡の法則
野口さんのブログのなかで一番反響の大きかった記事で、本も出版された。子供がいじめにあっていることに悩む主婦が、ある経営コンサルタントのコーチングにより、たった一日で驚くべき変化を遂げた実話である。 主婦が悩んでいる問題は、いじめにあっている子供ではなく、主婦自身の問題で、その原因は過去にあった。その原因を取り除き、その原因が影響していた現在の夫との問題も解決する。それが子供の問題まで解決することにつながる。 すべての問題の原因はじつは、主婦自身の心の中にあった。その原因に気づくために必要なのは、ちょっとした勇気と行動力である。気づくことで主婦は自らの問題を解決し、悩みから解放されるという話である。 主婦が気づくために、経営コンサルタントがコーチした方法は、心理学の古典的な「原因と結果の法則」に基づいている。「現実に起きる出来事は、ひとつの結果である。結果にはかならず原因がある。」ということで、「あなたの人生の現実は、あなたの心を映し出した鏡」だといい、これを「鏡の法則」とよんでいる。 主婦と経営コンサルタントの話はじつに感動的である。読むものをして感涙に咽ばざるを得なくする。わたしも感動に泣いた。父と娘の愛、「ありがとう」「すみません」といった簡単な言葉をいうだけで、どれだけの誤解を氷解させ、互いを理解することになるかを改めて認識させられた。 話の内容には敢えて触れない。ぜひ原文のpdfファイルを読んでいただきたい。これをそのまま配布することは許可されています。EQの特筆すべき事例でもある。普通の感情を持った人間であれば、最後に気づいた主婦とその父と同じように嗚咽することまちがいなしです。 【潜在意識の法則】 「人生に起きるどんな問題も、何か大切なことに気づかせてくれるために起きるのです。偶然起きるのではなくて、起きるべくして必然的に起きるのです。ということは、自分に解決できない問題はけっして起こらないのです。 前向きで愛のある取り組みさえすれば、あとでかならず「あの問題が起きてよかった。そのおかげで・・・」といえるような恩恵をもたらすのです。」"
2006-10-30 16:54:00,潜在意識と集合的無意識
・シンクロニシティーと成功法則の関係とは?l
・成功法則が作用しない人はいるのか?
・頑張っても成功できない「根本的な理由」は何か?
・許せない時は、どうすればいい?
・遺伝子に秘められた"幸せな成功"の鍵 <参考になる本> ・「鏡の法則」野口嘉則著、総合法令出版 ・「生き方」稲盛和夫著、サンマーク出版 ・「原因と結果の法則」ジェームズ・アレン著、サンマーク出版 ・「生きがいの創造」飯田史彦著、PHP ・「ゆるすということ」ジェラルド・G・ジャンポルスキー、サンマーク出版 ・「オーケストラ指揮法」高木善之著、総合法令出版 ・「幸せ成功力を日増しに高めるEQノート」野口嘉則著、日本実業出版社"
2006-10-31 08:32:00,
| 日本版Wikiエンジン |
オープンソース分野で日本が主導権を握って開発しているソフトウェアの中では、Wikiエンジン開発が最も活発なのではないだろうか。日本のWiki開発の先駆者は結城浩さんで、今日使われている多くのWikiは結城さんのYukiWikiから派生したものだといっても過言ではない。
わたしはPukiWiki, FreeStyleWikiを自分のサーバに設置して使っている。個人的に文書作成や備忘録に頻繁に使うのはTiddlyWikiであるが、日本では PukiWikiが一番ポピュラーなのではないかと思う。このGroupsはページの履歴を保存しているが、Wikiスタイルや差分、RSSなどを取り入れると、Wikiに慣れた人にとっては利便性が高くなるだろう。他の人たちはどういう理由でどんなWikiエンジンを使っているのでしょう?
AsWiki (Ruby) by (谷口貴紀) BitChannel (Ruby) by 青木峰郎 FreeStyle Wiki (Perl) by Naoki Takezoe HashedWiki (PHP) by Shimada Keiki Hiki (Ruby) by 竹内仁 KbWiki (Perl) by 川合孝典 MobWiki (Java) by Project Mobster PalmWiki (C) by 増井俊之 PnutsWiki (Pnuts) by 戸松豊和 PukiWiki (PHP) by sng / PukiWiki開発チーム RWiki (Ruby) by 咳、なひ Tiki (Ruby) by ksr UniWiki (Perl) by 千田大介 WalWiki (Perl) by 塚本牧生 WiLiKi (Scheme) by Shiro Kawai YukiWiki (Perl) by 結城浩 YukiWikiMini by 結城浩
"
2006/11
2006-11-02 23:28:00,eBay本社ハロウィーン爆破事件
31日午後7時34分頃、サンノゼ市ハミルトン通りに面したeBay本社北棟(4階建て延べ10万平方フィーと)が爆破されガラス窓が割れる事件があった。就業後の時間帯のため従業員約1,900人にけがはない。ビルにはPayPal本部・技術・営業・ネットワーク事業センターが入っている。
シリコンバレーで企業が襲撃されるのは異例の事態。「ハロウィーンの悪戯か子どもの遊び、もっと大きな事件の可能性もある。ハロウィーンの愉快犯にしては手口は巧妙」(サンノゼ警察署長)、「相当破壊力の強いものだ」(同消防署長)。
火災探知機のアラームで署員が現場に駆けつけた時には地階出口近くの厚さ2インチの防弾ガラス(6×7ft)が粉々に割れていた。サンノゼ警察とFBIが合同で捜査に当たっている。(ソース:SJMercury)
"
2006-11-03 13:17:00,生き神少女
AP通信によると、ネパールの最高裁判所が、少女を生き神として隔離し、信仰対象とする同国の風習が子どもの権利違反を定めた法律違反にあたるか調査するよう、政府に命じた。最高裁の報道官が2日に明らかにした。児童権利保護団体からの訴えに基づいたもので、調査期間は3カ月。 ヒンズー教徒と仏教徒によって崇拝される「クマリ」は、選ばれた3?4歳ぐらいの幼女を首都カトマンズ中心部の「クマリ宮」と呼ばれる寺院に、親元から引き離して住まわせ、生きた女神として信仰の対象とするもの。選抜過程にも、生贄として殺されたヤギや水牛の頭とともに一夜を過ごすなどの儀式があるほか、選ばれた場合、世話人以外はほぼ社会と隔絶され、外出も祭りの際に山車に乗って市中を練り歩くなど年に2、3回ほどに限られる。 クマリは完全な肉体を持つとされるため、ケガや初潮などで出血があった場合はその資格を失い、次のクマリが選ばれる。"
2006-11-03 13:20:00,世界で最も背が低い少年,
AP通信によると、ネパールのカゲンドラ・タパ・マガル君(14)が、世界でも最も背が低い少年として、ギネスブック(ギネス・ワールド・レコーズ)に記録を申請し、認定を心待ちにしているという。少年の関係者が30日、明らかにした。マガル君の身長はわずか20インチ(50.8センチ)、体重も10ポンド(約4.5キロ)にすぎないという。
2006-11-03 13:29:00,世界最高齢116歳のエクアドル女性死亡
AP通信によると、ギネスブック(ギネス・ワールド・レコーズ)が男女を問わず世界最高齢と認定していた116歳のエクアドル女性、マリア・エステル・デカポビジャさんが27日午前3時(日本時間同日午後5時)、グアヤキルで死亡した。デカポビジャさんは、映画の喜劇王チャーリー・チャップリンやドイツのナチス総統アドルフ・ヒトラーと同年の1889年の9月14日生まれ。1917年に結婚し、1949年に夫と死別した。 ギネスの老人学コンサルタント、ロバート・ヤング氏は、デカポビジャさんの死去に伴い、米ミシシッピ州メンフィス在住の女性、エリザベス・ボールデンさんが新しい最高齢者となる見込みとしていた。ロンドンで正式発表するという。ボールデンさんも116歳だが、デカポビジャさんより11カ月若い。"
2006-11-03 13:32:00,世界最高齢115歳の誕生日,
AP通信によると、プエルトリコの世界最高齢の男性が21日、115歳の誕生日を迎えた。この男性は1891年生まれのエミリアノ・メルカド・デルトロさん。生まれた当時、プエルトリコはまだスペイン領だった。第1次世界大戦にも従軍している。デルトロさんは長寿の秘訣を、健康的な食事と「体に悪いこと、酒とタバコをやめることだね。私は90歳で禁煙したよ」と答えている。
2006-11-03 13:39:00,豊胸のおかげで命拾い
![]() ブルガリア紙スタンダートは、同国北部のルセで9月30日、24歳の女性が交通事故を起こしたものの、豊胸手術で胸に挿入していたシリコンがエアバッグの役目を果たし、命拾いしたと報じた。≪写真は豊胸手術用のシリコン≫ 女性は交通量の多い市中心部の交差点で、赤信号を無視し、別の車に衝突。2台の車は原形をとどめないほど破壊された。ところが、目撃者によると、女性はシリコンのおかげで一命を取りとめたという。〔AFP=時事〕"
ブルガリア紙スタンダートは、同国北部のルセで9月30日、24歳の女性が交通事故を起こしたものの、豊胸手術で胸に挿入していたシリコンがエアバッグの役目を果たし、命拾いしたと報じた。≪写真は豊胸手術用のシリコン≫ 女性は交通量の多い市中心部の交差点で、赤信号を無視し、別の車に衝突。2台の車は原形をとどめないほど破壊された。ところが、目撃者によると、女性はシリコンのおかげで一命を取りとめたという。〔AFP=時事〕"
2006-11-03 14:19:00,日本のパワハラ事情
モタモタしている部下を見ると、上司は息が詰まりそうになる。だからといって怒りを鎮められずに「バカ」「辞表書け」と言ったが最後、えらい目に遭う。上司だからという理由で部下を捕まえ腹いせの対象にしたら、身を滅ぼしかねない。このところ「パワハラ(パワー・ハラスメント」、つまり「職権のある上司が部下の人格を侵害する現象」が社会問題になっている日本では、こうしたことが多い。 ◆相次ぐ自殺 9 月6日に千葉県千葉市立中学校教諭、土岐文昭さん(50)が自殺した。スポーツ好きな明るい先生だった。しかし4月に転勤してきたこの学校では校長とそりが合わなかった。生徒がベランダから落ちケガをした事故では、校長に「殺人者だ」と怒鳴られた。仕事のストレスで教頭昇任試験をあきらめると、校長は「辞表を書け」「おれに恥をかかせるのか」と責めた。他の教師の前で「(土岐教諭は)おれの使用人」と人格を傷つける発言までしていた。 土岐教諭は9月に病院でうつ病の判定を受け、結局自殺してしまった。妻は先月28日に記者会見を開き「夫はパワハラのために自殺した」と教育委員会に真相究明を求めた。 6 月には新潟県で自殺した会社員の遺族が「息子は上司の人格冒とくのため自殺した」とし、会社と上司を相手取り慰謝料4200万円を求め提訴した。2004 年 10月からホームセンターに就職、農業資材を担当していた玉橋亮治さん(自殺当時26)は、上司から暴言を受けたほか、足げにされていた。店長に訴えたが何の役にも立たなかった。うつ病にかかった玉橋さんは去年8月に除草剤を飲み自殺した。 ◆損害賠償命令 8 月、京都地方裁判所は金融会社「レタスカード」に対し慰謝料670万円を元営業部長に支払うよう命じた。勝訴した元営業部長(45)は「社長が"アホ、ぼけ"とののしり、たばこでやけどさせるなどの暴行を加え、うつ病にかかった」として慰謝料6200万円を請求する裁判を起こしていた。 パワハラで東京大学の助教授が停職になる事件も起きた。研究所に勤務するこの助教授は、ある助手を「仕事が遅い」とののしり、研究用品を実際の価格より高く買ったとして差額120万円を返納するよう暴言を浴びせた。耐えかねた助手は去年研究所を退職、大学に陳情書を提出した。東京大学は問題の助教授を2カ月の停職処分、研究所長は監督責任を問い厳重注意に処した。日本の大学でも教授と助手の関係は「王と臣下」に例えられる。 東京都産業労働局によると、職場内のパワハラによる被害相談件数は2004年に4,012件だった。1999年の2,170件に比べると約2倍。パワハラの訴えが増えているのは、職場内の競争が激しくなったためと分析されている。成果を上げなければならない上司と、ストレスがたまった部下が互いに「うっぷんの尽きない時代」に突入しているというものだ。 ◆対処法は? 日本の経済誌「週刊ダイヤモンド」は今年3月に専門家の監修の下、自分がパワハラ上司なのかどうかを見極める質問15問を掲載した〈図参照〉。程度により自らを戒めなければならないということだ。併せて、部下がパワハラ上司に対処する方法も紹介している。 ▲大声を出し、全身で部下を攻撃する血の気の多い上司 →弱腰なところを見せたり、言い訳を言ったりする部下は「格好の獲物」だ。毅然(きぜん)として強い態度でいるべき。相手が「手ごわいやつ」と思えば引っ込む。同様に熱くなって反発すれば逆効果。 ▲大勢の前でかんしゃくを起こし部下を恥さらしにする上司 →知らん振りで無視。反対に「それはどういう意味ですか」と言い返すのも手だ。こうした上司は周りの視線が集まるのを嫌うため、攻撃をやめる。 ▲自己主張が強く、自分が物知りだと自慢して反対意見を嫌がる上司 →なるべく気にしないようにして、まず上司の言葉を認める。反論するときは間接的な方法で表現する。 東京=鮮于鉦(ソンウ・ジョン)特派員 朝鮮日報"
2006-11-03 23:57:00,GreeとKDDI
 「PCの成功モデルをケータイで」――au向けSNS「EZ GREE」の狙い http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0610/30/news080.html KDDI、初の携帯専用SNS・グリーと組む http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20061030AT1D3004J30102006.html KDDIとグリー、携帯向けSNS「EZ GREE」を2006年11月に開始 http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20061030/252243/?ST=newtech 「参加するケータイ」へ、KDDI、グリーと提携して携帯向けSNSを提供 http://journal.mycom.co.jp/news/2006/10/30/422.html KDDIとグリー、11月から携帯向けSNS「EZ GREE」開始 http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/31728.html"
「PCの成功モデルをケータイで」――au向けSNS「EZ GREE」の狙い http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0610/30/news080.html KDDI、初の携帯専用SNS・グリーと組む http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20061030AT1D3004J30102006.html KDDIとグリー、携帯向けSNS「EZ GREE」を2006年11月に開始 http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20061030/252243/?ST=newtech 「参加するケータイ」へ、KDDI、グリーと提携して携帯向けSNSを提供 http://journal.mycom.co.jp/news/2006/10/30/422.html KDDIとグリー、11月から携帯向けSNS「EZ GREE」開始 http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/31728.html"
2006-11-04 00:06:00,父親のためのSNS
2006年11月中旬に、父親のためのSNSが開設される。 www.daddaily.com http://prweb.com/releases/2006/10/prweb465110.htm ▼デジタルハリウッド大学院 話題のバーチャル3Dワールド、「セカンドライフ」研究室を設立。専用講座を12月開講、仮想空間クリエイターを育成http://www.dhw.co.jp/news/release/contents20061026.html
▼新たな支店はネット世界内、「Second Life」を有効活用する米企業たちhttp://www.gamenews.ne.jp/archives/2006/10/second_life12.html
▼Nissan Integrates Second Life into Sentra Campaign http://freshtakes.typepad.com/sl_communicators/ ▼Pontiac Empowers Car Culture In Second Life (米国自動車企業GMのプレスリリースです。) http://media.gm.com/servlet/GatewayServlet?target=http://image.emerald.gm.com/gmnews/viewpressreldetail.do?domain=2&docid=29830
▼一歩先行くネットワークゲーム『セカンドライフ(Second Life)』の日本語版、まもなく公開 http://www.gamenews.ne.jp/archives/2006/09/second_life.html
▼マス・マーケティング崩壊の足音が聞こえる http://katoler.cocolog-nifty.com/marketing/2006/10/post_ea19.html
▼エムログ、オウケイウェイヴと資本/業務提携。動画ビジネス分野で協業 http://www.venturenow.jp/news/2006/10/30/1129_013377.html ▼グーグルによるYouTube買収とWeb2.0無料経済の普及 http://techtarget.itmedia.co.jp/tt/news/0610/25/news01.html
何れにしても次世代のネットコミュニティは、社会的ネットワーク論やパーソナルネットワーク論など、SNSで注目された社会学研究の成果を意識したものになると思います。
そしてそれにゲームなどで培われた創造性が新たに加わりそうです。
これまでのようにIT屋さんが技術論だけでネット・コミュニティを考える時代は終わっています。(無論、下位のレイヤーが技術論であることには変わりありませんが)
また広告費のインターネットシフトは我が国でも確実に進んでいます。(上の記事「マス・マーケティング崩壊の足音が聞こえる」参照)
Web2.0と下位コンセプトである集合知やラディカル・トラスト、自己表現やコモンズなどを貫く社交インフラを示すコンセプトに『ソーシャルメディア』があります。
■インデックスHD、ゆびとまを子会社化--SNS事業を拡大 http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000056020,20293867,00.htm インデックス・ホールディングス(インデックスHD)は10月30日、小学校から大学まで全国6万校を網羅した同窓会支援SNS「この指とまれ!」を運営するゆびとまの発行済み株式5100株(50.5%)の取得に関して基本合意し、同社を子会社化すると発表した。
■クイズで学ぶ安全なSNSの使い方――FTCが公開 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0611/01/news087.html 米連邦通信委員会(FTC)は10月31日、子どもがクイズ形式でソーシャルネットワーキングサイト(SNS)の安全な使い方を学べるゲーム「Buddy Builder」を発表した。
"
2006-11-04 00:18:00,本当の国際競争はこれから始まる
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061102-00000025-inet-sci
■米国フーバーがビジネスSNSを立ち上げた『Hoovers Connect !!』 Hoovers Launching Business Social Networking Site http://www.webpronews.com/blogtalk/blogtalk/wpn-58-20061030HooversLaunchingBusinessSocialNetworkingSite.html ビジネスSNSはLinkedInが七百八十万人の参加者を持っているだけであり、どうも存在感が薄かったのですが、ここに来て変化がありました。
本当のコネクション作りは消費の世界ではなくビジネスの世界だと言う訳です。ソフトウエアはビジネスSNSパッケージ大手のビジブルパスを使っています。
ビジネスのSNSが伸びない理由が幾つか述べられていますが、一つにはマイクロソフトのデスクトップ環境が邪魔だと主張しています。そこでこれをビジネスSNSで改善しようと言う訳ですね。
"
2006-11-04 00:26:00,海外のSNSのビジネスモデル
【2004-9】 Social networks seek financial friends■Friendster 本部: Sunnyvale 従業員: 50 資本: $1300万ドル from Kleiner Perkins Caufield & Byers, and Benchmark Capital. 参加方法: 招待 目的: 友達とつながること(三ステップまでの) ユーザは、ネットワークを広げることもできるし、身内でひっそりすることも出来る。 ビジネスモデル: 広告 ■Tickle 本部: San Francisco 従業員: 60以上 資本: 900万ドル (August Capital invested $7 million, individual investors $2 million). In May acquired by Monster, for undisclosed sum. 参加方法: www.tickle.com.から 目的: さまざまな方法で人々をマッチさせる。 質問事項やSNS的な方法で。 デフォルトは、4ステップまでの交流。金を払うとそれ以上。 ビジネスモデル: マッチメークや他のサービスで手数料を取る。 今はMonsterに統合 ■LinkedIn 本部: Mountain View 従業員: 27 資本: 470万ドル from Sequoia Capital. 参加方法: Can sign up at wwww.linkedin .com, can then invite in others into your network. 目的: 産業や会社や地理的、またはプロフィールのタイトルやキーワードによって 人々がお互いを検索し、出会う。4ステップまでの人と知り合うことができる。 ただ間にいる人の認証が必要。 ビジネスモデル: プレミアサービスが来年の早くに登場。 ヘビーユーザターゲットであり、大部分はリクルーターだろう。 第二の収入源としての広告。 ■Tribe Networks 本部: San Francisco 従業員: 28 資本: 630万ドル in venture financing from Mayfield Fund, Knight Ridder and the Washington Post. 参加方法: Sign up at www.tribe.net. 目的: ネットワークは4ステップまで。 ただ、個々の興味ベースで組織されたTribesによってさらに つながることが可能。Tribesは、管理人によって OPENもCLOSEもある。 ビジネスモデル: 個々の項目別広告費用(仕事やアパートなど) ■Orkut 本部: Mountain View, service offered by Google. 参加方法: 招待生 目的:友達と知り合う ビジネスモデル: 不明"
2006-11-04 00:33:00,ソーシャルネットワーキング体験記
【2004年01月29日 09:12】 LinkedInは、出会い系ではなくプロフェッショナルネットワークにフォーカスしたSocial Networkingのスタートアップ。セコイアが470万ドル投資してバックについてはいるが、まだまだアーリーステージのベンチャーである。
1月6日「ソーシャルネットワーキングがブレークするには」でもご紹介したように、LinkedInですぐ仕事が見つかったという有効事例が出たりする一方、ビジネスモデル全体に胡散臭さを感じる人も少なくない。賛否両論が渦巻いている状態と言えよう。
ケースで疑似体験
今日は、このLinkedInにはまっている人の話から。
「NOTHING.BUT.NET | Social Networking, Link by Link」
「These hot new businesses are known as "social networking" companies. They are Web sites and software companies whose goal is to let you leverage your network of relationships by discovering existing connections of which you may not be aware. In a Valley desperate for the "new new thing," social networking has even been declared the next revolution.」
まずはSocial Networkingについての要約がこれ。
そしてこの記事のここから先がけっこう親切に書かれていて、読むとLinkedIn疑似体験ができるようになっている。
まず最初の段階は、
「A week ago, a former boss of mine telephoned. He is in the process of moving and wanted ideas for how to "get connected" in his new locale. I invited him to join LinkedIn and then suggested he search the system for venture capitalists in his new area. Sure enough, he found the names of three people who might be helpful, including one especially interesting venture capitalist.」(元上司から連絡有。彼は引っ越しの最中で、新しい場所でつながるためのアイデアを求めていた。私は彼をLinkedInに Inviteし、彼にその場所に居るVCをシステムでサーチするように勧めた。彼は3人のVCを見つけた。)
LinkedInでは、登録されているすべての人(今はだいたい15万人くらい)を対象にしたサーチができるから、場所や職業でサーチして、ああこの人に会いたいな、というターゲットをまず定めることができる。そして次の段階に入る。
「Next, my former boss requested an introduction through the system. LinkedIn doesn't allow users to cold contact each other; instead, they need to be referred through a chain of mutual contacts (with the aim of keeping down the spam and maintaining users' privacy). So LinkedIn sent his request to me, and I forwarded it to the person LinkedIn told me was the next link in the chain to the venture capitalist. Two links later, the VC received my former boss's request. A week later, they had lunch.」(元上司が、紹介を求めてきた。LinkedInは、知らない者同士がコールドコールで連絡を取り合うことを禁じている。よって、 LinkedInは私に彼のリクエストを送ってきた。私は、VCにつながる鎖の次の人へ、そのリクエストをフォーワードした。2リンク先でVCはリクエストを受け取り、元上司はそのVCと1週間後にランチをとった。)
この記事の書き手が元上司をinviteしたわけだから、LinkedInシステムに登録した瞬間の元上司のLinkedIn上のダイレクトリンクは、この記事の書き手しか存在しない。よって書き手がまずは元上司の「VCに会いたい」というリクエストをendorse(承認)してやる必要があるわけだ。
「I don't know the VC in question. In fact, I don't even know who does. But I do know Ross, a very well-connected CEO of a start-up in Silicon Valley. LinkedIn knows that Ross and I know each other because we told the system so. Similarly, LinkedIn knows who else I know and who else Ross knows.」(私はそのVCを全く知らない。でも私はRossという顔の広いベンチャーのCEOをよく知っている。LinkedInはRossと私が知り合いであることを知っている。LinkedInは私が他に誰を知っているかも知っているし、Rossが他の誰を知っているかも知っている。)
というわけで、LinkedInの指示に従って、Rossを手がかりに、知人の知人をたどっていくことで、目的にたどりつこうとするのである。知人の知人がendorseしてくれなければ何も起こらないが、endorseしてくれれば、どんどんつながっていく。
「In short, by building these kinds of links, a social networking site such as LinkedIn creates a vast web of relationships that link each individual to thousands of others through three and four degrees of separation.」
LinkedInは、個々の人と、3リンクか4リンク先までの膨大な人々とを結びつける関係のウェブ(蜘蛛の巣)を作っているというわけだ。
そして、この書き手のLinkedIn事始めがこちら。
「In total, I've sent LinkedIn invitations to nearly 70 people. As of this writing, my direct network consists of 45 people. Through them, I'm connected to more than 15,000 individuals. Of those who were new to the system when they accepted my invitation, most have started slowly, with an average of two to five connections each. About one-fourth of those who were new have just one connection (me), suggesting that they're not actively seeking to build their networks but are instead willing to let others find them (through me). On the other hand, one friend who seems to be seeking actively now has 15 connections in just a couple of weeks.」
まずは70人の知人にInvitationを送ったという。LinkedInのユーザにならないですか、と。そのうち45人がLinkedInのユーザになった。つまり書き手のダイレクトリンクになった。それらの人々を通して今、書き手は1万5000人の人とつながっている。Inviteされた新しいユーザの中には、義理で入った人も多いから、そういう人のダイレクトリンクが大きくなるのはゆっくりしたもの。だいたい2人から5人くらいしかコネクションが登録されない。45人のうち4分の1は、この書き手以外にリンクがない。つまり招待は受けたが、それっきりという人だ。でも2週間以内に15コネクションくらい作ったアクティブユーザもいる。何となくリアルな話である。
実際に使ってみた
さて百聞は一見にしかず。僕も実験してみることにした。
幸い、Pacifica Fundの同僚Tim Orenと、仕事仲間の渡辺千賀からInvitationが来ていたのを思い出して、そのInvitationを受けることにした。
これで、僕のダイレクトリンクは2人。
そしてJTPA仲間の2人(彼らはたぶん渡辺千賀からのInvitationに義理でOKと言っただけなので、彼らのダイレクトリンクは1か2の状態にあった)にInvitationを出し、ついでにCNET Japan山岸編集長がユーザ登録しているのを発見してInvitationを出してみた。Invitationを出した3人は、数時間のうちに皆、その Invitationを受けてくれたので、僕のダイレクトリンクは5人になった。
Tim Orenと渡辺千賀の2人は、たぶん遊び半分・実験半分で、けっこうたくさんダイレクトリンクを張っていた。Tim Orenは24人へ。渡辺千賀は21人へ。他の3人は、言えば、義理ユーザ、休眠ユーザである。
さてそれだけで、僕の4 degree先までのネットワークは何人になったでしょう。
答え。3万3104人。
これだけの人へ、一応、何らかの形でつながりの経路ができたわけだ。たぶんその大半は、僕のダイレクトリンクの5人のうち、たくさんリンクを張っているTim Orenと渡辺千賀経由のものと考えられる。
数千人のネットワークが手に入るということの価値
自分がダイレクトリンクを張る人を、「まぁ、自分が頼めば、その先のリンクを紹介してくれるくらいには、自分との間にトラストがある人」だけに絞って登録すれば、2 degrees of separationまではかなり高い確率で到達できるだろう。そして、そのもう一つ先、つまり3 degrees of separation先にも、「あいつが言うなら」くらいのことをその先に居る人が思えば紹介してもらうことができるかもしれない。3 degrees of separation先までの総数は、LinkedIn事始めから比較的簡単に、数千のオーダーにまではいってしまうのではないかと考えられる。
それがどうした? と思う人もいるだろうし、凄い!、と思う人も居るだろう。読者の皆さんはどうだろう。
LinkedInは今のところ誰でも無償で登録できて何をしても無償。そこから、「ほぼすべてのユーザは無償で、ネットワークから目的を持って価値を引き出そうとするユーザに課金」というモデルに、ある時期が来たらスイッチしようと考えているようだ。課金モデルが本当にワークするほど、このネットワークにリアルの価値があるのか、というところが最大の疑問ではあるが、LinkedInは、ユーザ・インタフェースも機能も、そこそこよく考えられて作られていると思う。
LinkedInについては、渡辺千賀Blog「ネットワーク:LinkedIn」、「LinkedIn2」にも、その感想が書かれているので、そちらもご参照のうえ、ぜひ皆さんも軽く実験してみたら面白いと思いますよ。
"
2006-11-04 01:17:00,インターネットの普及がもたらした学習の高速道路と大渋滞
2004年12月06日 09:36 トラックバック (51) コメント (8)
さてその中で、伊藤さんと吉岡さんの文章の中に「高速道路」という比喩が出てきました。 伊藤さんの「インターネット時代のエンジニアの価値」では、
「先日梅田さんにお会いしたときに「(人の成長に影響を与えるものとしての)インターネットは、高速道路だ」と仰っていました。プログラムのソースコードのように、「ネットワーク上を伝播することが可能な物」がナレッジの基礎となるような分野においては、その道のプロになるための高速道路が敷かれているのが昨今の状況なのです。」
「プロになるための高速道路が整備されたということは何を意味するでしょうか。それは、エンジニアの相対価値の低下を意味します。これまでその道のプロだとして希少性をもって価値を発揮していた人々は、後続の高速道路乗りたちにあっという間に追いつかれてしまいます。そこから先はもう大混雑。数歩先に抜きん出るのも大変な状況です。」
「対外的な交渉能力や管理能力などのメタな知識を除いた、いわゆる技術に関しての能力という意味では、高速道路の登場により各個人間での差がどんどん縮まってきているのが今の状況なのです。」
というふうに。また、吉岡さんの「スパコン開発にもコモディティ化の波」では、
「梅田望夫流に言えば「高速道路」が整備されたおかげでスーパーコンピュータ製作という敷居が劇的に下ったということか。」
というふうに。
「高速道路」のオリジナルは将棋の羽生善治さん
今日は、この比喩としての「高速道路」ということについて、補足しておきたいと思う。
11月の東京出張中に、高林さんは残念ながら海外出張中で欠席だったが、今回ゲストをお願いした宮川さん、伊藤さん、吉岡さんと、CNET Japanの山岸編集長らも交えて、あれこれと話をする機会を得た。そのときに話題になったのが、この「高速道路」という比喩だったのだ。
ただ実はこの「高速道路」の比喩は僕のオリジナルではなく、将棋の羽生善治さんに教わったことだった。
東京で久しぶりに羽生さんと食事をしていたとき、ごくごく自然に「ITやインターネットが将棋に及ぼす影響」へと話題が展開していった(今日ここでその話の内容について書くことは、羽生さんの了解をいただいた。念のため)。
ITの進化とインターネットの普及で変わる将棋
この10年のITの進化とインターネットの普及によって将棋の世界の何がいちばん変わったか。
羽生さんは簡潔にこう言った。
「将棋が強くなるための高速道路が一気に敷かれたということだと思います。でも、その高速道路を走り切ったところで大渋滞が起きています」
羽生さんは1970年生まれの34歳。彼は15歳のときにプロになった。彼の修行時代たる10代は1980年代にあたっている。1980年代といえば、IT化がそれ以前に比べれば少しは進んでいた時期。でも自分は、「IT化以前(特にインターネット以前)の環境で強くなった」というのが羽生さん自身の認識である。そして今の若い人たちの将棋の勉強の仕方は、自分たちの頃のやり方と全く違うと彼は言った。
本欄は将棋にあまり興味のない読者が大半だろうから、その話の詳細は割愛するが、要は「情報の整理のされ方と行き渡り具合の凄さ・迅速さ(序盤の定跡の整備、最先端の局面についての研究内容の瞬時の共有化、終盤のパターン化や計算方法の考え方など)」と「24時間365日、どこに住んでいようと、インターネット(例、将棋倶楽部24)を介して、強敵との対局機会を常に持つことができる」という2つの要素によって、将棋の勉強の仕方が全く変わってしまった。そしてそれによって、将棋の勉強に没頭しさえすれば、昔と比べて圧倒的に速いスピードで、かなりのレベルまで強くなることができるようになった。そこが将棋の世界で起きているいちばん大きな変化なのだ、と彼は言った。
アマチュア最高峰までの高速道路が整備された
僕は思わず、
「それで、かなりのレベルまで強くなるって、どのくらいのレベルのことをおっしゃっているんですか?」
と質問した。羽生さんの答えは、
「奨励会の二段くらいまででしょうか」
だった。制度的には、奨励会は三段までで、四段からプロ棋士になる。
ただ羽生さんの言う「奨励会の二段」の強さということをざっくりと解釈すれば、アマチュアならほぼ最高峰の強さ、現実の制度としてはプロ棋士の一歩手前、でも実際は弱いプロよりはかなり強い、そんなレベルの強さという意味である。
そのレベルまで強くなるための道具立ては、ITとインターネットによって整備された。
それを羽生さんは「高速道路が一気に敷かれた」と表現するのである。
「将棋の駒の動かし方すら知らない小学校高学年生が5年くらいでプロ棋士にまで駆け上がる」ということが将棋界では起きているそうなのだが、そのことは、天才・羽生善治をもってしても、
「自分たちの世代の感覚からすると、全く信じられないスピードなんです」
ということになる。
高速道路の後の大渋滞
つづいて僕は、
「でもそれで、そのあとの大渋滞って、どういうことなんですか?」
と問うた。
彼の答えは、言葉の表現までははっきりと覚えていないのだが、
「確かにそのレベルまでは一気に強くなれるのだが、そこまで到達した者たち同士の競争となると、勝ったり負けたりの状態になってしまい、そこから抜け出るのは難しい。一方、後ろからも高速道路を駆け抜けてくる連中が皆どんどん追いついてくるから、自然と大渋滞が起きる。最も効率のよい勉強の仕方、しかし同質の勉強の仕方で、皆が、高速道路をひた走ってくる。結果として、その一群は、確かに一つ前の世代の並のプロは追い抜いてしまう勢いなのだが、そうやって皆で到達したところで直面する大渋滞を抜け出すには、どうも全く別の要素が必要なようである」
ということであった。
なるほど最高峰の人が語る内容は深いなぁ、とその場で思ったばかりでなく、噛んでも噛んでも味が出てくる含蓄のある内容であったと、あとになって思う。
ネット産業にもあてはまる「高速道路と大渋滞」
羽生さんと別れたあと、僕はこの「高速道路と、その先の大渋滞」という話が、頭にこびりついて離れなくなった。
それで、ゲストブロガーの皆さんと会ったときに、この「高速道路と大渋滞」の話を、ネット産業の発展やエンジニアのキャリアに置き換えてもかなり共通点があるのではないか、というようなテーマを視点として提供したのだった。伊藤さんと吉岡さんが、それに反応してくださって、冒頭に引用した文章になったという経緯であった。
伊藤さんは、「インターネット時代のエンジニアの価値」の中で、プログラマにとっての「高速道路」の一例としてネット上に溢れるソースコードを挙げ、また、大渋滞を抜ける彼なりの戦略を語ってくれている。たいへん貴重な内容である。まだの方は是非、ご一読いただきたい。
吉岡さんが、「スパコン開発にもコモディティ化の波」で提示された、広島県立広島国泰寺高等学校のPCクラスタも、間違いなく「高速道路」の一例であろう。
何かを学ぶことにおいて「高速道路を走る」競争というのは、それをやり遂げる意思の強さを競うということなのかもしれない。意思さえあれば、かなりのところまで一気に行ける環境が整ったことが、「高速道路が敷かれた」ということの意味なのだろうからだ。
「大渋滞を抜ける」には
しかしその先の「大渋滞を抜ける」競争を抜けるためには、それだけではない、もっと違う何かが必要になる。
羽生さんと会って以来、僕は毎日、この「高速道路と、その先の大渋滞」の意味を考え続けている。
結局、羽生さんとの議論でも容易に言語化することができなかった「では大渋滞を抜けるためには何が必要なのか」ということについては、いずれ考えが深まって、いつかどこかに書ける日が来たらいいなと思う。ITやインターネットの意味を考えていく上で、ものすごく本質的な問題提起だと思うからだ。
"
2006-11-04 01:42:00,※Mobile2.0を特徴付ける事例
Daniel K. AppelquistというブロガーはMobile2.0を特徴づける事例を次のように挙げている。 (ソース:What is "Mobile 2.0"?,Dan's Blog)
| Mobile1.0→ | Mobile2.0 |
| SMS → | IM (e.g. Yahoo! messenger for mobile) |
| MMS → | Media sharing (e.g. ShoZu) |
| Operator Portals → | Mobile Web and Search |
| Operator chooses → | User chooses |
| Premium SMS billing → | Mobile stored value Accounts (e.g. Luup) |
| Java Games → | Embedded Applications (e.g. Blogger application) |
| Presence & Push-To-Talk → | Embedded VOIP applications |
| WAP sites → | Mobi sites |
| WAP push → | RSS readers |
| Wallpaper → | Idle screen applications |
| Location services → | Google maps application |
| Time or volume-based pricing → | "All you can eat" data charging |
| Content consumption → | Content creation (e.g. mobile blogging) |
"
2006-11-04 01:44:00,※欧米のMobile2.0サービス
・Blinkx ・Bluepulse Internet 2 cell phone ・Clicktoscan Scan, store & share documents with your phone camera ・CommonLoop ・Crickee With Crickee, users can send and receive loads of SMS ※LINK"
2006-11-04 02:59:00,※弱い絆の強み
スタンフォード大学社会学部教授のマーク・グラノヴェッターが1972年に発表した「The Strength of Weak Ties」という論文がある。後世の社会学に大きな影響を与えた論文である。 この論文の主張は、「社会的絆によって形成される社会ネットワークにおいては、古くからの友人といった、自分にとって強い絆で結ばれている人物よりも、ちょっとした知り合いのような弱い絆で結ばれた人物のほうが、自分に与える影響が大きい。」ということである。 ※LINK"
2006-11-04 04:30:00,出会い系サイトのサクラ
323 :名無しさん@ピンキー:2006/11/03(金) 00:58:24 ID:YRBbPqXe --------------------------------------------------- 出会い系サイトのサクラをやっていました。 ぼくは男です。 顔写真は、古い雑誌から拝借していました。 いくつものサイトをかけもちしていました。 全てポイント制のサイトです。 自分とやり取りしたメールのポイントに応じて報酬があります。 ぼくの場合は完全歩合制でした。 99%の出会い系サイトは、99%がサクラです。 良心的なサイトもあるにはあると思いますが、 そんなサイトにも女性として登録していました。 来たメールには丁寧に返信し、最終的にポイント制サイトに誘導します。 間に入っている業者とトラブルになり頭来ています。 殺されるのでサイト名やその業者の事は言いません。 「PCデータ入力」などの名目でバイト募集していることがあります。 コピペして構いませんので、できるだけ多くの人に知らせてほしいです。"
2006-11-06 20:19:00,※日本のIRC事情
日本のIRC事情を調べた。Googleやはてなで調べただけであるが、英語圏に比べるとほとんど普及していないと思った。日本のIRCサーバとりまとめの役割をしていた京大IRCサイトもなくなっていたし、検索に引っかかるサイトや記事も少ない。 はてな記事で紹介されていた日本のIRCネット6サイトを覗いたが、「閑散としている」という印象であった。その中ではIRC@2chが、JavaベースのUIを備えているためか参加者が多かった。多いといっても訪問者数は、チャネル合計でせいぜい2千人で、英語圏からみれば1チャネル相当である。 ※LINK
"
2006-11-16 19:22:00,IT普及による学習の高速道路と渋滞
この話は2年前にさかのぼる。ミューズアソシエートの梅田さんが、「この10年のITの進化とインターネットの普及によって将棋の世界の何がいちばん変わったか?」と、将棋の羽生善治さんにたずねたら、こう答えたと言う。
「将棋が強くなるための高速道路が一気に敷かれたということだと思います。でも、その高速道路を走り切ったところで大渋滞が起きています」
この話は、まさしくソフトウェア業界やコンサルタント業界でも起こったことである。比喩としてたいへんわかりやすいので梅田・羽生さんの問答(一部編集・割愛)を紹介する。
ITの進化で変わる将棋
羽生さんは1970年生まれで、15歳のときにプロになった。彼の修行時代たる10代は1980年代にあたっている。その時代は、IT化がそれ以前に比べれば少しは進んでいた時期だが、「IT化以前(特にインターネット以前)の環境で強くなった」というのが羽生さん自身の認識である。そして今の若い人たちの将棋の勉強の仕方は、自分たちの頃のやり方と全く違う。
「情報の整理のされ方と行き渡り具合の凄さ・迅速さ」と「24時間365日、どこに住んでいようと、インターネット(将棋倶楽部24など)を介して、強敵との対局機会を常に持つことができる」という2つの要素によって、将棋の勉強の仕方が全く変わってしまった。そしてそれによって、将棋の勉強に没頭しさえすれば、昔と比べて圧倒的に速いスピードで、かなりのレベルまで強くなることができるようになった。そこが将棋の世界で起きているいちばん大きな変化なのだ。
アマチュア最高峰までの高速道路が整備
かなりのレベルというのは、「奨励会の二段くらいまで」という。アマチュアならほぼ最高峰、プロ棋士の一歩手前で、弱いプロよりもかなり強いというレベルだそうだ。そのレベルまで強くなるための道具立ては、ITとインターネットによって整備された。それを羽生さんは、「高速道路が一気に敷かれた」と表現する。
「将棋の駒の動かし方すら知らない小学校高学年生が5年くらいでプロ棋士にまで駆け上がる」ということが将棋界では起きているそうなのだが、そのことは、天才・羽生善治をもってしても、
「自分たちの世代の感覚からすると、全く信じられないスピードなんです」
ということになる。
高速道路のあとの大渋滞
そのあとの大渋滞とはどういうことか?梅田さんの問いに対する羽生さんの答えである。
「確かにそのレベルまでは一気に強くなれるのだが、そこまで到達した者たち同士の競争となると、勝ったり負けたりの状態になってしまい、そこから抜け出るのは難しい。一方、後ろからも高速道路を駆け抜けてくる連中が皆どんどん追いついてくるから、自然と大渋滞が起きる。最も効率のよい勉強の仕方、しかし同質の勉強の仕方で、皆が、高速道路をひた走ってくる。結果として、その一群は、確かに一つ前の世代の並のプロは追い抜いてしまう勢いなのだが、そうやって皆で到達したところで直面する大渋滞を抜け出すには、どうも全く別の要素が必要なようである」
「最高峰を極めた人の語る内容は深いなぁ」と梅田さんは感嘆しているが、まったく同感である。この話は2年前の2004年秋頃、梅田さんのブログ記事から知った。良質の記事はいつまでも記憶に残る。含蓄のある内容に共感し、そこで指摘している「高速道路と大渋滞」の意味することを考え続けさせてくれる。「高速道路が整備され、学習のスピードが上がった」ことは理解できる。私自身が日ごろ実感していることであるからだ。そして、この将棋の世界での話は、あらゆるビジネスの世界にも当てはまる話であろう。
高速道路の例
ソフト業界では、はてなの伊藤さんが、プログラマにとっての「高速道路」の一例としてネット上に溢れるソースコードを挙げ、ものすごい勢いでプログラミング技術を学習できると論じている。ミラクル・リナックスの吉岡さんは、いまや高校生がスパコンを開発できる時代であることを指摘し、広島県立広島国泰寺高等学校のPCクラスタの例を挙げている。普通のPCとオープンソース、そしてちょっとした工夫をして、10年前だとトップ30に入るスパコンをいとも簡単に作ったことを紹介している。
Webサービス構築
私自身の経験で言えば、ブログサービスのインフラは、数時間で作れるようになった。LAMP環境(30GB)を月800円でレンタルして、オープンソースのブログソフト(Movable TypeやWordPress)をインストールすれば開発完了である。2年前にブログを自分がレンタルしたサーバ上で始めたときは学習に数日かかった。いまはLAMPの環境が整備されているので、新しいオープンソースのブログあるいはCMSやWIKIソフトを使えるようにするのに要する時間は1時間以内である。いま流行の、といっても話題になったのは2年前であるが、SNSサービスのインフラ開発もたった一日でできた。こうしたシステムを伝統的なSI業者に「どれくらいの期間と費用でできるか?」と聞いたら、その多くは「早くて半年で、開発費は5000万円から1億円・・・」と答えるのではないだろうか?
情報力の増大
別のブログにも書いたが、情報を掴む、読む、伝えるというプロセスのスピードは、この十年で十倍、20年前に比較すれば100倍にあがったといっても言い過ぎではないくらいである。しかも、そのことが、ニュース記者や特派員、企業の駐在員、企画部員や広報部員といった情報を扱うことを専門とする人たちだけでなく、また現地駐在という地理的条件によらず、いつでもどこでもだれでもができるようになったとうことは驚くべきことである。そのことに気づき、これを活用して、「ネットの向こう側に潜んでいるもの」を知って、コミュニケートするかどうかの違いが、これからの知識と智恵の質量を左右するのだと思う。ときとして、それまで知らず、まったく係わりのなかった「ネットの向こう側に棲んでいるもの」と対峙せざるを得ない状況にも遭遇する。それは人生の新しい冒険の始まりであり、実にエキサイティングなものでもある。"
2006-11-17 05:51:00,ワンタイムパスワード
ワンタイムパスワードは何のためにあるのか http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20061021.html TrackBack URL: http://takagi-hiromitsu.jp/diary/tb.rb/20061021再利用はできないのだから、「再利用によって不正取引される」ことがないのは事実だが、一回目の利用としてその瞬間(30秒以内)に不正取引される可能性があるのだから、「万が一フィッシングなどで......ありません」などと、フィッシングされても大丈夫であるかのような誤解を与える表現は危険だ。
野村総研がリンクする際には文書で申し出よというので文書で申し出た
野村総合研究所はWebサイトの「サイト利用規定」で、リンクについて「必ず事前に文書で申し出よ」と定めている。 http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20061001.html#p01
"
2006-11-17 06:32:00,日本語とオブジェクト指向
http://satoshi.blogs.com/life/2004/09/post.html 日本語はまさにオブジェクト指向である。テーブルの上の塩をとって欲しい場合、たいていの日本人は、「すいません、塩を...」まで言ったところで一呼吸置く。「塩」というオブジェクトを指定した時点で、「とって欲しい」ことは自明であり、ここまで言えば、99.9%の日本人は塩をとってくれる。「え、この塩で何をしろって言うんですか?」と聞き返す人はよほどの変人である。エレベーターに乗って、階ボタンの近くにいる人に、「すいません、12階を...」まで言えば十分なのも同じである。つまり、日本人が「塩を...」とか「12階を...」とかで一呼吸置いて相手に類推を促すのは、ウィンドウズにおけるダブル・クリックと同じことをしているのである。 http://satoshi.blogs.com/life/2006/03/post_8.html
ソフトウェアの仕様書は料理のレシピに似ている
経済産業省の今の悩みは、「IT産業の階層化の弊害によっておこる下流のプログラマーの収入の低下」だそうである。「プライムベンダー」と呼ばれる「上流コンサルタント」たちがインドや中国にも仕事を発注できることを理由に、激しく値切り始めたために、今やわずか一人月30万円というケースもあるという。 「どんなに優秀なエンジニアでも、決してプログラムを自分自身で書かずに良い詳細仕様を作ることは出来ない」という絶対的な法則があるのだ。私の知っている優秀なエンジニアは、皆それを知っており自ら実行している。もちろん、彼らはプログラムを書き始める前に大まかな設計をするのだが、十分な経験を積んだエンジニアは、その段階でのものが「仮設計」でしかないことを良く知っている。だから、その段階で詳細設計書を書くような時間の無駄使いはせず、すぐにプログラム(もしくはプロトタイプ)の作成にかかるのである。 階層構造化されたエンタープライズ系のエンジニアたちよりは、オープンソース系の「設計からコーディングまで全部自分でやる」エンジニア達の方がずっと元気があるし幸せそうだ、ということだけははっきりと言える。"
2006-11-17 06:54:00,スティーブ・ジョブスに学ぶプレゼンのスキル
「多くの人が勘違いをしているのだが、プレゼンの主役はパワポのスライドではなく、プレゼンをしている本人である。社内の企画会議であれ、顧客に対するセールスであれ、一番強く印象付けるべきは、提案する企画や商品ではなく、プレゼンをする自分自身なのだ。もちろんプレゼンの中身も重要なのだが、本当に重要な情報はどのみち文書で別途提出することになるので、プレゼンの段階で重要となるのは、とにかく自分を印象付け、「こいつの提案する企画に社運を賭けてみよう」、「こいつを見込んでこのテクノロジーを導入してみよう」などと思わせることである。やたらと文字ばかり並べたスライドを読み上げるだけの人がいるが、それでは、貴重な時間を使ってプレゼンをしている意味がない。スライドにはわずかなキーワードと画像データ(商品の写真、グラフ、ブロックダイアグラムなど)だけを置いておき、大切なことは自分の口でしゃべる、というのが正しいプレゼンの方法だ。それも、話す内容をあらかじめ丸暗記などしてはだめで、相手の理解度や興味に応じて、適切に言葉を選んだり重要なポイントを繰り返したりしながら進めなければいけない。」 スティーブ・ジョブスによる新型iMacの発表 2005.10.12 http://news.com.com/1606-2-5894182.html (1)文字が極めて少ないこと、 (2)画像が効果的に使われていること、 (3)ほとんどの情報は文字ではなく、スティーブ・ジョブスの口から伝えられること 中島聡ブログよりhttp://satoshi.blogs.com/life/2005/10/post_4.html 時代にマッチした「サイト利用規約」を作ってみた"
2006-11-18 12:46:00,Open Source Everywhere
Wired誌Open Source Everywhere「Software is just the beginning ... open source is doing for mass innovation what the assembly line did for mass production. Get ready for the era when collaboration replaces the corporation.」 「ソフトウェアは始まりに過ぎない」、つまり、組み立てラインによって大量生産(マス・プロダクション)時代が始まったように、オープンソースによってマス・イノベーション時代が始まる。企業・組織を越えてのコラボレーションが企業・組織を置き換える時代への準備が整った。 オープンソース的コラボレーションが社会を変える 「オープンソースは単にボランティアの活動に依存して独占的でない知的所有権を形成し、コストを引き下げる手段ではない。創造の結果だけでなく過程を共有することによって参加者が互いに触発し合い、これまでに無かったもの、素晴らしいものを作ることができるのだ。それはまた、無数の凡人が互いに思考を共有し、足りない部分を補い、アイディアの連鎖反応を起こすことにより、より大きなインパクトを文明に与えることを可能にするのである。より多くの人に、「自分の生きた証」「自分のいなくなった後に残るモノ」を残す道を開いた、と言っても良いかもしれない。」 知的所有権などで定義される「テクノロジー」そのものを売るビジネスから、そのテクノロジーを使って何かを行う「アプリケーション」を提供するビジネスに価値がmigrateする過程が起きているのではないか."
2006-11-18 22:54:00,報道パワーの源泉
徹底討論「ジャーナリズムの復興をめざして」 立花隆×外岡秀俊 2006年07月31日(土)東京・築地 浜離宮朝日ホール 立花隆・基調講演より
(1)「ニュースギャザリング力」なんです。ニュースを集める力です。大きな報道機関というのは、これを組織的にやるわけです。その組織としてのニュースを集める能力です。日本語では取材力という。
(2)「編集する力」なんですね。ニュースを集めて、その中から取捨選択して重み付けを与えて、それをそれぞれ伝えるメディアに載せる。それに載せる時に、その取り扱い方を決める。一つの紙面の配分を決めるという、それがまさに編集という作業なんですが、その編集の力です。
(3)「すぐれた一覧性紙面の制作能力(整理力)」というものを通じて、社会にその制作物を出していくわけです。一覧性紙面の情報伝達力をもつのは新聞だけです。 (4)「解説力」というのが、メディアにとって、新聞にとって、特に重要なわけですね。 (5)「論説力(オピニオン形成力)」。これは英語ではエディトリアルという、いわゆる論説あるいは社説のページに書かれることなんですが、それが基本的にやろうとしているのは、社会のオピニオンを形成する、そういうパワーです。
"
2006-11-19 20:04:00,10 Ways Women Judge You
 ...And how to win them over anyway Photographs by: , By: Reviewed on 04/06/2005
...And how to win them over anyway Photographs by: , By: Reviewed on 04/06/2005
"So much subliminal information is conveyed in those first seconds of contact
says Carol Kauffman, Ph.D., a relationship therapist and psychology instructor at Harvard medical school. Okay, so you're on the clock. Make every second count. Below are 10 ways - in rough chronological order - a woman judges your fitness to be her proverbial daddy.
"She's watching to see if you put some energy into your dress and groomingsays Aline Zoldbrod, Ph.D., a psychologist and sex therapist in Boston. "If you don't take the trouble to dress well for her now, she could see it as disrespectful."
Does he stare at my breasts? Does he have any sense of humor? If you're a total loser, it pays for her to ascertain that on the first date, says Zoldbrod.
Yes, we always pay for the last guy's sins. "What women want is often based on their past negative or positive experiencessays Kauffman. So when she talks about past boyfriends, heed well.
She needs full use of your closets. There's no room for baggage.
She'll carry 80 percent of the conversation load. Just make sure your 20 percent is about something.
Women somehow see a correlation between leaving a 10 percent tip and having a propensity to drown kittens.
If you can't succinctly state her values, her politics, and her ambitions, you're probably failing here. Ask more questions. Listen to the answers this time.
Ace the other nine criteria here and your odds of appearing needy will edge toward nil.
If you're not reliable, you're not viable, especially not for the ultimate goal of all this. . . .
"For long-term potential, she considers whether you have the values she wants in a man says Jean Koehler, Ph.D., president of the American Association of Sex Educators, Counselors, and Therapists. If she can't see tykes on your knee, she's wasting her time. How you interact with your own family can be a strong indicator here. Link"
2006-11-26 22:07:00,Web 2.0: The power of 2
Revolution UK 20 Jul 2006
Web 2.0 could have a huge impact on marketing, but what is it? Susie Harwood attempts a definition.
The web has always had more than its fair share of buzzwords and acronyms. But, every now and then, one pops up that causes everyone to go completely nuts, yet no-one can actually explain what it means. Web 2.0 is one. A search for it on Google returns no less than 820 million results, more than 'iPod'. At this year's Internet World in May, six speakers, including Lastminute.com founder Brent Hoberman, chose to talk about Web 2.0, and drew the biggest crowds as a result.
But, what is it and, more importantly, what impact will it have on brands' web marketing? As with most buzzwords, there are various interpretations.
Even Tim O'Reilly, founder and CEO of computer book publisher O'Reilly Media, who coined the term in 2004, required 17 pages to clarify its meaning in an article last year, in which he admits: "There's a huge amount of disagreement about what Web 2.0 means, with some people decrying it as a meaningless buzzword and others accepting it as conventional wisdom."
It might be easier to start off with explaining what Web 2.0 isn't, rather than what it is. James Aylett, chief technical architect at Tangozebra, says: "One of the things everyone is agreed upon is that Web 2.0 isn't a technology or even a group of technologies: it's a different way of thinking about web sites."
Many see Web 2.0 as the second generation or phase of the internet, and the key thing that differentiates it from 'Web 1.0' is that it is more open. Or, as Julian Smith, senior research analyst at Jupiter, says: "(The web) has moved relatively quickly from a predominantly one-way, read-only medium to a more two-way, participatory, collaborative and interconnected medium."
This is reflected in the popularity of blogging platforms such as MSN Spaces and Blogger. According to a report by Technorati last year, a new blog is created every second.
Other sites seeing huge growth include: social networking site MySpace.com (now owned by News Corp); online encyclopaedia Wikipedia, edited by millions of people; Youtube, which lets users upload videos; and photo-sharing web site Flickr.com. These are all regularly cited as classic examples of Web 2.0 services, and what they have in common is that they allow users to upload and share their own content.
The Web 2.0 movement is being aided by new technologies such as AJAX, RSS and Ruby on the Rails, which enable web developers to create more dynamic, interactive content. These tools, along with the rapid growth of broadband, are giving users more control over what they consume.
Consumer content
If we take Web 2.0 to mean the democratisation of content and the empowerment of people, it becomes more than just a meaningless buzzword. There's no getting away from the fact that many web sites being built today are more interactive than those developed 10, or even, five years ago.
"Applications like Flickr and Youtube have the consumer at the centre.
These sites exist because of the content consumers contribute and their success speaks volumes. Millions of people are viewing the content says Rob Forshaw, managing partner at digital creative agency Grand Union.
MySpace's user base has more than quadrupled to nearly 80 million over the past year, with as many as 270,000 joining every day.
The idea of users participating online and creating communities isn't new. For example, eBay is an online community built around people buying from, and selling to, each other. Shopping sites like Amazon have allowed consumers to post their reviews for many years. Agency.com's European chairman and founder, Andy Hobsbawm, says: "The difference is that (user participation) is on a much bigger scale now because there are more than a million people online."
Steve Sponder, director of digital marketing agency Lawton eMarketing adds that, because people have been doing it for some time, they are "more comfortable" with participating.
To a certain extent, it could be argued that Web 2.0 is being over-hyped.
But it could have a huge impact on web marketing. Many digital marketers believe traditional advertising models - broadcasting messages via banners and other rich-media formats - will not work in the Web 2.0 world, where the balance of power is shifting from media owner to consumer.
"I suppose you could stick some ads around the content that consumers are placing, but that's going to have limited cut-through and reach says Damian Blackden, Universal McCann's European VP of strategic marketing technologies. "You're talking to an advertising-cynical audience, so it's going to be the more collaborative marketing techniques that work."
Brands can let people have conversations on their sites in any number of ways: by allowing them to post comments or reviews; set up discussion boards; or rewrite content, which is how Wikipedia works. "Different ways are appropriate to different sites, but the aim should not just be to generate content but to build a community says Tangozebra's Aylett.
Some brands are already doing this. Travel company Thomson invites people to write reviews on its web sites while Lastminute.com has created a branded blog platform for its customers. There have also been great examples of high-profile campaigns using offline media to drive people to a site to participate.
Dove's 'Campaign for real beauty', for example, asked consumers to vote on pictures used in its offline ads.
Alternatively, brands can go one step further and give users the tools to create their own content, such as a TV spot, or play with existing content. This practice has been called 'mash-up' and 'co-creation'. High-profile examples include last year's Levi's Mobile Audio Mixer (MAX), where users could create their own ringtone as part of an online competition, with the winner having their track remixed and pressed on to vinyl.
In the US, Converse lets brands create their own TV spots via its site, while car brand Chevrolet placed tools on its site that allowed users to remix and 'mash-up' its latest Chevy Tahoe ads. Some brands have even let users influence the creative of their online ads. In a campaign by mustard brand Colman's, users could create their own characters to participate in a virtual march through banner ads. All these examples are less about pushing a message to users and more about coming up with a creative idea they can be part of. "This phenomenon means brand managers and guardians are having to cede control of the brand and its messages to consumers says Chris Clarke, executive creative director, London, at Modem Media.
Huge step
For businesses that have invested millions in creating a brand, this is a daunting prospect as it can easily go wrong. Chevrolet took down its 'Make Your Own Tahoe Commercial' site after receiving a different response than expected. While it attracted 400,000 participants, 16 per cent created ads mocking the over-sized cars, the nature of the ads and the company.
Graham Donaghue, head of new media at TUI UK admits it was a huge step for the company to allow users to write their own reviews on its site.
"We're not in control any more, and that's a huge move for us, but we have to do it because our customers tell us they want it he says. "With the power of blogs and citizen journalism, someone can easily write information about your brand and post it online, so it's almost better that it's on your own site than elsewhere. It's also incredibly powerful content; a Forrester survey last year revealed that while people trust recommendations from their friends most, reviews on sites were the second most trusted source."
Sponder agrees it's better to let users talk about you in a branded environment: "A brand can gain so much in terms of the credibility it will receive by being approachable and having a human face rather than just communicating one way."
The difficulty for brands is to get the balance of power right. How much control should they concede? Clarke believes E brand control will become less about a set of strict guidelines and more about a core concept or 'DNA'. "You have to be clear on what you can control and comfortable about what you can't he says, adding that there will always be people who are negative. If brands try to control these environments too much, they could end up doing more damage than good. "There's a fine line between making a success of it and your customers thinking it's a big publicity stunt adds Sponder.
While it's relatively easy to see how brands can allow users to create content on their sites, it's not so easy to see how brands can participate in user-centric sites such as MySpace without appearing intrusive. There have been ads on MySpace and some brands have hosted a specific area and these have received a mixed response so far.
But, simple moves like making TV ads or content available to these channels can be effective. Forshaw says Sony uploaded the photos from its Bravia bouncing-balls campaign to Flickr before the ad aired on TV. This linked to a site where the ad and images could be downloaded. "By the time the commercial aired on TV there was a good deal of consumer involvement and activity around it, with people posting the ad on their blogs and distributing it through their social networks says Forshaw.
Tom Hyde, new business director at Profero, feels that, to earn the right to exist in this space, advertisers should enable and enrich consumers' creative tendencies. "Help them to make their MySpace the best and reach a bigger audience. We should celebrate their creativity rather than take advantage of it."
Time to innovate
This could involve creating tools that allow people to do something new or save time. Lastminute.com co-founder Brent Hoberman believes innovation will be increasingly important. "There's never been a better time to innovate.
The viral nature of the web means that if you innovate, people will talk about it, and you won't have to spend a lot of money on marketing. It's simple - give customers tools they can use all the time and they will tell their friends about it he says.
Rather than simply being a place where people go to find out more about the company and its products, a brand site could become more application-based, suggests Modem's Clarke. "Brand sites, as we know them, will probably become a series of applications that are useful, relevant or entertaining he says, adding that these branded applications should be viewed as media spend in the same way as an ad campaign.
With so many consumers expressing their views online, Web 2.0 also has a huge impact on reputation management. Katy Howell, managing director of PR firm Immediate Future, thinks Web 2.0 bridges the gap between PR and marketing.
"Social networks, blogs, user-generated content, tagging, wikis, P2P - all those are about conversation and fall neatly under 'reputation management', which is, essentially, PR says Howell. Companies need to be out there, looking at what people say about them online, and respond in an open and appropriate way. Ignoring even one customer's negative comments on a blog could do serious damage to a brand's reputation.
She highlights the Dell Hell example, where one individual, Jeff Jarvis, ranted in a blog about his bad customer service experience, which quickly spiralled out of control, with more bloggers joining in and spreading the message. "It must be a nightmare being a brand marketer and seeing all these messages going around about you, but you can't just ignore the web because it makes you feel uncomfortable says Howell. "Web 2.0 is making it more powerful, but it would be a shame if people look at it with fear. The reality is that there's a great opportunity to build true advocacy."
Brands can learn an awful lot from blogs and social networks, which they can use to their advantage; not just to get their marketing messages right but also on a deeper business level, by involving consumers in product development. It's a great way to find out what people are talking about and what the key trends are. Or, as Lawton's Sponder puts it, to identify the 'zeitgeist'.
"It's probably one of the best opportunities we have and can help forgo the enormous expense of creating the wrong products. By talking to the people who buy them in a cost-effective way early on in the process, brands can find out what products are likely to be well-received says Forshaw.
"It also overcomes the large-scale changes that a brand has to undertake when trends take hold." He says many debates, such as the current ones over obesity and global warming, actually start online before they hit mainstream media.
Web 2.0 may be difficult to define and is, perhaps, being hyped up more than it deserves, but it's clear that something significant is happening that should be taken seriously by marketers. If a company's messages do not align with what consumers are saying about it online, a credibility gap could emerge, which will have a huge impact on brand reputation.
Forshaw adds: "One of the problems with Web 2.0 is that it is a fashionable, fickle term, but many of the things that are happening in terms of social networking and social computing are phenomena that are going to stay."
Marketing 2.0: campaigns that have embraced user control
A rising number of digital marketing campaigns over the past year have enabled users to generate their own content. Here's a few:
Orange Paper Film Festival, by Poke
Entrants were invited to shoot a film on their mobile and send the clip via MMS to the Orange web site, where they could then edit them, and add a soundtrack and titles. Winners of the 'Palm de Paper' were presented with awards at a ceremony. The campaign won a BIMA award for best integrated campaign last year.
Sony PlayStation Summer of Freedom, Greenroom Digital
Sony ran a competition to find four 'Freedom Explorers' to act as cheerleaders for the brand. They were whisked to events throughout the summer and kept video blogs of their experiences, which users could read on the PlayStation Freedom site. Visitors could also upload their own video blogs, with a prize awarded to the best each week.
Coca-Cola World Cup campaign, bdnetwork
The soft-drinks giant invited users to take a digital photo of themselves, which showed just how much they love the World Cup, and send it in via MMS or email for the chance to win a pair of tickets to see a World Cup game every day throughout June.
Levi's Mobile Audio Mixer (MAX), Lateral
The fashion brand created web tools that enabled users to create a ringtone as part of an online competition last year. The best submission had their track remixed and pressed on to vinyl. There are rumours that the brand is considering launching the winning track as a single.
"
2006-11-27 03:11:00,The Long Tail of software
March 10, 2005
 Joe Kraus, one of the founders of Excite, has a new company that's based on what he calls the Long Tail of software. Called JotSpot, it's building a wiki-like platform that makes it easy for firms to create custom applications for their specific business needs, much as they do with Excel spreadsheets today. He briefed me about this some time ago, but I wasn't able to talk about it until now. Fortunately, he's done all the talking for me with a really interesting post on his own blog that nicely shows how broadly the Long Tail theory can be applied.
Joe Kraus, one of the founders of Excite, has a new company that's based on what he calls the Long Tail of software. Called JotSpot, it's building a wiki-like platform that makes it easy for firms to create custom applications for their specific business needs, much as they do with Excel spreadsheets today. He briefed me about this some time ago, but I wasn't able to talk about it until now. Fortunately, he's done all the talking for me with a really interesting post on his own blog that nicely shows how broadly the Long Tail theory can be applied.
The long tail doesn't just apply to music and movies. There's a long tail for software as well. Here's why.
First, every business has multiple processes. Things like hiring, firing, selling, ordering, etc. Second, while some of these are pretty common in name from business to business (recruiting, for example), in practice, they are usually highly customized. Finally, there are simply a large number of processes that are either unique or that are common to millions of very small markets and therefore not traditionally worth the effort to buy software for (for example, the process by which an architecture firm communicates between it's clients and the city planning office).
These three facts
- every business has multiple processes
- processes that are similar in name between businesses are actually often highly customized
- there exist a large number of processes unique to millions of small clusters of industries.
means that there is a combinatorial explosion of process problems to solve and, it turns out, little software to actually support them.
Said another way, there is a long tail of very custom process problems that software is supposed to help businesses solve.
There are also loads of great charts illustrating the point in a ppt file you can download from his site here.
September 24, 2005
The Long Tail of software (part 2)
 Last week I gave a keynote address at the annual Salesforce.com user meeting, which has become a huge, multi-thousand-person affair at San Francisco's Moscone center. Salesforce was launching its new application marketplace, called AppExchange, which is modeled on the Long Tail theory.
Last week I gave a keynote address at the annual Salesforce.com user meeting, which has become a huge, multi-thousand-person affair at San Francisco's Moscone center. Salesforce was launching its new application marketplace, called AppExchange, which is modeled on the Long Tail theory.
I'd been speaking with CEO Marc Benioff and his staff during the development of the exchange and I was both enthusiastic about the idea and curious to see how well the theory would apply in enterprise software. The answer is: surprisingly well.
Joe Kraus of Jotspot was the first to really develop a Long Tail framework for software, which I wrote about here. As he pointed out, you can think of the many thousands of Excel templates that have been created over the years by individuals for their specific needs as small, targeted software applications running on a common platform. Although they probably didn't think of it this way, each of those accountants, project leaders and HR managers was acting as a software developer of sorts. But the "software" they developed was rarely used by anyone outside their company, and it was limited by the constraints of the platform--Excel--on which it ran.
The old commercial software model was, like so many others, largely hit-driven. Software companies developed bloated one-size-fits-all software applications for big markets, and then left the customizing of that software to IT consultants or the users themselves. As Joe put it, "the traditional focus has been on dozens of markets of millions instead of millions of markets of dozens."
Now that's changing. Joe started the new model with Jotspot, which focuses on the "millions of markets of dozens" by using the Wiki approach to let individuals build custom apps easily. Salesforce's AppExchange takes that one step further by creating a marketplace of such small, niche applications (everything from market research to health care management) that run on the hosted Salesforce platform. And others, such as SAP, are preparing to launch similar aggregators of Long Tail software based on their own platforms.
I covered all of this in my Salesforce speech, which is now online (both slides and audio) here. Check it out, if only for the nice job they did in prettying up my charts and graphics.
"
2006-11-27 03:19:00,Long Tail framework for software
Joe Kraus of Jotspot was the first to really develop a Long Tail framework for software, March 09, 2005 ------------------------------------------------------------------------
The long tail of software. Millions of Markets of Dozens.
Hello blogging, my old friend...
You know you've been constipated in getting a post out the door when you start it with three caveats:
- This post is WAY long. For that I'm sorry. Some things just take a while to say.
- This post is not so much about entrepreneurship as it is about where I see opportunities for entrepreneurs to create new businesses and describing the general direction of my new company, JotSpot.
- This post is based on a presentation I've been giving for the last five months. If you want a copy of it, you can download it here. Download jotspot_long_tail_sw.ppt
Excite and the Long Tail.
In Excite's heyday, we were handling millions of searches a day. If you graphed the frequency of those searches (the Y axis being the number of times a query was asked per day and the X axis being the actual query listed in order of frequency) you got a power law curve that looked something like this (excuse my lame-ass powerpoint graphing...).
The most popular searches (things like Sex, MP3, and the bare midriff female singer du jour) were vastly more popular than the 1000th most popular search. For example, "sex" was on the order of 100,000 times more popular than the 1000th most popular search (whatever that was). Said another way, there were a handful of extraordinarily common queries and millions of far less popular queries.
In fact, the frequency of the average query was 1.2. That means if you wrote each of the millions of queries on a slip of paper, put them all in a fish bowl and grabbed one at random, there was a high likelihood that this query was asked only once during the day. Of ten-plus million queries a day, the average search was nearly unique.
The most interesting statistic however, was that while the top 10 searches were thousands of times more popular than the average search, these top-10 searches represented only 3% of our total volume. 97% of our traffic came from the "long tail" ? queries asked a little over once a day.
Down the tubes
You know the real reason Excite went out of business? We couldn't figure out how to make money from 97% of our traffic. We couldn't figure out how to make money from the long tail ? from those queries asked only once a day.
Overture figured it out, Google perfected it and we all know what happened from there. Those guys figured out something revolutionary -- the long tail of search was a advertising marketplace. But it wasn't a traditional advertising marketplace like television, where a handful of large advertisers reached out to a handful of very large markets. It was a special kind of marketplace where small advertisers could reach small markets efficiently. It was and is a revolution to the traditional economics of advertising (where the cost of producing and distributing advertising requires large markets to justify the expenditure).
Search is a long tail business and that is the source of its power and profit.
Other Long Tail Businesses
Can I get a shout-out for Chris Anderson? For those of you who don't know him, he's the editor-in-chief of Wired Magazine and he wrote a great article called the Long Tail about six months ago.
Chris pointed to three other long-tail businesses (Rhapsody, Netflix and Amazon) as examples of the power of the tail.
Here was the first set of charts Chris showed.
Let's look at the Amazon example. This graph shows that Amazon sells roughly 2.3M books and that the average Barnes and Noble retail store stocks 139,000 books. So, Amazon stocks roughly 2.2M more books that Barnes and Noble.
No surprise here. That's the benefit of an online storefront. Massive inventories housed in ultra-low-rent areas that are fronted electronically.
The astonishing figure is the percent of sales that comes from the "long tail" of books (books that Amazon carries but that Barnes and Noble doesn't).
57%.
57% of Amazon's sales come from books you can't even buy at a Barnes and Noble (to be fair, there is some skepticism around this number voiced here). This runs totally counter to the traditional 80/20 rule in retailing ? that 80% of your sales come from 20% of your inventory. In Amazon's case, 57% of their book revenue comes from 0% of Barnes and Nobles inventory.
To quote Gary Coleman, I can hear retailers across the globe saying, "What you talking about Willis!?"
ITunes and the Long Tail
iTunes has over one million songs in it's catalog. You know how many have been bought at least once?
Every one.
Completely counter to the traditional 80/20 rule, every iTunes song has been purchased at least once.
What this says to me is that the tradition 80/20 "rule" is more a function of consumers having their expectations set by the limits of physical inventory in retail stores than it is about real human nature. Amazon and iTunes are great examples.
So what?
What all these data points mean to me (and to most folks who are interested in long-tail stuff) is that the most interesting, transformative businesses that have been built over the last decade and that will be built over the next one are going to operate in and make money from the long tail.
Google, eBay, Amazon, Rhapsody, Netflix, iTunes. What do they all have in common? They all work the long tail and they're all radically changing the dynamics of their more traditional businesses.
The Long Tail of Software
The long tail doesn't just apply to music and movies. There's a long tail for software as well. Here's why.
The purpose of software in business is to support the way a business does business ? from the way a business runs it's hiring and firing to the way it orders materials to the way it tracks sales. In the market-speak that surrounds the technology business, the purpose of software in business is to support these "business processes".
Let's do some simple math. First, every business has multiple processes. Things like hiring, firing, selling, ordering, etc. Second, while some of these are pretty common in name from business to business (recruiting, for example), in practice, they are usually highly customized. Finally, there are simply a large number of processes that are either unique or that are common to millions of very small markets and therefore not traditionally worth the effort to buy software for (for example, the process by which an architecture firm communicates between it's clients and the city planning office).
These three facts
- every business has multiple processes
- processes that are similar in name between businesses are actually often highly customized
- there exist a large number of processes unique to millions of small clusters of industries.
means that there is a combinatorial explosion of process problems to solve and, it turns out, little software to actually support them.
Said another way, there is a long tail of very custom process problems that software is supposed to help businesses solve.
Inaccessible Tail
In the past, software's long tail has been generally inaccessible because software has been
- Too difficult to write
- Too expensive to write and distribute
- Too brittle or expensive to customize once deployed.
It just hasn't been economical for someone to create a custom software company to help architecture firms.
That's why, in the software business, the traditional focus has been on dozens of markets of millions instead of millions of markets of dozens. The traditional software model is to make software have enough features and address enough of a homogeneous market that you can sell millions of copies of the same software. In the past, that's been the only way to make money.
How the software tail gets address today
The market doesn't like a vacuum and people do solve their software needs in the long tail. They do it using two basic tools: Microsoft Excel and email. I've seen so many business that run on Excel+email. People build structured lists in Excel and then send them out over email for comments and updates ? a list of people to hire, a list of deals they want to do with action items included, a list of features for the next product. Something like this
 While normal users don't think of it this way, what they're really building is an long-tail application ? a custom application, built by the end user and networked over email.
While normal users don't think of it this way, what they're really building is an long-tail application ? a custom application, built by the end user and networked over email.
Doing better (warning, personal plug for JotSpot coming...)
Excel and email are the wrong tools for software in the tail and we all know it. It's really easy to start with, which is fantastic, but it suffers from.
- Versionitis. We all know what happens with spreadsheets like these. You create it, you mail it to 10 people. One of them changes and mails it back out. Rinse, lather, repeat until everyone's inbox is full of this thing and no one knows who has the latest version.
- Updates. You only know the sheet has changed is when someone emails it to you.
- No integration. What about the stuff that doesn't fit in the grid? ? the email and documents that go along with these spreadsheets?
That's where JotSpot comes in. JotSpot is a company that is building a platform to make it easy and affordable to build long-tail software applications. To take those Excel spreadsheets and turn them into real web-based applications where you don't have versionitis, where updates find you instead of you looking for them and where you can integrate data in your hard drive with data from the web, email and other applications.
Please, really Joe, wrap it up...
So, my tip for entrepreneurs? It's all about the long tail. Whatever business your starting, think about how to serve millions of markets of dozens instead of dozens of markets of millions. Serving the head isn't a bad strategy. You can build a great business. But, figure out how to serve the tail of your market efficiently and you've got a blockbuster.
March 9, 2005 | Permalink
"
2006-11-29 10:48:00,pros and cons
http://frbourbon.cocolog-nifty.com/english/2004/11/pros_and_consna.html
"
2006-11-29 10:51:00,オープンソースが社会を変える
Wired誌Open Source Everywhere
「Software is just the beginning ... open source is doing for mass innovation what the assembly line did for mass production. Get ready for the era when collaboration replaces the corporation.」
「ソフトウェアは始まりに過ぎない」、つまり、組み立てラインによって大量生産(マス・プロダクション)時代が始まったように、オープンソースによってマス・イノベーション時代が始まる。企業・組織を越えてのコラボレーションが企業・組織を置き換える時代への準備が整った。
オープンソース的コラボレーションが社会を変える LINK
「オープンソースは単にボランティアの活動に依存して独占的でない知的所有権を形成し、コストを引き下げる手段ではない。創造の結果だけでなく過程を共有することによって参加者が互いに触発し合い、これまでに無かったもの、素晴らしいものを作ることができるのだ。それはまた、無数の凡人が互いに思考を共有し、足りない部分を補い、アイディアの連鎖反応を起こすことにより、より大きなインパクトを文明に与えることを可能にするのである。より多くの人に、「自分の生きた証」「自分のいなくなった後に残るモノ」を残す道を開いた、と言っても良いかもしれない。」
知的所有権などで定義される「テクノロジー」そのものを売るビジネスから、そのテクノロジーを使って何かを行う「アプリケーション」を提供するビジネスに価値がmigrateする過程が起きているのではないか."
2006/12
2006-12-01 15:41:00,情報大航海時代
|
ITによる「情報大航海時代」の情報利用を考える研究会(第1回) 議事要旨 |
|
(1)商務情報政策局長(代理 西川審議官)から挨拶。 (2)喜連川構成員を互選により座長として選任。喜連川座長から挨拶 後、各構成員から挨拶。 (3)事務局より「情報大航海時代に向けて」について説明。 (4)自由討議。 主な意見は下記のとおり。
(5)喜連川座長より第一分科会「次世代知的情報アクセスに関するビ |
配布資料"
2006-12-01 15:47:00,第2回
|
ITによる「情報大航海時代」の情報利用を考える研究会(第2回) 議事要旨 |
|
議事の経過
|
"
2006-12-01 15:49:00,第3回
|
ITによる「情報大航海時代」の情報利用を考える研究会 |
|
|
日時:平成18年6月12日(月)13:00?14:30 場所:経済産業省本館17階国際会議室 出席者: 喜連川座長、小川構成員(奥代理)、片山構成員、國尾構成員、 議題: 「情報大航海時代」プロジェクト・コンソーシアムついて 議事概要 (1)「情報大公開プロジェクト・コンソーシアムの組成及び発起人会設立の報告」について事務局より説明がなされた。(資料「情報大航海時代に向けて」) (2)自由討議がなされた。委員からの主な意見および事務局の発言要旨は以下のとおり。 ○次世代知的アクセスの研究開発基盤構築の必要性についてはコンセンサスが得られていると考えている。ただし、例えばモバイル、ユビキタス、情報家電などは他国に有利な条件がそろっているにもかかわらず、研究開発に関し、日本は着手が遅れており、喫緊の課題であるという合意が得られていると認識している。 この種の研究開発は、組織を超えた共通のプラットフォーム(解析のための共通プラットフォーム等)や大量のコンテンツ収集が重要であるとの認識から、大学、企業など一組織では対応できないため、このタイミングでのコンソーシアムの設立は極めて重要であると考える。 ○社会的財としての情報を共有するためには、知的情報アクセスが必須であることが、第二分科会では共通の認識になっており、以下の3点はとりわけ重要と認識している。 第1点は、情報メディアとしての検索システムは、影響力が非常に増大しており、情報提供の適切性の評価を考える必要がある。また、検索サービスの事業者には、結果表示の順序や公平性等につき、説明責任があると考える。第2点として、情報発信・提供側が情報をコントロールできていないことへの対応が必要である。情報発信・提供側にとっては検索エンジンにより、知的情報権を侵害されないこと、利用者にとっては検索エンジンに表示された情報が知的財産権違反でなく、安心して使えることが重要である。第3点として、これからは音声・動画などの検索が、利用者個人に必要になってくると同時に、アジアの国とも連携する中で、新しい産業の創造が可能ではないかと思われる。 上記の3点を踏まえ、社会的・文化的影響を考慮した上での新しい技術の開発が必要であり、そうした意味からもコンソーシアムは重要な役割を担うし、また期待される。 ○情報大航海プロジェクト利用シーン案について説明をしたい。情報家電向け検索に関しては、大量の情報の中から自分のほしいものを探し出す検索テクノロジーが、入ってくると考える。一つの使い方としては、現在のパソコンのようなWebを使って商品購入を行うなどのWeb連携による高付加価値化や、ユーザーインターフェイスに近いものとして、ユーザーの視聴、操作履歴等による興味・状況に応じた気の利いた検索、キーボードを使わない、利便性の高いインタフェースなどがある。また、映像検索なども考えられる。 さらに進化した利用シーンとして、リアルタイムの情報を検索できる時代が来ることが考えられる。こういった検索サービスの利用として、センサ情報等を収集してリアルタイムでモニタリングすることで、安心・安全に対するサービスを提供することができると考える。 本プロジェクトにおいては、既存サービスの補完からスタートして、世界最高のところを目指すべきであると考える。その手段として、ユビキタス環境対応での独自性、世界最高をめざすのがよいと思われるし、非言語情報、映像、音響などを対象とした先進性の切り口があると考える。本プロジェクトの成果として、一企業、一組織で(プラットフォームを)構築することは規模的に困難であるため、共同利用可能な検索基盤プラットフォームの確立に期待する。検索技術には、大量の情報の存在が前提となるので、メタデータを含んだデジタル・メディアデータの大規模データソースの確立が重要である。このような組織を超えた協力を実現するためのオープンイノベーションの場の設定が必要であると考える。 ○この研究開発プロジェクトがうまくいくかどうかは、大量のデータ、情報を使えるかどうかにかかっている部分がある。我々は、Web のデータについては、140億といったかなりの量のデータを蓄積しているが、大学や企業内にある大量のデータを、ほんとうに使えるかどうかということについては、大学、企業でも、なかなかできないことである。本プロジェクトで、大学、企業にある大量のデータを扱えることができれば、大きな一歩を踏み出すこととなる。 ○リアルタイムの情報の検索、解析、ユーザー端末の展開が非常に重要である。非本邦系の技術で先行しているところはますます技術を加速しているが、コンソーシアムでの取り組みスピードや日本特有の強い技術とのマッチングがポイントになっていくのではないか。 ○社会的な課題に対応していくこともコンソーシアムの中に入れていただきたい。社会で求められている具体的な事例としては、安心・安全の問題や医療サービス、デジタルディバイドなどがある。 ○社会的な課題への対応については、世界的にも課題とされている部分に対して、日本から開発を先行して提供するのがよいという議論があった。安心・安全などは面白いテーマである。日本の技術要素が多数使える。産学官で行う意味に関しては、経産省だけでなく、総務省、文科省、関係省庁も含めて議論する場になればよい。 ○検索エンジンについても、軍事的、政治的に利用され得る可能がある。検索技術の開発も大事であるが、アルゴリズムも重要である。今はブログ、SMSが重要視されているが、例えばマス媒体の記者の判断による記事や写真が検索の上位にはでてこないなど懸念がある。広告産業に携わるものとしては、テレビで検索サービスが使えるようになり、それが購買行動に結びつくことは大変ありがたいことであるが、アルゴリズムについての研究も、取り組んでいただきたい。 ○検索の結果表示の順序でいえば、結果表示順序をユーザーが選択して決められるというプラットフォームをつくるべきではないか。 ○検索サービスは、大量のデータを扱っているので、インデックスして運用・保守を行う面では、非常に多くのコンピューティングパワーと、人手がかかるものである。運用保守で、どう効率化し、コスト削減するかが重要な課題である。 ○Web上でのメガサービスを実現するためには、メガプラットフォームが必要であるが、これは個々の企業では持つことはできないので、イノベーションプラットフォームとして提供しようというのが(本プロジェクトの)意図であると思われる。一方でテール部分、個別のコンテンツに対しての運用経費をいかに下げていくかも、ホットな課題になっている。利用シーンでのシナリオが議論となっているが、バックヤード側の議論も重要な課題と認識する。 ○そのとおりである。新しい情報・経済等のネットワーク基盤をいかに作るかも議論をしていただきたい。 ○企業が技術開発を進めるなかで、ボツになり活用されない技術があるものと思われる。基礎技術を企業間でやりとりすることは難しいと思うが、コンソーシアムの場でオープンなディスカッションができれば、ブレークスルーとしていろいろなものが出てくるのではないか。 ○検索サービスのためには、いかに情報を蓄積するか、情報の貯め方を工夫していくということも重要である。企業で活用されないデータを、オープンイノベーションの場で利用できる工夫ができればよい。そのための仕掛けとして、知財の扱いなどのルールづくりを行うことも肝要である。 ○コンソーシアムでは、情報、技術を持ち寄る、あるいは共通のプラットフォームを作るだけでは不十分であり、新たなイノベーションをどのようにして生み出していくかということをよく考えていくべきではないか。 ○Googleの求人の基準はシンプルで、ただ「スマート」な人が欲しいとしている。恐らく、Googleではそのような能力ある人材がシナジーを発揮できるようにしくみをつくっているのではないかと考える。 委員からは、コンソーシアムにおいて、多様な分野の人の知恵をあわせるシナジーにより、非常におもしろいものが生まれるポテンシャルがあるといことをご指摘いただいた。 ○コンソーシアムには、大企業の参加が多いが、ベンチャー企業もプラットフォームを使って価値を作り、活躍できるようにしていきたい。例えば、ベンチャーキャピタルなどにコンソーシアムに参加してもらうと、ベンチャーの活躍もサポートできるのではないか。 ○開発してみたら現在の問題がそのまま積み残しになっていたということのないように、今どのような問題点があるのかをよく整理した上で対応していくべきと考える。さらに、エンドユーザーの考え方や求めているものなどを吸い上げ、反映させていただきたい。 ○アルゴリズムやランキングなど技術的な課題の他、データソースの確立が重要な点であると思われる。 以上 |
"
2006-12-01 15:50:00,第4回
|
ITによる「情報大航海時代」の情報利用を考える研究会(第4回) 議事要旨 |
|
|
日時:平成18年7月7日(金)14:00?16:00 場所:東海大学校友会館阿蘇の間 出席者: 喜連川座長、小川構成員、片山構成員、國尾構成員、 議題:最終報告に向けて 4.議事概要 (1)「情報大航海の船出にあたって」(資料1)について事務局から説明。 (2)「知的情報アクセスがもたらす文化・社会・経済的影響を考える分科会」について(資料2)を第2分科会主査から報告 (3)知の再編を超えた技術連鎖を求めて」(資料3)について事務局から説明 (4)自由討議。委員からの主な意見および事務局の発言要旨は以下のとおり。 ○第一分科会では、情報大航海時代の技術的なビジョンについて検討を行ったところ、日本には基本的な技術があり、これらを結集すればイノベーションが起きるという合意がえられた。これを実現するための共通基盤、すなわち共通プラットフォーム、共通ツールの整備、共通データの整備、共通APIに関する検討が非常に重要である。「情報大航海時代」のイノベーションを生み出すために、本プロジェクトの役割は非常に重要であり、今後の発展を期待している。 ○情報処理推進機構のソフトウェア・エンジニアリングセンターでは、ソフトウェアの開発に関するさまざまな手法を開発している。大きなキーワードの1つが、開発プロセスの可視化であり、現在、エンプリカル・プロジェクト・モニターツールを活用して実証的な研究を行っている。これはソフトウェア開発者のコンピュータの中にデータ収集ツールを入れて、その更新・修正履歴、バグの履歴、メール履歴を自動的に収集するというもの。これによってプロジェクト管理者が現在の開発プロジェクトの状況が常に把握できる。現在、これを簡単にインストールができるようにツール化をしているので、こうしたことで貢献できるのではないかと考えている。 セキュリティセンターでは、Webアプリケーションをつくるときに脆弱性を作りこまない方法をまとめている。このプロジェクトでも、Webアプリケーションを前提に開発されると考えられるので、こういったノウハウの提供が可能。 このプロジェクトの成果はオープンソースとして公開される予定とのことだが、オープンソース・ソフトウェアセンターも開設しているので、成果の取り扱い等について、我々の知見が生かせるのではないかと考えている。それ以外にも、今後、コンソーシアムで検討される共通的な基盤の開発について、どのように協力できるか、引き続き検討を続けたい。 ○情報弱者への対応が強調されていたが、産業の育成という観点からは、情報の強者をより強くすることが大切である。全体を引き上げるために重要なことは、弱者を底上げするより、強者を強くする方である。情報弱者は救済すべきものであり、情報弱者に対しては、情報弱者がそのままでも生きていける社会を作ることが必要である。 ○「言語」「文化」「価値観」「知識」などは日々変化しており、これらの壁は高くなっていくため、超越するのは難しい。例えば、専門分野においては、研究が進めば用語がどんどん増大するし、文化については、新しい文化がどんどん創造される。壁はどんどん高くなっていくため、決して超えることはできない。壁を超える方法ではなく、壁に穴をあけて相手が見えるようにするといった方法を考えればよいのではないか。 ○言語と音声や画像など言語以外の媒体がいずれ結びつかなければならないという方向性が出されていたが、歴史的に見ると、言語と外界を関連づけようとする技術は失敗してきた。成功するのは、機械翻訳や検索エンジンなど、言語の中に閉じた技術である。 ○情報リテラシーの格差が拡大することに懸念がある。特定の人だけが使えるというのではなく、だれでもが使いやすいという観点からの技術開発も重要であるというのが、第2分科会の考えである。 ○情報の流れが変わってきている。評判情報がWebに書き込まれると、それに対して過敏に反応が起き、それがまた書きこまれ、反応が拡大していくことがある。このような言語情報の活用は、身近な社会で起こっているが、言語を超えた多様な情報のひもづけは、簡単には起こらないだろうし、映像マイニングから音声認識技術まで、すべてが複数化してつながるようになるまでには、大きなミッシングリンクがあると思う。だが、プロフィタブルな技術につなげるためには何をすべきかについて、議論のきっかけは作れたのではないかと思う。 ○ブログのように生の声や極端な声が増幅されるような、情報を重ねすぎた社会は、不安定化要因を生じる。この不安定な要因を、マジョリティの意見として常識的なところへ引き戻すための技術も、情報を扱う者の義務であり、技術の発展の方向であると思う。 ○ITの発展により、時定数が短くなってきており、ほぼすべての制御系において安定 性が低くなっている。それを元に戻すのは、ソーシャルデザインの議論だろう。 言語に関しては、検索サービスの中で情報処理の形態が変わってきている。例えば、大きなパラダイムの変化は、従来の辞書が基本的に使えない点。検索サービスに問い合わされる言葉は、辞書にはない固有名詞がほとんどであり、この語とこの語が違うというような技術は、何にも使えない世界になってきた。新しい技術の領域に我々が入り得るような糸口をつくっていただいた。 ○画像、映像に対する解析や検索に対する要求、要望がどんどん高まっているが、技術はまだ成熟されていないという状況。テキストがうまくいったと思うのは、検索サービスのようなものが立ち上がる前に、コーパスのようなものが整備されて、技術が一気に立ち上がった点である。画像、映像については、産業のほうが先に立ち上ってしまい、権利関係でがんじがらめになってしまったところで、技術開発をしなければならない状況になっている。そのため、このプロジェクトの役割に期待している。 ○ADRについては、即できることであるし、検索サービスを提供している会社がこうした窓口がなくて困っているようなので、取り組んでいけばよいと思う。 ○情報大航海時代には、技術で一転突破をするのは難しい。日本の企業は、世界の中でも最も総合技術をもっていると思うが、コンソーシアムで、情報大航海というゴールに向かって、これらのいろいろな技術を集めていけば、新しい総合的な技術が出てくるかもしれないし、意義があることだと思う。 ○情報が爆発的に増え続けている「情報大爆発」の状況では、いろいろな企業の技術を総動員して、ソリューションを出していくことが必要である。 ○検索を行うと、どのサイトでも同じような解説がでてくるが、それでは楽しくない。「大航海時代」には、いろいろな種類の検索が出てきて、それが一つの産業につながっていくだろう。それをコンソーシアムでやっていただきたい。同時に、検索のメディアを育てるという観点で、アナログ的なメディアも必要と考える。 ○コンソーシアムでは、研究開発ターゲットを一つに絞らないで、多様性があった方がよいと思う。世の中の動きを見て、一つの方向にだけ偏らないようなスキームをもっていただいたほうがよいのでは。 ○機械軸と人間軸の連携が重要になるという話があったが、これからの技術開発を行う上で、重要な点だと思う。さらに、機械軸と人間軸を融合させるという方向性も加えていただきたい。 ○具体的な利用シーンを想定して、開発を進めていくと、ニッチかもしれないが実態がある成果を得られるのではないか。全体を考えるとなかなか進まないかもしれないので、最初に手をつけるテーマを決めて、そこから始めるとよいと思う。リテラシーの差をなくす技術もこのテーマにすればよいのではないか。 ○半年間、議論をして、課題の整理ができた。わからなかったことを知ることは重要であり、この研究会報告によって、世の中の人にも課題の存在を示せることは、有意義なことと考える。技術をうまく活用して人間軸にどのように転化していくかを前面に出す形で、技術開発を進めてほしい。また、それを支える制度的な部分も並行して行っていただきたい。 ○研究会等での議論を具体化していくためには、いくつかの柱となるビジョンを再構築することが必要だと思う。 ○目指すものは、高度な技術の集大成となると思うが、その中からうまい要素技術を見つけて、ユーザーに新たな利便性やエンターテイメントを与えるアプリケーションを考えたい。 ○「検索エンジン」と言うと具体的で分かりやすい半面、産業が拡大するイメージに欠ける可能性があるため、情報流通業のような、業界として市場が大きくなるイメージを表す言葉が欲しい。この産業には、基本的に、水平に分かれて、付加価値をつけるプレーヤーが多く出てきたほうが、産業全体がよくなると思う。また、利用者に近いところにいろいろなプレーヤーが参入できるようになれば、もっとユーザーのことを考えるプレーヤーが出てくるだろう。そのようなアーキテクチャーを作っていただきたい。 ○パブリックとプライベートの問題も大きなテーマである。検索エンジンが収集したデータはパブリックに使えるものだが、データの一つ一つは個人のものであり、プライベートの要素の残っているものが、パブリックに扱われるという問題が残っている。 ○情報リテラシーの差をなくすために、ヒューマンインターフェースには最大限の配慮を払ってほしい。また、モノだけを作るのではなく、教育等とパッケージにして市場にだすことも必要である。これは、ソフトウェアの技術だけでは解決できないので、制度的な補完が必要である。技術だけではなく、制度的な補完にも予算をとっていただきたい。 ○映像コンテンツを社会に還元することは、義務であると思っているが、コンテンツは著作権や個人情報の塊であり、壁があって難しい。映像検索についても、その大きな壁にぶつかると考えられるので、その点をどのようにクリアするかを考える必要がある。 ○一般消費者が使うもののユーザーインターフェースは、リテラシー教育がなくても使えることが望ましい。リテラシー教育がなくても使えるような検索エンジンを考えたほうがよいのではないか。 ○総務省では、ユビキタスやコンテキストアウェアネスに取り組んでいるが、このような分野も今後、取り込んでいただけるということであり、一緒に取り組みたい。また、仲良くやるのも大事だが、競うことにより特徴を出していくことができるので、競わせることも重要ではないか。 ○大学の基礎研究から出発したこのようなプロジェクトが、コンソーシアムという形に発展してきたが、成功することを期待している。また、情報分野でのいろいろな研究に波及していくことを期待する。 ○IT が著しく進展し、人間が生み出す情報量が飛躍的に増大した「情報大爆発時代」に入ってきた。情報量が劇的に増加したことにより、検索を中心とする新たな技術の創出が不可欠になるため、従来にないビジネスチャンスが生み出されているということが、このプロジェクトの技術的な観点での出発点。 また、今までの問題は情報へのリーチあるいは情報量が少ないことだったが、情報過多の時代への急激な転換点を迎え、新たな多くの問題が生まれており、インターネットの世界での滞留時間を無視できなくなった。このため、サイバー空間のライフスタイルを考えなければならないことが、社会的な側面での動機付けとなっている。 この2つをあわせて今までの動きをみると、インターネット上にeBay、Amazon、Googleなど斬新なサービスが生まれ、そのサービスの中で、1日に数億人の人間が動いている。それを見ることによって、ロングテールという現象を見て取ることができる。これは発見である。この発見がまた新たな時代のビジネスプリンシプルになる。 こうした技術革新とライフスタイルの大きな変化の中で、日本として高付加価値ビジネスを戦略的に生み出すという観点と、安らぎのある生活を送るという観点の両面で、サイバー情報空間の環境設計を目指すのが、情報大航海プロジェクトの目的とみなすとよいだろう。 情報環境設計は大きな広がりがあるテーマだが、コンソーシアムには多岐にわたるセグメントから参加いただいており、広範囲であることが情報大航海プロジェクトの大きな特徴となっている。 出口については、日本が強い、携帯、情報家電、自動車、大規模システムインテグレーションなどから、新しい戦略が打ち出されるだろう。また、大きな競争力を背景に、ブロードバンドの上にビジネスモデルを乗せることで、サービスが創出されているが、この特徴を使った、従来にないプロジェクトの形態で攻めていくことが肝要だと思う。 ビジネス機会は大きく、勝負はこれからである。このプロジェクトを成功させるには、産学官が一体となることが重要。 以上 |
"
2006-12-01 20:58:00,米IBM、人工知能の連携技術「UIMA」を公開へ
CNET Japan 2003/01/21 10:57 IBMがソースコードを公開したUIMAの紹介 IBMのUIMA担当Marc AndrewsのBLOG 澤田智明 IBM UIMA SDK [CNET] 米IBM、人工知能の連携技術「UIMA」を公開へ [MYCOM PC WEB] IBM、UIMAをオープンソースで公開 UIMA Java Framework 1.3.1 [インターネットコム] IBM、データ検索アーキテクチャ『UIMA』のソースコードを開示 [ITmedia1] IBM、検索フレームワークをオープンソースに [ITmedia2] 勤務時間の30%が情報検索に費やされている」とIBMのDE、マットス氏
Text analytics for life science using the Unstructured Information Management Architecture UIMAの説明としては次の資料が一番わかりやすいので、この中から転載されてはいかがでしょう?これはUIMA SDK ユーザガイドで、24ページ目の図が UIMA のできることを一番よく表していると思います。 http://dl.alphaworks.ibm.com/technologies/uima/UIMA_SDK_Users_Guide_Reference.pdf WITとマネックスの作る新会社が、プログラムを用いた個人向け資産運用アドバイスをするそうです。Unstructured Data を「理解」することがビジネスにつながる例になるかもしれませんね。 http://www.monexbeans.net/pdf/press/mbh/press2006_03_09_1.pdf
IBMが2月に発表した"Discovery Server"にUIMA技術が採用されているようですね。これにあわせてコンサルタントの大量採用の記事が話題を呼んでいるようです。また4月3日の「a Business Face on SOA」の中でもInformation Management関連の大々的な発表がされているようです。まだ日本語での内容はないのですが。
Multimedia Analysis and Retrieval Engine(MARVEL) 画像とビデオの検索ツールで、マルチメディアコンテンツのアノーテイトを自動的に行ってくれる。MPEG?7のサポートを目指している。Wall Street Journal's 2004 Technology Innovation Award を受賞した。 UIMA はどちらかというと、ChaSen や kakashi をアノテーターとして使います。UIMA用に実装した形態素解析ツールのラッパーがあれば、ChaSen, kakashi, JUMAN, MeCab など個々のツールの使い方を覚えなくて済むというのも、1つのメリットです。ちなみに上の4つの中では、解析速度、精度、メンテナンス頻度などの点で MeCab がトップレベルなので、おすすめです。 UIMAの利用事例は、利用できるコンポーネントの数が増えるにしたがって確実に増えていく。想像としてはデータマイニングを利用したCRMなどでしょうか。 CMUのSE授業で、Medline医学論文データベースの中にでてくるたんぱく質名をアノテートして、たんぱく質検索エンジンを作成したと報告されている。このほかに、マルチエンジン機械翻訳 (GALE project) や質問応答 (Javelin project) に UIMA を使っている。東大では辻井教授らが生命科学文献用の言語処理に使うそうだ。もし会社名アノテータ、ポジティブ/ネガティブ文書アノテータなんかを作ったら、カブロボコンテストで、ニュースで報道された内容を元に株価を予測するカブロボが作れるかも・・・?UIMA 自体はアーキテクチャなのでコンポーネントがないと何もできないということで、アメリカ政府は企業や大学を巻き込んで UIMA ワーキンググループを支援することになり、CMU が UIMA で使われるコンポーネントのリポジトリサイトを作ることになった(Firefox でいう拡張機能をダウンロードするサイトのようなもの)。
米IBMは、UIMA(Unstructured Information Management Architecture)を使った実験を2003年3月に公開する予定である。
IBMが現在取り組んでいるのは、UIMAと呼ぶXMLベースのデータ収集アーキテクチャーで、さまざまな人工知能の連携を可能とする技術。 IBMの研究部門、サービス・アンド・ソフトウエアのバイスプレジデント、Alfred Spectorによると「UIMAとは、データベースの検索技術を大幅に拡充し、より高度なものにするもの」という。
SpectorはUIMAについてさらに説明する。「UIMAとは、データベースの一部を構成するもの。というより、データベースがUIMAにアクセスする、と言った方が正しいだろう」
例えば、車のシステムにUIMAを組みこむと、交通情報をリアルタイムに表示したり、高速道路を走行している車の平均速度を割りだしたり、整備工場で給油や車体の管理を行ったりするこが可能となる。自動翻訳や自然言語処理なども可能になるという。
UIMAが用いるのは、Combination Hypothesisという理論。今後はこの理論の元で、統計的な手法を使ってコンピューターが学習する機能(例えば、Googleのデータランキングなどの検索機能など)や、統計的な機能を持つ人工知能が連携することになるという。
「異なる人工知能を同時に動作することができれば、エラー率を乗法的に減らせる」(Spector)
プロセシング技術やデータストレージの性能が向上し、演算技術や人工知能関連のソフトウエアが進歩を続ける今、人工知能の開発はより現実のものとなっている。またインターネットの普及に伴い、自立的な連携作業を行うコンピューターの需要が高まると考えられている。 原文へ
IBM aims to get smart about AI
In the coming months, IBM will unveil technology that it believes will vastly improve the way computers access and use data by unifying the different schools of thought surrounding artificial intelligence.
The Unstructured Information Management Architecture (UIMA) is an XML-based data retrieval architecture under development at IBM. UIMA will greatly expand and enhance the retrieval techniques underlying databases, said Alfred Spector, vice president of services and software at IBM's Research division.
UIMA "is something that becomes part of a database, or, more likely, something that databases access he said. "You can sense things almost all the time. You can effect change in automated or human systems much more."
Once incorporated into systems, UIMA could allow cars to obtain and display real-time data on traffic conditions and on average auto speeds on freeways, or it could let factories regulate their own fuel consumption and optimally schedule activities. Automated language translation and natural language processing also would become feasible.
The theory underlying UIMA is the Combination Hypothesis, which states that statistical machine learning--the sort of data-ranking intelligence behind search site Google--syntactical artificial intelligence, and other techniques can be married in the relatively near future.
"If we apply in parallel the techniques that different artificial intelligence schools have been proponents of, we will achieve a multiplicative reduction in error rates Spector said. "We're beginning to apply the Combination Hypothesis, and that is going to happen a lot this year. I think you will begin to see this rolling out in technologies that people use over the next few years. It isn't that far away.
"There is more progress in this happening than has happened, despite the fact that the Nasdaq is off its peak he added.
The results of current, major UIMA experiments will be disclosed to analysts around March, with public disclosures to follow, sources at IBM said.
Although it's been alternately touted and debunked, the era of functional artificial intelligence may be dawning. For one thing, the processing power and data-storage capabilities required for thinking machines are now coming into existence.
Researchers also have refined more acutely the algorithms and concepts behind artificially intelligent software.
<P. exist=""" t=""" didn=""" serious=""" anything=""" do=""" to=""" power=""" the=""" reality=""" in=""" lab=""" microprocessor=""" s=""" intel=""" management=""" technology=""" and=""" software=""" application=""" of=""" manager=""" moghadam=""" omid=""" said=""" overhyped=""" was=""" it=""" that=""" problems=""" one=""" history=""" spotty=""" a=""" somewhat=""" has=""" ai=""">Additionally, the explosive growth of the Internet has created a need for machines that can function relatively autonomously. In the future, both businesses and individuals simply will own far more computers than they can manage--spitting out more data than people will be able to mentally absorb on their own. The types of data on the Net--audio, text, visual--will also continue to grow.
XML, meanwhile, provides an easy way to share and classify data, which makes it easier to apply intelligence technology into the computing environment. "The database industry will undergo more change in the next three years than it has in the last 20 due to the emergence of XML Spector said.
A new order Artificial intelligence in a sense will function like a filter. Sensors will gather data from the outside world and send it to a computer, which in turn will issue the appropriate actions, alerting its human owners only when necessary.
When it comes to Web searching, humans will make a query, and computers will help them refine it so that only the relevant data, rather than 14 pages of potential Web sites, match.IBM's approach to artificial intelligence has been decidedly agnostic. There are roughly two basic schools of thought in artificial intelligence. Statistical learning advocates believe that the best guide for thinking machines is memory.
Based in part on the mathematical theories of 18th century clergyman Thomas Bayes, statistical theory essentially states that the future, or current events, can be identified by what occurred in the past. Google search results, for example, are laundry lists of sites other individuals examined after posing similar queries ranked in a hierarchy. Voice-recognition applications work under the same principle.
By contrast, rules-based intelligence advocates, broken down into syntactical and grammatical schools of thought, believe that machines work better when more aware of context.
A search for "Italian Pet Rock" on a statistically intelligent search engine, for example, might return sites about the 1970s novelty. A rules-based application, by contrast, might realize you mistyped the Italian poet Petrarch. A Google search on UIMA turned up the Ukrainian Institute of Modern Art as the first selection.
"The combination of grammatical, statistical, advanced statistical (and) semantics will probably be needed to do this, but you can't do it without a common architecture Spector said. Thinking in humans, after all, isn't completely understood.
"It's not exactly clear how children learn. I'm convinced it's statistically initially, but then at a certain point you will see...it is not just statistical he said. "They are reasoning. It's remarkable."
"
2006-12-01 23:14:00,IBM、非構造化データ処理アーキテクチャ「UIMA」をオープンソースコミュニティで公開
ZDNet Japan 2006/01/24 19:41 IBMは米国時間1月23日、「Unstructured Information ManagementArchitecture(UIMA)」技術をオープンソースコミュニティに公開したことを発表した。UIMAは、ドキュメントなどの非構造化データを処理するためのアーキテクチャで、キーワードだけでなく、さまざまな関連性や意味を発見するのに役立てられる。IBMは、UIMAのソースコードを、オープンソース関連の最大のウェブサイトであるSourceForge.netで公開した。
UIMAは、非構造化データを検索/分析するのに利用されるソフトウェア同士をネットワーク上で連携させるうえで、役に立つ。非構造化データとは、電子メールやWord文書などのように、行や列の形式で保存されていないデータのこと。 IBM、『UIMA』のオープンソース化と標準化を推進 著者: Sean Michael Kerner オリジナル版を読む プリンター用 記事を転送 ▼2006年11月16日 11:40 付の記事 ■海外internet.com発の記事 IBM (NYSE:IBM) は、データ検索アーキテクチャ『Unstructured Information Management Architecture』(UIMA) のオープンソース化を決め、今年1月にオープンソース ソフトウェア開発サイト『SourceForge.net』でのダウンロード提供を開始した。 だが、10か月を経て、IBM はこれまでの路線を捨て、UIMA を新たなオープンソースの土壌に移そうとしている。同社は15日、オープンソース開発団体 Apache Software Foundation が、UIMA ベースのソフトウェア開発プロジェクトを発足させたと発表した。 ----------------------------- 「オープンソースって"タダ"なんでしょ?」の誤解を解く 米持幸寿(日本アイ・ビー・エム) ZDNet Japan 2006/12/01 16:42
オープンソースソフトウェア(OSS)の説明として、「ボランティアが開発している無償ソフトウェア」という言い方を聞くことがあります。実際、そのように理解している人も多いはずです。しかし、その考え方はすでに古いと言えます。
確かに、オープンソースにはコミュニティが存在し、そのコミュニティで開発されたソフトウェアは無償でダウンロードできます。オープンソースが始まったばかりのころ、コミュニティを構成していたのは、研究者、教育者、個人などでした。それらの人は、自分が所属するなんらかの団体の意図でオープンソースに参加していたわけではなく、個人的な思いでオープンソースに参加していることが多く、ボランティア的だったのは確かです。
近年になり、OSSは高機能化してきました。このため、オープンソース・ソフトウェアを無償ダウンロードによって入手し、企業のシステム構築に利用するケースが増えてきました。しかし、オープンソース・ソフトウェアを企業システムで使うときによく問題になることがあります。それは、サポートや品質に関するものです。
コミュニティに企業が参加する理由
ソフトウェアを企業システムで稼働させる場合、サポートや品質の面で「だれかが責任を持つ」必要があります。個人的な意思の集合によって形成されたコミュニティがそうした点で責任を持つことは難しく、ボランティアベースのオープンソースではサポートや品質の面がどうしても不安材料となってしまうわけです。
オープンソースには、ベンダーの壁を越えて共同開発ができ、オープンな場での議論や意見交換を行うというすばらしい文化があります。この文化は止められませんし、とても価値の高いものです。この文化に「責任をもったサポートと品質」を付加するために、世界中のソフトウェアベンダーやIT企業がオープンソースに対して投資をするようになりました。
投資の方法には、さまざまな形態があります。オープンソースを集めて来てパッケージ化し、それを商用ソフトウェアと同様かつ安価に販売する企業、オープンソースを利用するベンダーのサポートを請け負う企業、オープンソースを自社の商用ソフトウェアに組み込む企業、自社のソフトウェアをオープンソースとして公開する企業などです。こうした企業は、ソフトウェアの専門企業であり、ソフトウェア開発のプロフェッショナルでもあります。 OSS投資の方法には、さまざまな形態があります。 *オープンソースを集めて来てパッケージ化し、それを商用ソフトウェアと同様かつ安価に販売する企業 *オープンソースを利用するベンダーのサポートを請け負う企業 *オープンソースを自社の商用ソフトウェアに組み込む企業 *自社のソフトウェアをオープンソースとして公開する企業 などです。こうした企業は、ソフトウェアの専門企業であり、ソフトウェア開発のプロフェッショナルでもあります。 (1) OSSに対する有償サポートを行っている企業があるとします。ソフトウェアのサポートは開発した人から受けたい、というのがサポートを受ける側の意識です。そのためには、サポートを提供する企業そのものが、オープンソースコミュニティに参加することが望まれます。つまり、ボランティアでコミュニティに参加するのではなく、ユーザーが利用するOSSをサポートするためにオープンソースコミュニティの一部となるのです。こうすることで、ユーザーはコミュニティ参加者から直接、有償サポートを受けることができます。サポートを有償で提供している企業は、サポート料金から得た利益を、コミュニティでのソフトウェア開発に投資することができます。 (2) ソフトウェアには品質も重要です。長くソフトウェア開発を行ってきたベンダーには、品質を維持するための多くのノウハウがあります。こういった企業に何らかの対価を支払ってでも、品質の高いソフトウェアを入手したい、というユーザーの声もあります。オープンソースコミュニティでの開発にソフトウェアベンダーが自ら参加し、自社で品質を向上してからユーザーに有償で提供することができます。この有償ソフトウェアの売り上げを原資に、オープンソースコミュニティでの活動を続けることができます。 (3) より高い価値のソフトウェアを提供することも考えられるでしょう。ソフトウェアはスタック(階層)の構造を持ちますが、スタックの低い層の部分、つまり、より基本的な機能を提供する部分は徐々に価値が下がっていき、コモディティ化(一般化)していきます。そうなると、維持のコストばかりがかかり、上位の層(=価値の高いソフトウェア)への投資がしにくくなります。低い層からオープンソース化し、コミュニティでの共同開発を行うことによってコストを下げ、新しい、価値の高いソフトウェアの開発に投資を向けることによって、社会全体でのソフトウェアの価値を高めることができます。そして、その付加価値に高いソフトウェアを有償でユーザーに提供し、それを原資にオープンソースを維持することが可能となります。 今や、ソフトウェアベンダーの存在なしに、OSSはありえないのです。
つまり、OSSは決して「無料」ではありません。ソフトウェアへの対価の支払いかたが、「ライセンス契約」というものではなくなってきているにすぎません。
ソフトウェアベンダーが自らオープンソースコミュニティの一部となって、品質や価値の高いソフトウェアを作り、共同で維持していく。このように、企業団体が寄り集まったコミュニティによってコードが開発、維持され、さまざまな形態で対価がコミュニティーに還元されていくようなモデルを形成しているのが現代のオープンソースの姿と言えます。 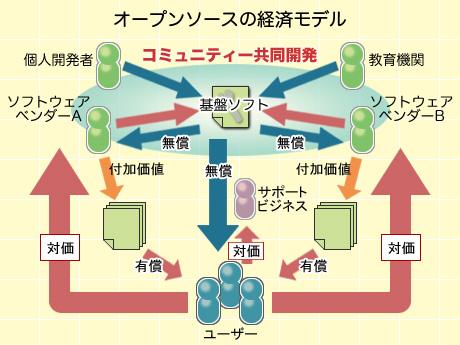
コミュニティーに参加しているのはボランティアではなく、ユーザーから投資を受けた代理人としての開発者であり、そのコミュニティから直接、有償で、サポート、品質、高付加価値といったものを得られるようなオープンソースという経済構造が形成されているのです。 現在のオープンソースを取り巻く経済モデル。OSSを利用して有償の製品やサービスを提供する多くの企業が、自らコミュニティに参加し、利益を再投資することによって、高い品質を継続的に維持することが可能になっている。
"
2006-12-01 23:58:00,携帯電話でのインターネット利用がPCを初めて上回る
携帯電話でのインターネット利用がPCを初めて上回る--総務省調査
目黒譲二
2006/05/22 09:52
総務省は5月19日、2005年末時点の世帯、企業および事業所における情報通信サービスの利用状況、情報通信機器の保有状況等について調査した「通信利用動向調査」の結果を取りまとめ、公表した。
通信利用動向調査は、世帯(全体、構成員)、企業および事業所を対象とし、統計報告調整法に基づく承認統計として1990年から毎年実施されている。
今回の調査は2006年1月に、全国の世帯主が20歳以上の6400世帯およびその構成員、常用雇用者規模100人以上の3000企業、常用雇用者規模5人以上の5600事業所を対象に、郵送による調査票の配布および回収によって実施された。有効回答数(率)は、3982世帯、1万2879人(62.2%)、1406企業(46.9%)、2821事業所(50.4%)だった。
調査によると、インターネット利用者数は、前年比581万人増(7.3%増)の推計8529万人に達し、引き続き増加していることがわかった。それにともない、人口普及率も推計66.8%となり、4.5ポイント増加した。
個人のインターネット利用端末について見ると、携帯電話等の移動端末の利用者数が前年末から1098万人増加(18.8%増)して推計6923万人に達し、パソコン利用者数(推計6601万人)を初めて上回り、モバイル化がさらに進展した。また、インターネット利用者(推計8529万人)の過半数(57.0%、推計4862万人)は、パソコンと移動端末を併用する一方、パソコンのみの利用者は521万人減少した。
ブロードバンドの普及状況については、光回線の利用率が伸びる一方、DSL回線の利用率は初めて減少した。ブロードバンド回線の利用者数は、前年末と比べて460万人増加(10.8%増)して推計4707万人となり、インターネット利用者に占める割合も55.2%に達するなど、ブロードバンド化が引き続き進んでいる。自宅パソコンをインターネットに接続している世帯の約3分の2(65.0%)およびインターネット利用企業の68.1%が、ブロードバンド回線を使用している。自宅パソコンに接続するブロードバンド回線の種類については、光回線の利用率が6.1%から14.8%に倍増した一方、DSL 回線の利用率は39.2%から34.2%へと、初めて減少した。企業、事業所においても、同様の傾向だった。
世代別、世帯年収別、男女別および都市規模別によるインターネット利用率の差はそれぞれ前年末より縮小したものの、60歳以上の世代と他の世代の利用率の差は、50代と60代前半で20ポイントの差があるなど、依然として顕著だった。
携帯電話とパソコンの利用率の比較では、携帯電話利用率(71.9%)がパソコン利用率(56.7%)を約15ポイント上回り、世代別に見てもほぼ同様だが、「6?12歳」のみ約37ポイント差でパソコンが携帯電話を大きく上回っている。携帯電話利用率は、20代?40代では9割を超えており、 60代後半でも約5割と高い利用率を示した。一方、パソコン利用率は、20代?40代では7割を超えていたものが、50代で55%、60代後半で 22.7%に落ち込んでおり、操作に相応の知識が必要なパソコンは、世代間での差異が携帯電話以上に顕著だった。
IP電話の企業普及率は、前年末から11.6ポイント増の39.4%と、約4割の企業に普及する一方、世帯普及率は2.3ポイント増の15.0%にとどまり、前回調査の伸び(5.4ポイント増)よりも鈍化した。
情報通信ネットワーク利用企業のうち何らかの個人情報保護対策を実施しているところは、前年末から16.7ポイント増加して73.2%となり、企業の個人情報保護への取り組みが進んでいることが伺える。対策内容は、「社内教育の充実」(45.7%)が最も多く、次いで「個人情報保護管理責任者の設置」(41.4%)の順だった。
"
2006-12-02 00:05:00,ドコモ検索、一般サイトが70%
NTTドコモ夏野氏が語る、モバイル検索サービスを導入した理由
永井美智子(編集部)
2006/07/20 21:57
NTTドコモ執行役員プロダクト&サービス本部マルチメディアサービス部長の夏野剛氏が7月20日、携帯電話関連の展示会「WIRELESS JAPAN 2006」において講演し、10月より開始するiMenuの検索サービスについて紹介した。
これは、公式サイトをキーワードで検索できるほか、ドコモが連携する9社の検索サービスを使って、一般サイトと呼ばれるドコモ非公認のサイトも検索できるようになるもの。これまでiMenuではカテゴリ別に公式サイトを紹介するディレクトリ型サービスのみを提供していた。検索サービスの導入により、ユーザーが目的のサイトにたどり着きやすくなる。
夏野氏によれば、ドコモユーザーのアクセスを見ると、すでに2003年ごろから公式サイトよりも一般サイトのほうがページビューが多いといい、現在では全アクセス量に占める一般サイトの比率は70%程度にまで高まっているという(グラフ)。
「iモードはサービス開始当初から一般サイトの存在を前提にしているオープンモデルだ。ただ、アクセス量の多さは必ずしも(サイトの)情報の重要性に比例しない。一般サイトのほうがページビューが多いことを是としたビジネスモデルを採っている」(夏野氏)
ただし、iモード開始当初にくらべて、公式サイト、一般サイトともに量が増えており、どこにどんな情報があるのかが分からなくなってきている。一般サイトではすでにさまざまなモバイル検索サイトも存在しているが、「ユーザーの中にはモバイル検索サイトのURLが分からないという人もいる。そのため、検索サービスをドコモが提供することにした」(夏野氏)
現在はNTTレゾナントやライブドアなど9社と連携し、ドコモの検索サイトから各社の検索結果に1クリックで移動できるようになっている。夏野氏は「我々は常にオープンであり、この9社以外の検索サービスについてもウェルカムだ。(ソフトバンクグループの)ヤフーでも構わない」と話し、連携する検索サービスの数を増やす考えも示した。
 グラフ:公式サイトと一般サイトのアクセス量
グラフ:公式サイトと一般サイトのアクセス量"
2006-12-02 09:28:00,IBM、仮想技術を現実のビジネスに活かすため新事業計画発表へ
Intenetnews.com November 13, 2006 Real Cash in $100M Virtual IBM Investment IBMの CEO (最高経営責任者) Sam Palmisano 氏は14日、1億ドルにのぼる支出計画を7000人以上の従業員の前で発表する予定だ。 しかし、Palmisano 氏も大勢の従業員も、生身の体で一堂に会する訳ではない。 全員が集まるのは、人気オンライン仮想世界サービス『Second Life』の中のタウンホールで催す仮想会議だ。そこで Palmisano 氏は、というよりも同氏のアバター (仮想世界における存在) は、同社が今後注力する10の新事業計画を明らかにする。 IBM は各計画について、今後12か月でそれぞれおよそ1000万ドルの資金を投じる。 Palmisano 氏が発表する計画の1つは、顧客が仮想世界で学んだ事柄を、現実世界のビジネス問題に応用できるよう手助けする新事業部門の設立だ。 この新部門が、サービスや半導体をはじめ、スーパーコンピューティング、メインフレームに至る他事業の多くにとって、この世のものとは思えないほどの成長を遂げるための足がかりになると、同社は期待している。 「こうした仮想的で高度な視覚化能力を用いて、あらゆる事業活動における設計/シミュレーション実施/最適化/運営/管理に役立てることが、今後10年間の IT 産業界で最も重要な飛躍の1つとなるだろう」と、IBM 技術戦略および技術革新担当副社長の Irving Wladawsky-Berger 氏は語る。 同氏は自身の Blog で、次のように記している。「現在の商用アプリケーション、特に企業リソース管理 (ERP) に関係するものは、非常に複雑で、画一的かつ静的なため、ユーザーに不満を与える結果となりがちだ。こうした業務アプリケーションを、ある種のシミュレーションゲームのように処理することで、すなわち業務とその運営について、現実味のあるシミュレーションと見なせるようなアプリケーションに仕立てることで、IT だけでなくビジネスそのものを変化させることになると確信している」 Transforming Business through Virtual Worlds Capabilities Irving Wladawsky-Berger eightbar IBM Virtual Worlds event in London and SL IBM Meets Up In Second Life"
2006-12-02 10:27:00,検索履歴を見れば人となりが分かる
Google Search History を利用すると、過去に自分が検索した履歴と統計が見られる。 フランスの美食家サバランが、「君の食するところを言いたまえ。君がどんな人物かを言い当てよう」といったり、「本棚を見ればその人の人となりがわかる」といったりする。検索履歴をみれば、もっと直接的にその人となりや最近の関心ごとがわかる。 Googleのパーソナライズド検索履歴(Beta)をご存知だろうか。利用するためにはGoogleアカウントが必要だが、ログインすればいつでもそれまでの履歴を参照できる。月別、週別、日別の検索回数やクエリ回数の多い単語、アクセス回数の多いサイトなどの統計データも表示してくれる。 個人的に再建策などに使うと便利であるが、なんだか自分の検索行動を監視されているようで不愉快に思う人もいるのではないか。もちろんオプトインで、検索履歴を残すもの、ウェブ、イメージ、ニュースなどを選択できる。プライバシが気になる人は設定に気をつけたほうが良い。"
2006-12-02 10:56:00,アメリカの大学生のネットワーキング
Creating a Gem of a Career とにかく若者のほとんどが厖大なネットワークを持った状態でキャリア構築を行う時代だということである。これは明らかに、我々の時代と全く違う。
そして皆、プライベートな情報の開示も含めて、旧世代には理解できないほどものすごくオープン。そして、おそろしいスピードで厖大な量の情報を皆がシェアする文化。
そしてチーム、プロジェクト、協力という感覚を皆が共有していて、たとえば何か技術的な問題に直面すればギークの友人にIMで尋ね、問題を解決する。会社の境界など考えずに、外部の人間の知恵を求める。 http://d.hatena.ne.jp/umedamochio/20060323 人ひとりの後ろに「Wisdom of Crowds」の個人ネットワーク版がくっついていて、そこに常時アクセス可能な状態で仕事をしていくのが当たり前になり、それで仕事のパフォーマンスが決まってくる時代になれば、その「Wisdom of Crowds」の個人ネットワーク版の質が、個の競争優位の源泉になっていくではないか。
昨日の午後、大学生を子供に持つ同世代の友人と話をしていたら、アメリカのいまの若者たちは、そのことを明確に意識して、高校時代の友人たち、大学で全米に散った友人たちのそれぞれの先でできる友人たち、大学の友人たち、大学を卒業して全世界に散った友人たち、そしてまたその先でできるグローバル・ネットワーク・・・・・、そういうネットワーク全体を「自分の財産」として蓄積し、きちんと丁寧に日々メンテナンスしていこうときわめて意識的だというのである。そこで昨日紹介したSNSの「Facebook」が使われるわけだ。
そしてそれが、ただ人生を豊かにする友達のネットワークというだけではなく、組織に属しながらもリアルタイムで「外部の知恵」としてそのネットワークを活用しながら仕事をしていくために使われる。一つ前の世代とは感覚が全く違うだけでなく、それがうまくワークしたときのパフォーマンスたるや、我々の想像を超える。
まさに「個のエンパワーメント」である。
"
2006-12-02 11:11:00,個のエンパワーメント
「Fast Company」という雑誌があり、創刊十周年を迎えた。http://www.fastcompany.com/magazine/103/ Fast Talk: What's the Biggest Change Facing Business In the Next 10 Years? The cornerstone for this millennium is the end of time and space. 元インテル副社長のAvram Millerは、「時間と空間の終焉、つまり我々一人ひとりが時間と空間の制約を感じずに生きる時代だ」と言う。会社が個に提供できるものがなくなるため、会社の従業員になりたいと思う人は減り続け、個がそのスキルを売る新しい手立てを見つけるだろうと言っている。
Esther Dysonにとっては、「an erosion of power」「Empowered people」が、「次の十年」を考察し続ける彼女の最近の大テーマのようだ。 Creating a Gem of a Career キャリア構築の未来についての話。「次の十年」のキャリア構築のあり方は大きく変わると説く。五つの波について書かれている。 Today's power networkers aren't just hoarding contacts but sharing information in unprecedented amounts at unbelievable speed. "They're far more open about discussing their private lives, from what they did at that party this weekend to salary information about their jobs says Morris. "What used to be difficult to get, you can now just ask [for]." warp-speed, ultraconnected culture at work とにかく若者のほとんどが厖大なネットワークを持った状態でキャリア構築を行う時代だということである。これは明らかに、我々の時代と全く違う。
そして皆、プライベートな情報の開示も含めて、旧世代には理解できないほどものすごくオープン。そして、おそろしいスピードで厖大な量の情報を皆がシェアする文化。 チーム、プロジェクト、協力という感覚を皆が共有していて、たとえば何か技術的な問題に直面すればギークの友人にIMで尋ね、問題を解決する。会社の境界など考えずに、外部の人間の知恵を求める。 こうした若者文化は、米国企業の仕事の仕方や組織のあり方を、今後大きく変えていく可能性が強い。よって、「個」にとってのネットワークの重要性が、さらに増してくる。当然のことながらSNSをはじめとする道具は道具にすぎず、その道具を使いこなして、いかに自分にとって「真に価値あるネットワーク」を構築し、維持し続けることができるかがキャリア構築の鍵を握る時代がやってくるはずだ。この記事は第一の波をこう総括している。
"
2006-12-02 11:17:00,富の再配分
「表現者と「ウェブ進化論」、住太陽 ウェブに関するなにがしかの専門家として、やってみる限りは、それで「飯を食う」程度のことができなくて、何を偉そうなことが言えるか、という気持ちがあるわけです。もちろん、僕のケースでは、勤めに出ている人たちとは始めから環境が違います。Adsenseであれアフィリエイトであれ、それに本気で取り組むだけの時間を捻出できますし、やるからには「小遣い程度になればいい」というような気持ちではありません。なにがしかの専門家としてのプライドのようなものをかけて取り組むわけです。
この結果、僕がこの種の広告収入で得るお金は、2005年9月に既存のサイトにAdsenseを貼り付け、その当月にいきなり980ドル程度の報酬を得たところから始まり、その後のアフィリエイトへの参加などで報酬は増え続け、今では月間70万円程度に達し、今も増え続けています。この種の「富の分配システム」を活用し始めてから、わずか半年しか経っていませんが、このようなことは現実に可能であり、単に「飯が食えるか」という点で言えば、既存メディアで表現を行って報酬を得るよりも、ウェブ上の広告収入のほうが遙かに率がよいのです。 既存の表現者たちは他に収入の途があるために、そのインパクトを積極的に活用していないだけだと、僕は思います。 dsenseやアフィリエイトを使って月収が数百万円という人はまあまあいるようです。例えば、以下はアフィリエイトのA8ネットの「個人会員」の「1ヶ月」の報酬ランキングですが、度肝を抜かれますよ。 http://support.a8.net/as/best3.html --------------------------------------------- http://server.typepad.jp/adsense/2006/03/adsense_2b15.html ProBloggerの読者がAdsenseによってどの程度の収入を得ているか去年の11月に行われた調査の結果です。 Adsense Earnings for November - Poll Results: ProBlogger Blog Tips この調査によると回答者全体の8割が~$1000/monthですが、5%が$10000~/month稼いでいるようです。このProBlogger、Adsense関連の様々なtipsに言及しているので、そういった方面に興味のある方は面白く読めるかもしれません。僕も軽く読みましたが、小手先のテクニック以前に一定以上のアクセスを集めていないと収益を十分にあげるのは難しい、という所に結局落ち着くみたいです。
"
2006-12-02 13:01:00,ベキ法則の仲間たち
一番最初に聞いたのは、アリの20:80の法則(パレートの法則)で、アリは20%の働き者と80%の怠け者に分けられて、働きものだけを集めても、さらに20%と80%に分かれるというもの。 単語の分布に関しては何故Zipfの法則が成り立つのかわかってないみたいですが、シンプルなモデルなので使われているみたいです。最初は自明な感じがしてましたが、良く考えると不思議ですね...。 ずっと前に集めた、ベキ法則関連の応用例です。 リンク先にてグラフが見られます。 ミクシィの友達数 (記事によるとミクシィ特有のでこぼこな形になるらしい) http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0509/14/news040.html ライブジャーナルの友達数 (本人は直線だといっているがミクシィと似たような現象が起きている・・・?) http://arvindn.livejournal.com/12395.html アメリカの都市の人口 http://www.kobe-toshi-seibi.or.jp/matisen/0urban/urbantalks/200009c.htm ここからは読み物。 雑学ドットコムに記事がありました。 http://www.zatsugaku.com/archives/2004/05/20040520.html 前にも紹介した「ベキ法則と民主主義」 http://www.can.or.jp/archives/articles/20030315-01/ 500以上の関連論文を集めたサイト。 Zipf's law, Benford's law, Bradford's law, Heaps' law, Lotka's law, Paretos principle の違いについても。Mandelbrot's law については記載なし・・・? http://www.nslij-genetics.org/wli/zipf/
"
2006-12-02 13:23:00,バンテージポイント
若者はバンテージポイント(有利な場所)でキャリアを磨け2004年01月30日 09:30
見晴らしの良い場所に行け
世界で何が起ころうとしているのかが見える場所に行け。シリコンバレーなら、まずはGoogle。GoogleがダメだったらApple。いやYahooかな。Oracleだっていい。シアトルならMicrosoftだな。こういうところは皆、「a great vantagepoint」((見晴らしのきく地点、よい観戦場所)なんだ。そういう会社で職を得れば、世界でこれから何が起ころうとしているかが皆見える。thenext big thingが来たとき、そこに陣取っていれば、見ることができる。
"
2006-12-02 14:18:00,Top 10 technologies 2006
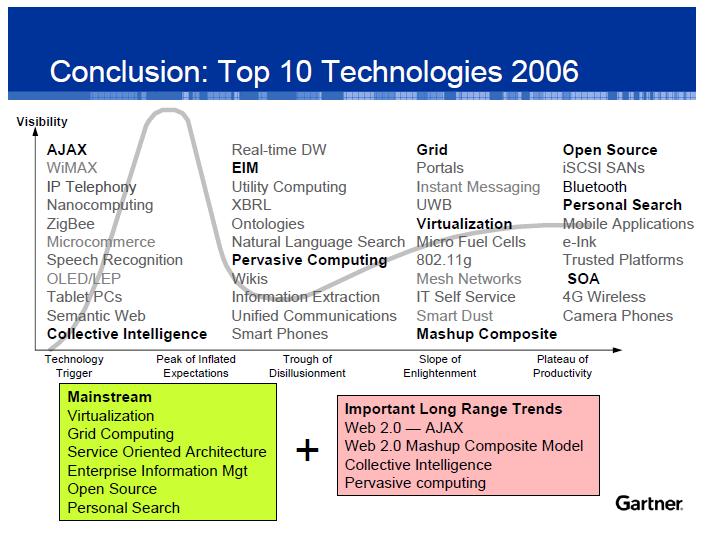 "
"
2006-12-02 14:34:00,Technology Growth Drivers
Morgan StanleyのMary Meeker基調講演 SIA
2006-11-14 Google+Yahoo!+eBay+Yahoo!Japan+Amazon.comの市場価値は、2000年3月時点の$178Bより46%高い$260B(06年11月14日)になった。2000年IPO以前の価値は$2Bだった。 公開市場における純資産価値の100%近くが、テクノロジー企業の2%以下が占有している。 過去平均で年に2社がTen-baggers(株価が1000%に高騰)になった。 Yahoo! 418MM、PayPal 123MM、Shopping.com 40MM CGM: Wikipedia+MySpace+YouTube躍進 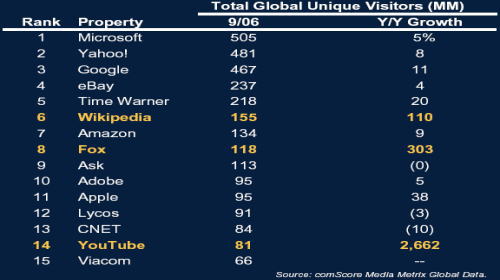 北米ユーザ 2000年:36% ⇒2007年:20% TMT成長:インターネットユーザ9億人(18%)、携帯16億台(14%)、PC7億台(11%) インターネット企業の36%が広告モデル収入 2005年$13B USオンライン広告収入 Google31%(2.7B) Yahoo!27%(1.6B)
北米ユーザ 2000年:36% ⇒2007年:20% TMT成長:インターネットユーザ9億人(18%)、携帯16億台(14%)、PC7億台(11%) インターネット企業の36%が広告モデル収入 2005年$13B USオンライン広告収入 Google31%(2.7B) Yahoo!27%(1.6B) 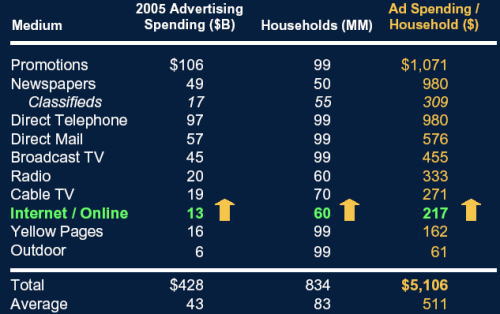 検索が顧客獲得手段のトップ(全体の36%) 利用者の67%が利用 P2Pトラフィックが60% BitTorrent30%
検索が顧客獲得手段のトップ(全体の36%) 利用者の67%が利用 P2Pトラフィックが60% BitTorrent30% 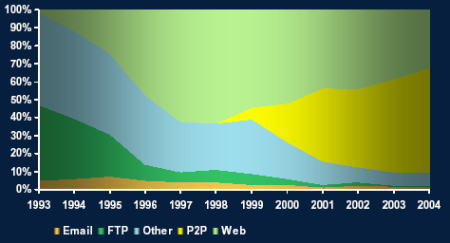 Mobile Internetアジア市場がトップ
Mobile Internetアジア市場がトップ 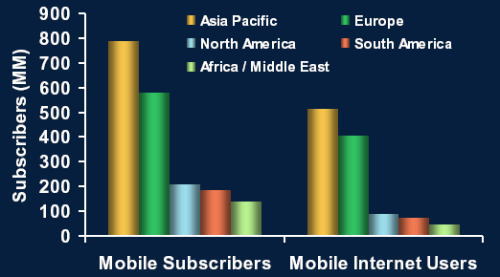 Watch Where Global Younger Generation Goes
Watch Where Global Younger Generation Goes  Mary Meeker delivered a keynote presentation at the Semiconductor Industry Association's Annual Forecast & Award Dinner. The presentation, titled "Global Technology Trends", discussed how the combination of mobile technology and the Internet are changing commerce, business strategies, and the adoption of technology on a global scale.
Mary Meeker delivered a keynote presentation at the Semiconductor Industry Association's Annual Forecast & Award Dinner. The presentation, titled "Global Technology Trends", discussed how the combination of mobile technology and the Internet are changing commerce, business strategies, and the adoption of technology on a global scale.
Below, we have provided a link to the presentation delivered at the event.
Global Technology Trends Presentation (31 Pages)
"
2006-12-02 16:49:00,情報源のトップにWeb検索情報
ガートナー調査結果(2006年11月発表)によると、ビジネスマンが利用する情報源のうち、「検索エンジンで入手するWeb情報」が「新聞・書籍・雑誌」といった既存のメディアを上回った。 これはビジネスマンの知的ワークスタイルが、インターネットの影響を受けて大変革を遂げていること示す。Web2.0潮流がさらに進化し、より使いやすく、より新しい価値を提供するようになるとともにインターネットへの依存度がますます高まる傾向にある。 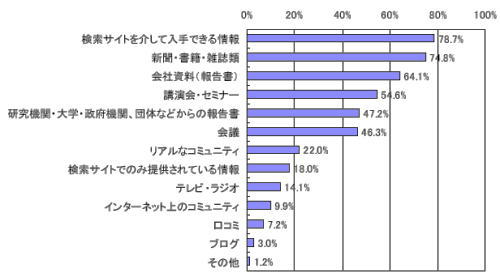 同時に膨大な情報の海からの必要な情報の選択と分析、情報発信もとの信用度についての判断など、個人と組織のスキルが重要になってくる。 長い間、ビジネスマンの情報源として中心的な存在は紙媒体であったのが、インターネットがこれを上回るようになったというのは、インターネットがもたらした歴史的変革のひとつといえる。 さらに、もうひとつの重要な情報源であるTV放送についても、世界的に起こっているインターネットでの広告や映像配信の進展により、インターネットが中心的な情報源にシフトしていく。すでに若い世代ではTVを見たり新聞を読んだりすることが少なくなり、インターネットで見たり読んだりするほうが多くなっている。"
同時に膨大な情報の海からの必要な情報の選択と分析、情報発信もとの信用度についての判断など、個人と組織のスキルが重要になってくる。 長い間、ビジネスマンの情報源として中心的な存在は紙媒体であったのが、インターネットがこれを上回るようになったというのは、インターネットがもたらした歴史的変革のひとつといえる。 さらに、もうひとつの重要な情報源であるTV放送についても、世界的に起こっているインターネットでの広告や映像配信の進展により、インターネットが中心的な情報源にシフトしていく。すでに若い世代ではTVを見たり新聞を読んだりすることが少なくなり、インターネットで見たり読んだりするほうが多くなっている。"
2006-12-02 19:57:00,IBM WebFountain
WebFountainで次世代の検索に挑むIBM IBM sets out to make sense of the Web CNET News.com February 5, 2004 「現在のウェブは巨大な掲示板だ。この掲示板を眺め、その変化を観察していけば、"何がどうなっているのか"という問いにも答えることができる。WebFountainはテキストから予測可能な構造を読み出し、人間と同じように情報を分析し、分類し、理解する」 ―市場調査会社IDCのアナリストSue Feldman  WebFountainは大量のウェブデータから意味を見つけようとする。その基盤となるのがテキストマイニングで、「自然言語処理(NLP)」といわれるものだ。WebFountainはサイトをインデックス化し、ページ内のすべての単語にタグを付け、単語固有の構造を明らかにし、相互の関連性を分析する。規模は違うが、このプロセスは5年生の国語の時間に習う文章構造の分析とよく似ている。テキストマイニングはデータのかたまりを品詞ごとに展開し、相互の大まかな関連性を明らかにする。 2004夏にはDow Jones & Reuters傘下の情報検索企業Factivaからも、WebFountainを採用したアプリケーションが発売される予定だ。Factivaは昨年9 月にWebFountainのライセンスを取得し、企業の評判を判断するソフトウェアの開発に取り組んできた。
WebFountainは大量のウェブデータから意味を見つけようとする。その基盤となるのがテキストマイニングで、「自然言語処理(NLP)」といわれるものだ。WebFountainはサイトをインデックス化し、ページ内のすべての単語にタグを付け、単語固有の構造を明らかにし、相互の関連性を分析する。規模は違うが、このプロセスは5年生の国語の時間に習う文章構造の分析とよく似ている。テキストマイニングはデータのかたまりを品詞ごとに展開し、相互の大まかな関連性を明らかにする。 2004夏にはDow Jones & Reuters傘下の情報検索企業Factivaからも、WebFountainを採用したアプリケーションが発売される予定だ。Factivaは昨年9 月にWebFountainのライセンスを取得し、企業の評判を判断するソフトウェアの開発に取り組んできた。
Analysts said they expect to see increasing demand from corporations for services that mine so-called unstructured data on the Web. According to a study from researchers at the University of California at Berkeley, the static Web is an estimated 167 terabytes of data. In contrast, the deep Web is between 66,800 and 91,850 terabytes of data.
Providing services for unstructured-information management is an estimated $6.46 billion market this year and a $9.72 billion industry by 2006, according to research from IDC. ◆エコノミスト誌9月4日号「Fountain of truth?」 ◆IEEE Spectrum誌 A Fountain of Knowledge 2003年のコンピューティング分野におけるベスト研究開発プロジェクトに、このWebFountainプロジェクトを選んだ。 このプロジェクトでIBMが発見したことは・・
・ウェブの30%はポルノ ・ウェブの30%は他の繰り返し ・一日に新たに変更されるのは5千万ページ ・ウェブの65%は英語 ◆Roland Piquepaille's Technology Trends ◆GoogleとYahoo検索結果の視覚化
◆Esther Dyson Life after Google 新しい3つの方向性を、PERSONALIZATIONと、GEOGRAPHY-SPECIFIC RESULTSと、BETTER-DISPLAYED RESULTS、として提示している。 サーチの近未来 PERSONALIZATION (検索結果の個別カスタマイズ) 結果をカスタマイズするには、過去の利用履歴でも利用者の属性でもカスタマイズするヒントとなる情報が何か必要となる。しかし、属性情報を取り扱う処理速度等システム的な問題と合わせて、使い勝手や個人情報の取り扱いの問題が出てくる。 GEOGRAPHY-SPECIFIC RESULTS これはポータルサイトでも広告バナーや地域情報の表示(ex天気)で実用化され始めている。日本では何より浮かぶのがGPS付き携帯との融合だろう。アクセスポイントや入力されたアドレス情報をヒントに表示する情報を選択するのは、Googleをはじめ実際サービスされている。他、まだ見えてきていないがノートはPDAなどの情報端末だとWi-Fiとも連動していくのか、GPS携帯と似たような仕組みになるが、カーナビと連動していくのかなど興味深い。ウェブの世界は物理的な距離感の無いまさしくサイバースペースという掴みようのない空間認識がこれまでだったが、物理世界の位置情報と積極的に繋がっていくことが今後予想される。 BETTER-DISPLAYED RESULTS これも最近良く聞く。検索結果があまりに多いと、片っ端から見るわけにもいかず、結局欲しい情報の辿りつけないことがある。結果をどうにか整理して見せる事は出来ないかという試み自体は決して古いものではない。中でも最近気になっているのはクラスタリング検索のvivisimo。eBay専用のサーチを開始するなど微妙な動きを見せ始めている。"
2006-12-02 21:39:00,TRECVID
http://www-nlpir.nist.gov/projects/trecvid/  13th International Conference on Multimedia Modeling (MMM 2007) [9-12 January 2007, Singapore]
13th International Conference on Multimedia Modeling (MMM 2007) [9-12 January 2007, Singapore]  Fifth International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI 2007) [25-27 June 2007, Bordeaux, France]
Fifth International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI 2007) [25-27 June 2007, Bordeaux, France]  International Conference on Image and Video Retrieval (CIVR 2007) [9-11 July 2007, Amsterdam, the Netherlands]
International Conference on Image and Video Retrieval (CIVR 2007) [9-11 July 2007, Amsterdam, the Netherlands]  14th International Conference on Image Analysis and Processing (ICIAP 2007)[10-13 September 2007, Modena, Italy] 仏・独政府が共同で進める次世代検索エンジン開発プロジェクト「Quaero」 2億5000万ユーロ(約350億円)を投入"
14th International Conference on Image Analysis and Processing (ICIAP 2007)[10-13 September 2007, Modena, Italy] 仏・独政府が共同で進める次世代検索エンジン開発プロジェクト「Quaero」 2億5000万ユーロ(約350億円)を投入"
2006-12-06 10:54:00,ネットワークと一体化する個人
KDDI伊藤副社長 基調講演 CEATEC2006 2006年10月05日 ネット通信の世界 10の変化 (補足) 1. Googleに聞けば何でも分かる 2. 情報はスモールグループで共有 (SNSで濃密な交流) 3. メールは古い、マルチで仕事 (SNS+Webブラウザ+IRC+Saas) 4. 携帯とメディアが融合しつつある 5. ワンセグ携帯の登場 6. 3セグ端末ももうすぐ登場 (デジタルラジオも) 7. ストリーミング画像を含めP2Pトラフィックが増えている (BitTorent) 8. 携帯でも映像データのトラフィックが増えている (YouTube) 9. ネットワークただ乗り論 10. IPの信頼性、セキュリティが問われるようになってきた 1.BB環境の変化 2005年3月にFTTHがDSLを回線数で抜いた。2006年6月から、DSL改選数は純減。 Google VideoやYou Tubeなどは日本でも人気で、ネットに動画を流す時代に入った 2.ブログやSNSが一般化 CGMアップロードが増加している。ユーザが情報を発信する時代になった。急激なトラフィックの増加にどう対応するか。KDDIは次世代ネットワークとして「ウルトラ3G」構想で変化に対応しようとしている。 3.ビジネスも2.0時代 トーマス・フリードマンのベストセラー"The World is flat(フラット化する世界)"がUPS宅配ビジネスの事例を取り上げている。PCの修理サービスを始めるという、ビジネスの分業、アウトソース化が進む。一方では、技術の進歩により、広告制作のようにビジネスの集約化も進む。つまり撮影や編集も、専門家に任せるのではなく自分で行うようになる。「垂・平モデル」がこれからのビジネス2.0の可能性を考える鍵ではないか。 EZwebトップメニューをGoogle検索にして「情報閲覧」は無料化。着うたフルダウンロードは有料化という、オープンとクローズドの併用をしている。Google導入によりアクセスが2倍になった。 4.携帯で個人認証 ユーザは複数のサービスを横断して利用するようになる。そのときに重要になるのが「簡単で確実な個人認証」である。携帯は個人しか使わないので、この用途に適している。テレビやラジオで紹介された商品を、携帯で本人認証をしてそのまま買えると便利である。潜在的な商流を発掘出るのではないか。"
2006-12-06 11:13:00,どこでもヤフー!
Yahoo! Everywhereは日本がリード(ヤフー井上社長)している。日本のインターネット人口は1996年の1000万人から、8000万人以上に増加した。インターネット業界は、こうした量の拡大の中で成長してきた。 利用者の伸びは減速しているが、利用時間が延びている。2000年と比較して2.3倍になり、月間18時間(2006年5月)に達した。このうちYahoo!Japan利用時間は3時間26分を占める。ページビューは1日12億PVに達し、利用者数は4500万人(ユニークユーザー)。 今後は規模の拡大による成長から、ビジネスモデルによる成長への転換が不可欠になる。その基軸となるのが、Yahoo! Everywhereである。PC利用から、時間や場所にとらわれずに利用できるようにするものである。 この先10年で携帯インターネットをオープンにする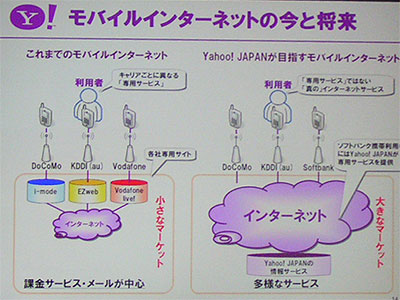 ―ヤフー井上社長 --------------- 「FTTH・ADSL・CATVなど、ブロードバンド市場規模は8000億円で、参入している会社の数は約300社。一方の携帯事業は8兆8000億円の市場規模で、利用者は9350万人であるのに、事業者はわずかに3つという寡占状態。ユーザーが損をしている状態を是正したい」―千本倖生氏 ---------------- デジタルコミュニティ 「今まで個別の事業者ごとに、ユーザーを囲い込む手段として、電子決済やカードは普及してきました。個々の企業のビジネス的動機が新しい技術を普及させる上で非常に大きな原動力となってきたわけです。ところが、たくさんのサービスが登場しますと、逆にそれが不便になり、いろいろなICカードをたくさん持ち歩かなければならなくなり、不便になってきます。そこで、今度はそれをいかに統合し、事業者ではなく、消費者のほうの利便性を上げていくことができるかという実験をすることになります。」―経済産業省の商務情報政策局の参事官・土本一郎氏 ⇒九州大学 e-Worldプロジェクト ⇒高松デジタルコミュニティ
―ヤフー井上社長 --------------- 「FTTH・ADSL・CATVなど、ブロードバンド市場規模は8000億円で、参入している会社の数は約300社。一方の携帯事業は8兆8000億円の市場規模で、利用者は9350万人であるのに、事業者はわずかに3つという寡占状態。ユーザーが損をしている状態を是正したい」―千本倖生氏 ---------------- デジタルコミュニティ 「今まで個別の事業者ごとに、ユーザーを囲い込む手段として、電子決済やカードは普及してきました。個々の企業のビジネス的動機が新しい技術を普及させる上で非常に大きな原動力となってきたわけです。ところが、たくさんのサービスが登場しますと、逆にそれが不便になり、いろいろなICカードをたくさん持ち歩かなければならなくなり、不便になってきます。そこで、今度はそれをいかに統合し、事業者ではなく、消費者のほうの利便性を上げていくことができるかという実験をすることになります。」―経済産業省の商務情報政策局の参事官・土本一郎氏 ⇒九州大学 e-Worldプロジェクト ⇒高松デジタルコミュニティ
"
2006-12-06 15:46:00,世界のCEOが考えるイノベーション
 イノベーション実現に向けた取り組みを明確にすることを目的に、世界のCEO(公共機関のリーダを含む)765人(日本91人)に直接インタビューした調査結果がIBMから公表されている。The Global CEO Study 2006 ?今こそイノベーションを実現させるために?という調査レポートによると、世界のCEOの65%が今後2年間に根本的な変革が必要と考えている。過去の根本的な変革の成功度合いは、グローバルで15%、日本で13%が「大きく成功した」という。 イノベーションを「新規性の高いアイデアあるいは既成概念を今までとはまったく異なる発想で実行し、大きな変革を実現させること」と定義している。なかでも日本のCEOは86%が、今後2年間に根本的な変革が必要だと答えており、全世界で最も変革に積極的であった。 1.ビジネスモデルまで踏み込んだイノベーション 競争優位や飛躍的な成長を実現するためには、新商品やサービスを創り出すこと以上に、ビジネスモデルでのイノベーションが必要だと認識されている。これは営業利益率の成長をもたらす傾向がある。 2.社外組織とのコラボレーション CEOは、新たな発想の源泉として、社内の研究開発部門への期待以上に、ビジネスパートナーや顧客などの社外に期待している。ときには競合企業までも視野に入れ、企業や業界の壁を越えたコラボレーション(協業)が求められている。業績の好調な企業ほど、社外とのコラボレーションを積極的に推進している。 3.イノベーションの「指揮者」はCEO イノベーションの実現を奨励するような企業風土を醸成する責任はCEOにあると自ら感じている。しかし、どうすればうまくいくかに確信があるわけではない。二つの要素がある。「チーム単位での活動を重視し、貢献は個人別に評価する」ということと、「ビジネスと産先端技術の融合に徹底的にこだわる」ということである。 ≪5つの提言≫ 1.CEOは「指揮者」である。自ら大きな構想を描き、イノベーションを複合的に推進するよう社内を動機付けていかなければならない 2.ビジネスモデルの革新性は固定観念の排除から生まれる 3.最先端技術を新しいビジネスの起爆剤とする 4.コラボレーションの可能性に壁はない 5.社員がいつでも社外に目を向けるようにさせるのはCEOの役割だ
イノベーション実現に向けた取り組みを明確にすることを目的に、世界のCEO(公共機関のリーダを含む)765人(日本91人)に直接インタビューした調査結果がIBMから公表されている。The Global CEO Study 2006 ?今こそイノベーションを実現させるために?という調査レポートによると、世界のCEOの65%が今後2年間に根本的な変革が必要と考えている。過去の根本的な変革の成功度合いは、グローバルで15%、日本で13%が「大きく成功した」という。 イノベーションを「新規性の高いアイデアあるいは既成概念を今までとはまったく異なる発想で実行し、大きな変革を実現させること」と定義している。なかでも日本のCEOは86%が、今後2年間に根本的な変革が必要だと答えており、全世界で最も変革に積極的であった。 1.ビジネスモデルまで踏み込んだイノベーション 競争優位や飛躍的な成長を実現するためには、新商品やサービスを創り出すこと以上に、ビジネスモデルでのイノベーションが必要だと認識されている。これは営業利益率の成長をもたらす傾向がある。 2.社外組織とのコラボレーション CEOは、新たな発想の源泉として、社内の研究開発部門への期待以上に、ビジネスパートナーや顧客などの社外に期待している。ときには競合企業までも視野に入れ、企業や業界の壁を越えたコラボレーション(協業)が求められている。業績の好調な企業ほど、社外とのコラボレーションを積極的に推進している。 3.イノベーションの「指揮者」はCEO イノベーションの実現を奨励するような企業風土を醸成する責任はCEOにあると自ら感じている。しかし、どうすればうまくいくかに確信があるわけではない。二つの要素がある。「チーム単位での活動を重視し、貢献は個人別に評価する」ということと、「ビジネスと産先端技術の融合に徹底的にこだわる」ということである。 ≪5つの提言≫ 1.CEOは「指揮者」である。自ら大きな構想を描き、イノベーションを複合的に推進するよう社内を動機付けていかなければならない 2.ビジネスモデルの革新性は固定観念の排除から生まれる 3.最先端技術を新しいビジネスの起爆剤とする 4.コラボレーションの可能性に壁はない 5.社員がいつでも社外に目を向けるようにさせるのはCEOの役割だ
"
2006-12-08 19:36:00,The Innovator's Dilemma
クリステンセン教授の出発点 そして、その失敗の原因は、この優れた経営そのものにある。 - 顧客の声に謙虚に耳を傾け - 顧客の求める、より優れたプロダクトをより多く提供し - 市場トレンドを注意深く研究し - 最大のリターンをもたらすイノベーションにシステマティックに投資する これらの優れた経営それ自体が、Excellent Companiesを失敗に導いた。
Christensen, Clayton, "The Innovator's Dilemma", p xii ----- テクノロジーの定義 組織が、ヒト、モノ、カネ、情報を、より価値の高い製品やサービスに変容させる過程
このテクノロジーは、エンジニアリングや製造に限定されず、マーケティング、投資、マネジメントの過程などの広範な範囲に及ぶ。
これらのテクノロジーの要素のひとつが変容することを、イノベーションと呼ぶ。
Christensen, Clayton, "The Innovator's Dilemma" , p xiii ----- Sustaining TechnologyとDisruptive Technology
Sustaining Technology - 主要市場の主流の顧客が歴史的に価値をおいている既存製品の性能の向上をもたらす - Excellent Comapnyが、このSustaining Technologyのイノベーションの導入に失敗し、それが、失敗の原因となったことはなかった。
Disruptive Innovation -- Disruptive Technology - 短期的には、製品の性能は低い - しかしながら、Excellent CompaniesはこのDisruptive Technologyの導入に失敗し、それが、失敗の原因となった。
Disruptive Technologyは、 - 従前に市場に存在しなかった価値をもたらす。 - 主流の市場の既存製品よりも性能は低い。 - しかし、少数の周辺的(一般には新しい)顧客は価値を見い出す。 - 製品は、安く、より単純であり、より小さく、より使い勝手が良い
例:オートバイ産業におけるHonda, Yamaha, Kawasaki vs Harledy-Davidson, BMW 将来的には、インターネット家電 vs PCソフト、ハード
Innovator's Dilemmaにおける実証 - HDD - 掘削機械
Disruptive Technology vs. 企業における合理的意思決定 主流企業、Excellentとされている企業が合理的意思決定を行うとdisruptive tech nologyは採用されない。 1)製品がよりシンプルであり安い:マージンが低く利幅が小さい 2)disruptive technologyは最初にemerging marketか重要性のない市場で商品 化される。 3)主流企業に最大の利益をもたらす顧客は、初期段階において、disruptive tec hnologyにもとづく製品を欲しないし、初期においては要求仕様が満たされないため 、使いようがない。
----- チャート
----- Disruptive Technologyによって引き起こされる変革のプロセス
step1 最初、主流企業においてdisruptive technologyは開発される。 step2 マーケティング部門が主要顧客の反応を探る。 -- 顧客の仕様を満たす段階にない -- disruptive technologyがテイクオフするために必要な資源投入と いう意思決定が主力企業ではなされない。 step3 主流企業ではSustaining Technologyの開発により既存主力顧客の要望に応 え続けようとする。 step4 新たな企業が設立され、Disruptive technologyを用いた市場が試行錯誤を 経て、発見される。 step5 新規参入企業は、徐々に主力顧客にも食い込む step6 (旧)主流企業は主力顧客ベースを防衛するために遅ればせながらdisrupti ve technologyを使った製品/サービスを投入するが・・・手遅れになる。
----- 主力企業がDisruptive Technologyを活用することができた事例
1. 主力企業がしたがわなければならない原則 1)資源の依存性:順調な企業の資源配分は顧客が効果的にコントロールしている。 2)小さな市場は、大企業の成長を満たせない。 3)disruptive technologiesの究極の市場は、予めわかるものではない。失敗は成 功に向けた必要なステップと認識しなければならない。 4)テクノロジーがもたらすものが需要と一致するとは限らない。既存市場において disruptive technologiesを魅力的になしえない特徴(欠点)が、新たな市場におい ては大きな価値をもたらすこともある。
2.成功した企業がしたこと 1)disruptive technologiesを必要とする顧客を有する組織に、disruptive techno logiesの開発と商品化を担うプロジェクトを設置する。マネジャーがdisruptive tec hnologiesを「適切な」顧客とマッチさせることができれば、その顧客の需要がdisru ptive innovationを発展させるためのリソースをもたらす。 2)disruptive technologiesのプロジェクトを小さい組織に埋め込み、小さい事業 機会、小さい成功にも喜びを見い出しうるようにした。 3)disruptive technologiesに適する市場を特定するにあたっては、できるだけ早 期にかつ大きな損失をもたらさずに失敗できるように計画した。市場は、試行、学習 、さらなる試行というインタラクティブなプロセスを通じて形成されるものであるこ とを発見した。 4)disruptive technologiesの商用化にあたっては、disruptiveな製品の特徴に価 値を見い出す市場を発見するか開拓するかした。主流市場で新たなsustaining techn ologyとして競争しうるようなブレークスルーを探索しようとはしなかった。 ----- 通信産業におけるdisruptive technology -- VOIP, Internet VPN, IP over DWDM
通信産業の新サービスが顧客となるさまざまな業界にとってのDisruptive Technolog iesの主要構成要素ともなる。
99.06.11 中川一郎記す
"
2006-12-17 21:56:00,SNSの現在と展望
SNSの現在と展望 -コミュニケーションツールから情報流通の基盤へ- Current Status and Future Perspectives of Social Networking Services
大向 一輝 Ikki Ohmukai
国立情報学研究所 / 総合研究大学院大学 National Institute of Informatics / The Graduate University for Advanced Studies
1. はじめに
近年、家庭向けブロードバンドやインターネット接続可能な携帯電話の普及によって、Webのユーザ数が飛躍的に増加している。これにともなって、Webは情報収集のためだけではなく、個人間のコミュニケーションの場として利用されるようになってきた。
Web上でのコミュニケーション手段として、すでに普及が進んでいる電子掲示板システム(BBS)やブログ(Weblog)[1]に次いで、利用者が急増しているのがソーシャルネットワーキングサービス(SNS)である。SNSは、会員制のコミュニティサイトの一種である。SNSでは、参加者がそれぞれに固有のページを持ち、他の参加者と相互にリンクすることで小規模のコミュニティを形成する。コミュニケーションはその内部でのみ行われるため、不特定多数に情報が公開されるBBSやブログとは異なる密接なコミュニケーションが可能になる。
SNSは海外で誕生したサービスであるが、国内でも普及が進み、国内最大のSNSは600万人以上の会員を得ている。また、既存の情報サービスとSNSが融合した例も数多い。
SNSは、旧来のWebサイトやBBSと異なり、参加者の同一性を特定しやすいため、コミュニケーション分析の研究対象として注目を集めている。また、SNS上では大規模な社会ネットワークが形成されるため、ネットワーク分析手法を適用することで新たな知見が得られる可能性がある。
本稿では、SNSの発祥から現在に至るまでの変遷について述べた上で、研究対象としてのSNSの位置づけについて議論し、今後の課題や展望について述べる。
2. SNSとは 2.1. Webコミュニケーションの変化 ネットワークを利用したコミュニケーション手段としては、古くから会員制パソコン通信におけるBBS・フォーラムや、インターネットにおけるUsenet・ニュースグループといったシステムがある。これらのシステムでは、カテゴリ分けされたテーマごとに議論の場が設けられ、参加者は各自の興味に沿ってそれぞれの場にメッセージを投稿する。特定のトピックに関する一連のメッセージの集合はスレッドと呼ばれ、コミュニケーションの履歴はこのスレッドごとに管理される。
Webにおけるトピック指向のコミュニケーションシステムとしては、パソコン通信と同様のBBSや、コミュニティサイトと呼ばれる会員制のものがある。また、メーリングリストは電子メールを利用したスレッド指向コミュニケーションであるといえる。
トピック指向コミュニケーションシステムは、トピックに対してメッセージを投稿するだけでそのコミュニティに参加できるため、参加に対する敷居が低い。また、議論の内容が重要であるため、投稿者の記名性が問題にされないことも多い。この特徴を積極的に活用した大規模コミュニティが、匿名BBSの集合体ともいえる「2ちゃんねる」である。また、米国ではオンライン上のクラシファイド(個人向け3行広告)サービスである「craigslist」による情報交換が盛んである。
その反面、トピック指向コミュニケーションにおいては、投稿者の存在が見えにくい。あるスレッドにおける特定の投稿者が、他にどのようなトピックに興味を持ち、投稿しているかを知ることは極めて難しい。
SNSは、日常的なコミュニケーションの支援を目的として、コミュニケーション主体である個人の存在を明示化し、個人間の情報流通を実現するためのシステムであると定義できる。本稿では、このようなコミュニケーションの形態を個人指向コミュニケーションと呼ぶこととする。
代表的なSNSである「mixi」のスナップショットを図1に示す。SNSの各参加者は、サービス上で自分のページが与えられ、プロフィールや日記など、自身に関する情報を掲載する。他の参加者の情報を閲覧するためには、その参加者と知人関係を構築する必要がある。多くのSNSでは、相互承認を行うことで知人関係が成立する。自身の情報は、原則として知人のみに公開されるが、間接的な知人への公開や、SNSの参加者全員に公開するなどの制御が可能である。関係を構築した知人の情報は制御の結果に応じてすべて自分のページに集約されるため、周囲の情報を容易に得ることができる。
知人関係に基づく情報の発信・受信に加えて、トピック指向のコミュニケーション機能を備えるSNSもある。ここでは、トピックはコミュニティと呼ばれ、コミュニティごとにBBSが設置されている。各コミュニティには、参加者のリストが表示され、各自のページとリンクされるため、一般のBBSのような匿名性はない。
SNSの形態に近いコミュニティサイトとしては、企業・大学といった所属組織ごとのコミュニティサイトがある。このようなサイトでは、組織内のコミュニケーションの活性化が目的であるため、話題・トピックを限定せず、各参加者の存在を可視化する機能を持つものが多い。その点で、SNSは組織内コミュニティサイトをWeb全体に拡張したものであると考えることもできる。
2.2. SNSの歴史 個人指向のコミュニティサイトがSNSと呼ばれるようになったのは、2003年に米国で開設された「Friendster」が最初であるとされている。Friendsterは急速にユーザを獲得し、開設後3ヶ月で100万人に達したことから注目されるようになった。その後、Googleによる「Orkut」が人気を集め、2004年の初頭には日本のユーザにも知られるようになった。同時期に、米国ではSNSを利用してジョブマッチングを行う「LinkedIn」など、多様なサービスが展開されるようになった。
日本では、2004年2月に「GREE」および「mixi」が開設され、米国と同様に普及している。国内最大手のmixiは、2006年12月現在で670万ユーザを獲得している。
SNSの普及は全世界的に進行しており、世界最大のSNSである「MySpace」の会員数は1億1,000万人を超え、1日あたり25万人の新規登録がある。他にも、大学生向けSNSの「Facebook」やMicrosoftが運営する「Wallop」など、ユーザ数が1,000万を超すSNSがいくつか存在する。これらは英語でのサービスであるため、参加者の国籍・居住地は多種多様であるが、韓国のSNS「CyWorld」は韓国語圏でのサービスながら1,300万ユーザを抱えており、韓国の総人口の30%程度、20代の女性の95%が参加しているといわれている。
利用者数の統計としては、米Nielsen//NetRatingsによる2006年4月の全世界の利用者数が6億8800万人、総務省による日本国内の利用者数が716万人という数字がある。
このように、SNSは急速に普及しており、認知度が高まるにつれて類似サービスが続々と登場している。SNSの最新事例の詳細は、「ソーシャルネットワーキング.jp」に掲載されている。現在では、既存のサービスとSNSの機能を統合したサービスが多く、どのサービスがSNSであるのかを明確に区別することが難しくなっている。当初はSNSの定義として、すでに参加しているユーザからの招待が必要(招待制)、というものがあったが、現在では多くのサービスが登録制になっている。
例えば、ブログとの統合では、友人関係を定義した上で、ブログ記事のそれぞれについて公開・非公開をコントロールすることが可能な「LiveJournal」が広く普及している。また、ブックマーク共有の「del.icio.us」、画像共有の「Flickr」、動画共有の「YouTube」などのサービスにおいても、SNSとしての機能を一部備えている。
また、話題・トピック限定のSNSや、地域限定のSNSなど、ユーザの範囲を限定したSNSも数多い。後者の例として、熊本県八代市による「ごろっとやっちろ」を筆頭に、行政主導のサービス展開が模索されている。
コミュニケーション手段としてのSNS以外に、他の用途にユーザ間の社会関係を導入する動きもある。「Rojo」では、RSSリーダーとSNSを統合することで、大量の記事の中から知人が興味を持っているものを優先的に表示させるなど、検索・推薦の手段としてSNSを利用している。
3. SNS研究の現状 SNSでは、個々の参加者のふるまいだけでなく、参加者間のつながりの総体としての大規模ネットワークを観察することができる。この特徴を利用して、工学やコンピュータ科学のみならず、社会学や心理学、物理学のアプローチを用いた研究が進められている。
本章では、これらの研究をコミュニケーション分析、社会ネットワーク分析、および情報・知識共有の3つの観点に基づいて分類し、紹介する。また、研究者に特化したSNSの構築・運用例について取り上げる。
3.1. コミュニケーション分析 SNSに関する代表的な研究のひとつとして、社会学ならびに心理学の観点からSNSにおけるコミュニケーションの特性を明らかにするものがある。川浦らは、mixiの参加者に対してアンケートを行い、SNS利用の目的(日記・コミュニティ)、実名・顔写真の公開の有無とコミュニケーション指向との関連を調査している[2]。これによれば、日記すなわち知人とのコミュニケーションを主に利用するとの回答が80%にのぼり、mixiが記名制のBBSとは異なった利用のされ方をしていることがわかる。また、実名・顔写真の公開の有無については、それぞれを公開している参加者ほど新たな他者とのコミュニケーションを求め、非公開であるほど現実の知人関係でのコミュニケーションを求めている傾向が明確になっている。また、同じアンケート調査から性別・年代別の利用者意識を抽出する研究もある。ただし、これらの研究は2005年3月時点(会員数約40万人)のアンケートに基づいており、その後の参加者層と傾向が異なっている可能性があるため、継続的な調査が必要であると思われる。
海外の研究事例では、英語で提供されているSNSにおいて、参加者の国籍あるいは国民性とふるまいの特性との関連を調査した研究がある。この研究では、参加者同士が知人関係を成立させるにあたり、事前にどの程度のコミュニケーションがあったかを参加者の国籍ごとに分類して議論している。SNSの使われ方には背景となる文化による違いが存在すると思われるため、こういった比較研究は増えていくものと予想される。
3.2. 社会ネットワーク分析 社会ネットワーク分析は、社会学の中でも、人と人を結ぶ関係に着目し、関係構造であるネットワークを分析することでコミュニティ全体の特性を明らかにする学問分野である。社会ネットワーク分析を行うためには、計量可能な形でネットワークを記述する必要があるが、個人間の関係は非明示的であることから、従来の研究ではアンケート調査等によってネットワークを把握していた。この方法ではコストの問題から大規模なネットワークを扱うことが難しかったが、インターネット上では容易に社会ネットワークを得ることができるため、急速に研究が発展している。社会ネットワークの例として、mixiの参加者によるネットワークの一部を図2に示す※。
※社会ネットワークの可視化には「mixiGraph」を利用した。
SNSが出現する以前にも、メールやコミュニティサイトを対象とした社会ネットワーク分析研究は多数存在しており、この時点で方法論はある程度確立されている。これについてはWellmanの論文[3]にて詳しく議論されている。
基本的には、各ノード(参加者)について中心性と呼ばれる指標群を計算し、その結果を用いてノードの評価やクラスタリング等の処理を行う。中心性には、ノードの持つリンクの数(次数)、任意のノードとの平均距離(近接性)、任意の2ノード間の最短経路に含まれる割合(媒介性)、固有ベクトルの値等がある。他にも、ネットワークの密度を計測する指標として、あるノードと接続されたノード同士がどの程度接続されているかを見るクラスタリング係数等がある。なお、ネットワークの分析に際してどの中心性・指標を重視するかは、分析の対象および内容によって異なる。
こういった指標を利用した分析の例として、安田らは数年間に渡って人工知能学会関係者のネットワーク(取得方法は後述)を分析し、ある年度における各研究者の媒介性が、次年度の共著論文の数と相関するといった知見を示している[4]。この知見は因果関係としては採用できないが、研究コミュニティにおける研究トピックの推移を俯瞰するための手段として有用であると思われる。
SNSの分析としては、このように具体的な内容に踏み込んだ研究はまだ見られないが、いくつかの構造分析がなされている。森らは、2005年2月時点のmixiの全参加者36万人に対して中心性を用いたクラスタ分析を行い、参加者を3つのグループに分類した。また、松尾らは同じデータについて知人数の上位200名のみで構成されたネットワークを分析し、どのノードも孤立することなしに1つのネットワークに集約されることを示した。これらの結果より、多数のリンクを持つノードのグループ同士が密接につながっていることが確認された※。
※森ら、松尾らの研究は、株式会社ミクシィより個人情報を特定できない形で提供されたデータに基づく。各研究グループの成果は社会情報学フェア2005にて発表された。
この現象は、大規模な複雑ネットワークにおいて普遍的に観察されるスケールフリー性およびスモールワールド性を示している。スケールフリー性とは、ネットワークを構成するリンクの大部分が少数のノードに接続され、大多数のノードにはごく少数のリンクしか存在しないような状態を指す。このようなネットワークについて、図3のようにノードとリンクの関係をプロットすると、規模に関わらず同様のべき乗分布を示すため、スケールフリーと呼ばれている。一方、スモールワールド性とは、ネットワークの規模に比して任意の2ノード間の距離が短くなるような性質のことであり、これを満たすためにはランダムネットワーク(ノード間の関係に法則性がないネットワーク)と比較してクラスタリング係数が高い必要がある。
これらの知見より、SNSはランダムネットワークではなく、知人同士が密接につながった小規模なコミュニティが、リンク数の多いノード(ハブ)によって大域的に連結された構造であると予想される。
スケールフリー構造を持つ大規模複雑ネットワークがどのように形成されるかについては、Barabasiらが優先選択モデルを提案している[5]。これは、新たなノードが生成された場合に、そのノードがすでに存在するノードに対してリンク数に応じた確率に基づいてリンクを張るというモデルであるが、SNSにおいては、ネットワークは実世界の人間関係の転写という一面があるために、このような優先選択モデルをそのまま採用することはできない。湯田らは、mixiに対する大規模ネットワーク分析を行い、純粋なスケールフリー構造とは一部異なる構造が観察されると指摘している※。このような差異を作り出すネットワーク形成モデルについてはさらなる研究が必要である。
※社会情報学フェア2005より
3.3. 情報・知識共有 SNSに対する情報・知識共有の立場からの興味としては、システム上で流通する情報のアクセスコントロールがある。グループウェア等の情報共有システムは、単一の組織内で運用されるものであるため、システム管理者がアクセス権を制御することができる。しかしながら、SNSにおける知人関係は単一の組織を超えて構築されるのが普通であり、それらをトップダウンに管理することはできない。各参加者は自身で情報管理を行う必要があるが、日常的な情報交換にあたってそのような管理を綿密に行うのは現実的でない。そのため、多くのSNSにおいては、アクセス権限を、直接の知人関係のみ、間接的な知人関係、SNSの参加者全員のように、ホップ数に基づく段階的な設定のみを提供している。しかしながら、この方法では、複数のコミュニティにまたがる情報公開を余儀なくされるため、適切であるとは言えない。
このような問題に対して、Yahoo!のSNSである「Yahoo! Days」などでは、知人関係をコミュニティごとに分類し、情報のアクセス権をコミュニティ単位で付与する機能を提供している。ただし、この方法であっても、コミュニティとして明確に区分できないような範囲に対して情報を発信する場合の作業負荷は大きくならざるを得ない。また、コミュニティを中心としたアクセスコントロールにおいては、コミュニティの参加者が時系列的に変化する場合に、新たな参加者に過去のコンテンツへのアクセス権を付与してよいかといった問題もある。
これについては、コミュニティをあらかじめ定義するのではなく、情報へのアクセス時に現状のネットワーク構造を動的に分析し、その結果を用いて制御を行う手法が模索されている。前節で述べたように、大規模な社会ネットワーク分析手法が整備されつつあり、これらを用いることによって実用的なアクセスコントロールが可能になると期待される。
3.4. 研究者のSNS SNSに関する研究は、多大なデータを必要とすることから、実サービスの運営者と連携して進められることが多い。その一方で、研究者自らがコミュニティ支援システムを構築し、運用している例もある。人工知能学会大会支援ワーキンググループでは、2003年度より人工知能学会全国大会の論文著者および参加者を対象としたWeb情報支援サービス「Polyphonet Conference」を提供している。Polyphonet ConferenceにはSNS機能が含まれ、研究者のネットワークに関するデータの収集および分析を行っている。図4にスナップショットを示す。
PolyphonetConferenceでは、一般的なSNSと同様に、参加者ごとのページが用意され、他の参加者と相互にリンクすることでネットワークを拡張していく。しかしながら、論文著者・参加者の全員がシステムを利用するとは限らないため、このようなネットワークによってコミュニティの構造を正確に表現することは難しい。そこで、Matsuoらは、Web全体を情報源としてネットワークを抽出する手法を適用している[6]。この手法では、あらかじめ用意された人名(ここでは論文著者・参加者)のセットから、任意の2名について人名が共起するWebページを検索し、その数から関係の強さの判定およびネットワークの構築を行う。また、得られたWebページの内容を分析することで、関係の種類(共著関係・同じ研究室に所属している関係など)を判別し、ラベル付けを行っている。
PolyphonetConferenceに格納されたネットワーク情報は、さまざまな方法で検索することが可能である。図5に示すように、自身を出発点として、他の研究者との間にどのような知人関係が存在するかや、ある研究者を取り巻く複数の研究コミュニティを概観することができる。
また、Polyphonet Conferenceでは、各研究者の活動内容をWeb情報を用いて推定することや、知人との関係を明示的に記述するタグ機能、協調フィルタリングによる聴講スケジュールの推薦など、社会関係を利用したアプリケーションを多数提供している。
4. SNSのオープン化とメタデータ これまでに取り上げてきたSNSは、そのほとんどが中央集権型のアーキテクチャになっている。これは、一定レベルのプライバシーの保護や、意図しない情報公開の抑止に役立っている。その一方で、SNSではブログで見られるようなデータの互換性については全く考慮されていないため、複数のSNSへの参加や活動は非常に面倒である。
先に述べたように、SNSは個人的なコミュニケーションのツールとしてだけではなく、幅広い利用が可能である。用途によっては知人関係を公開することは問題ではない場合もあり、そのような用途に対してオープンなSNSを構築するための基盤が構築されつつある。
代表的な例として、知人関係をメタデータとして記述するためのFOAF(Friend of a friend)がある。FOAFは、RSS 1.0と同じくRDF(ResourceDescriptionFramework)の応用例として提案されおり、自身に関する記述および知人との関係に関する記述が可能になっている。一部のブログでは、プロフィールと知人のサイトへのリンクを表現する手段としてFOAFが利用されている。
その他には、XHTMLに埋め込むためのメタデータであるmicroformatsのプロジェクトとして、知人関係を表現するXFN(XHTMLFriendNetwork)がある。XFNでは、ハイパーリンク(Aタグ)のrel属性として"friend"や"met"などの関係を記述する。microformatsを認識する一部の検索エンジンでは、XFNで表現されたコンテンツ間の関係を可視化することができる。
知人関係には多様性があるが、これをメタデータでどのように表現するかは議論の余地がある。FOAFでは"knows"の1種類に限定しているが、XFNでは18種類の属性が定義されている。さらに詳細は関係を表現するためには、知人関係についてのオントロジーが必要になると思われる。
特定のコミュニティサービスのアカウント情報を他のサービスでも利用可能にすることで、汎用化を目指す方向性もある。ブログサービス等を提供している「はてな」では、アカウント情報を図6のようにRDFを用いて記述するフォーマットを提供し、他のブログサービスを利用するユーザに対しても「はてな」が提供する少額決済サービスを利用できるようにしている。
SNSは、その本質からして究極的には各個人が自身の情報を管理し、知人とはP2Pによる通信を行うようなアーキテクチャであることが望ましい。「imeem!」や「Affelio」は、個人がサーバを設置し、サーバ間通信によって情報交換を行うSNSを提供している。
複数のサービスを透過的に利用するという意味では、認証の統一化、シングルサインオン技術が重要である。シングルサインオンは、グリッドなどさまざまな分野で研究が進められているが、Webサービスに特化した活動としては「OpenID」や、ブログのコメントを認証するための「TypeKey」がある。
5. SNSの課題・展望 5.1. 情報の信頼性 SNS上で流通する情報は、その情報源である個人間の関係、あるいはコミュニケーション過程が明示化されることよって信頼性が高いものであるとされている。しかしながら、このような信頼性は、最終的にはシステムを利用する個人の判断に帰着するものであり、何らかの技術が担保するものではない。そのため、SNSはチェーンメールやデマなど、悪意のある情報操作に弱いという一面がある。あるSNSでは、個人情報に関するシステムの脆弱性が発見され、即座に対策がなされたものの、脆弱性に関する情報が参加者の日記を通じて数万人に広まるといった現象が起こっている。典型的な伝播のパターンとしては、知人の日記からこの問題を知り、より詳細な情報を得るために検索を行うと、同じような情報が多数存在するために問題の信憑性が高まり、他の知人へ伝えようとする。大規模なSNSにおいては、このプロセスが数回繰り返されるだけでも広範囲な影響を与えることになる。
また、SNSは容易に情報を発信できるため、自らが過剰な情報公開を行ってしまう例も見られる。とくに、未成年などコンピュータのリテラシーが十分でない層にその傾向が強く、犯罪を誘発しやすい状況になっている。大部分のSNSでは参加者の年齢制限をかけることによりこの問題を回避しようとしているが、実効的に機能しているとはいえない。
これらは情報を扱ううえでの本質的な問題であり、SNSに限定されるものではない。しかしながら、SNSの普及速度に対して問題の周知が遅れているため、さまざまな事象が起こっている。今後は、長期的な視野に立った情報リテラシー普及などが求められる。
技術的観点から情報の信頼性を扱う研究分野としては、セマンティックWebが挙げられる[7]。セマンティックWebは、論理に基づいて記述されたコンテンツや意味体系を整備し、エージェントがそれらを処理することで適切な情報収集を提供する。セマンティックWebにおいても、情報そのものの信頼性を完全に担保することはできないが、電子署名との組み合わせなどによって信頼性の阻害要因を除去するという方向性はSNSにも適用することが可能であると思われる。
5.2. コミュニケーションツールから情報流通の基盤へ 2章でも述べた通り、SNSはコミュニケーションツールの一形態として登場した。個人間の関係の明示化とコミュニケーションは極めて親和性が高く、参加者にとって受け入れやすいものであったため、急速な普及につながったと考えられる。一方、SNSの普及は、基盤となる社会ネットワークの有用性に目を向けさせることにつながった。社会ネットワークとコミュニケーションは分離可能であり、コミュニケーションとは異なる社会ネットワークの利用方法がさまざまな分野で提案されている。広告やマーケティングの分野では、パーソナライゼーションの一環としてSNSの利用が模索されているほか、情報検索や推薦、組織内の人事評価など、対象および利用目的は多岐に渡る。
将来的には、4章で述べたような認証基盤上に各種サービスが構築され、ユーザが自由に必要な機能を選択するオープンなSNSが普及するものと思われる。
情報流通基盤としてのSNSでは、これまで以上に多様なデータが取り扱われることになる。これにともなって、SNSを対象とした研究も高度化すると考えられる。社会ネットワーク分析の分野では、同じ個人が形成する、ドメインに応じた多層のネットワークの分析が注目されている。また、数千万人単位のネットワークを分析するにあたっては、計算量の問題を解決しなければならない。今後は、実サービスを運用する企業と研究者の密な連携によって、SNSの可能性を追究することが望ましい。
参考文献
[1] 武田英明, 大向一輝: Weblogの現在と展望:セマンティックWebおよびソーシャルネットワーキングの基盤として. 情報処理, Vol.45, No.6, pp.586-593, 2004. [2] 川浦康至, 坂田正樹, 松田光恵: ソーシャルネットワーキング・サービスの利用に関する調査:mixiユーザの意識と行動. コミュニケーション科学, Vol.18, pp.91-110, 2005. [3] Wellman, B.: Computer Networks As Social Networks. Science, Vol.293, pp.2031-2034, 2001. [4] 安田雪: 人脈づくりの科学. 日本経済新聞社, 2004. [5] Barabasi, A.: Linked: The New Science of Networks. Perseus Books Group, 2002. [6]Matsuo, Y., Mori, J., Hamasaki, M., Ishida, K., Nishimura, T., Takeda,H., Hasida, K. and Ishizuka, M.: POLYPHONET: An Advanced Social NetworkExtraction System. Proceedings of the Sixteenth International WorldWide Web Conference (WWW2006), 2006. [7] Berners-Lee, T., Hendler, J. and Lassila, O.: The Semantic Web. Scientific American, 2000.
----
本論文は非公式バージョンです。学術論文へ引用される場合には、必ず「情報処理」2006年9月号掲載の論文をご参照ください。(大向一輝: SNSの現在と展望 -コミュニケーションツールから情報流通の基盤へ-, 情報処理, Vol.47, No.9, pp.993-1000, 2006.) http://i2k.vox.com/library/post/sns%E3%81%AE%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E3%81%A8%E5%B1%95%E6%9C%9B.html
 Blogger
Blogger  She is now in the vile embrace of the Apollo of the evening. Her head rests upon his shoulder, her face is upturned to his, her bare arm is almost around his neck, her partly nude swelling breast heaves tumultuously against his, face to face they whirl on, his limbs interwoven with hers, his strong right arm around her yielding form, he presses her to him until every curve in the contour of her body thrills with the amorous contact. Her eyes look into his, but she sees nothing; the soft music fills the room, but she hears it not; he bends her body to and fro, but she knows it not; his hot breath, tainted with strong drink, is on her hair and cheek, his lips almost touch her forehead, yet she does not shrink; his eyes, gleaming with a fierce, intolerable lust, gloat over her, yet she does not quail. She is filled with the rapture of sin in its intensity; her spirit is inflamed with passion and lust is gratified in thought. With a last low wail the music ceases, and the dance for the night is ended, but not the evil work of the night.
She is now in the vile embrace of the Apollo of the evening. Her head rests upon his shoulder, her face is upturned to his, her bare arm is almost around his neck, her partly nude swelling breast heaves tumultuously against his, face to face they whirl on, his limbs interwoven with hers, his strong right arm around her yielding form, he presses her to him until every curve in the contour of her body thrills with the amorous contact. Her eyes look into his, but she sees nothing; the soft music fills the room, but she hears it not; he bends her body to and fro, but she knows it not; his hot breath, tainted with strong drink, is on her hair and cheek, his lips almost touch her forehead, yet she does not shrink; his eyes, gleaming with a fierce, intolerable lust, gloat over her, yet she does not quail. She is filled with the rapture of sin in its intensity; her spirit is inflamed with passion and lust is gratified in thought. With a last low wail the music ceases, and the dance for the night is ended, but not the evil work of the night.
 We love ads that think outside the box, unfortunately we don't have any information about the brand, who created it or where its located. Anyone?
We love ads that think outside the box, unfortunately we don't have any information about the brand, who created it or where its located. Anyone?
 Bonusfive sez, "A company is providing services to etch up to 196,000 pages (nano microscope retrieval) onto a 2 inch square of nickel for archival purposes, which should last 1,000 years and survive heat up to 500 degrees C. They can also cram up to 18,000 pages for optical microscope retrieval."
Bonusfive sez, "A company is providing services to etch up to 196,000 pages (nano microscope retrieval) onto a 2 inch square of nickel for archival purposes, which should last 1,000 years and survive heat up to 500 degrees C. They can also cram up to 18,000 pages for optical microscope retrieval." 








