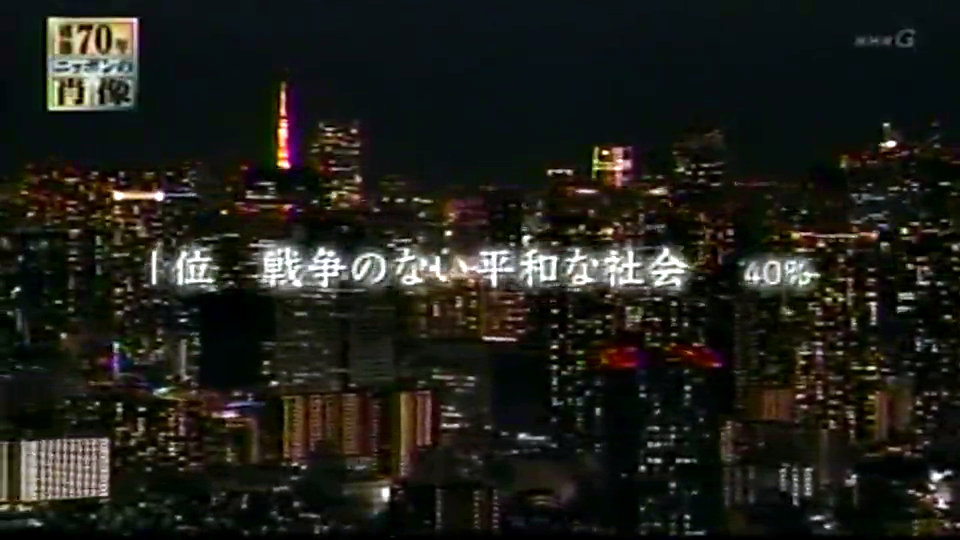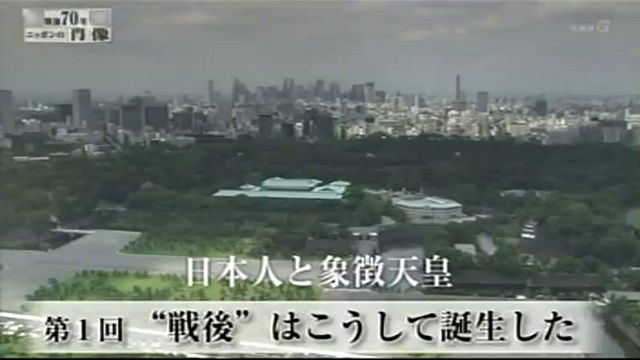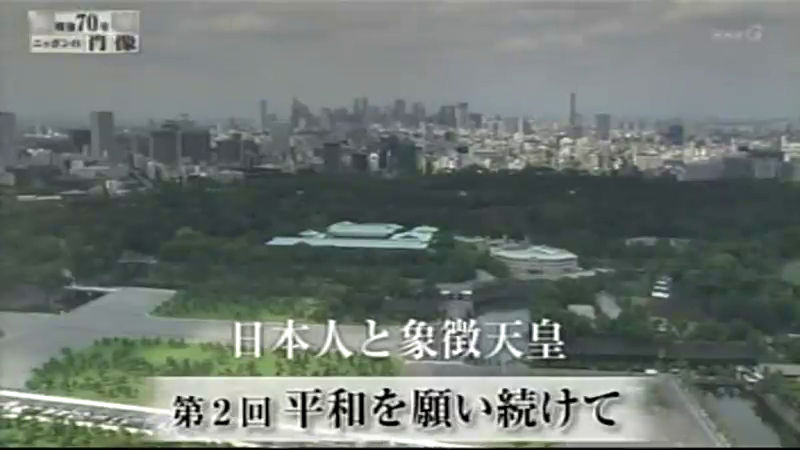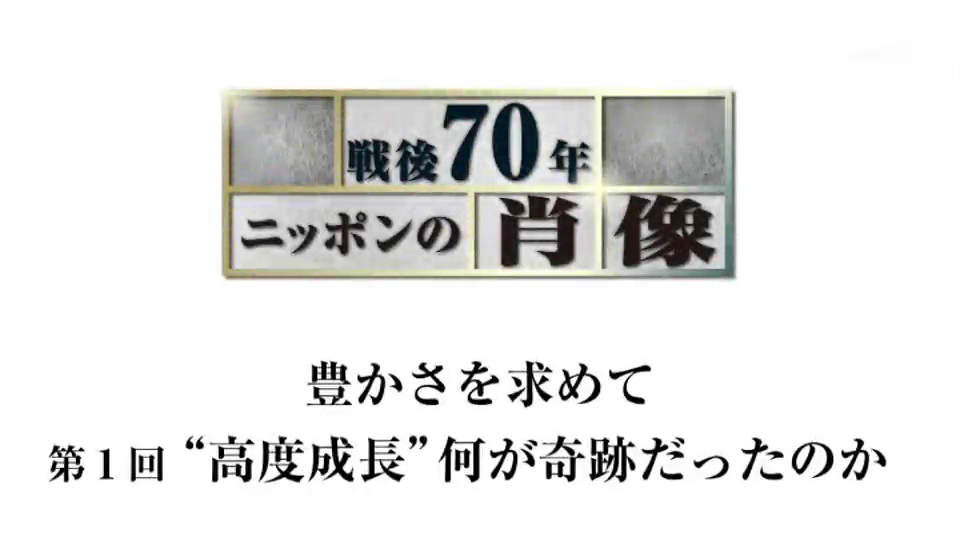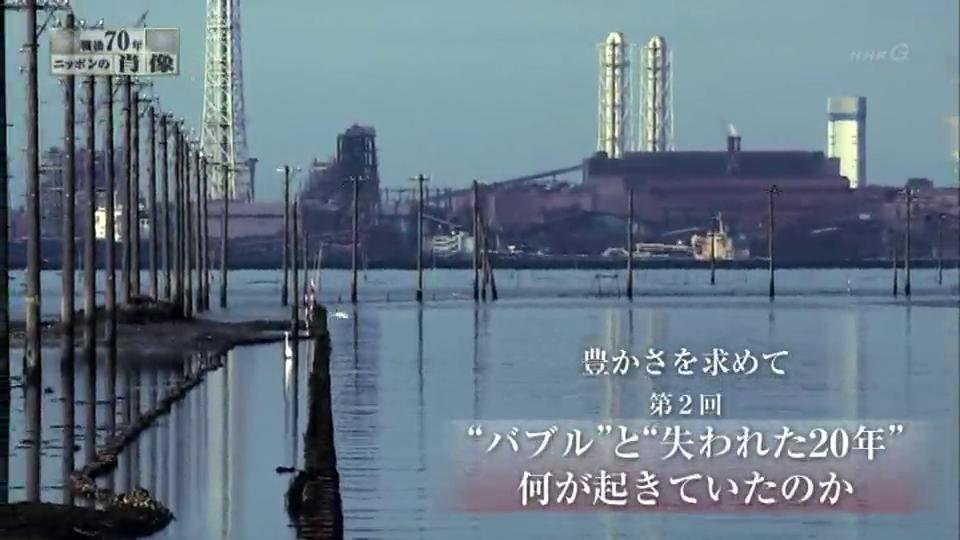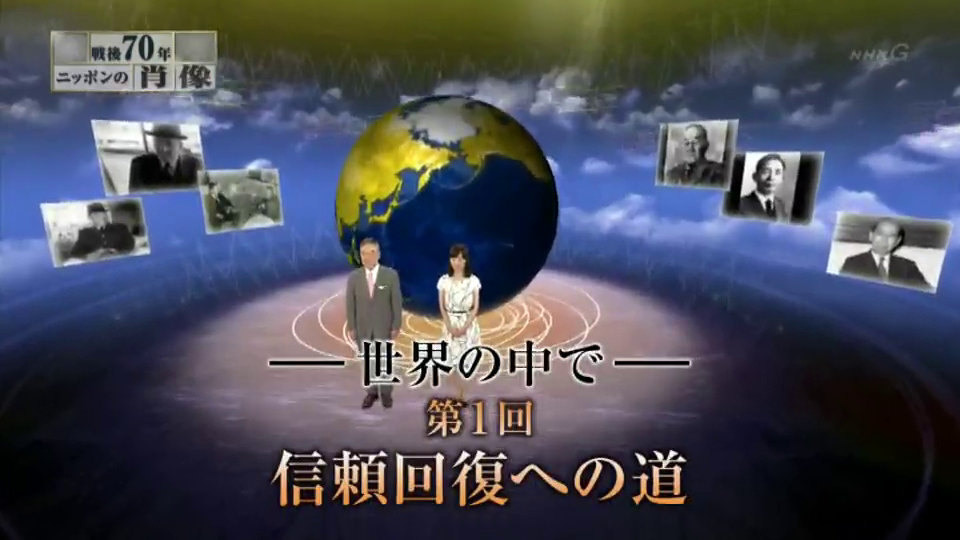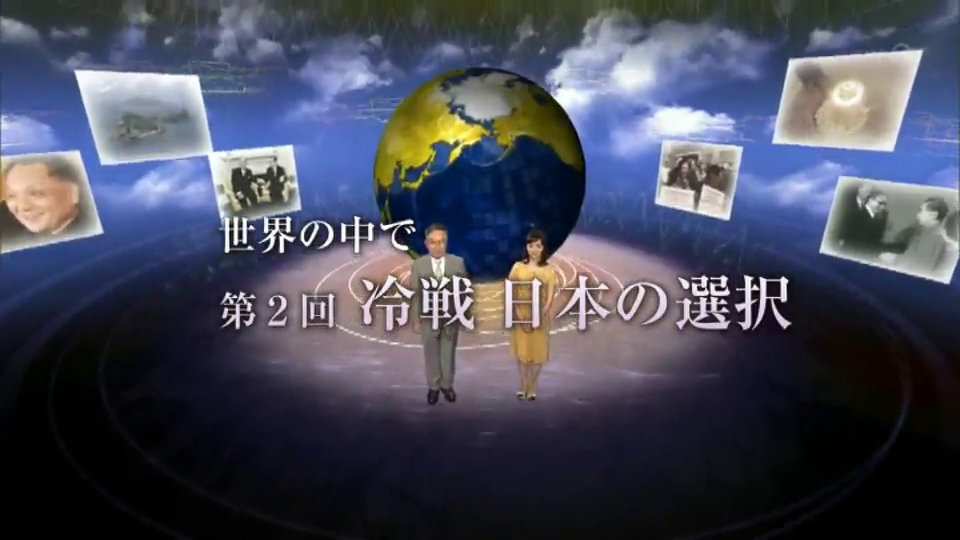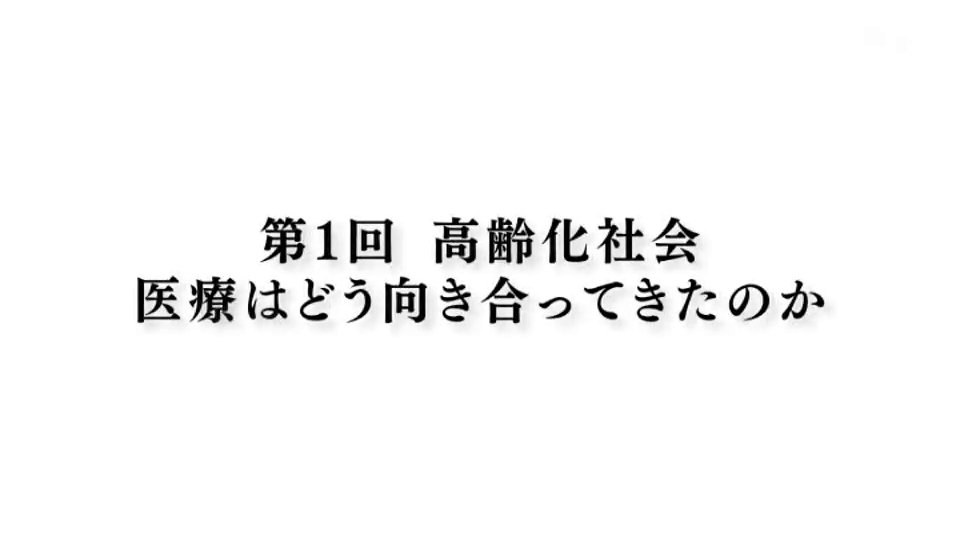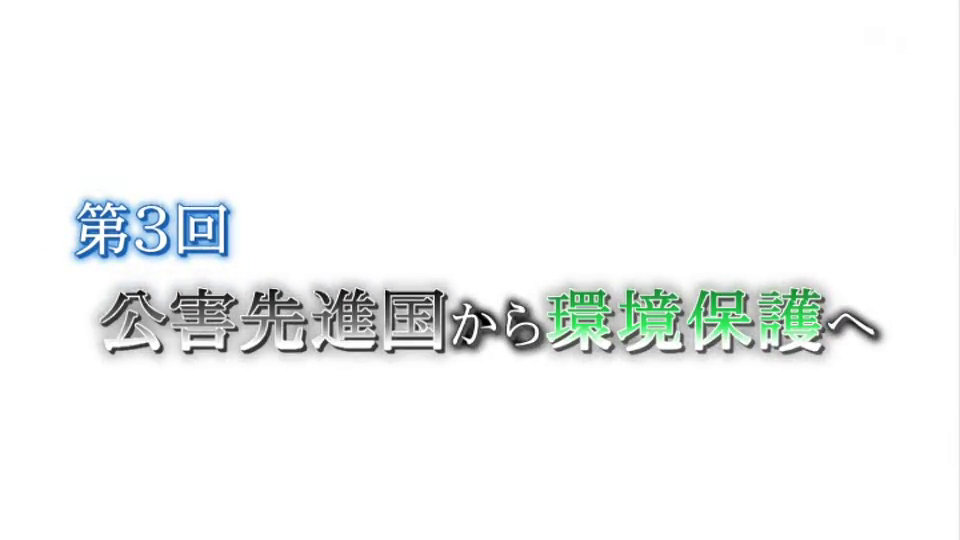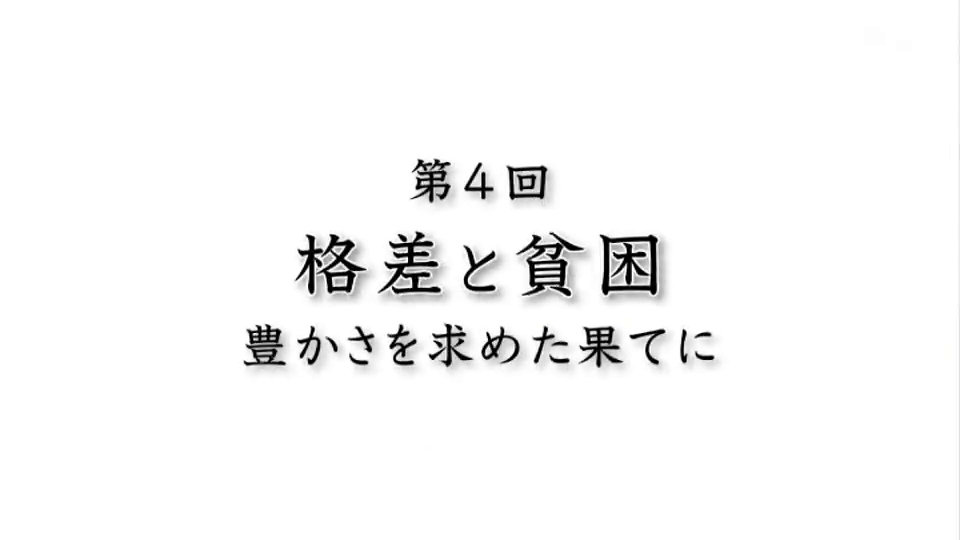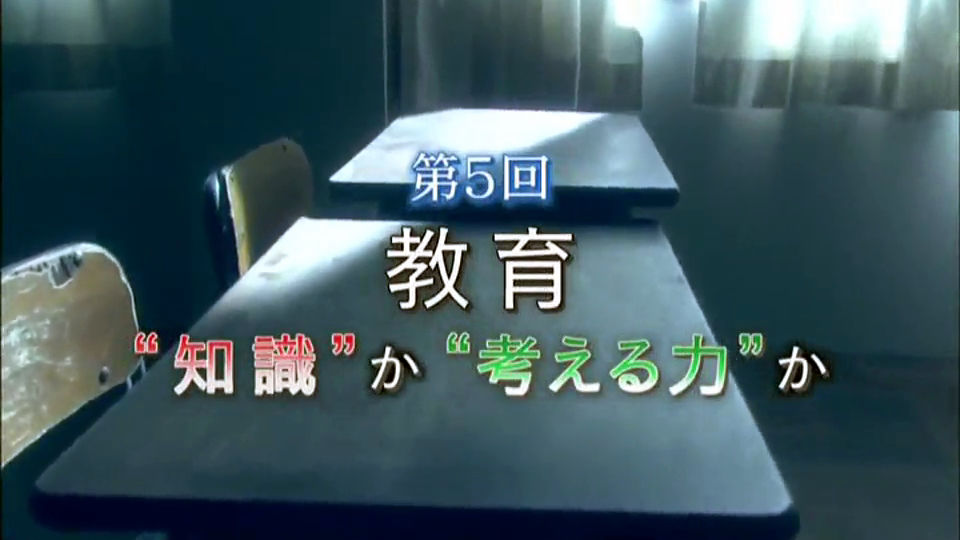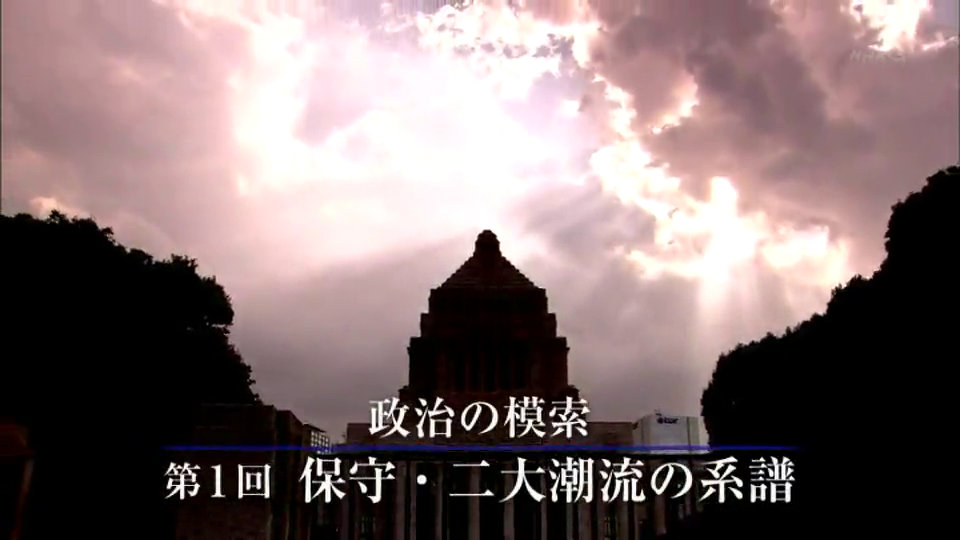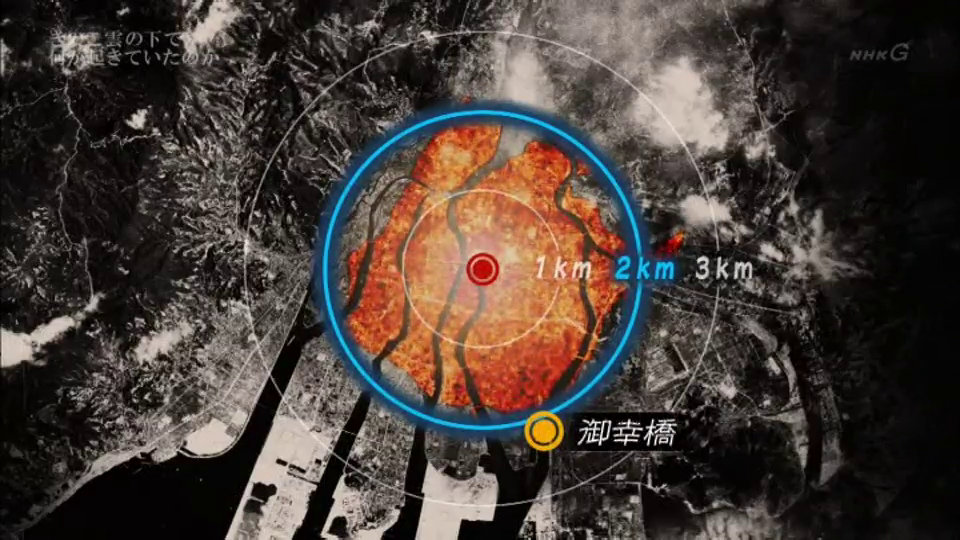戦後史証言プロジェクト 日本人は何をめざしてきたのか 未来への選択 第3弾
第1回 高齢化社会 医療はどう向き合ってきたのか
医療
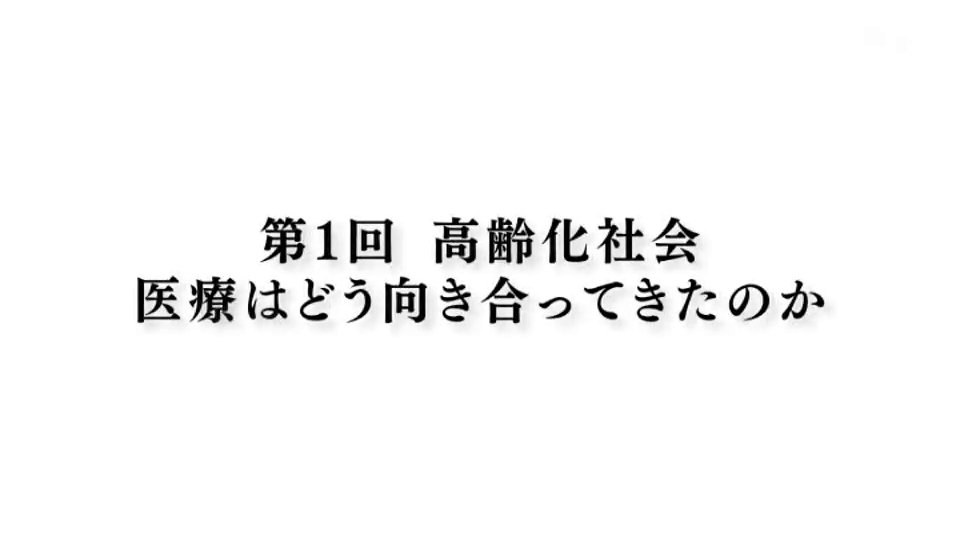
戦後70年の今年は日本人の暮らしの中にある問題を取り上げる。第1回のテーマは高齢化社会。「生命行政」を掲げ全国に先駆け老人医療費無料化を実施した岩手県旧沢内村や、80年代から高齢者を在宅で支えてきた多摩市の病院を中心に、医療の現場や国の政策担当者がどのように対応してきたかを証言で振り返る。超高齢社会が進み“老い”の課題が増える未来に向け、とるべき進路とは?
第3回 公害先進国から環境保護へ
公害
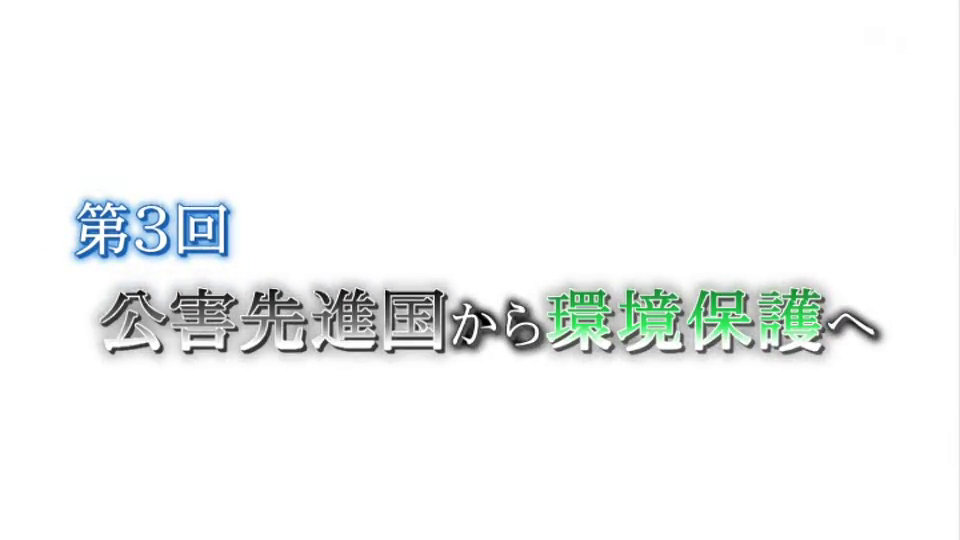
日本の環境問題への取り組みは、高度経済成長期の「公害」の発見からはじまった。三重県四日市では、石油化学コンビナートから出る亜硫酸ガスにより、住民が喘息に悩まされた。漁師の野田之一さん(83)は語る。「最初は四日市が賑わうから両手を挙げて賛成したけど、こんなことは想像もしなかった」。四日市を教訓として、住民達がコンビナート進出を阻止したのが静岡県三島沼津の住民だった。主婦の山本保子さん(81)は「勉強会を繰り返しました。子どもたちを苦しめるわけにはいかなかった」という。
行政は公害の対策として、1967年には公害対策基本法を成立させた。さらに1971年には環境庁を設立。この頃、良好な環境を享受するのは基本的人権であるという考え方「環境権」が共有されるようになる。北海道の伊達市では、火力発電の建設をめぐり、環境権を旗印に市民たちが闘った。結果として、市の条例に環境権がうたわれるようになった。そして日本は徐々に環境を重視する社会へと変貌していった。
第4回 格差と貧困
豊かさの果てに
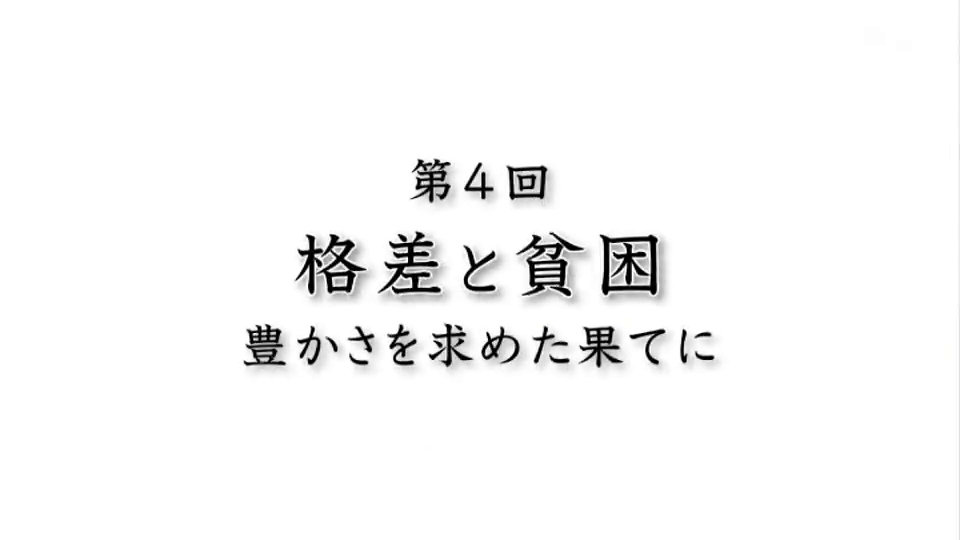
戦後の日本は、格差や貧困に、どのように向き合ってきたのか。
敗戦後、新憲法の25条は、「健康にして最低限度の文化的生活を営む」権利を保障した。この生存権の理念を実現すべく、病床から生活保護の充実を求めて裁判を起こした朝日茂さんの「朝日訴訟」(1957年)。支援の輪とともに、日雇いや中小零細企業の労働者を支援する個人加盟の労働組合が全国に広がる。
1965年、国は貧困世帯の調査を打ち切り、地方への補助金や公共事業などの経済対策で所得再分配を行う政策を推進。正社員になれば安定した生活がおくれる日本型の「企業社会」が作られていく。高度経済成長期、低所得者層の社会調査を続けてきた経済学者の江口英一は1972年に“働いても働いても最低限の生活が送れないワーキング・プアーworking poorが存在する”と指摘。しかし、世界第2位の経済大国となり「一億総中流」の意識が広がる中で、格差と貧困は注目されることはなかった。そしてバブル崩壊後、派遣法が改正されて非正規雇用が大量に生まれると、ようやく人々は格差と貧困を社会問題として「再発見」する。
敗戦から2008年の年越し派遣村まで、生活保護と雇用の現場で声を上げてきた市民たち、そして社会保障政策を担ってきた官僚や政治家などの証言をもとに、格差と貧困の戦後史を描く。
第5回 教育
知識か考える力か
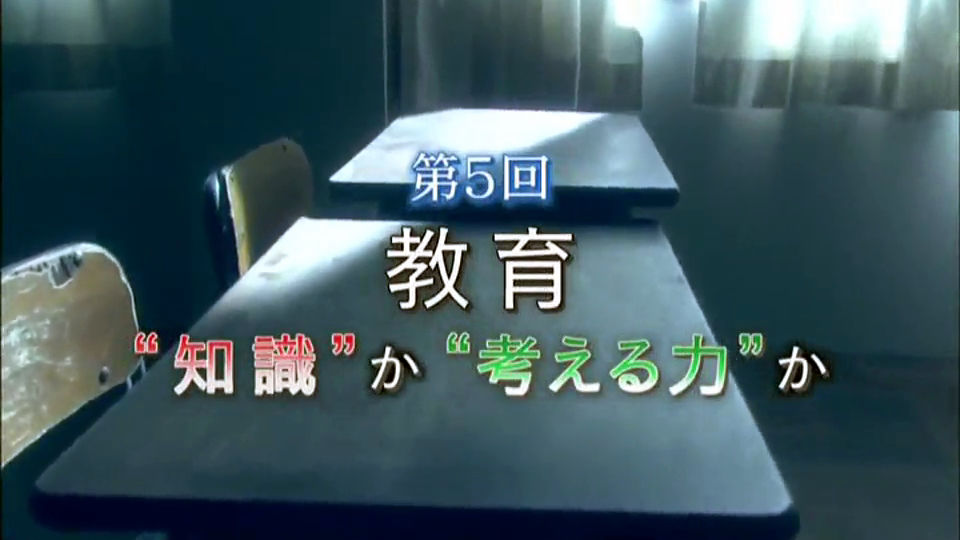
GHQの下スタートした戦後日本の民主主義教育。中学が新たに義務教育になった。三重県・尾鷲の中学教師、内山太門さん(95)は、「それまで中学に行く人は微々たるものだったから活気づいた」と語る。全国で地方独自のカリキュラムが模索され、山形の「山びこ学校」で生活綴り方を進めた無着成恭さん(87)は語る。「子どもたちが作文を通して、自分たちの身近な問題を真剣に考えるようになった」。
国民の教育水準を飛躍的に向上させ、高度成長をひた走った日本。尾鷲中でも、「金の卵」を育てようと、職業教育に注力する。その一方、“落ちこぼれ”や“無気力”など問題が発生し、“詰め込み教育”が自ら考える力をつぶしているとの批判が生じ、尾鷲中学では、校内暴力事件がおこった。
1980年代以降、国も“詰め込み教育”からの脱却を模索。中曽根政権下の臨教審提言を受けた文部省は、“ゆとり教育”へと転換。「総合的な学習の時間」を創設し、教える内容は3割削減する方針を打ち出す。しかし、学力や国際競争力の低下を危惧する声が高まった。2002年、文科省は「確かな学力」を向上させる「学びのすすめ」を発表。文部科学事務次官だった小野元之さんは語る。「このままでは日本が危ない。文科省は学力を軽視しません」。2011年から、再び学習内容拡大へと舵を切り直した。
その間、日本の公教育予算の対GDP比はさがり、現在OECD参加国の中で最低レベルに。また、子供をとりまく経済環境も深刻化している。問題に取り組むNPO代表の青砥恭は調査を行った結果、「親の経済的な差がそのまま学力の差につながっている」という。
あまねく平等な教育を、と始まった戦後教育。その変遷を、文部官僚、教師などの証言をもとにたどっていく。