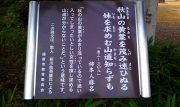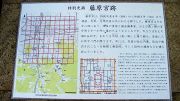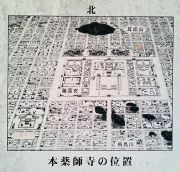人麿神社
車道を避け、田園地帯と住宅街を抜けてさらに10分ほど走ると「柿本人麻呂神社」があった。
本殿は、棟木銘に康永四年(1345年)の墨書があり、重要文化財に指定されている。江戸時代以降には人丸大明神社・柿本人麻呂大明神社と称したが、現在は「人麿神社」という。神社の入口に万葉集詠歌の石碑があった。
秋山の 黄葉を茂み 迷いぬる 妹を求めむ 山道知らずも(巻二-二〇八)
柿本人麻呂(660頃-720頃)は歌聖と呼ばれ、万葉集の詠歌で有名だが、その出自や経歴には不明なことが多い。人麿神社は島根県や兵庫県にもある。前者は人麿終焉の地といわれる。後者は後世になって寺の住職が人麿の夢を見て祀るようになったという。
途中迷って民家の人におふさ観音への道を聞いた。日差しが強かったので玄関の中に招き入れてくれ、親切に地図を書いて教えてくれた。
「花が好きなら三輪明神裏手の山間にある谷ゆりの群生がきれいですよ」という。別の機会に訪れてみよう。
15分ほどおしゃべりをした後、おふさ観音に直行した。十数分で着いた。2300種のバラが栽培されており境内の庭は色とりどりのバラの花で埋め尽くされていた。5月中旬から6月末まで楽しめる。
本堂の裏手に回ると亀の池と日本庭園、広い茶店(茶房おふさ)がある。おふさ観音は、高野山真言宗の別格本山のお寺。この辺り一帯はかつて鯉ケ淵と呼ばれた大きな池だったそうだ。慶安三年四月、おふさという娘が池の辺りを歩いていると、白い亀の背中に乗った観音様が現れた。そこで、小さなお堂を建てその観音様を祀ったのがはじまり。庶民信仰の寺で、ボケ封じにご利益があるという。大和の夏の風物詩として毎年7/1~8/31には風鈴まつりがある。期間中、境内に約2000個もの各地の風鈴が飾られる。 たくさんの風鈴の音色で厄払いをして心身を癒すのもいい。茶房おふさでは奈良女子美術大学の絵画展をやっていた。